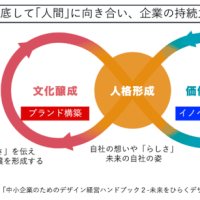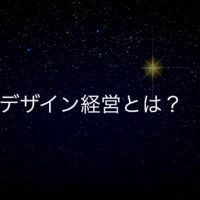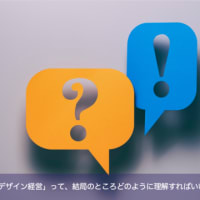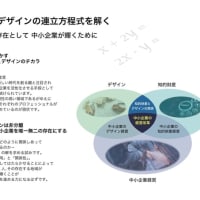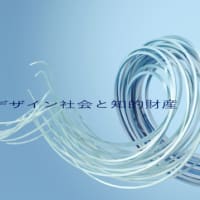先週金曜は‘中小企業のための知的財産経営シンポジウムin広島’、大阪に続き多くの方にご参加をいただき誠に有難うございました。
経営・事業に貢献する知財、事業・研究開発・知財の三位一体・・・といったもキャッチコピーも最近はちょっと食傷気味になってきた感がありますが、これから取り組んでいかなければならないのは、それが重要だと叫ぶだけではなく、「わかっていてるのになぜ実践が難しいのか」という部分にスポットを当てて解決策を探ることであると思います。わかっているのに実践できない理由、たとえばこんな要因があるのではないでしょうか。
1. 現場でリマインドができていない。←細かい実務に取り組むうちに原則を見失ってしまう。
2. 関係者への広がりが足りない。←知財活動の具体的な貢献が関係者にピンときていない。
3. システムができていない。←要するに業務プロセスや体制の問題。
そういう意味で、今年の特許庁の地域中小企業知財経営基盤定着支援事業全体委員会(それにしても長い名前だ・・・)で取り組んできて、今回のシンポジウムでご披露させていただいた‘定着モデル’は1.に対する一つの解決案、昨年度から取り組んでいる経営者へのインタビューとその生の声を伝える活動は2.に対する一つの解決案、3.については今年度のヒアリング調査でいろんな事例を収集してきましたので4月以降に特許庁のホームページに公開されることになると思います(広島のシンポジウムでも‘身の丈に合った’知財活動のあり方が話題になりましたが、決して厚い体制を組めばよいという話ではありません)。
広島のパネルのまとめは、こんな感じで締めさせていただきました。
経営者の悩み、事業の責任者の悩みから、知財活動で解決できるものを見つけ出すことは、知財人の大事な仕事である。「知財に限らず社長の悩みをまず話してみて下さい」(広島で登壇いただいた木戸弁理士の言)と訊ね、その中から知財活動でできることを探るのはこちら側の仕事であって、「知財はこういうものですから、ネタを出してください」なんて訊ねてスクリーニングを相手に委ねるのは方向が逆。「はじめから特許ありきではなく、ビジネスプランが先でそこから特許ネタを探すのが、たぶん正しい」という信末弁理士のお話も、同じことを指摘されているのであろうと思います。
経営・事業に貢献する知財、事業・研究開発・知財の三位一体・・・といったもキャッチコピーも最近はちょっと食傷気味になってきた感がありますが、これから取り組んでいかなければならないのは、それが重要だと叫ぶだけではなく、「わかっていてるのになぜ実践が難しいのか」という部分にスポットを当てて解決策を探ることであると思います。わかっているのに実践できない理由、たとえばこんな要因があるのではないでしょうか。
1. 現場でリマインドができていない。←細かい実務に取り組むうちに原則を見失ってしまう。
2. 関係者への広がりが足りない。←知財活動の具体的な貢献が関係者にピンときていない。
3. システムができていない。←要するに業務プロセスや体制の問題。
そういう意味で、今年の特許庁の地域中小企業知財経営基盤定着支援事業全体委員会(それにしても長い名前だ・・・)で取り組んできて、今回のシンポジウムでご披露させていただいた‘定着モデル’は1.に対する一つの解決案、昨年度から取り組んでいる経営者へのインタビューとその生の声を伝える活動は2.に対する一つの解決案、3.については今年度のヒアリング調査でいろんな事例を収集してきましたので4月以降に特許庁のホームページに公開されることになると思います(広島のシンポジウムでも‘身の丈に合った’知財活動のあり方が話題になりましたが、決して厚い体制を組めばよいという話ではありません)。
広島のパネルのまとめは、こんな感じで締めさせていただきました。
経営者の悩み、事業の責任者の悩みから、知財活動で解決できるものを見つけ出すことは、知財人の大事な仕事である。「知財に限らず社長の悩みをまず話してみて下さい」(広島で登壇いただいた木戸弁理士の言)と訊ね、その中から知財活動でできることを探るのはこちら側の仕事であって、「知財はこういうものですから、ネタを出してください」なんて訊ねてスクリーニングを相手に委ねるのは方向が逆。「はじめから特許ありきではなく、ビジネスプランが先でそこから特許ネタを探すのが、たぶん正しい」という信末弁理士のお話も、同じことを指摘されているのであろうと思います。