デジデリオの作品にはまったく動きというものがない。壮麗な建築群は、静かにそこに立って崩壊を待っているか、あるいは崩壊が終わったあとの静寂の中に置かれている。「偶像を破壊するユダ王国のアサ王(聖堂の倒壊)」という柱が崩壊するその瞬間を描いた作品もあるが、それすらストップモーションのように動きというものを剥奪されて描かれている。
山尾悠子の「傳説」の書き出しは、デジデリオの作品のように動きを欠いているが、山尾はそれに動きを与えていく。小説は絵画と違っていつまでも動かないままでいることはできないから。
「神々の没落をとうに見送り果てた筈のこの世界に、或る日変化が起きたと思え
動くものが現れたのだ。地平を超え、罌粟粒ほどに小さく、しかし確実に動いてくるものが」
山尾の描く動きは微細なものに過ぎない。終末の世界を思わせる廃墟の中を一組の男女が静かに進んでいく。いずことも知れぬ方向に向かって。「世界の涯ての涯ても、いつかは尽きると思え」――つまり世界の涯てさえ尽きるところへ向かって……。
山尾悠子の作品はゴシック的である。デジデリオの作品がそうであるようにゴシック的である。漱石の「幻影の楯」もゴシック的だが、そこにはロマンスがあった。“ゴシックロマンス”というときのロマンスが。一方山尾の作品はロマンスを欠落させたゴシックに他ならない。
山尾悠子の「傳説」における文体は死後硬直のように“古風”であるが、それがロマンスを欠いている限り十分に“古風”ではない。やはり山尾は現代の作家なのだ。
山尾は「傳説」のことを自分で「神懸かり的な小説」と言っているが、確かに命令文の効果もあって、信じられないほどの緊張感を漂わせている。しかし作品は極めて短い。これほどのテンションを長い時間維持できるはずもない。こうして山尾のロマンスを欠いたゴシックは、小説であるよりも詩の世界に近づいていく。カタレプシーのような散文詩である。
(1) で『リテラリーゴシック・ジャパン』に触れたときに、「真にリテラリーゴシック(文学的ゴシック)と呼べるのは、高橋睦郎の「第九の欠落を含む十の詩編」と吉岡実の同じく詩編「僧侶」そして我らが山尾悠子の「傳説」の三編だけではないか」と書いたが、その意味が分かってもらえるだろう。現代にあってゴシックは詩としての方が成立しやすいということは言える。
以上まだ山尾悠子の「傳説」にしか触れていない。先を急がなくてはならない。

「偶像を破壊するユダ王国のアサ王(聖堂の倒壊)」
山尾悠子の「傳説」の書き出しは、デジデリオの作品のように動きを欠いているが、山尾はそれに動きを与えていく。小説は絵画と違っていつまでも動かないままでいることはできないから。
「神々の没落をとうに見送り果てた筈のこの世界に、或る日変化が起きたと思え
動くものが現れたのだ。地平を超え、罌粟粒ほどに小さく、しかし確実に動いてくるものが」
山尾の描く動きは微細なものに過ぎない。終末の世界を思わせる廃墟の中を一組の男女が静かに進んでいく。いずことも知れぬ方向に向かって。「世界の涯ての涯ても、いつかは尽きると思え」――つまり世界の涯てさえ尽きるところへ向かって……。
山尾悠子の作品はゴシック的である。デジデリオの作品がそうであるようにゴシック的である。漱石の「幻影の楯」もゴシック的だが、そこにはロマンスがあった。“ゴシックロマンス”というときのロマンスが。一方山尾の作品はロマンスを欠落させたゴシックに他ならない。
山尾悠子の「傳説」における文体は死後硬直のように“古風”であるが、それがロマンスを欠いている限り十分に“古風”ではない。やはり山尾は現代の作家なのだ。
山尾は「傳説」のことを自分で「神懸かり的な小説」と言っているが、確かに命令文の効果もあって、信じられないほどの緊張感を漂わせている。しかし作品は極めて短い。これほどのテンションを長い時間維持できるはずもない。こうして山尾のロマンスを欠いたゴシックは、小説であるよりも詩の世界に近づいていく。カタレプシーのような散文詩である。
(1) で『リテラリーゴシック・ジャパン』に触れたときに、「真にリテラリーゴシック(文学的ゴシック)と呼べるのは、高橋睦郎の「第九の欠落を含む十の詩編」と吉岡実の同じく詩編「僧侶」そして我らが山尾悠子の「傳説」の三編だけではないか」と書いたが、その意味が分かってもらえるだろう。現代にあってゴシックは詩としての方が成立しやすいということは言える。
以上まだ山尾悠子の「傳説」にしか触れていない。先を急がなくてはならない。

「偶像を破壊するユダ王国のアサ王(聖堂の倒壊)」










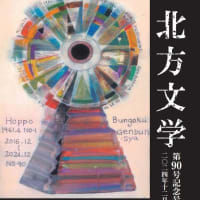
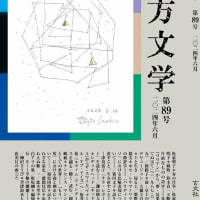
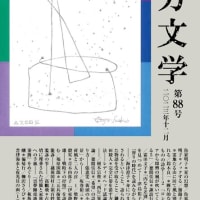

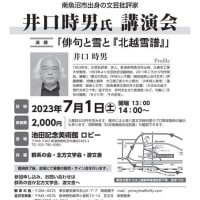

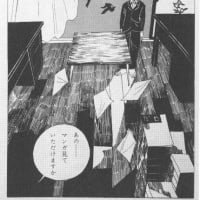
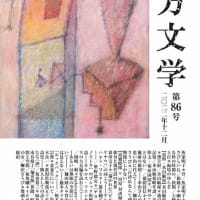
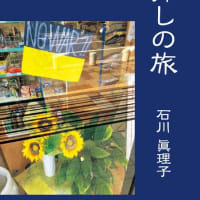
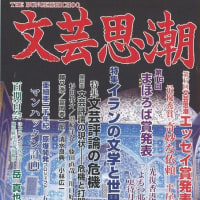

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます