バークは『崇高と美の観念の起原』を第五編の言語についての考察で締めくくっている。言語はいかにして崇高の観念を呼び起こすかがテーマであるが、その前提となるのは「詩歌は厳密には模倣的芸術ではない」という考え方である。
例えば絵画は模倣によって自然界の対象物を、我々にとって刺激的なものにすることができる。一方言語はいかなる映像をも生み出すことなしに作用することができるし、観念に先立ってさえ機能する。
絵画は自然界の中に客観的等価物を持つことができるが、言語はそうではないということについて、バークは次のように書いている。
「模倣ということは或る事物が他の或る事物と似通う限りでのみ成立するのであってそれ以外の領域では模倣はあり得ぬ道理であるが、言葉は疑いもなくそれが意味する観念との如何なる相似も持たないのである」
これが18世紀の人間の言葉であることに驚きを禁じ得ない。言語と観念の間にはいかなる相似関係もない。この言葉から我々は、ソシュールの「意味するものと意味されるものとの恣意的関係」ということを想起することも可能である。
つまり、言語と観念は相似関係において結びついているのではないのであるから、そこには模倣ということはあり得ない。絵画が自然的事象を模倣して成立するというようなことは、言語においてはあり得ない。だからこそ「詩歌は模倣的芸術ではない」ということになる。
確かに言語は日常会話においても、書かれたものを読む場面においても、いかなる映像をも喚起せずして機能するし、いかなる観念をも再現することなしに機能もするのである。言語は客観的等価物を持たない。言語は言語自身を指し示すのだと言ったら、これはもう20世紀の言語学の世界である。
バークは第五編で言語について大変画期的なことを考え始めているのであるが、バーク自身そのことに気づいてはいないように思う。
「正直な話、詩歌や修辞学は厳密な描写という点ではとうてい絵画に立ち討ちできないのであって、それの本務は模倣よりもむしろ共感によって心を動かすことに、つまり事物それ自体についての明晰な観念を再現するよりも、むしろ話者その他の人々の心に及ぼすこれらの事物の効果を描くことに存するのである」
と書く時、バークは決して間違ってはいない。
しかしでは、模倣による快がもたらす美が言語にはないのであれば、言語にとって美はどのようにして生み出されるのかについては説明されない。言語は“共感”によってひとの心を動かすということが強調されているが、どのようにしてなのかについては充分に解明されることはない。
最後はゴシック小説の話題とはかけ離れてしまったが、バーク自身言語の問題に突入した途端に頓挫してしまっているので、これ以上私にも言うことはない。
(この項ようやくおわり)
例えば絵画は模倣によって自然界の対象物を、我々にとって刺激的なものにすることができる。一方言語はいかなる映像をも生み出すことなしに作用することができるし、観念に先立ってさえ機能する。
絵画は自然界の中に客観的等価物を持つことができるが、言語はそうではないということについて、バークは次のように書いている。
「模倣ということは或る事物が他の或る事物と似通う限りでのみ成立するのであってそれ以外の領域では模倣はあり得ぬ道理であるが、言葉は疑いもなくそれが意味する観念との如何なる相似も持たないのである」
これが18世紀の人間の言葉であることに驚きを禁じ得ない。言語と観念の間にはいかなる相似関係もない。この言葉から我々は、ソシュールの「意味するものと意味されるものとの恣意的関係」ということを想起することも可能である。
つまり、言語と観念は相似関係において結びついているのではないのであるから、そこには模倣ということはあり得ない。絵画が自然的事象を模倣して成立するというようなことは、言語においてはあり得ない。だからこそ「詩歌は模倣的芸術ではない」ということになる。
確かに言語は日常会話においても、書かれたものを読む場面においても、いかなる映像をも喚起せずして機能するし、いかなる観念をも再現することなしに機能もするのである。言語は客観的等価物を持たない。言語は言語自身を指し示すのだと言ったら、これはもう20世紀の言語学の世界である。
バークは第五編で言語について大変画期的なことを考え始めているのであるが、バーク自身そのことに気づいてはいないように思う。
「正直な話、詩歌や修辞学は厳密な描写という点ではとうてい絵画に立ち討ちできないのであって、それの本務は模倣よりもむしろ共感によって心を動かすことに、つまり事物それ自体についての明晰な観念を再現するよりも、むしろ話者その他の人々の心に及ぼすこれらの事物の効果を描くことに存するのである」
と書く時、バークは決して間違ってはいない。
しかしでは、模倣による快がもたらす美が言語にはないのであれば、言語にとって美はどのようにして生み出されるのかについては説明されない。言語は“共感”によってひとの心を動かすということが強調されているが、どのようにしてなのかについては充分に解明されることはない。
最後はゴシック小説の話題とはかけ離れてしまったが、バーク自身言語の問題に突入した途端に頓挫してしまっているので、これ以上私にも言うことはない。
(この項ようやくおわり)










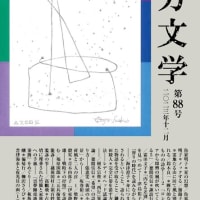

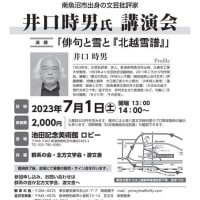

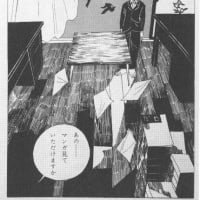
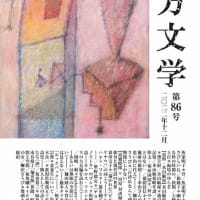
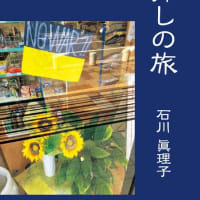
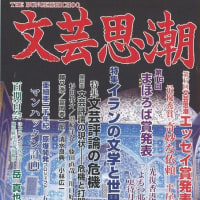
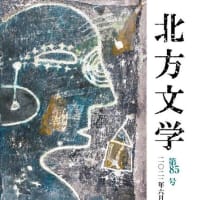


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます