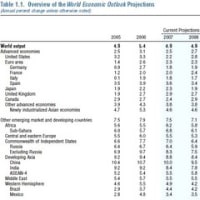| SAPIX カリキュラム-なぜサピックスは驚異的な合格実績をあげられるのか杉山 由美子WAVE出版このアイテムの詳細を見る |
☆本書は言うまでもなく、SAPIXという塾のブランディング戦略の本である。だから、他塾の経営企画室なら、マーケティングの一環としてリサーチしているだろう。もしそうでないなら、その塾の行く末は危うい。
☆まず、SAPIXが御三家に592人合格させているというのはどういうことか。御三家マーケット44.2%シェアということを意味する。このシェアをそれぞれの塾の経営企画室、いや経営陣はどう判断するのだろう。
☆この44.2%というシェアは、SAPIXにとっては御三家は商品である。クライアントはこの商品を購入するのである。クライアントが欲しいというブランド商品なのである。
☆しかし、残念ながらオークションのように、いくらお金を積んだからといって、買えるものではない。商品の思考力とクライアントの思考力をマッチングさせる必要がある。
☆御三家の考える思考力あるいは学力像をできるだけ正確に合理的に映し出しているカリキュラムと子どもが十分に吸収し使えるようになるカリキュラムの仕掛けが、そのマッチングを果たす。
☆カリキュラムの構成要素は、テキスト、テスト、評価、授業方法、自律学習、補講、面談、キャリア・デザイン、時間割だが、もう1つ「知的コミュニケーションの環境」として人材と学習ツール。えっ、テキストや授業方法とどう違うの?と思われるかもしれない。
☆この差異がわかるかわからないかが、各塾の成功の鍵である。中学受験は御三家だけが学校ではない。偏差値にかかわらず、「知的コミュニケーションの環境」は共有できる。この環境を持っている学校は伸びるし、この環境に囲まれている子どもは伸びる。そして同じように塾も。
☆しかし、いかにシステムがしっかりしていても、「知的コミュニケーションの環境」なき塾やテスト会は、私立中高一貫校のマーケットではマッチングできない。市場の原理によって、敗者になるはず。
☆ただ、問題は私立中高一貫校に対しこの「知的コミュニケーションの環境」を撤廃させ、自分たちのレベルに無理やり合わせようとしている教育産業もある。このような動きに迎合する私立中高一貫校があるとしたら、残念だ。そういう教養なき市場も、資本力によって形成されるのが常だからだ。
☆「知的コミュニケーション環境」VS「土建国家的コミュニケーション環境」。どちらの市場を形成すべきか。それは私立中高一貫校が主導できることである。本当の商品を販売しているのは、私立中高一貫校であり、塾は小売店なのだから。











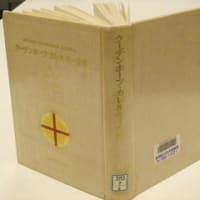


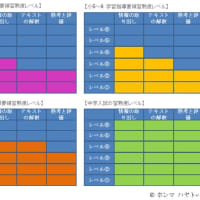
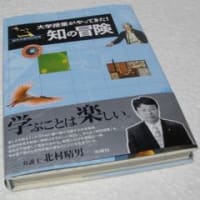
![府知事選の行方[了]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/e9/3d13aadc415722befc574b161350f584.jpg)
![府知事選の行方[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/80/2c2c23ed16365dd67e6b840f66b72c44.jpg)