カラマーゾフの兄弟の私的感想。但し読み終って10数年経過。
1・印象的ところ
【アリョーシャ。五つになるちっちゃな女の子が、両親に憎まれた話もある。この両親は『名誉ある官吏で、教養ある紳士淑女』なんだ。僕はいま一度はっきり断言するが、多くの人間には一種特別な性質がある。それは子供の虐待だ。もっとも子供に限るのだ。ほかの有象無象にたいするときには、もっとも冷酷な虐待者も、博愛心に満ちた教養あるヨーロッパ人でございというような顔をして、慇懃謙遜な態度を示すが、そのくせ子供をいじめることが好きで、この意味において子供そのものまでが好きなのだ。つまり、子供のたよりなさがこの種の嗜虐者の心をそそるのだ。どこといって行くところのない、だれといってたよるもののない小さい子供の、天使のような信じやすい心――これが暴君のいまわしい血潮を沸かすのだ。もちろん、あらゆる人間の中には野獣がひそんでいる。それはおこりっぽい野獣、責めさいなまれる犠牲の叫び声に情欲的な血潮を沸かす野獣、鎖を放たれて抑制を知らぬ野獣、淫蕩のために通風だの肝臓病だのいろいろな病気にとっつかれた野獣なのだ。で、その五つになる女の子を、教養ある両親は、ありとあらゆる拷問にかけるんだ。自分でもなんのためやらわからないで、ただ無性にぶつ、たたく、ける、しまいには、いたいけな子供のからだが一めん紫ばれに成ってしまった。が、とうとうそれにも飽きて、巧妙な技巧を弄するようになった。ほかでもない、凍てつくような極寒の時節に、その子を一晩じゅう便所の中へ閉じこめるのだ。それもただその子が夜中にうんこを知らせなかったから、というだけなんだ。(いったい天使のようにすやすやと寝入っている五つやそこいらの子供が、そんなことを知らせるような知恵があると思っているのかしら)。そうして、もらしたうんこをその子の顔に塗りつけたり、むりやり食べさしたりするのだ。しかも、これが現在の母親の仕事なんだからね!この母親は、よる夜なかきたないところへ閉じ込められた哀れな子供のうめき声を聞きながら、平気で寝ていられるというじゃないか!お前にはわかるかい、まだ自分の身に生じていることを完全に理解することのできないちっちゃな子供が、暗い寒い便所の中でいたいけなこぶしを固めながら、痙攣に引きむしられたような胸をたたいたり、悪げのない素直な涙を流しながら、『神ちゃま』に助けを祈ったりするんだよ、――え、アリョーシャ、おまえはこの不合理な話が、説明できるかい、おまえはぼくの親友だ、神につかえる修行僧だ、いったいなんの必要があってこんな不合理がつくり出されたのか?一つ説明してくれないか!この不合理がなくては、人間は地上に生活してゆかれない、なんとなれば、善悪を認識することができないから、などと人は言うけれども、こんな価を払ってまで、くだらない善悪なんか認識する必要がどこにある?もしそうなら、認識の世界ぜんたいをあげても、この子供が『神ちゃま』に流した涙だけの価もないのだ。】
【ぼくはそのとき『主よ』と叫びたくないよ。まだ時日のある間に、ぼくは急いで自分自身を防衛する、したがって、神聖なる調和は平にご辞退申すのだ。なぜって、そんな調和はね、あの臭い牢屋の中で小さなこぶしを固め、われとわが胸をたたきながら、あがなわれることのない涙を流して、『神ちゃま』と祈った哀れな女の子の、一滴の涙にすら価しないからだ!なぜ価しないか、それはこの涙が永久に、あがなわれることなくして棄てられたからだ。この涙は必ずあがなわれなくてはならない。でなければ、調和などというものがあるはずはない。しかし、なんで、何をもってそれをあがなおうというのだ?それはそもそもできることだろうか?それとも、暴虐者に復讐をしてあがなうべきだろうか?しかし、われわれに復讐なぞ必要はない。暴虐者のための地獄なぞ必要ない。すでに罪なき者が苦しめられてしまったあとで、地獄なぞがなんの助けになるものか!それに、地獄のあるところに調和のあろうはずがない。ぼくはゆるしたいのだ。抱擁したいのだ。決して人間がこれ以上苦しむことを欲しない。もし子供の苦悶が、真理のあがないに必要なだけの苦悶の定量を満たすのに必要だというなら、ぼくは前からきっぱり断言しておく、――いっさいの真理もこれだけの代償に価しない。そんな価を払うくらいなら、母親がわが子を犬に引き裂かした暴君と抱擁したってかまわない!母親だってその暴君をゆるす権利はないのだ!もしたって望むなら、自分だけの分をゆるすがいい、自分の母親としての無量の苦痛をゆるしてやるがいい、しかし、八つ裂きにされたわが子の苦痛は、決してゆるす権利を持っていない。たとえわが子がゆるすと言っても、その暴君をゆるすわけにはいかないのだ!もしそうとすれば、もしみんながゆるす権利を持っていないとすれば、いったいどこに調和がありうるんだ?いったいこの世界に、ゆるすという権利を持った人がいるだろうか?ぼくは調和なぞほしくない、つまり、人類にたいする愛のためにほしくないと言うのだ。ぼくはむしろあがなわれざる苦悶をもって終始したい。たとえぼくの考えがまちがっていても、あがなわれざる苦悶と、いやされざる不満の境にとどまるのを潔しとする。それに、調和ってやつがあまり高く値踏みされてるから、そんな入場料を払うのはまるでぼくらのふところにあわないよ。だから、ぼくは自分の入場券を急いでお返しする。もしぼくが潔癖な人間であるならば、できるだけ早くお返しするのが義務なのだよ。そこで、ぼくはそれを実行するのだ。ねえ、アリョーシャ、ぼくは神さまを承認しないのじゃない、ただ『調和』の入場券をつつしんでお返しするだけだ。「それは謀反です」とアリョーシャは目を伏せながら小さな声で言った。「謀反?ぼくはおまえからそんなことばを聞きたくなかったんだよ」とイヴァンはしみじみとした声で言った。「謀反などで生きてゆかれるかい。ぼくは生きてゆきたいんだからね。さあ、ぼくはおまえを名指してきくから、まっすぐに返事をしてくれ。いいかい、かりにだね、おまえが究極において人間を幸福にし、かつ平和と安静を与える目的をもち、人類の運命の塔を築いているものとして、このためにはただ一つのちっぽけな生物を――例のいたいけなこぶしを固めて自分の胸を打った女の子でもいい、――ぜがひでも苦しめなければならない、この子供のあがなわれざる涙の上でなければ、その塔を建てることができないと仮定したら、おまえははたしてこんな条件で、その建築の技師となることを承諾するかね。さあ、偽らずに言ってみな!「いいえ、承諾するわけにはゆきません」とアリョーシャは小さな声で言った。「それから、世界の人間が小さな受難者の、償われざる血潮のうえに建てられた幸福を甘受して、永久に幸福を楽しむだろうというような想念を、平然として許容することができるかい?」】
http://m.blogs.yahoo.co.jp/tdhdf661/38845494.html
2・内容
「罪障功徳の体となる こおりとみずのごとくにて こおりおおきにみずおおし さわりおおきに徳おおし」
親鸞『高僧和讃』(『真宗聖典』493頁)
【昭和四十六年、専修学院に入学しました。その時の私は、まるで生きる屍。行くところがないからここに来たのであって、何の期待もない。虚無的な心に覆われて、この身だけが生きている感じでした。そんな私が、入学式の信國先生の言葉に感動し、涙さえ流れてきたのです。「ああこんな私でも、人の話に感動出来るんだな」と、久しぶりに生きている自分を体験したのです。
しかし、勤行、合掌念仏に終始する学院の生活は、真宗念仏の伝統に触れたことのない私には、身の置き所のないものでした。長い間そういう鬱積が、身体全体に溜っていたのですが、とうとうそれを全部吐き出すような出来事が始まったのです。それは、レポート面接から始まりました。信國先生と初めて会話を交わしたのも、この時でした。硬くなって座っている私に先生は、
「あなたの場合は、もう本を読んだり、考えたりしてみても、解決はつかんでしょう。人に遇うほかありませんね。アリョーシャがゾシマ長老に遇ったように、あなたの問題を一気に解決してくれるような人に。ただ、その人に遇えるまで、じっと耐えてゆかねばならないが、あなたは、何に対してなら自分の心を開いていけますか?文学ですか?芸術ですか?自然に対してはどうですか?」
と尋ねられましたが、そのどれにも拒否反応を示したので、「あんたは全く自閉的なんだなあ」と感心したようにつぶやかれました。
面接はこんな風にして終わったのですが、外に出た私の目には、学院の庭木が本当に生き生きとひと回り大きく、くっきりと沁み込んできたのです。そして、先生が会話の中で仰しゃった言葉の一つ一つが私の身に深く入り込んで、その底から揺さぶりをかけてきているような感じでした。
翌日のことですが、何か重くのしかかってくるものに耐えられないようになって、私はふらふらと、初めて先生の家を訪ねました。先生の家は、今の高倉会館の側にありました。当時女子の寮がまだ出来ていなくて、私達は先生と一つ小路を挟んだところに下宿しておりました。夜も十時近かったのではないかと思うのですが、ふらふらと先生の家を訪ねていました。迎え入れられて、先生の前に座ったのですが、何から切り出してよいかわからず、項垂れているだけでした。先生も、何も問うてはくれません。むしろ、何か無関心そうに見えました。そのうち、「どうかしましたか」と問われて、私は反射的に、「私、生きたいんです」と答えました。「その『たい』が生きさせない!」と、即座にぴしゃりと机を叩かれて、先生の言葉が跳ね返ってきました。その強い語気に私は我に返って、姿勢を正し、先生の方に全身を傾注していきました。
「あなたは、自分が病人だということがわかりますか。その病人であるあなたをまな板にのせて、癒そうとするんでなくて、もう見込みがない見込みがないと殺しかかっているのが、またあなただ。そんな自分の姿が見えますか。本当に冷淡な人だなあ」
私はこの時、自分のいのちを、私よりももっと深く、温かく包んで生かそうとしているものがある、そして、自分以上に自分を知っている人がいる、自分以上に自分を本当に愛して生かそうとしているものがあると感じたのです。先生は続けて、
「あなたは、いつも自分に対して人生の意味だとか、価値だとかを振りかざして関わっているんだ。そうして、その期待に応えられない自分を受け入れようとせず、殺してしまおうとする。それはいくら美しく咲いていたとしても、自然の花ではない。造花ですよ。それは高嶺に造花を咲かせようとする生き方だ」
そう仰しゃって、傍らの聖典を開いて示して下さった箇所には、こう書かれていました。
『淤泥華というは『経』(維摩経)に説いて言わく、「高原の陸地に蓮を生ぜず、卑湿淤泥に蓮華を生ず。」』(聖典四六五頁)
蓮は、じめじめした泥を大地として花を咲かせるという意味ですね。
『これは凡夫、煩悩の泥の中にありて、仏の正覚の華を生ずるに喩うるなり。』(同)
それから先生は、机の上に一輪挿してあった紫陽花(註・アジサイ)を、本当に満足そうに眺めながら、その花の生き方の、無私、無心、あるがままの自然な生き方を、あたかも花に向かってその花を讃えるようかのようにお話されました。私はその時、花と話せる人がそこに居て、その人の方に向かっては、花も嬉しそうに自らを精一杯開示しているというような、そんな光景を見た思いがしました。そんな花のような生が、お念仏をいただく心から始まるのだと、
南無仏の御名なかりせばうつそみのただ生き生くることあるべしや
先生がお念仏に出遇われた時に、こういう歌を詠まれたんだそうですが、その歌を教えてくださいました。
そのまた翌日のことなんですが、一連の自分の興奮状態から頭痛がして、私は友達よりもひと電車遅れて学院に向かったのですが、その電車の中に乗っている人たちがみんな暗い顔をして、私を瞋り責めたてているような錯覚を覚えました。そして私の心にも、瞋りの炎が燃えていくのに気付き、怖くなって夢中で電車をおりて、学院まで走って行きました。その時の感じというのは、暗い暗い業のトンネルを歩いているといった感じでした。いのちあるものを見ると、せめぎあって、殺気立ってくる私のいのちだったのです。通りすがりの人も、犬も、みんな私を脅かす恐ろしい存在でした。そういう自分を抱えて、院長室へ泣きながらふらふらの体でなだれ込んでしまいました。「私は人を殺しました」と言って泣き伏したそうです。許してください、許してくださいと、心の中で叫びますが、許してくれというのも自己主張じゃないかと気付いた途端、どうしてよいかわからぬまま、そうしているうちに私は自分が合掌しているのに気付きました。その合掌は、本当にいのちの底から、いのち自身の力が私をそうさせたとしかいえないものでした。
「久遠劫来はじめて合掌する人となられた」と先生は仰しゃり、そして、先生の「ナンマンダブツ」というお念仏の声に促されて、私も初めて、「ナンマンダブツ」と申しました。私をして、そうさせた力が何だったのか。ともかく、その日から私は素直に、「ナンマンダブツ」と掌を合わせることになりました。
これまで長い間、自己意識によって抑圧されていた私のいのちが、その解放の道を求めて、もがき苦しみながら、やっと光を見たという感じでした。あるいはこれは、妄想とかヒステリー症状とかいうものでしょうか。しかし私にとっては、信國先生という存在と言葉によって、私の心を縛り、私のいのちを閉じこめていた厚い自我の殻を突き破って、やっとやっと生き生きとものに触れ、人に交わっていく自分自身を取り戻したという出来事だったのです。エゴイストという殺人鬼から、やっと自身を取り戻したという出来事だったのです。先生の内なる如来様が、私のいのちを呼び出してくださったのかもしれません。
「縁の下のじめじめしたところに芽を出した草も、光の方へ、光の方へと伸びてゆくでしょう。そんなふうに、光を求めて行かねばならない」
と、先生が仰しゃる「向日性(註・こうじつせい)」という、光に向かって生きるということを聞いて、私は今までずっと俯いて歩いていたのですが、その私の頭が、身が、梢の上の方を見上げて歩くようになったのでした。不思議なことでした。
こういう出来事、出遇いを経て、初めて私はこれまでの心の座、自分一身に囚われた心、自我心を中心としていた座から起ち上がって、先生の真似をして、上に阿弥陀如来を礼拝し、口に、声に念仏申すという聞法の生活が始まることになったのでした。
(第三十二回青草会法話 藤谷純子『出遇い』より。願生・第149号)】
1・印象的ところ
【アリョーシャ。五つになるちっちゃな女の子が、両親に憎まれた話もある。この両親は『名誉ある官吏で、教養ある紳士淑女』なんだ。僕はいま一度はっきり断言するが、多くの人間には一種特別な性質がある。それは子供の虐待だ。もっとも子供に限るのだ。ほかの有象無象にたいするときには、もっとも冷酷な虐待者も、博愛心に満ちた教養あるヨーロッパ人でございというような顔をして、慇懃謙遜な態度を示すが、そのくせ子供をいじめることが好きで、この意味において子供そのものまでが好きなのだ。つまり、子供のたよりなさがこの種の嗜虐者の心をそそるのだ。どこといって行くところのない、だれといってたよるもののない小さい子供の、天使のような信じやすい心――これが暴君のいまわしい血潮を沸かすのだ。もちろん、あらゆる人間の中には野獣がひそんでいる。それはおこりっぽい野獣、責めさいなまれる犠牲の叫び声に情欲的な血潮を沸かす野獣、鎖を放たれて抑制を知らぬ野獣、淫蕩のために通風だの肝臓病だのいろいろな病気にとっつかれた野獣なのだ。で、その五つになる女の子を、教養ある両親は、ありとあらゆる拷問にかけるんだ。自分でもなんのためやらわからないで、ただ無性にぶつ、たたく、ける、しまいには、いたいけな子供のからだが一めん紫ばれに成ってしまった。が、とうとうそれにも飽きて、巧妙な技巧を弄するようになった。ほかでもない、凍てつくような極寒の時節に、その子を一晩じゅう便所の中へ閉じこめるのだ。それもただその子が夜中にうんこを知らせなかったから、というだけなんだ。(いったい天使のようにすやすやと寝入っている五つやそこいらの子供が、そんなことを知らせるような知恵があると思っているのかしら)。そうして、もらしたうんこをその子の顔に塗りつけたり、むりやり食べさしたりするのだ。しかも、これが現在の母親の仕事なんだからね!この母親は、よる夜なかきたないところへ閉じ込められた哀れな子供のうめき声を聞きながら、平気で寝ていられるというじゃないか!お前にはわかるかい、まだ自分の身に生じていることを完全に理解することのできないちっちゃな子供が、暗い寒い便所の中でいたいけなこぶしを固めながら、痙攣に引きむしられたような胸をたたいたり、悪げのない素直な涙を流しながら、『神ちゃま』に助けを祈ったりするんだよ、――え、アリョーシャ、おまえはこの不合理な話が、説明できるかい、おまえはぼくの親友だ、神につかえる修行僧だ、いったいなんの必要があってこんな不合理がつくり出されたのか?一つ説明してくれないか!この不合理がなくては、人間は地上に生活してゆかれない、なんとなれば、善悪を認識することができないから、などと人は言うけれども、こんな価を払ってまで、くだらない善悪なんか認識する必要がどこにある?もしそうなら、認識の世界ぜんたいをあげても、この子供が『神ちゃま』に流した涙だけの価もないのだ。】
【ぼくはそのとき『主よ』と叫びたくないよ。まだ時日のある間に、ぼくは急いで自分自身を防衛する、したがって、神聖なる調和は平にご辞退申すのだ。なぜって、そんな調和はね、あの臭い牢屋の中で小さなこぶしを固め、われとわが胸をたたきながら、あがなわれることのない涙を流して、『神ちゃま』と祈った哀れな女の子の、一滴の涙にすら価しないからだ!なぜ価しないか、それはこの涙が永久に、あがなわれることなくして棄てられたからだ。この涙は必ずあがなわれなくてはならない。でなければ、調和などというものがあるはずはない。しかし、なんで、何をもってそれをあがなおうというのだ?それはそもそもできることだろうか?それとも、暴虐者に復讐をしてあがなうべきだろうか?しかし、われわれに復讐なぞ必要はない。暴虐者のための地獄なぞ必要ない。すでに罪なき者が苦しめられてしまったあとで、地獄なぞがなんの助けになるものか!それに、地獄のあるところに調和のあろうはずがない。ぼくはゆるしたいのだ。抱擁したいのだ。決して人間がこれ以上苦しむことを欲しない。もし子供の苦悶が、真理のあがないに必要なだけの苦悶の定量を満たすのに必要だというなら、ぼくは前からきっぱり断言しておく、――いっさいの真理もこれだけの代償に価しない。そんな価を払うくらいなら、母親がわが子を犬に引き裂かした暴君と抱擁したってかまわない!母親だってその暴君をゆるす権利はないのだ!もしたって望むなら、自分だけの分をゆるすがいい、自分の母親としての無量の苦痛をゆるしてやるがいい、しかし、八つ裂きにされたわが子の苦痛は、決してゆるす権利を持っていない。たとえわが子がゆるすと言っても、その暴君をゆるすわけにはいかないのだ!もしそうとすれば、もしみんながゆるす権利を持っていないとすれば、いったいどこに調和がありうるんだ?いったいこの世界に、ゆるすという権利を持った人がいるだろうか?ぼくは調和なぞほしくない、つまり、人類にたいする愛のためにほしくないと言うのだ。ぼくはむしろあがなわれざる苦悶をもって終始したい。たとえぼくの考えがまちがっていても、あがなわれざる苦悶と、いやされざる不満の境にとどまるのを潔しとする。それに、調和ってやつがあまり高く値踏みされてるから、そんな入場料を払うのはまるでぼくらのふところにあわないよ。だから、ぼくは自分の入場券を急いでお返しする。もしぼくが潔癖な人間であるならば、できるだけ早くお返しするのが義務なのだよ。そこで、ぼくはそれを実行するのだ。ねえ、アリョーシャ、ぼくは神さまを承認しないのじゃない、ただ『調和』の入場券をつつしんでお返しするだけだ。「それは謀反です」とアリョーシャは目を伏せながら小さな声で言った。「謀反?ぼくはおまえからそんなことばを聞きたくなかったんだよ」とイヴァンはしみじみとした声で言った。「謀反などで生きてゆかれるかい。ぼくは生きてゆきたいんだからね。さあ、ぼくはおまえを名指してきくから、まっすぐに返事をしてくれ。いいかい、かりにだね、おまえが究極において人間を幸福にし、かつ平和と安静を与える目的をもち、人類の運命の塔を築いているものとして、このためにはただ一つのちっぽけな生物を――例のいたいけなこぶしを固めて自分の胸を打った女の子でもいい、――ぜがひでも苦しめなければならない、この子供のあがなわれざる涙の上でなければ、その塔を建てることができないと仮定したら、おまえははたしてこんな条件で、その建築の技師となることを承諾するかね。さあ、偽らずに言ってみな!「いいえ、承諾するわけにはゆきません」とアリョーシャは小さな声で言った。「それから、世界の人間が小さな受難者の、償われざる血潮のうえに建てられた幸福を甘受して、永久に幸福を楽しむだろうというような想念を、平然として許容することができるかい?」】
http://m.blogs.yahoo.co.jp/tdhdf661/38845494.html
2・内容
「罪障功徳の体となる こおりとみずのごとくにて こおりおおきにみずおおし さわりおおきに徳おおし」
親鸞『高僧和讃』(『真宗聖典』493頁)
【昭和四十六年、専修学院に入学しました。その時の私は、まるで生きる屍。行くところがないからここに来たのであって、何の期待もない。虚無的な心に覆われて、この身だけが生きている感じでした。そんな私が、入学式の信國先生の言葉に感動し、涙さえ流れてきたのです。「ああこんな私でも、人の話に感動出来るんだな」と、久しぶりに生きている自分を体験したのです。
しかし、勤行、合掌念仏に終始する学院の生活は、真宗念仏の伝統に触れたことのない私には、身の置き所のないものでした。長い間そういう鬱積が、身体全体に溜っていたのですが、とうとうそれを全部吐き出すような出来事が始まったのです。それは、レポート面接から始まりました。信國先生と初めて会話を交わしたのも、この時でした。硬くなって座っている私に先生は、
「あなたの場合は、もう本を読んだり、考えたりしてみても、解決はつかんでしょう。人に遇うほかありませんね。アリョーシャがゾシマ長老に遇ったように、あなたの問題を一気に解決してくれるような人に。ただ、その人に遇えるまで、じっと耐えてゆかねばならないが、あなたは、何に対してなら自分の心を開いていけますか?文学ですか?芸術ですか?自然に対してはどうですか?」
と尋ねられましたが、そのどれにも拒否反応を示したので、「あんたは全く自閉的なんだなあ」と感心したようにつぶやかれました。
面接はこんな風にして終わったのですが、外に出た私の目には、学院の庭木が本当に生き生きとひと回り大きく、くっきりと沁み込んできたのです。そして、先生が会話の中で仰しゃった言葉の一つ一つが私の身に深く入り込んで、その底から揺さぶりをかけてきているような感じでした。
翌日のことですが、何か重くのしかかってくるものに耐えられないようになって、私はふらふらと、初めて先生の家を訪ねました。先生の家は、今の高倉会館の側にありました。当時女子の寮がまだ出来ていなくて、私達は先生と一つ小路を挟んだところに下宿しておりました。夜も十時近かったのではないかと思うのですが、ふらふらと先生の家を訪ねていました。迎え入れられて、先生の前に座ったのですが、何から切り出してよいかわからず、項垂れているだけでした。先生も、何も問うてはくれません。むしろ、何か無関心そうに見えました。そのうち、「どうかしましたか」と問われて、私は反射的に、「私、生きたいんです」と答えました。「その『たい』が生きさせない!」と、即座にぴしゃりと机を叩かれて、先生の言葉が跳ね返ってきました。その強い語気に私は我に返って、姿勢を正し、先生の方に全身を傾注していきました。
「あなたは、自分が病人だということがわかりますか。その病人であるあなたをまな板にのせて、癒そうとするんでなくて、もう見込みがない見込みがないと殺しかかっているのが、またあなただ。そんな自分の姿が見えますか。本当に冷淡な人だなあ」
私はこの時、自分のいのちを、私よりももっと深く、温かく包んで生かそうとしているものがある、そして、自分以上に自分を知っている人がいる、自分以上に自分を本当に愛して生かそうとしているものがあると感じたのです。先生は続けて、
「あなたは、いつも自分に対して人生の意味だとか、価値だとかを振りかざして関わっているんだ。そうして、その期待に応えられない自分を受け入れようとせず、殺してしまおうとする。それはいくら美しく咲いていたとしても、自然の花ではない。造花ですよ。それは高嶺に造花を咲かせようとする生き方だ」
そう仰しゃって、傍らの聖典を開いて示して下さった箇所には、こう書かれていました。
『淤泥華というは『経』(維摩経)に説いて言わく、「高原の陸地に蓮を生ぜず、卑湿淤泥に蓮華を生ず。」』(聖典四六五頁)
蓮は、じめじめした泥を大地として花を咲かせるという意味ですね。
『これは凡夫、煩悩の泥の中にありて、仏の正覚の華を生ずるに喩うるなり。』(同)
それから先生は、机の上に一輪挿してあった紫陽花(註・アジサイ)を、本当に満足そうに眺めながら、その花の生き方の、無私、無心、あるがままの自然な生き方を、あたかも花に向かってその花を讃えるようかのようにお話されました。私はその時、花と話せる人がそこに居て、その人の方に向かっては、花も嬉しそうに自らを精一杯開示しているというような、そんな光景を見た思いがしました。そんな花のような生が、お念仏をいただく心から始まるのだと、
南無仏の御名なかりせばうつそみのただ生き生くることあるべしや
先生がお念仏に出遇われた時に、こういう歌を詠まれたんだそうですが、その歌を教えてくださいました。
そのまた翌日のことなんですが、一連の自分の興奮状態から頭痛がして、私は友達よりもひと電車遅れて学院に向かったのですが、その電車の中に乗っている人たちがみんな暗い顔をして、私を瞋り責めたてているような錯覚を覚えました。そして私の心にも、瞋りの炎が燃えていくのに気付き、怖くなって夢中で電車をおりて、学院まで走って行きました。その時の感じというのは、暗い暗い業のトンネルを歩いているといった感じでした。いのちあるものを見ると、せめぎあって、殺気立ってくる私のいのちだったのです。通りすがりの人も、犬も、みんな私を脅かす恐ろしい存在でした。そういう自分を抱えて、院長室へ泣きながらふらふらの体でなだれ込んでしまいました。「私は人を殺しました」と言って泣き伏したそうです。許してください、許してくださいと、心の中で叫びますが、許してくれというのも自己主張じゃないかと気付いた途端、どうしてよいかわからぬまま、そうしているうちに私は自分が合掌しているのに気付きました。その合掌は、本当にいのちの底から、いのち自身の力が私をそうさせたとしかいえないものでした。
「久遠劫来はじめて合掌する人となられた」と先生は仰しゃり、そして、先生の「ナンマンダブツ」というお念仏の声に促されて、私も初めて、「ナンマンダブツ」と申しました。私をして、そうさせた力が何だったのか。ともかく、その日から私は素直に、「ナンマンダブツ」と掌を合わせることになりました。
これまで長い間、自己意識によって抑圧されていた私のいのちが、その解放の道を求めて、もがき苦しみながら、やっと光を見たという感じでした。あるいはこれは、妄想とかヒステリー症状とかいうものでしょうか。しかし私にとっては、信國先生という存在と言葉によって、私の心を縛り、私のいのちを閉じこめていた厚い自我の殻を突き破って、やっとやっと生き生きとものに触れ、人に交わっていく自分自身を取り戻したという出来事だったのです。エゴイストという殺人鬼から、やっと自身を取り戻したという出来事だったのです。先生の内なる如来様が、私のいのちを呼び出してくださったのかもしれません。
「縁の下のじめじめしたところに芽を出した草も、光の方へ、光の方へと伸びてゆくでしょう。そんなふうに、光を求めて行かねばならない」
と、先生が仰しゃる「向日性(註・こうじつせい)」という、光に向かって生きるということを聞いて、私は今までずっと俯いて歩いていたのですが、その私の頭が、身が、梢の上の方を見上げて歩くようになったのでした。不思議なことでした。
こういう出来事、出遇いを経て、初めて私はこれまでの心の座、自分一身に囚われた心、自我心を中心としていた座から起ち上がって、先生の真似をして、上に阿弥陀如来を礼拝し、口に、声に念仏申すという聞法の生活が始まることになったのでした。
(第三十二回青草会法話 藤谷純子『出遇い』より。願生・第149号)】














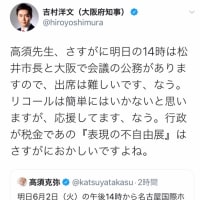

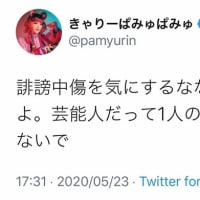
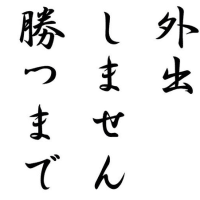
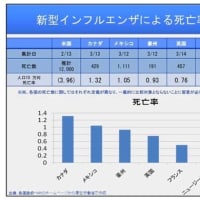

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます