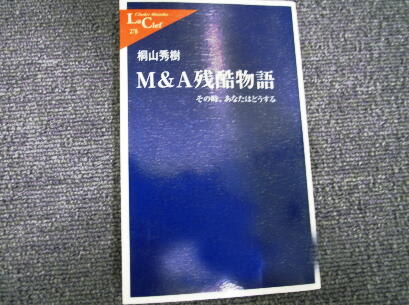世界第二位の消費国・日本経済を無視する不思議さ
日本経済についていつも不思議なのは、世界第二位の経済大国にして、大消費国の日本がなぜ米国の株価に影響されるのかと言うことではないか。
日本と米国との直接貿易額は大方18%。
一方、アジア諸国へのシェアは、輸出で約50%。
アジア諸国の日本企業から米国への貿易とか、日系企業における現地生産と言うものもあるから日本企業が米国から稼ぐ額は大きなものになろう。
しかし、米国の日系企業は米国企業であって、日本ではない部分がある。
又、アジア諸国の日本企業から米国への輸出も一概には論じられないところがある。
そして、米国が転けたらあと消費してもらうというのは日本しかないというのは事実だ。
GDPを見てみてると、日本の民間最終消費支出が約60%、政府最終消費支出約18%、これを加えると78%は日本の消費と言うことになる。
だから日本が発展途上国だった頃のように、輸出一本やりでGDPをたたき出している訳ではない。
その現実を現している事がある。それはこの8月末米国向けに生産したカメラを米国が在庫過多となったために、急遽日本向けに直してネットで密かに格安で売ったメーカーがあった。
いずれにせよ、高価な商品を買えるのは米国でなければ、日本しかないというのは間違いないところだ。
それなのに、日本に金がないというのはどういう事なのだろうか。
米国は、本来借金だらけの国で、財務省証券(国債)を日本や中国が多額に購入しているからそれで金が回っている国だ。
しかも、サブプライムローンというインチキな債権をテコの原理で拡大して高金利に偽装。
それを世界中で金利が高いと言う理由で買ったのが今度の問題だというもの。
しかも、日本かゼロ金利に近い時に、米国は5%程度という金利を維持していたから余計に「金」を呼び込んだ。
当然、日本の年金基金も証券会社に丸投げして、今年の3月期頃には8兆円もの損を被ったはず。
この様に、日本の金も、そしてファンドに貸す金融機関の金も全て米国に向かっているからこそ、米国は維持出来たのであるし、問題が大きくなった。
その責任は、かねてから言っているように日銀の「ゼロ金利政策」であることは間違いないことだった。
本来、大消費国の日本に金が集まらなければおかしい。
なぜなら、大消費国であるならば「金が流動」するからだ。
ところが、その流動する金に関して、企業は金が出来れば銀行に返済して益々市場から金が吸い取られる状況にあった。
これがデフレであって、その上低金利のために金が市場に戻らない仕組みになっている。
結局、日本経済、株価というものは米国経済の株価に連動するシステムになってしまった。本来、米国消費に頼らずとも日本だけでかなりの部分消費出来るはずなのに、日本の現状を反映しないのはおかしいだろう。
そして、その日本の株価を動かしているのが、日本の銀行から投資資金へ出ているお金であるというのが、春先まで言われていた「円キャリー取引」と言うものだった。
最近、めっきりその話は聞かなくなったが、「円キャリー取引」が今でも続いているというのは間違いないだろう。
なぜなら、米国がこれだけ株価が下がり、景気が悪くなっても「円相場は」少しも動かないからだ。
これは、誰かが何かを動かしていると言う理由。
多分、将来その問題が大きくならなければよいかと思う昨今ではある。