児童書ってもちろん子供のための本なんでしょうが、中には大人が読んでも面白い、時には子供より大人の方がもっとずしーんとくる本もあったりします。
Onjali Q. Raúf の本は前に読んだ"The Boy At the Back of the Class"もそうでしたが、大人より子供の方が夢中になるだろうなあという正統派。
特に"The Night Bus Hero" はクラスのいじめっ子がヒーローになるという話なので、これは絶対子供に受けそう!
"The Night Bus Hero"も"The Man on the Street"、偶然にもどちらも「ホームレス」を取り上げています。
そしてどちらもイギリス。意識的に選んでいるわけじゃないのに、気が付けばまたイギリスものを読んでいる。
英語だと思って使っていたらそれは「和製英語」だった、ということがありますが、それは「アメリカ」での場合で、イギリスでは同じ言い方をするということがけっこうあります。
"The Night Bus Hero"、"The Man on the Street" 両方に出てきたのが、
"rucksask" ということば。日本語では「リュックサック」。
英語では"backpack"ですと習いますが、イギリスでは"rucksack"。
でも発音は「リュックサック」ではなく「ラックサック」みたいな感じだから、「リュックサック」と発音したらやっぱり通じないか?
多分ブリティッシュだろうと思うことば。
advert 広告
home time 下校時間
punter 客
pushchair 折り畳み式のベビーカー
minging ひどい、臭い















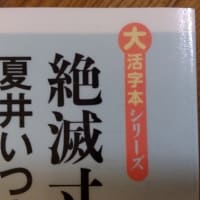
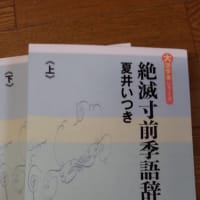











この記事を読んだ後に、最近頼りにしているイギリス人の先生に聞いてみました。リュックサックの画像を送って「これは何と言うの?」と。彼、backpackと最初に言いました。そのあとに「ラックサック」、そして日本語もわかっているので「リュックサック」とも言いましたけれどね。
1800-2019年まで折れ線グラフでアメリカとイギリスでbackpack, rucksackがどのくらい使われてきたかを見せてくれましたが、イギリスでも1970年代から少しずつbackpackの使用が増えてきて現在ではrucksackを引き離しているようです。アメリカでも同じ時期に両方が同じくらい使われていたものの、今では大きくbackpackが引き離しているみたいです。もちろんイギリスからの移民がいたり、年代・好みなどあるのでしょうけれど。先生は若い世代はアメリカの影響を受けているしbackpackという人が多いかもしれないと。同じようにアメリカのアニメの影響でイギリスの子どもがトラックをrulleyと言わずにtruckと言ったりするようです。
そこからイギリス英語とアメリカ英語の違いになって、おなじみのクッキーとビスケット、そして先生が「男性のtrousersにつけるのは?」と聞いたので、見事に引っかかってsuspenders!と言ったら、ご存じのようにそれはイギリスではガーターベルトだと直されました(^^;そしてクリスティなどでもおなじみの大好きなスリーピーススーツのベスト、waistcoatですよね。昔はweskitと発音したらしいですけれど、「イギリスのベストはこれだ!」と日本でいうところのタンクトップ(tank top/undershirt)の画像をくれました。イギリスのtank topは日本人も着るニットベストなんですね。もうこんがらがってしまいます。
Famous Fiveに出てきたjolly goodって使う?と聞いたら戦時中に使っていたような古い言い方だと言われました。冗談で使うかもしれないけどと。まあ本が古いので使われている表現も古いものが少なくないのかもしれません。
前に学校で人にアドバイスをするときにhad betterを使うと習ったのに、大人になってからそれは非常に強い表現だと言われてショックだったと言ったら、そうとは限らないと言われました。それでますます混乱してしまいました。けさ、日本人のTOEIC
TOEICに力を入れている英語講師が「had betterは脅し」と書いていたので、再度聞いたら首を振っていました。「たとえば貴女と僕が一緒にお菓子を焼いているとして、生地が生焼けだったらもう少し焼いたほうがいいんじゃないとhad betterを使って言える」と言っていました。他のイギリス人、あるいは北米の人たちがどう思うかわかりませんが、日本で教わることはアップデートされていないのか、途中で間違った情報が正しいこととして認識され始めているのか。前回もAdvanced Grammar in Useの説明を例に教えてくれたのですが、確かにそこにWe can use had better instead of should/ought to, especially in spoken English,to say that we think it is a good idea to do something.
We prefer had better if we want to express particular urgency or in demands and threats.
このテキストを読んでのことか分かりませんが、最後の部分から「had betterは脅し」となってしまう可能性もありなんでしょうか。例文はThere is someone moving about downstairs. We had better call the police,quickly.でした
文法に詳しい北米の先生の意見も聞けたらと思いますが、色々なものを見聞きして判断するしかないのかなあ。刺激にはなりました。
ばっちもんがらさんが書いていらっしゃるpunterというのも面白いですね。主にスポーツに賭ける人のことなんですね。
リュックサックの件、そうなんだあとすごく参考になりました。
イギリス人もかたくなに米語は使わない人と、気にしない人と色々なんですね。
そのイギリス人の先生、すごく対応が早くて、頼もしい!Lilyさんの「きっとこういうことが知りたいんだな」というところをよくわかってくれてるんでしょうね。
"had better" もそうですが、結局は「状況次第」ってことなんでしょうね。こういう場面なら、使うかも、、、という状況は考えればありそう。
どんな表現も「基本的には」という但し書きが必要ですよね。
イディオムも普通はもう古くて使わないものも、この状況ならまさにぴったり!ということありますからね。
waistcoat はメモをしたのが
A Tailor of Gloucester と
The Little White Horse
からで、いかにもって感じです。
"punter" はThe Man on the Street ではパブの客のことだったので、customer と同じ意味で使われることもあるのかもしれません。
rulley はメモしてませんでした。そのうち出会うことがあるかな。
時代と共に変化をすることもありますし、おっしゃるとおり「基本的には」というのは大事かもしれませんね。日本語のことを考えてもそうだなと思います。イディオムはいくら使わないとか古いとか言われてもそれが一番その状況を言い表していると思えるものがありますよね。そのイギリス人の先生はrain cats and dogsとかnot one's cup of teaなんて耳にしないから使わないでくれと言っていましたが、上の世代では違うことを言うかもしれないと思いました。本で出会うこともありますし、知っていて損はないでしょうね。
The Little White Horseはアマゾンのレビューで子どもの頃に児童文学全集で読んだと書いている方がいました。私は知らなかったのですが、ばっちもんがらさんもそうですか?福武文庫や岩波文庫で「まぼろしの白馬」というタイトルで出たみたいで。映画も「ムーンプリンセス秘密の館とまぼろしの白馬」という邦題で出ているのですね。ヨアン・グリフィズが出ているみたいなので気になります。
カタカナ英語あふれてますね。
久しぶりに「ノッティングヒルの恋人」を見たんですが、何かあるとTea は?とまるで万能薬のように聞くところが可笑しくて、やっぱりイギリスのTea の伝統はずっと消えないでほしい。
例えネイティブでもどんな環境で暮らしているかによって、使うイディオムも違うかも。
私たちのように、オタクだとやたら使ってみたいというずうずしているし^^
The Little White Horse はものすごく思い入れがある本です。
あかね書房の「国際児童文学賞全集」といういのが図書館にあって「まぼろしの白馬」その第1巻だったこともあって、特に人気があったようです。
一次絶版でしたが、今では翻訳も、もちろん原作も手に入ります。
あかね書房の「国際児童文学賞全集」と聞いて、ああ、あれと思い当たる人はたいてい同年代です^^
映画化は原作とは全く別物で、同じだったのは登場人物の名前くらいですね。