 |
小判商人―御宿かわせみ (御宿かわせみ) 平岩 弓枝 文藝春秋 このアイテムの詳細を見る |
「小判商人」の中の一遍「文三の恋人」にこんな一節がありました。
「彦右衛門の爺さんがおっかない顔をしているんで、元締に聞きに来たのさ」
「おっかない」というは栃木の方言かと思っていました。
でもこれは生粋の江戸っ子である神林東吾のせりふなので、栃木弁ではなかったんですね。
語源語由来辞典によるとおっかないとは
身の程知らず、恐れ多いという意味の形容詞「おおけなし(おほけなし)」が促音化して「おっかなし」になったのではという説があるそうです。
異説もあるようですが、私は迷わずこれに1票!
「おほけなく」と聞くと浮かぶのが百人一種のこの歌。
おほけなく うき世の民に おほふかな わがたつ杣に 墨染の袖
百人一種は圧倒的に恋の歌が多いですが、この前大僧正慈円の歌は数少ないその他のジャンルの一首。
私の好きな歌はこの前大僧正慈円の歌も含めて、こんなのです。
ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花のちるらむ
朝ぽらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木
どーも恋の歌は好みではないらしい。
久しぶりに百人一首を眺めてみると、もともと好きだった歌ですが、この年になってひときわじーんとこたえる歌があることに気がつきました。
ながらへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき
花さそふ 嵐の庭の雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり
人もをし 人もうらめし あぢきなく 世を思ふゆゑに 物思ふ身は
きっちり年を取っているんですよね。












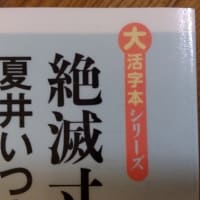
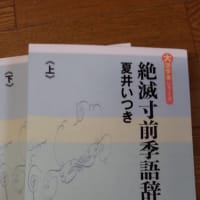






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます