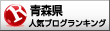農業高校でお馴染みのFFJは日本語では日本学校農業クラブ連盟。
農業を学習する全国の高校が加入しており、
その数、およそ370校8万人にもなります。
農業の学びの基本はプロジェクト学習。つまり研究活動です。
どこの学校でも1年生はまだ研究見習いという位置付けですが
8万人もの生徒が生物生産、加工、流通、バイオや環境、地域活性など
何らかの研究活動に取り組んでいるのです。
その農業クラブの機関誌がリーダーシップ。
年に数回ですが全クラブ員に配布されます。
つまり購読者は8万人以上。ここに掲載されると
全国の多くの仲間の目に触れることになります。
先日、届いたリーダーシップには名久井農業高校の取り組みが紹介されています。
ひとつは名農農業クラブが校内で行ったSDGsの企画。
どの研究班でもSDGsに関連した活動をしていることを
再認識してもらったという内容です。
もうひとつはフローラハンターズの沖縄の赤土流出抑制活動。
沖縄の高校生と連携して行ったダイナミックな活動が紹介されました。
きっと後輩たちの励みになることでしょう。
さて農業クラブの年に1度の祭典、全国大会が10月25〜26日に開催されます。
今年の73回大会は北陸。石川、富山、福井の3県が合同で開催。
果たして2022年はどんな研究が日本一になるのでしょう。楽しみです。
また名農からは農業鑑定競技に各科の代表がエントリーしています。
文化祭直前ですが、大いに頑張ってきてもらいたいものです。
農業を学習する全国の高校が加入しており、
その数、およそ370校8万人にもなります。
農業の学びの基本はプロジェクト学習。つまり研究活動です。
どこの学校でも1年生はまだ研究見習いという位置付けですが
8万人もの生徒が生物生産、加工、流通、バイオや環境、地域活性など
何らかの研究活動に取り組んでいるのです。
その農業クラブの機関誌がリーダーシップ。
年に数回ですが全クラブ員に配布されます。
つまり購読者は8万人以上。ここに掲載されると
全国の多くの仲間の目に触れることになります。
先日、届いたリーダーシップには名久井農業高校の取り組みが紹介されています。
ひとつは名農農業クラブが校内で行ったSDGsの企画。
どの研究班でもSDGsに関連した活動をしていることを
再認識してもらったという内容です。
もうひとつはフローラハンターズの沖縄の赤土流出抑制活動。
沖縄の高校生と連携して行ったダイナミックな活動が紹介されました。
きっと後輩たちの励みになることでしょう。
さて農業クラブの年に1度の祭典、全国大会が10月25〜26日に開催されます。
今年の73回大会は北陸。石川、富山、福井の3県が合同で開催。
果たして2022年はどんな研究が日本一になるのでしょう。楽しみです。
また名農からは農業鑑定競技に各科の代表がエントリーしています。
文化祭直前ですが、大いに頑張ってきてもらいたいものです。