
軸装 紫陽花
自画 水墨画のあじさいの条幅を本格的な表装で軸装に仕上げました。
掛軸の一幅が仕上がりました。これからの季節は乾燥が早く、暑くて表装の仕事は苦労が多いです。
ところで本格表装の先行きには以前から不安を感じていますが、これにはいろいろな要因が考えられます。
先ず、良い材料の入手が難しくなってきたことです。これは手間のかかる和紙を漉く職人や軸先、上巻絹などを作り手の
高齢化と後継者不足が深刻なこと。また、座敷と床の間のある和風建築から使い勝手のよいマンションへの居住環境の変化で
掛軸や屏風の需要が少なくなったこと。更に表具制作店でも技術の継承がないまま安直な機械表装に頼らざるを得ない現実
があるようです。
一見ピーンと本紙がきれいに貼られて素敵に見える書道展や水墨画展で見かける軸装は機械での圧縮、
熱接着で短時間に仕上げた即席表具。掛軸の裏の上巻絹を省略したり、紙で代用したり、八双の棒が条幅の幅より少し出ておらず
きっちり揃えていたり(八双の棒の両端は軸を巻き取る際に軸を傷めないよう軸幅より少し出すという先人の智恵)、軸の耳折も
無いような軸も出てきて驚きです。
素人の人で軸の知識がない人が総裏の喰い先の繋ぎがあると紙を節約したように思われ一枚裏を望まれる。
上巻絹が表から見ると繋ぎ目の段差ができるからないのが良いと希望されたり、軸の本来の智恵がだんだんとなくなっていくようです。
総裏を何枚も継ぐのは軸のそりがないように、宇田紙の白土を入れて漉いてあるのは気温の変化を土が吸ったり吐いたりの原理を
分かっていないから、、と色々な面で思いがけないことが起こりびっくりします。
格安で直ぐに出来るということですが、目の肥えた方には一目瞭然その違いが分かります。
でも時代の趨勢で致し方ないのかも知れません。寺社仏閣の掛軸の修復にも影響が出なければいいのですが。
私は一つ一つ手間をかけて作る昔からの本格表装を少しでも残したいと思い30年以上頑張っています。


















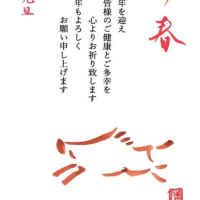


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます