京都文化博物館で開催されている日本の表装展の鑑賞に行きました。
私は表装を始めて四十五年になりますが、掛軸に代表される表装の歴史を知りたくて出かけました。
会場には沢山の方が熱心に観られていましたが意外にも若い人も多くて頼もしく思いました。
紙や絹などの脆い素材に描かれた大切な書画を長く保存するにはどうしたらよいか、持ち運びに
都合良くするにはどうしたものかなど先人の智恵と工夫の試行錯誤から生まれたのが掛軸であるがその発想に
今更ながら感心しました。
本紙(書画などの作品)を裏打ちして裂地で表装仕立てにしたものを軸棒をつけて巻けば作品を大切に長く
保管できて持ち運びにも便利で場所も取らず今も有難く長く続いています。
会場には修復がなされた古い軸装や今にも崩れそうな軸がありましたが日本の貴重な文化を伝える大切な
一幅一幅でした。
纈染(けちぞめ) 繍佛(しゅうぶつ)という言葉も今回の展覧会ではじめて知った言葉でした。
美意識豊かな斬新な表装もあり凝った裂地もあり当時の創作の様子が伺えて刺激になった一日でした。
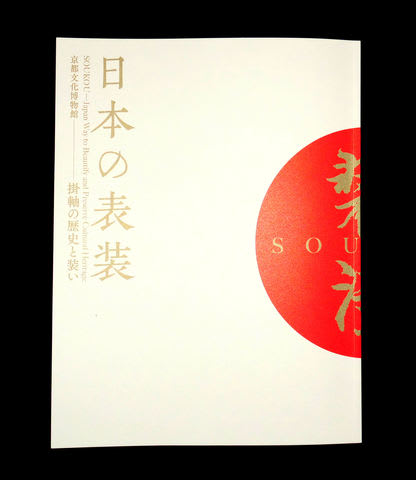
日本の表装(冊子)
描表装(かきびょうそう)という手法は古い時代からあって面白い手法だと感心しました。
今度創作表具をするときに見習ってやってみたいと思いました。
竹屋町織掛軸架鷹図はあえて裏打ちをせずに透かして夏に涼しく掛ける軸装にいいなあと思いました。


竹屋町織掛軸 (冊子より転写)










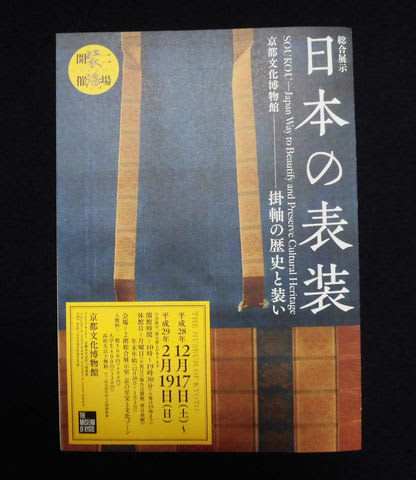




 月心寺
月心寺














 に手入れなさっていました。
に手入れなさっていました。 も欠かさず食事もしっかり摂られ、亡くなる寸前までお元気で僅か1日半の
も欠かさず食事もしっかり摂られ、亡くなる寸前までお元気で僅か1日半の



