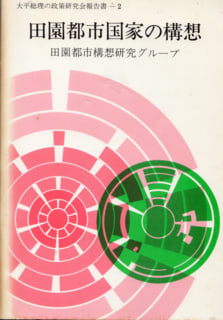news every 先週もいろいろありました。
1.東証システム障害 10月1日
9時を過ぎても東証のシステムが動いていないとの速報がネットに流れた。
バックアップシステムはどうなっているのだと思った。
あれだけやかましく言われていた危機管理対策で当然のセオリーが、あっさり動かない。
巨大システムには、システム規模と同じ大きさのリスクが潜んでいるということなのだろう。
コロナ時代には絶対に成立しないが、かつての立ち合いは、証券業界の伝統技能だった。(私の友人も昔やったことがあると言っていた。)今では出来る人もいなくなってしまったことだろう。
2.日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命拒否問題
やはり滝川事件を思い浮かべた人もいたようだ。
滝川事件とは、京都大学の教授であった滝川幸辰氏が中央大学で行った講演を政府が問題視し、政府に対する攻撃的思想の持主だとして(滝川教授の主張が国家に対する攻撃だと決めつけられた。)京都大学を追われた事件。その後天皇機関説事件の美濃部達吉、東大の矢内原忠雄事件など次々に学問の自由に対する弾圧事件が起きた。
前に麻生太郎副総理(当時)が「ナチスの手口に学んだらどうかね」との発言もあり大変不気味だ。
3.昨日と今日、港の汽笛がきれいに聞こえた。(私的な話)
風向きが良かったのか、いつになくクリアな音で聞こえた。
港町横浜に住んでいるというアイデンティティーが高まる。
最近、新年を迎えた時の汽笛の音が聞こえないのだが、鳴らしてはいけないという緘口令でも出ているのか心配だ。