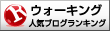記憶の底
毎週木曜日は国語をおさらいしています。
今週は「どちらの読みが正しいのか」をおさらいします。
<平面上の相異なる3個以上の有限個の点と、それらを結ぶ線分から
なる閉じた単純折れ線で囲まれた図形。>
これな~に?
答えは「多角形」
五角形や六角形を説明するこんなに難解な表現をするとは、如何にも理系
の考えそうなこと。
そう思ったのですが文系の考えることにも時々分からないことがあります。
辞書で「たかっけい」と引いたら見つからず、あれこれ探して漸く「たかく
けい」に辿り着きました。
「たかっけい」と読んではいけないのかと悩みます。
こんな解説がありました。
<どちらの読みでも良いが一般的には「たかっけい」が使われる。
これは日本語の促音化によるもので、促音の「っ」に変化したため。>
(ギモン雑学 より)
促音化は昔習った気がするけれど記憶の底の底に沈んでいて何も思い
出せません。
昭和以降に拡大
<ク、キ、チ、ツなどで起きる。
たとえばクの促音化は後ろにカ行の音が来たときによく現れる。
食器、若干、楽観などがこれに当たる。
しかし収穫期は「しゅうかくき」で「しゅうかっき」とはならない。>
言われてみればその通り、どんな理由があるのか教えてくだされ。
<前の部分が独立性の高い単語の場合は促音化が起こらない。
学期や客観等の場合は「学」や「客」だけの単一の単語として使うことは
あまり無く、使った場合は別の意味を持ってしまう。
だから学期や客観の形をした一単語なのだと考える。
つまり前の部分の独立性が低く全体として完全に融合している場合は促音化
が起こる。>
実際にはどちらが使われているか気になります。
<たとえば洗濯機の場合、「せんたくき」と読む人が48%、「せんたっき」
が51%。>(引用はいずれも NHK より)
促音化に分がありますが、辞書に無い理由は?
<一般の国語辞典や教科書などの表記はまちまちで統一が無い。>(文化庁 より)
載っている辞書も探せばあるようでした。
日本人は大昔からこんな面倒を続けてきたのかと感心しましたが、どうも
そうでは無い様子。
<「っ」「ッ」を日本語で積極的に使うようになったのは昭和以降に現代
仮名遣いが広まってからの話。>(22世紀の日本語を考える より)
それより前に伝来したロシアの酒「ウォッカ」、本来は「ヴォトゥカ」と
書くところを原語の発音に近づけるために「ウォッカ」と表記した。
これを後の日本人が読み間違えて今に至る。
ウォッカのッは促音化ではないそうで。
だからどうしたって話ですが。
毎週木曜日は国語をおさらいしています。
今週は「どちらの読みが正しいのか」をおさらいします。
<平面上の相異なる3個以上の有限個の点と、それらを結ぶ線分から
なる閉じた単純折れ線で囲まれた図形。>
これな~に?
答えは「多角形」
五角形や六角形を説明するこんなに難解な表現をするとは、如何にも理系
の考えそうなこと。
そう思ったのですが文系の考えることにも時々分からないことがあります。
辞書で「たかっけい」と引いたら見つからず、あれこれ探して漸く「たかく
けい」に辿り着きました。
「たかっけい」と読んではいけないのかと悩みます。
こんな解説がありました。
<どちらの読みでも良いが一般的には「たかっけい」が使われる。
これは日本語の促音化によるもので、促音の「っ」に変化したため。>
(ギモン雑学 より)
促音化は昔習った気がするけれど記憶の底の底に沈んでいて何も思い
出せません。
昭和以降に拡大
<ク、キ、チ、ツなどで起きる。
たとえばクの促音化は後ろにカ行の音が来たときによく現れる。
食器、若干、楽観などがこれに当たる。
しかし収穫期は「しゅうかくき」で「しゅうかっき」とはならない。>
言われてみればその通り、どんな理由があるのか教えてくだされ。
<前の部分が独立性の高い単語の場合は促音化が起こらない。
学期や客観等の場合は「学」や「客」だけの単一の単語として使うことは
あまり無く、使った場合は別の意味を持ってしまう。
だから学期や客観の形をした一単語なのだと考える。
つまり前の部分の独立性が低く全体として完全に融合している場合は促音化
が起こる。>
実際にはどちらが使われているか気になります。
<たとえば洗濯機の場合、「せんたくき」と読む人が48%、「せんたっき」
が51%。>(引用はいずれも NHK より)
促音化に分がありますが、辞書に無い理由は?
<一般の国語辞典や教科書などの表記はまちまちで統一が無い。>(文化庁 より)
載っている辞書も探せばあるようでした。
日本人は大昔からこんな面倒を続けてきたのかと感心しましたが、どうも
そうでは無い様子。
<「っ」「ッ」を日本語で積極的に使うようになったのは昭和以降に現代
仮名遣いが広まってからの話。>(22世紀の日本語を考える より)
それより前に伝来したロシアの酒「ウォッカ」、本来は「ヴォトゥカ」と
書くところを原語の発音に近づけるために「ウォッカ」と表記した。
これを後の日本人が読み間違えて今に至る。
ウォッカのッは促音化ではないそうで。
だからどうしたって話ですが。