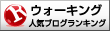9種類のウシ
毎週火曜日はウォーキングの途中で見かけた雑草を取り上げています。
今週は、 ナデシコ科 ハコベ属 ウシハコベ です。
ハコベと言えば春の七草ですが、こちらは夏の盛りにもよく見る草。
先日も森林公園の歩道脇にまとまって生えているのを見つけました。
<茎は地を這ってから斜上し葉は縁が波打ち先端が尖る。
白い5枚の花弁は深裂し10枚に見え柱頭は5本ある。>(身近な雑草300 より)
大抵の図鑑にはこう続きます。
「大きいので名前に牛が付いた」
このひと言がウシに拘る切っ掛けになりました。
一般にハコベと呼ばれるミドリハコベは大きなものでもせいぜい草丈20cm、
それに比べてウシが付くこちらは遥かに巨大な50cm丈。
倍も違えば牛の冠を付けたくなるのも道理です。
では「ウシ」がつく草は全てが大型の種類なのか、これも気になります。
草本では9種類程ある様ですが、よく名を聞くものをあげてみましょう。
カヤツリグサ科のウシクグは大きなものでは70cmなのでカヤツリグサを
遥かに凌ぎます。
エンバクの別称のあるウシムギは150cm程にも伸びるというのでこちらも
巨大サイズ。
ウシノヒタイとも呼ばれるミゾソバも高さは80cm。
いずれも背の高い種類なので「ウシ」が付くのは納得です。
馬の場合は
図鑑によっては「ウシハコベは史前帰化植物」の表記も見られます。
<史前帰化植物には3つの系統がある。
①稲作に伴って伝播した植物群で、イネの刈り取り前に実を稔らせ種子を
散布する。
②麦類の栽培伝来とともにやってきたもので、里山の春を彩る植物の多くはこれ。
③中国から有用植物として持ち込まれたもの。>(岡山理科大 より)
ウシハコベは②に属するそうで。
ちなみに同グループにはナズナ、カタバミ、スベリヒユ、オオバコ、ツユクサ、
ヤエムグラ、ハハコグサ、カラスムギなどお馴染みの面々が集っています。
次はウシハコベの字面からの連想。
自ずと「牛運べ」が浮かんできます。
今でこそ運搬に従事する牛など見かけませんが、江戸時代には最高の運送手段。
山国に重い塩を運ぶのに大いに役立ったと言います。
<牛は物を運ぶのに非常に優れた動物。
一頭に塩二俵を乗せて細い山道を登った。>(和楽 より)
牛が運んでくれた塩が信州のご先祖様の暮らしの支えになりました。
牛さんありがとう。
最後に「牛運べ」があるなら「馬走れ」もあるかもと調べたけれど、さすがに
そんなものは見つかりません。
毎週火曜日はウォーキングの途中で見かけた雑草を取り上げています。
今週は、 ナデシコ科 ハコベ属 ウシハコベ です。
ハコベと言えば春の七草ですが、こちらは夏の盛りにもよく見る草。
先日も森林公園の歩道脇にまとまって生えているのを見つけました。
<茎は地を這ってから斜上し葉は縁が波打ち先端が尖る。
白い5枚の花弁は深裂し10枚に見え柱頭は5本ある。>(身近な雑草300 より)
大抵の図鑑にはこう続きます。
「大きいので名前に牛が付いた」
このひと言がウシに拘る切っ掛けになりました。
一般にハコベと呼ばれるミドリハコベは大きなものでもせいぜい草丈20cm、
それに比べてウシが付くこちらは遥かに巨大な50cm丈。
倍も違えば牛の冠を付けたくなるのも道理です。
では「ウシ」がつく草は全てが大型の種類なのか、これも気になります。
草本では9種類程ある様ですが、よく名を聞くものをあげてみましょう。
カヤツリグサ科のウシクグは大きなものでは70cmなのでカヤツリグサを
遥かに凌ぎます。
エンバクの別称のあるウシムギは150cm程にも伸びるというのでこちらも
巨大サイズ。
ウシノヒタイとも呼ばれるミゾソバも高さは80cm。
いずれも背の高い種類なので「ウシ」が付くのは納得です。
馬の場合は
図鑑によっては「ウシハコベは史前帰化植物」の表記も見られます。
<史前帰化植物には3つの系統がある。
①稲作に伴って伝播した植物群で、イネの刈り取り前に実を稔らせ種子を
散布する。
②麦類の栽培伝来とともにやってきたもので、里山の春を彩る植物の多くはこれ。
③中国から有用植物として持ち込まれたもの。>(岡山理科大 より)
ウシハコベは②に属するそうで。
ちなみに同グループにはナズナ、カタバミ、スベリヒユ、オオバコ、ツユクサ、
ヤエムグラ、ハハコグサ、カラスムギなどお馴染みの面々が集っています。
次はウシハコベの字面からの連想。
自ずと「牛運べ」が浮かんできます。
今でこそ運搬に従事する牛など見かけませんが、江戸時代には最高の運送手段。
山国に重い塩を運ぶのに大いに役立ったと言います。
<牛は物を運ぶのに非常に優れた動物。
一頭に塩二俵を乗せて細い山道を登った。>(和楽 より)
牛が運んでくれた塩が信州のご先祖様の暮らしの支えになりました。
牛さんありがとう。
最後に「牛運べ」があるなら「馬走れ」もあるかもと調べたけれど、さすがに
そんなものは見つかりません。