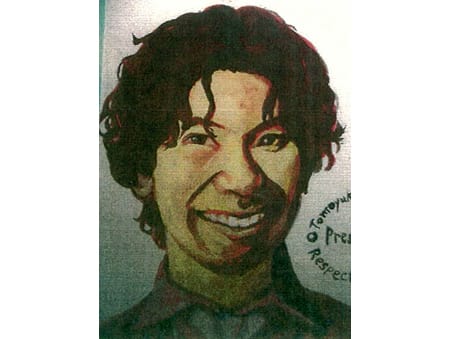
11月10日、宮崎商工会議所主催で宮日会館10階第会議室にて「お金をかけずに、お店を長く続けるコツ」と題して、経営コンサルタントの高橋幸司氏(有限会社高橋幸司の事務所 代表取締役社長)の講演会に参加した。150名収容の会場はほぼ満員で、若い女性が多かったことがとても印象的だった。
具体例を交えたわかりやすい話が多く、活用できるアイデアや考え方など参考となりました。
多くの事を学びましたが、主なものを5つにまとめてみました。 物事は相対的で、中心にいる事業主の考え方や動きが周り(スタッフ)の鏡となる。
物事は相対的で、中心にいる事業主の考え方や動きが周り(スタッフ)の鏡となる。
ちらしや売り方などを単純に前回通りにすると、スタッフも「売り方」も「考え方」も前と同じでいいと思ってしまう。スタッフにも顧客にもその「想い」や「熱」伝わる(伝染する)。それでは、客にもスタッフのこころの「琴線」に触れないことを自覚する。
それは即ち、「売り飽きること」とも言われ、手抜きの気配(効率を優先する)を感じて、結果的に、ビジネスがマンネリに陥る。まずは、ゆとりをつくり、準備し内容を豊かにしていくことが大切である。 お客様の為と言うより、お客の立場で考えよう
お客様の為と言うより、お客の立場で考えよう
よく「お客の為」にと言う言葉を聞くが、「お客の為」に・・は、ほぼ「主観的」な要素が多く、お客の立場では「客観性」が強い。このモノの見方は、顧客サービスへの考え方の基本と考え方となるため、一度こころに落とし込む必要がある。あらゆる場面で自問自答し、顧客の立場とは何かをゼロから考えてみることが必要である。 初めての店で購入体験するユーザー(初心者)は、価値ある顧客である。
初めての店で購入体験するユーザー(初心者)は、価値ある顧客である。
初めて買った店は印象に残り(感傷的なものも含まれている)比較的、その店に好印象を持ちやすい。
初めての顧客は、商品の良さをわかったもらう事からスタートする為、売りにくく比較的商品単価が低いからどこも敬遠しがち・・が、ファンにすれば口コミ顧客となったり、重要な顧客ににつながる
例えば、宝石店では「PT」は、プラチナの意味だが、プラチナと書かれていない店が多い。初めての人にはわかりずらい。
すべての顧客を初心者と思って店の対応(売り場・紙面・接客)をわかりやすく・徹頭徹尾行う。そうする事で、初心者は親切な店に移っている。 商いの基本は、「お客の立場で喜ぶものを、面倒臭がらず、先送りせずに、真剣に、丁寧にやりやすいところから実行すること」
商いの基本は、「お客の立場で喜ぶものを、面倒臭がらず、先送りせずに、真剣に、丁寧にやりやすいところから実行すること」
丁寧にするには、時間と労力が必要。その為には、早めに仕事に取りかかり(時間をつくる)熟度を上げることが重要。早く始める価値とはそこにある。
そこを突破口にして、ちいさな成功体験を積み重ねて自信をつけていく(例えば、先代がやっていたことなど・・地味だが他店がやりにくこと、敬遠していることを実施)そこに勝率が上がる。 「販促力(人や商品の存在価値をわかりやすく伝えること)×売り場力×商品力×接遇力」の四位一体の店づくりが価値負けしない店。
「販促力(人や商品の存在価値をわかりやすく伝えること)×売り場力×商品力×接遇力」の四位一体の店づくりが価値負けしない店。
どれかがゼロで店数は上がらない。
価値ある店とは「存在価値」のこと。あなたの店が無いと困ってしまうというお客がどれ位いるかということ。 ※他の切り口でも考えて見ることが大切である。

48歳を過ぎた頃から物忘れが多くなったが、年齢的なことだと半分諦め気味だった。
しかし、仕事上の些細なミスが物忘れが原因だと感じ、何かを変えなければ・・と考えていた。
色々と考えたが、続けられそうな読書を選んだ。もちろん、それで解決するとは思わなかったが、何かを始めなければという焦りがあった。
毎朝40分程度、読書を始めた。一ヶ月後、ふと思った、「折角読んだ本、ポイントをレポート用紙にまとめておけばいつでも活用できるのでは・・・」と考えた。
実は、これが物忘れ対策に大きな効果があった。
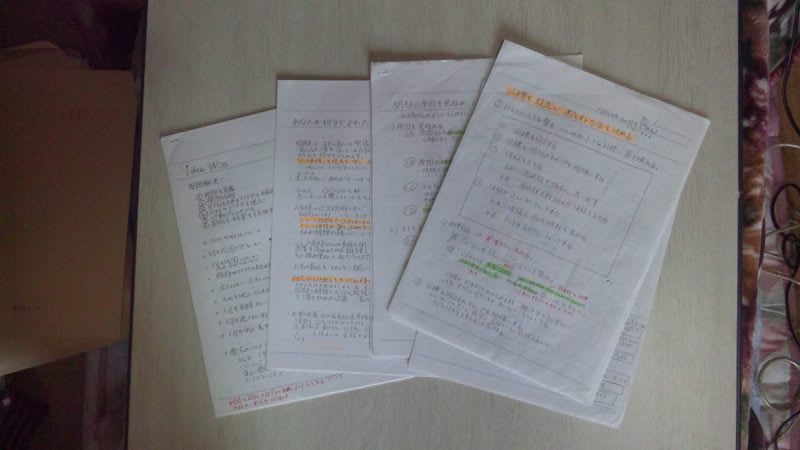
気付いてみると物忘れも以前より少なくなり、忘れても比較的早く気付くようになった。
たとえば、急いでいる時など"車のカギを忘れたこと"を車の前で気付いたが、最近は家のドアを開ける時点で気づくようになった。(忘れるのは変わりませんが(*^_^*))
「指を使うと、脳細胞が刺激されて脳が活性化する」というさまざまな研究が、国内外の脳科学者から発表されている。
「好奇心を持つこと」、「考えること」、「指を使うこと」が大切ではないかと言われている。
参考>>>頭脳向上委員会
ちなみに本は、県立図書館、市図書館、町の図書館で、1度に5冊、多いところで7冊借りられる。
図書館で借りるメリットは、「たくさんの本」や「資料」を「気軽」に「無料」で「簡単に返却」できるところだ。
返却は、開館日は窓口返却だが、夜間などは、図書館にある専用BOXに投函するだけ、レンタルショップと同じだ。
普段、読むこともないジャンルの本も無料なので、躊躇なく借りることができ、面白い本・楽しい本と出合う確率も高い。
これまでの読書で、「本1冊で3つのことを学び気付けば儲けもの、そしてその学びを具体的に活かす意識を持つ」ことも副産物だ。









