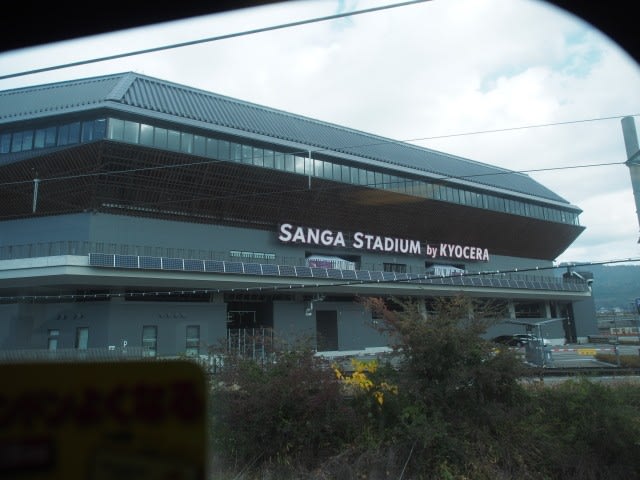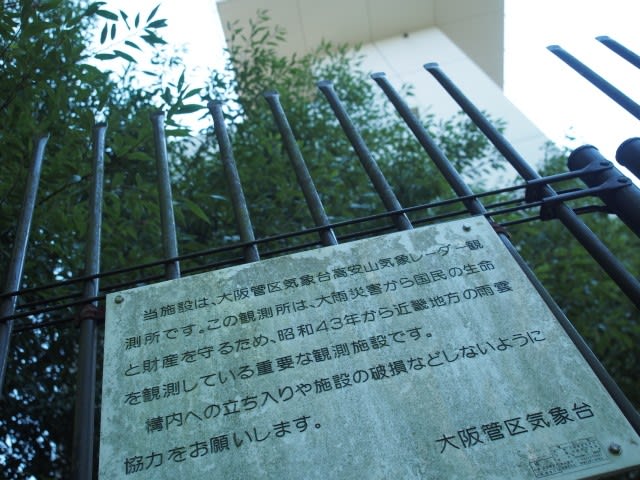翌朝、まだ暗い時間から起きだす人がいた。
山頂にご来光を見に行くようだ。
今日って雨ではないのか?
私はようやく眠りにつけたこの眠気を逃すまいと、そのまま寝続けた。
次に目を覚ました時、周りは明るくなっていて夜は明けたようだ。

今度は起き出して外に出てみると、雨は降っておらず、それどころか青空が覗いていた。
朝食までの時間、しばし辺りを散策。
山頂から戻ってくる人がちらほら。
ご来光は拝めたのだろうか。

食堂へ行って窓際の席に座り、外の様子を眺めながら朝食を食べた。
雨が降り出す気配はなく、別山もスッキリと見える。
なんだ雨降らないじゃない。
雨ならさっさと下山するだけだなと思っていたが、晴れるとなると話は別だ。
少し遠回りして、南竜ヶ馬場に寄り道して下りよう。

食後、荷物を詰めなおして出発。
展望歩道の方へ向かう。
こちらは主要道から外れているからか他に誰も歩いていない。
登山道に残っていた新しい靴跡もいつのまにかなくなり、静かな山歩きが楽しめた。
展望歩道はアルプスが望めるらしいのだが、そこまでお天気はよろしくなく、遠い山は雲の向こうだ。
しかし高山植物は種類多く咲いていて、手近の眺めは非常によろしい。

道は下り基調で楽々と歩く。
遠くに南竜ヶ馬場の盆地と山小屋が見えた。
8時半近くになると昨日と同じく山の谷間から雲が湧き始めた。
空もまた雲が広がって、白くなった。
それでも雨が降る気配はない明るさ。
南竜ヶ馬場は平たい笹原で、木道が敷かれていた。

南竜ヶ馬場にも山小屋がある。
まだ10時だが朝食も早かった事だし昼食にしようと山荘の扉を開けると、小屋の人が外に出ようとするところだった。
食事したいと告げると宿泊のみで食事の提供はしていないとのこと。
ありゃそうなのか。
午前中で下山するつもりだったからお弁当を注文しなかったんだが、どうするか。
仕方ないので小屋前のベンチを借りて、行動食のビスケットやら洋菓子の残りを昼食代わりにした。

そこからは南竜道という道を行き、上りに使った砂防新道の途中に合流する。
下りは観光新道を使いたかったのだがその為には標高にして200mほど登り返さなければならない。
左膝が痛くなってきたし、途中分岐するエコーラインの急坂を見て、そんな気持ちは萎えてしまった。
同じ道でつまらないが、行きと同じ砂防新道で下ろう。

砂防新道に入ってしばらく下ると、甚之助避難小屋に到着。
休憩だ、休憩。
辺りはいつのまにかガスの只中で、行きに見えた景色は白いベールの向こう。
日は陰っていてとても涼しい。
そうだよ、時間はあるんだし、せっかく山の中にいるんだから急いで下りる必要はない。
ここでゆっくりしていこうとベンチの上に横になった。
涼しくて気持ちいいし、睡眠不足だからうとうとした。

あれ?顔に水滴か?
目を開けると周りはさっきと同じ景色。
気のせいと思い再度横になったら霧雨な感じの水滴が再びあたった。
そんな暗さではないのだが、とうとう雨が降り出したようだ。
こうなるとゆっくりしている気分でなくなる。
仕方なくザックにカバーをかけて出発。
雨は徐々に徐々に粒が大きくなる感じだ。
風は無いし両手はフリーで歩ける道なので、カッパは着ずに傘を差して歩く。

下るに従い雨は強まったが、ずっとしとしと降る感じだった。
写真を撮る回数が減ったからか脚の疲れが抜けなくなって、雨降ると休む気が失せるのでずーっと歩き通したら、登山口の吊橋を渡る時には脚が痛くて仕方なくなってしまった。
登山センターの手前に鳥居があって、その脇の石碑に白山奥宮境内地とあった。
行きは鳥居しか気づかなかったな。
山頂だけかと思っていたが、登山口から全てが境内だったのね。
山体が御神体だ。

車まではまだ歩かねばならない。
駐車場までフラフラになって歩いた。
今度こそ到着。
荷物を積んでシートに座り、ようやくひと息。
ここでも細かな雨が降り続いたようで、フロントガラスには大きく育った水滴が均等に乗っかっていた。