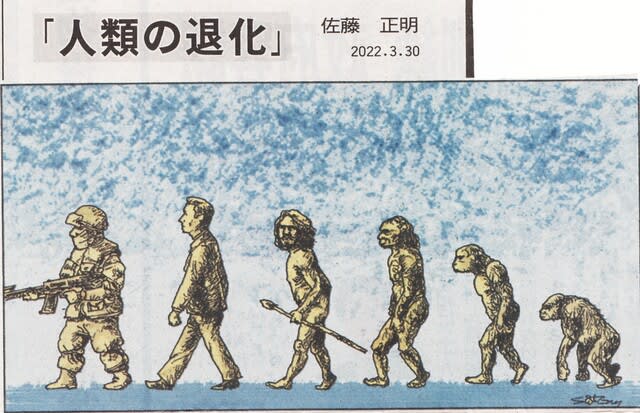フランシスコ教皇とウクライナ戦争(2)
―“白旗”発言への賛否両論―
前回は、佐藤優氏と手嶋龍一氏による、ローマ教皇の“白旗”発言に対する評価を説明しました
(BSFUJI 3月12日の『プライムニュース』)。
この二人は、教皇の発言は、少なくともカトリック教徒が多いウクライナ西部のガリツィア地
方の住民に対しては、”白旗“すなわち「停戦」へ向かうことへの影響がある、との立場でした。
それにたいして今回取り上げるのは、翌3月13日放送分についてです。ゲスト・コメンテー
タは、岡部芳彦氏(神戸学院大学教授。ウクライナ研究会会長・ロシア・ウクライナ協会常任
理事)と遠藤亮介氏(産経新聞外信部次長・論説委員)、そしてもう一人東郷和彦氏(元外務
省欧亜局長、在ロシア大使館次席公使を経て、静岡県立大学客員教授)もゲスト・コメンテー
タとして加わっています。
遠藤氏は2006年から11年8か月、ずっとモスクワ支局長を務めたジャーナリストで、2022
年のロシアによるウクライナ侵攻以後、しばしばウクライナを訪問しています。
岡部氏も遠藤氏も親ウクライナの立場を鮮明にしています。
今回の放送分では、フランシスコ教皇の発言は、あまり多くの時間を占めていませんが、それ
でも、前回の佐藤・手嶋氏のコメントを合わせて考えると、非常に参考になります。
まず、教皇の“白旗”発言に対して岡部氏は、まともに受け取る必要がない、といったコメント
でした。
岡部氏によると、フランシスコ教皇は“失言王”で、これまでも失言が限りなくある、今回の
“白旗”発言も、その失言の一つだ、と切って捨てています。
彼が挙げた“失言”とは、たとえば今回の戦争で最も残忍なのはロシアの少数民族のブリアート
人だ、と言ったようですが、これは人種差別だ、と岡部氏は述べています。
また、10年ほど前に、教皇は教会の出世主義は伝染病のようなものだ、と言って、伝染病
患者から批判を受けた、という事例も語っています。
しかも、今回の発言はテレビのインタビューなので、公式声明かどうかも分からない。
岡部氏は、知り合いのウクライナの人達からも、“教皇、何を言っているんだ”、という怒りの
のメッセージがきていると述べています。
そして、岡部氏によれば、ウクライナのカトリック教会(正確には「東方典礼カトリック教
会」)は、教皇の発言に対して、ウクライナはロシアに屈伏することはないし、これまで通
り今のまま進んでいく、との声明を出しているそうです。
遠藤氏は、教皇の発言に対して、どのように感じたか、反論は、と司会者から聞かれて、
“ウクライナからはいろいろ反論は出ていますが・・・う~~ん。私も岡部先生と同じように
に受け止めているんですけれどね”、と言って具体的にはこの件についての見解はありません
でした。
東郷氏は、これまで一刻も早く停戦、これが私が考えるべき、そして多くの人に考えてもら
いことだという立場を述べました。
東郷氏は、教皇の、“白旗”発言の意図は、白旗を掲げて停戦するためには交渉しなければなら
ない、そのためにはイニシアチブが必要だ“ということにある。東郷氏は、教皇の発言はその
イニシアチブの一つなのだ、という解釈のようです。
そして東郷氏は、“非常に僭越な言い方をさせていただければ(教皇の発言は)、“我が意を
得たり”という気持ちですね、と述べました。
司会者から、“ということは今回のフランシスコ教皇の発言は結果的にロシアの利害に沿った
発言になるんですね”、との問いかけに東郷氏は、“今の時点のプーチン氏の立場は、タッカー
・カールソン氏とのインタビュー(2月8日に公開)で繰り返し繰り返し言っているのは、
できるだけ早く停戦なんですね”、そして、その手掛かりとして2022年3月29日(ロシアの
和平案―筆者注)があるじゃないか“ということなんです、と答えています。
続いて東郷氏は、この時プーチンの“最も早く停戦”という言葉と、今回の教皇の発言は機を一
にしていると思うので、できるだけ皆そのことに注目していただいて、できるだけ早く交渉が
始まって欲しいとい、との立場を述べました。
ガリツィア地方はカソリック教徒の多い地域であり、その地域のカソリック教徒に向けて、
“今こそ白旗を掲げて交渉に入るべきだというのは、カソリックの教皇から主要なメッセージ
が来ていると考えるべきだと思う”、と述べています。
しかもこの地域が“ウクライナで最も強硬な主戦派ですから、教皇様がこのようなメッセージ
をたしたということはとても重要なことだと思っています”、というのが東郷氏の評価です。
さて、以上の議論は、できるだけ忠実にコメンテータの言い分の重要な部分を要約したもの
ですが、大きく分けると、
教皇の発言は影響を与え得るという立場と(佐藤・手嶋、東郷)、教皇の発言はまともに受け
取るに値しない、“失言”にすぎない、だから影響はない、との立場に分かれます。
確かに、今回の教皇の発言において“白旗”という言葉が適切であったかどうか多少の疑問があ
ります。しかし、仮に今回の“白旗”発言が“失言”だとしても、そう簡単に意味がない、と片付
けてしまうことには疑問を感じます。
教皇の真意はあくまでも、人の命を大切にすること、そのためにまずは停戦に向かって努力す
べきだ、という点にあります。3月の“白旗”発言に先立って、教皇はロシアの侵攻2年にあた
り、日曜の講話で次のように語りました(注1)。
多くの犠牲者と負傷者が生まれ、破壊と苦痛が起こり、涙が流されている。この戦争
は恐ろしく長期化し、終わりが見えない。地域を破壊するのみならず、憎悪と恐怖の
世界的な波を引き起こすものだ。
公正で永続的な平和の模索に向け、外交的解決の環境を整えるためにほんの少しの人
間らしさを見いだしてほ しい。
私は、教皇の発言が重要な転換点になる可能性があると思っています。
その理由の一つは、今回の教皇の発言は、これまでのいくつかの“失言”と違って、一国の運命
がかかっている重大問題なので、果たして、これまでのいくつかの”失言“と同列に扱うことに
は問題があるからです。
二つは、前回の記事で書いたように、教皇とバチカンには世界からあらゆる情報が集められ、
バチカンの国務省はそれらを慎重に分析した結果、このままウクライナが抵抗を続け戦争が長
引けば、死者が増えるだけなので、早く停戦に向かうべきだ、との結論に達したものと思われ
るからです。
手嶋氏の言葉を借りると、教皇の発言は軽はずみな”失言“などではなく、”練りに練った“うえ
で発せられたメッセージの可能性が多分にあります。
三つは、最近ではヨーロッパのNATO諸国の中には、ウクライナとの二国間の安全保障を締結
する動きがある一方、他方で、ウクライナ戦争への支援をいつまで、どこまで続けるのかにつ
いて再検討する意見も無視しえないからです。
四つは、世界の目は、日々死者が増えてゆくこの戦争をこのまま続けさせてはいけない、とい
う国際世論が徐々に高まっているからです。
教皇の発言は一刻も早く停戦し、命が失われることを止めようというメッセージですから、一
部のNATO諸国やそれ以外の多くの国が停戦を後押しする一つのきっかけになる可能性は十分
あります。
その時、佐藤優氏が言うように、教皇自身、あるいはバチカンがイニシアチブをとって停戦の
仲介の労をとることは決して荒唐無稽の空論ではないと思います。
私が最も恐れるのは、このまま戦争がずるずると続き、そこで尊い命が失われ続けることです。
言うまでもなくウクライナからすれば、現状で停戦となれば、国土の20%ほどをロシアに割
譲することになり、とうてい受け入れられないでしょう。
しかも、NATO諸国はますますウクライナへの軍事支援を強化すると公約しており、フラン
スのマクロン大統領のように、NATOは部隊をウクライナに送ることも排除すべきではない、
との勇ましい発言もあります。
こうなるとウクライナは、最後の1人まで戦うという方向に自らを追い込んでゆかざるを得な
くなり、それは双方にさらに多くの命が失われることを意味します。
NATO諸国は、ウクライナへの軍事支援と同時に、停戦への道筋を探る努力もしてくるべき
だったと思います。
いずれにしても、この戦争はいつかは終わらせなければならないし、その時、教皇は、中立的
な立場から物が言える仲介者の一人になり得ます。
その点で今回のフランシスコ教皇の発言は、後々、重要な意味をもってくると思います。
さて、フランシスコ教皇の停戦提案に対して日本では、一部のウェッブ・サイトで多少の扱い
はありましたが、全般的にほとんど話題にもなりませんでした(注1)。
日本においては、カトリック教の宗教的権威の影響力は無視し得るほどですから当然といえば
当然ですが、それでもこの戦争の停戦に対して何ができるかを真剣に考える必要があるのでは
ないでしょうか?
(注1)REUTERS (2024年2月26日午後 2:51 GMT+925日前更新)
https://jp.reuters.com/world/ukraine/EERHR46CHBKTRDWZ3VT2F7OKS4-2024-02-26/
―“白旗”発言への賛否両論―
前回は、佐藤優氏と手嶋龍一氏による、ローマ教皇の“白旗”発言に対する評価を説明しました
(BSFUJI 3月12日の『プライムニュース』)。
この二人は、教皇の発言は、少なくともカトリック教徒が多いウクライナ西部のガリツィア地
方の住民に対しては、”白旗“すなわち「停戦」へ向かうことへの影響がある、との立場でした。
それにたいして今回取り上げるのは、翌3月13日放送分についてです。ゲスト・コメンテー
タは、岡部芳彦氏(神戸学院大学教授。ウクライナ研究会会長・ロシア・ウクライナ協会常任
理事)と遠藤亮介氏(産経新聞外信部次長・論説委員)、そしてもう一人東郷和彦氏(元外務
省欧亜局長、在ロシア大使館次席公使を経て、静岡県立大学客員教授)もゲスト・コメンテー
タとして加わっています。
遠藤氏は2006年から11年8か月、ずっとモスクワ支局長を務めたジャーナリストで、2022
年のロシアによるウクライナ侵攻以後、しばしばウクライナを訪問しています。
岡部氏も遠藤氏も親ウクライナの立場を鮮明にしています。
今回の放送分では、フランシスコ教皇の発言は、あまり多くの時間を占めていませんが、それ
でも、前回の佐藤・手嶋氏のコメントを合わせて考えると、非常に参考になります。
まず、教皇の“白旗”発言に対して岡部氏は、まともに受け取る必要がない、といったコメント
でした。
岡部氏によると、フランシスコ教皇は“失言王”で、これまでも失言が限りなくある、今回の
“白旗”発言も、その失言の一つだ、と切って捨てています。
彼が挙げた“失言”とは、たとえば今回の戦争で最も残忍なのはロシアの少数民族のブリアート
人だ、と言ったようですが、これは人種差別だ、と岡部氏は述べています。
また、10年ほど前に、教皇は教会の出世主義は伝染病のようなものだ、と言って、伝染病
患者から批判を受けた、という事例も語っています。
しかも、今回の発言はテレビのインタビューなので、公式声明かどうかも分からない。
岡部氏は、知り合いのウクライナの人達からも、“教皇、何を言っているんだ”、という怒りの
のメッセージがきていると述べています。
そして、岡部氏によれば、ウクライナのカトリック教会(正確には「東方典礼カトリック教
会」)は、教皇の発言に対して、ウクライナはロシアに屈伏することはないし、これまで通
り今のまま進んでいく、との声明を出しているそうです。
遠藤氏は、教皇の発言に対して、どのように感じたか、反論は、と司会者から聞かれて、
“ウクライナからはいろいろ反論は出ていますが・・・う~~ん。私も岡部先生と同じように
に受け止めているんですけれどね”、と言って具体的にはこの件についての見解はありません
でした。
東郷氏は、これまで一刻も早く停戦、これが私が考えるべき、そして多くの人に考えてもら
いことだという立場を述べました。
東郷氏は、教皇の、“白旗”発言の意図は、白旗を掲げて停戦するためには交渉しなければなら
ない、そのためにはイニシアチブが必要だ“ということにある。東郷氏は、教皇の発言はその
イニシアチブの一つなのだ、という解釈のようです。
そして東郷氏は、“非常に僭越な言い方をさせていただければ(教皇の発言は)、“我が意を
得たり”という気持ちですね、と述べました。
司会者から、“ということは今回のフランシスコ教皇の発言は結果的にロシアの利害に沿った
発言になるんですね”、との問いかけに東郷氏は、“今の時点のプーチン氏の立場は、タッカー
・カールソン氏とのインタビュー(2月8日に公開)で繰り返し繰り返し言っているのは、
できるだけ早く停戦なんですね”、そして、その手掛かりとして2022年3月29日(ロシアの
和平案―筆者注)があるじゃないか“ということなんです、と答えています。
続いて東郷氏は、この時プーチンの“最も早く停戦”という言葉と、今回の教皇の発言は機を一
にしていると思うので、できるだけ皆そのことに注目していただいて、できるだけ早く交渉が
始まって欲しいとい、との立場を述べました。
ガリツィア地方はカソリック教徒の多い地域であり、その地域のカソリック教徒に向けて、
“今こそ白旗を掲げて交渉に入るべきだというのは、カソリックの教皇から主要なメッセージ
が来ていると考えるべきだと思う”、と述べています。
しかもこの地域が“ウクライナで最も強硬な主戦派ですから、教皇様がこのようなメッセージ
をたしたということはとても重要なことだと思っています”、というのが東郷氏の評価です。
さて、以上の議論は、できるだけ忠実にコメンテータの言い分の重要な部分を要約したもの
ですが、大きく分けると、
教皇の発言は影響を与え得るという立場と(佐藤・手嶋、東郷)、教皇の発言はまともに受け
取るに値しない、“失言”にすぎない、だから影響はない、との立場に分かれます。
確かに、今回の教皇の発言において“白旗”という言葉が適切であったかどうか多少の疑問があ
ります。しかし、仮に今回の“白旗”発言が“失言”だとしても、そう簡単に意味がない、と片付
けてしまうことには疑問を感じます。
教皇の真意はあくまでも、人の命を大切にすること、そのためにまずは停戦に向かって努力す
べきだ、という点にあります。3月の“白旗”発言に先立って、教皇はロシアの侵攻2年にあた
り、日曜の講話で次のように語りました(注1)。
多くの犠牲者と負傷者が生まれ、破壊と苦痛が起こり、涙が流されている。この戦争
は恐ろしく長期化し、終わりが見えない。地域を破壊するのみならず、憎悪と恐怖の
世界的な波を引き起こすものだ。
公正で永続的な平和の模索に向け、外交的解決の環境を整えるためにほんの少しの人
間らしさを見いだしてほ しい。
私は、教皇の発言が重要な転換点になる可能性があると思っています。
その理由の一つは、今回の教皇の発言は、これまでのいくつかの“失言”と違って、一国の運命
がかかっている重大問題なので、果たして、これまでのいくつかの”失言“と同列に扱うことに
は問題があるからです。
二つは、前回の記事で書いたように、教皇とバチカンには世界からあらゆる情報が集められ、
バチカンの国務省はそれらを慎重に分析した結果、このままウクライナが抵抗を続け戦争が長
引けば、死者が増えるだけなので、早く停戦に向かうべきだ、との結論に達したものと思われ
るからです。
手嶋氏の言葉を借りると、教皇の発言は軽はずみな”失言“などではなく、”練りに練った“うえ
で発せられたメッセージの可能性が多分にあります。
三つは、最近ではヨーロッパのNATO諸国の中には、ウクライナとの二国間の安全保障を締結
する動きがある一方、他方で、ウクライナ戦争への支援をいつまで、どこまで続けるのかにつ
いて再検討する意見も無視しえないからです。
四つは、世界の目は、日々死者が増えてゆくこの戦争をこのまま続けさせてはいけない、とい
う国際世論が徐々に高まっているからです。
教皇の発言は一刻も早く停戦し、命が失われることを止めようというメッセージですから、一
部のNATO諸国やそれ以外の多くの国が停戦を後押しする一つのきっかけになる可能性は十分
あります。
その時、佐藤優氏が言うように、教皇自身、あるいはバチカンがイニシアチブをとって停戦の
仲介の労をとることは決して荒唐無稽の空論ではないと思います。
私が最も恐れるのは、このまま戦争がずるずると続き、そこで尊い命が失われ続けることです。
言うまでもなくウクライナからすれば、現状で停戦となれば、国土の20%ほどをロシアに割
譲することになり、とうてい受け入れられないでしょう。
しかも、NATO諸国はますますウクライナへの軍事支援を強化すると公約しており、フラン
スのマクロン大統領のように、NATOは部隊をウクライナに送ることも排除すべきではない、
との勇ましい発言もあります。
こうなるとウクライナは、最後の1人まで戦うという方向に自らを追い込んでゆかざるを得な
くなり、それは双方にさらに多くの命が失われることを意味します。
NATO諸国は、ウクライナへの軍事支援と同時に、停戦への道筋を探る努力もしてくるべき
だったと思います。
いずれにしても、この戦争はいつかは終わらせなければならないし、その時、教皇は、中立的
な立場から物が言える仲介者の一人になり得ます。
その点で今回のフランシスコ教皇の発言は、後々、重要な意味をもってくると思います。
さて、フランシスコ教皇の停戦提案に対して日本では、一部のウェッブ・サイトで多少の扱い
はありましたが、全般的にほとんど話題にもなりませんでした(注1)。
日本においては、カトリック教の宗教的権威の影響力は無視し得るほどですから当然といえば
当然ですが、それでもこの戦争の停戦に対して何ができるかを真剣に考える必要があるのでは
ないでしょうか?
(注1)REUTERS (2024年2月26日午後 2:51 GMT+925日前更新)
https://jp.reuters.com/world/ukraine/EERHR46CHBKTRDWZ3VT2F7OKS4-2024-02-26/