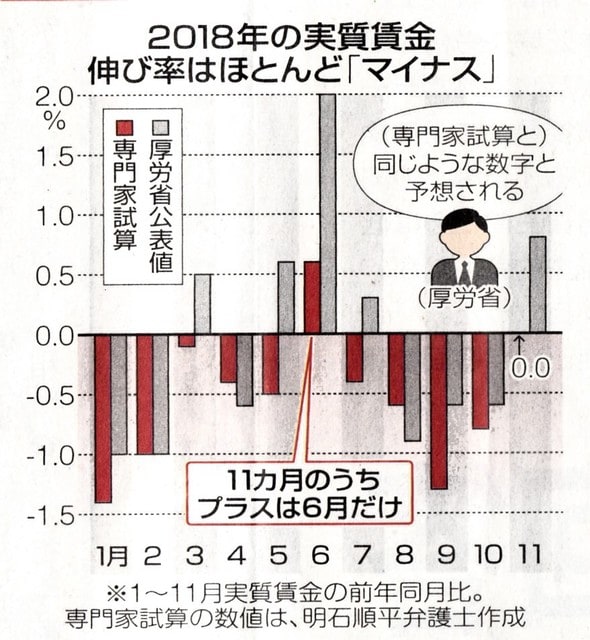日本学術会議問題に見る菅首相の本性(1)
―「菅義偉という人物の教養のレベルが露見した」―
日本学術会議(以下、「会議」と略す)が推薦した105人の新規会員のうち、6人が菅首相
によって拒否されたことが、今月初めに明らかになりました。
これにたいして、当事者である「会議」はいうまでもなく、多くの識者から抗議の声が上がり
ました。抗議の理由は後で述べるとして、まず、日本学術会議とは、どのようにして生まれ、
どんな法的な根拠をもち、何を目的とするのか、という基本を押さえておく必要があります。
上記の点を理解すると、今回6人の任命を拒否した菅首相は、「会議」設立の趣旨と経緯を無
視し、科学や学問にたいする敬意も理解がいかに希薄であるかが明になります。
まず、設立の経緯ですが、日本学術会議は昭和24年(1949)に設立された日本の科学者
を代表する機関で、その趣旨は発足時の「決意表明」に述べられています(注1)。
くわしくは、「決意表明」をみていただくとして、その中でも特に重要な部分は、「これまで
わが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し」という個所で、この具体的内容はは
発足の翌年1950と1967の声明に、より明確に示されています。
1950年に「会議」が出した宣言には、次のように書かれています。
われわれは、文化国家の建設者として、はたまた世界平和の使として、再び戦争の惨
禍が到来せざるよう切望するとともに、さきの声明を実現し、科学者としての節操を
守るためにも、戦争を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わないというわれわ
れの固い決意を表明する。(注2)
すなわち、決意表明の「反省」とは、戦前、科学者が戦争へ協力してきたことへの反省を指し、
二度出された声明は今後、軍事目的の研究を行わないことを宣言したものです。
この姿勢は、「会議」の法的根拠となる現行の「日本学術会議法」にもはっきり表れています。
まず、「日本学術会議法」の条文の前に、「前文」(元の法律には「前文」の文字はありませ
んが)に相当する文章があり、そこで、「会議」の理念が述べられています。
「日本学術会議法」は、一種の個別法ではありますが、その理念から説き起こしている点が、
「家族法」や「道路交通法」のような他の個別法と異なり、むしろ憲法に近い構成になってい
ます。
何よりこの法律は、「会議」が独立した特別な組織であることを示しています。以下に、「前
文」に相当する部分を示しておきます。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の
下に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の
進歩に寄与する ことを使命とし、ここに設立される。
この部分からもうかがえるように、科学が文化国家の基礎であることの確信に立って、わが国
の平和的復興だけでなく、人類社会や世界の学会と提携の福祉に貢献する、という崇高な理念
がこの会議を支えているのです。次に、「会議」の設立及び目的につては
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。 (平一一法一〇二・平一六法二九・一部
改正)
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を 図
り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
そして、重要な第二章の「職務および権限」では
第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
と定めている。つまり、「会議」の最も重要な性格は、その「独立性」あるいは「自律性」であ
ることを、謳っています。この「独立して」という部分は、単に個人が己の心情にしたがって、
という意味に留まらず、「日本学術会議」として、政治権力や軍部や企業などの干渉を受けずに、
という強い主張が込められているのです。
この学術の独立性こそが、仮にも日本が文化国家を名乗るならば、尊重されるべき最も重要な点
なのです。
それでは「会議」の具体的な組織の構成その他をみてみましょう。
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ れを
組織する。
第二項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
その第十七条は、「推薦」に関して、「 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研
究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内
閣総理大臣に推薦する ものとする」と規定しています。(平成一六法二九・全改)(注3)
なお、補足しておくと、「会議」は210人の「会員」の他に2000人ほどの「連携会員」が
おり、かれらは「会員」から選ばれて、会議の会長により任命されます。任期はいずれも6年で
3年毎に半数が入れ替わります
一般会員も連携会員(非常勤ではありますが)特別国家公務員という地位が与えられ、一般会員
と同様、日当と経費が支払われます。
以上を念頭において、改めて菅内閣が、6人の任命を拒否した問題を考えてみましょう。
まず、「会議」が、菅首相による任命拒否に対して強く反発していますが、それはなぜなのでし
ょうか。
学会側の反発の根拠は幾つかあります。第一は、1983年11月、中曽根首相(当時)が、国
会で、「政府が行うのは形式的任命」「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」
といった政府答弁があり、政府は「会議」が推薦した新会員を拒否することはない、と明言し、
それは公文書として残っていることです。
第二は、もし、「会議」が推薦した人の任命を拒否するなら、その理由をはっきり説明すべきだ、
という点です。これまで、政府側は誰一人、理由を明らかにしていません。
第三は、安倍政権の時から、一般の研究助成予算は徐々に減っているのに、軍事研究へはますま
す多額の予算をつける政策をとっていることに対する「会議」としての危機感があります。
具体的には、2017年には、軍事応用できる基礎研究に費用を助成する防衛省の「安全保障技術研
究推進制度」の予算を大幅に増やしている、という実態があります。
この制度のもとで、2015年度の予算は3億円だったものが、16年度には六億円、そして17年
度には110億円と激増しました。
これにたいして「会議」は17年、50年ぶりに軍事研究に関する声明を発表し、その中で「政
府による介入が著しく、問題が多い」と批判しました。
つまり、政府に協力して軍事研究をすれば研究費をつけてやるという、お金を通じて研究に介入
することを全面的に推進してきています。
これは、「会議」の根底にある、「学問の自由と独立」、そして軍事研究を絶対に行わない、と
いう発足の理由となった理念と真正面からぶつかり、これらの点は絶対に譲れないでしょう。
以上の背景を考えると、6人の任命がなぜ拒否されたのかが、浮かび上がってきます。
任命を拒否された6人とは、①宇野重規教授(東京大学 政治思想史)、②芦名定道教授(京都
大学 キリスト教学)、③岡田正則教授(早稲田大学大学院 行政法)、④小沢隆一教授(東京
慈恵会医科大学 憲法学)、⑤加藤陽子教授(東京大学大学院 日本近現代史)、⑥松宮孝明教
授(立命館大学大学院 刑事法)です。
この6人は、上記の順に、①特定秘密法を批判、②安保関連法に反対する学者の会等の賛同者、
③安保関連法に反対、④国会で安保関連法案について反対、⑤憲法学者でつくる「立憲デモクラ
シー」の呼び掛け人で改憲や特定秘密保護法に反対、⑥国会で「共謀罪」を「戦後最悪の治安立
法」と批判した、という背景があります。
一言でいえば、政府が強硬に推進してきた、これらの法律は「戦争への準備」という性格をもっ
ています。
これら拒否された人物と彼らの過去の言動を対応させれば、外形的には誰が見ても、そして、菅
首相をはじめ他の政府幹部が、どんな「理屈」をつけようが、拒否の背景に政府の施策に反対し
た学者を排除する意図があったとしか思えません。
「理由の説明もなく、到底承服できない。学問の自由への侵害ではないか」、もしそうでないな
ら、はっきりとした根拠を示すべきだ、もし、示せないなら拒否した6人を任命すべきだ、とい
うのが「会議」側の主張です。
任命を拒否した菅首相は、5日行われた内閣記者会によるインタビューで、ほとんどは官僚が書
いたと思われる文章を棒読みするだけでした。
そして、拒否の理由については「総合的、俯瞰的な活動を求めることになった。総合的、俯瞰的
な活動を確保する観点から、今回の任命についても判断した」「個別の人事に関するコメントは
控えたい」、とついに、本当の理由を一言も言っていません。
これ以後、政府側の答えには「総合的、俯瞰的」という言葉が、まるで「壊れたレコード」のよ
うに繰り返されました。
しかし、全体を通してみると、菅首相が、学問の自由とか独立、ということにほとんど関心がな
いことが分かります。
こうした首相の一連の言動をみて、静岡県の川勝平太知事は7日の定例会見で、「菅義偉という
人物の教養のレベルが露見した。『学問立国』である日本に泥を塗った行為。一刻も早く改めら
れたい」と強く反発しました。
川勝知事は早大の元教授(比較経済史)で、知事になる前は静岡文化芸術大の学長も務めた、い
わゆる「学者知事」です。川勝知事は6人が任命されなかったことを「極めておかしなこと」とし、
文部科学相や副総理が任命拒否を止めなかったことも「残念で、見識が問われる」と述べています
(注4)。
次回は、任命拒否の問題点を、さらにくわしく検討し、合わせて、この問題に対する内外の反応を
みてみます。
(注)
(注1)設立の際の声明は http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-01-s.pdf を参照。
(注2 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gunjianzen/index.html
(注3)http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf
(注4)『朝日新聞』デジタル版(2020年10月7日18時24分)
https://www.asahi.com/articles/ASNB761QMNB7UTPB00D.html?ref=mo r_mail_topix3_6
―「菅義偉という人物の教養のレベルが露見した」―
日本学術会議(以下、「会議」と略す)が推薦した105人の新規会員のうち、6人が菅首相
によって拒否されたことが、今月初めに明らかになりました。
これにたいして、当事者である「会議」はいうまでもなく、多くの識者から抗議の声が上がり
ました。抗議の理由は後で述べるとして、まず、日本学術会議とは、どのようにして生まれ、
どんな法的な根拠をもち、何を目的とするのか、という基本を押さえておく必要があります。
上記の点を理解すると、今回6人の任命を拒否した菅首相は、「会議」設立の趣旨と経緯を無
視し、科学や学問にたいする敬意も理解がいかに希薄であるかが明になります。
まず、設立の経緯ですが、日本学術会議は昭和24年(1949)に設立された日本の科学者
を代表する機関で、その趣旨は発足時の「決意表明」に述べられています(注1)。
くわしくは、「決意表明」をみていただくとして、その中でも特に重要な部分は、「これまで
わが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し」という個所で、この具体的内容はは
発足の翌年1950と1967の声明に、より明確に示されています。
1950年に「会議」が出した宣言には、次のように書かれています。
われわれは、文化国家の建設者として、はたまた世界平和の使として、再び戦争の惨
禍が到来せざるよう切望するとともに、さきの声明を実現し、科学者としての節操を
守るためにも、戦争を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わないというわれわ
れの固い決意を表明する。(注2)
すなわち、決意表明の「反省」とは、戦前、科学者が戦争へ協力してきたことへの反省を指し、
二度出された声明は今後、軍事目的の研究を行わないことを宣言したものです。
この姿勢は、「会議」の法的根拠となる現行の「日本学術会議法」にもはっきり表れています。
まず、「日本学術会議法」の条文の前に、「前文」(元の法律には「前文」の文字はありませ
んが)に相当する文章があり、そこで、「会議」の理念が述べられています。
「日本学術会議法」は、一種の個別法ではありますが、その理念から説き起こしている点が、
「家族法」や「道路交通法」のような他の個別法と異なり、むしろ憲法に近い構成になってい
ます。
何よりこの法律は、「会議」が独立した特別な組織であることを示しています。以下に、「前
文」に相当する部分を示しておきます。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の
下に、 わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の
進歩に寄与する ことを使命とし、ここに設立される。
この部分からもうかがえるように、科学が文化国家の基礎であることの確信に立って、わが国
の平和的復興だけでなく、人類社会や世界の学会と提携の福祉に貢献する、という崇高な理念
がこの会議を支えているのです。次に、「会議」の設立及び目的につては
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。 (平一一法一〇二・平一六法二九・一部
改正)
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を 図
り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
そして、重要な第二章の「職務および権限」では
第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
と定めている。つまり、「会議」の最も重要な性格は、その「独立性」あるいは「自律性」であ
ることを、謳っています。この「独立して」という部分は、単に個人が己の心情にしたがって、
という意味に留まらず、「日本学術会議」として、政治権力や軍部や企業などの干渉を受けずに、
という強い主張が込められているのです。
この学術の独立性こそが、仮にも日本が文化国家を名乗るならば、尊重されるべき最も重要な点
なのです。
それでは「会議」の具体的な組織の構成その他をみてみましょう。
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ れを
組織する。
第二項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
その第十七条は、「推薦」に関して、「 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研
究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内
閣総理大臣に推薦する ものとする」と規定しています。(平成一六法二九・全改)(注3)
なお、補足しておくと、「会議」は210人の「会員」の他に2000人ほどの「連携会員」が
おり、かれらは「会員」から選ばれて、会議の会長により任命されます。任期はいずれも6年で
3年毎に半数が入れ替わります
一般会員も連携会員(非常勤ではありますが)特別国家公務員という地位が与えられ、一般会員
と同様、日当と経費が支払われます。
以上を念頭において、改めて菅内閣が、6人の任命を拒否した問題を考えてみましょう。
まず、「会議」が、菅首相による任命拒否に対して強く反発していますが、それはなぜなのでし
ょうか。
学会側の反発の根拠は幾つかあります。第一は、1983年11月、中曽根首相(当時)が、国
会で、「政府が行うのは形式的任命」「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」
といった政府答弁があり、政府は「会議」が推薦した新会員を拒否することはない、と明言し、
それは公文書として残っていることです。
第二は、もし、「会議」が推薦した人の任命を拒否するなら、その理由をはっきり説明すべきだ、
という点です。これまで、政府側は誰一人、理由を明らかにしていません。
第三は、安倍政権の時から、一般の研究助成予算は徐々に減っているのに、軍事研究へはますま
す多額の予算をつける政策をとっていることに対する「会議」としての危機感があります。
具体的には、2017年には、軍事応用できる基礎研究に費用を助成する防衛省の「安全保障技術研
究推進制度」の予算を大幅に増やしている、という実態があります。
この制度のもとで、2015年度の予算は3億円だったものが、16年度には六億円、そして17年
度には110億円と激増しました。
これにたいして「会議」は17年、50年ぶりに軍事研究に関する声明を発表し、その中で「政
府による介入が著しく、問題が多い」と批判しました。
つまり、政府に協力して軍事研究をすれば研究費をつけてやるという、お金を通じて研究に介入
することを全面的に推進してきています。
これは、「会議」の根底にある、「学問の自由と独立」、そして軍事研究を絶対に行わない、と
いう発足の理由となった理念と真正面からぶつかり、これらの点は絶対に譲れないでしょう。
以上の背景を考えると、6人の任命がなぜ拒否されたのかが、浮かび上がってきます。
任命を拒否された6人とは、①宇野重規教授(東京大学 政治思想史)、②芦名定道教授(京都
大学 キリスト教学)、③岡田正則教授(早稲田大学大学院 行政法)、④小沢隆一教授(東京
慈恵会医科大学 憲法学)、⑤加藤陽子教授(東京大学大学院 日本近現代史)、⑥松宮孝明教
授(立命館大学大学院 刑事法)です。
この6人は、上記の順に、①特定秘密法を批判、②安保関連法に反対する学者の会等の賛同者、
③安保関連法に反対、④国会で安保関連法案について反対、⑤憲法学者でつくる「立憲デモクラ
シー」の呼び掛け人で改憲や特定秘密保護法に反対、⑥国会で「共謀罪」を「戦後最悪の治安立
法」と批判した、という背景があります。
一言でいえば、政府が強硬に推進してきた、これらの法律は「戦争への準備」という性格をもっ
ています。
これら拒否された人物と彼らの過去の言動を対応させれば、外形的には誰が見ても、そして、菅
首相をはじめ他の政府幹部が、どんな「理屈」をつけようが、拒否の背景に政府の施策に反対し
た学者を排除する意図があったとしか思えません。
「理由の説明もなく、到底承服できない。学問の自由への侵害ではないか」、もしそうでないな
ら、はっきりとした根拠を示すべきだ、もし、示せないなら拒否した6人を任命すべきだ、とい
うのが「会議」側の主張です。
任命を拒否した菅首相は、5日行われた内閣記者会によるインタビューで、ほとんどは官僚が書
いたと思われる文章を棒読みするだけでした。
そして、拒否の理由については「総合的、俯瞰的な活動を求めることになった。総合的、俯瞰的
な活動を確保する観点から、今回の任命についても判断した」「個別の人事に関するコメントは
控えたい」、とついに、本当の理由を一言も言っていません。
これ以後、政府側の答えには「総合的、俯瞰的」という言葉が、まるで「壊れたレコード」のよ
うに繰り返されました。
しかし、全体を通してみると、菅首相が、学問の自由とか独立、ということにほとんど関心がな
いことが分かります。
こうした首相の一連の言動をみて、静岡県の川勝平太知事は7日の定例会見で、「菅義偉という
人物の教養のレベルが露見した。『学問立国』である日本に泥を塗った行為。一刻も早く改めら
れたい」と強く反発しました。
川勝知事は早大の元教授(比較経済史)で、知事になる前は静岡文化芸術大の学長も務めた、い
わゆる「学者知事」です。川勝知事は6人が任命されなかったことを「極めておかしなこと」とし、
文部科学相や副総理が任命拒否を止めなかったことも「残念で、見識が問われる」と述べています
(注4)。
次回は、任命拒否の問題点を、さらにくわしく検討し、合わせて、この問題に対する内外の反応を
みてみます。
(注)
(注1)設立の際の声明は http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/01/01-01-s.pdf を参照。
(注2 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gunjianzen/index.html
(注3)http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf
(注4)『朝日新聞』デジタル版(2020年10月7日18時24分)
https://www.asahi.com/articles/ASNB761QMNB7UTPB00D.html?ref=mo r_mail_topix3_6