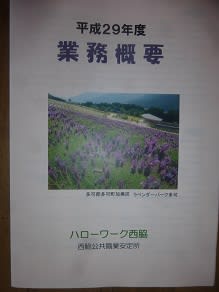4月13日(土)の午後、小野市うるおい交流館エクラで東京医療学院大学の上田諭教授による『認知症患者さんとの共生社会を目指して』と題した講演会が開催されるという案内をいただき、勉強になると考え参加してきました。

今回の講演会は、兵庫県保険医協会北播支部主催でしたので、開業医の先生方や看護師、介護施設の専門職員、行政職員が参加されていました。
上田教授は、関西学院大学を卒業後、朝日新聞に記者として入社されますが、医学への志向のため、北海道大学医学部に入学されました。卒業後、東京都医療センター精神科などを経て、平成17年4月より東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学部教授に就任されています。
演題『認知症患者さんとの共生社会を目指して』のサブタイトルに「医学モデル」から「生活モデル」をつけられていました。上田教授は、認知症は悲惨な病であり、介護は大変な労苦が伴うとよく言われるが、本当にそうかと参加者に問いかけられました。認知症は「治らない」ものであり、「医学モデル」ではなく「生活モデル」「人生モデル」と捉えるべきだと話されました。だから、自尊心が傷つき、対人関係が壊れることを防ぐことが大切だとも話されました。


認知症医の役割は、①診断、②治療1本人との対話、治療2介護・生活指導(家族への精神療法)、③治療・薬物療法(補助的に)である。しかし、薬に頼りすぎる傾向にあるのが問題だと指摘されました。フランス政府は、抗認知症薬は効果がないと本年8月より保険停止すると宣言されたそうです。
また、認知症患者に対して、告知する必要はないと話されました。すぐに告知しなくてよく、良い介護がされることが先で、本人が「私、認知症」と言えるまで待つことの方が良いのではと話されました。ただし、家族には正確に話し、対応の仕方等具体的に話す必要があるとのことでした。
上田教授の著書『治さなくてよい認知症』の中にある、「薬」より「生活の張り合い」を!。認知症は治らない、でも、私たちにできることがある。上田教授の実践を通した講演は、説得力がありました。

今回の講演会は、兵庫県保険医協会北播支部主催でしたので、開業医の先生方や看護師、介護施設の専門職員、行政職員が参加されていました。
上田教授は、関西学院大学を卒業後、朝日新聞に記者として入社されますが、医学への志向のため、北海道大学医学部に入学されました。卒業後、東京都医療センター精神科などを経て、平成17年4月より東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学部教授に就任されています。
演題『認知症患者さんとの共生社会を目指して』のサブタイトルに「医学モデル」から「生活モデル」をつけられていました。上田教授は、認知症は悲惨な病であり、介護は大変な労苦が伴うとよく言われるが、本当にそうかと参加者に問いかけられました。認知症は「治らない」ものであり、「医学モデル」ではなく「生活モデル」「人生モデル」と捉えるべきだと話されました。だから、自尊心が傷つき、対人関係が壊れることを防ぐことが大切だとも話されました。


認知症医の役割は、①診断、②治療1本人との対話、治療2介護・生活指導(家族への精神療法)、③治療・薬物療法(補助的に)である。しかし、薬に頼りすぎる傾向にあるのが問題だと指摘されました。フランス政府は、抗認知症薬は効果がないと本年8月より保険停止すると宣言されたそうです。
また、認知症患者に対して、告知する必要はないと話されました。すぐに告知しなくてよく、良い介護がされることが先で、本人が「私、認知症」と言えるまで待つことの方が良いのではと話されました。ただし、家族には正確に話し、対応の仕方等具体的に話す必要があるとのことでした。
上田教授の著書『治さなくてよい認知症』の中にある、「薬」より「生活の張り合い」を!。認知症は治らない、でも、私たちにできることがある。上田教授の実践を通した講演は、説得力がありました。