テニスの試合で、ネットにかかったボールがぽとりと相手のコートに落ちることはよくある。この場合にプレーヤーは、ゴメンねと相手プレーヤーに合図するのが一般的だ。コート上では目いっぱいの悪ガキだった、かのマッケンローも、ネットインした場合にはラケットを上げて相手に謝っていたし、ネットにかかったボールが自分のコートに落ちても、あるいは、相手のボールがネットインしても、感情を爆発させるのは見た事がない。同じボールゲームでも、ネットインして「サー」とガッツポーズを決めるような他のスポーツでは見られないしぐさだ。テニスは紳士・淑女のスポーツと言われるゆえんであろう。
ネットインは、試合の重大な局面でも当然起こる。試合が拮抗して、フルセットのタイブレークでわずかに1ポイント差で競ったゲームで、ネットインが試合の行く末を決定することもあり得ない話ではない。ぎりぎりの戦いをしている時ほど、ほんのわずかな運、不運が優劣をつけるものなのかもしれない。これは、スポーツのみならず、人生においても起こりえることなのだ。
ウッディ・アレンの映画「マッチ・ポイント」。ストーリーはかなり古典的だ。英国ロンドンを舞台に、上流階級の女性と結婚して社会階層の階段を上がろうとする青年クリス(ジョナサン・リース・メイヤーズ)が、同様に上流階級の生活を狙う米国女性ノラ(スカーレット・ヨハンソン)と運命的な恋に落ち、結婚後も情事を重ねる。その後、妊娠したノラから結婚を迫られたクリスは、上流階級の生活を手に入れるために彼女を殺害するに至る。そしてその後の警察の捜査を、それこそほんのわずかな運でかわしてしまうのだ。
映画のシーンの随所に、階級と伝統重視の国イギリス、ロンドンの上流階級の暮らしを象徴して、1930年代に録音されたノイズの多いノスタルジック・テイストなオペラが流れる。
上流階級の女性との結婚のために妊娠した愛人を殺すというモチーフは、セオドア・ドライサー原作の「アメリカの悲劇」を映画化した「陽のあたる場所」(ジョージ・スティーヴンス、1951)思わせる。「陽のあたる場所」では、ジョージ・イーストマン(モンゴメリー・クリフト)が恋人アリス・トリップ(シェリー・ウィンタース)をその手で殺めてしまい、裁かれ、最愛の令嬢、美しい、美しいアンジェラ・ヴィスカース(エリザベス・テイラー)と今生の別れになる。
妻との間に子供ができず、ノラとの間に赤ん坊ができたクリスが
「なぜ妻とは子供ができないのに、きみにはできるんだ」
と聞くと、ノラは答える。
「セックスするから子供ができるのではなく、愛があるから子供ができるのよ」
しかし妻との間にも子供はできる。上流階級の一員になるために、クリスが妻を愛するよう努力した結果なのだろう。
ほんのわずかな運で警察の追及をかわせたクリスだが、彼は幸せをつかむことができるのだろうか。クリスは本当に愛した女まで殺して上流階級の生活を得たが、それによって彼がつかんだ幸せは幻想に近いものなのかもしれない。ドストエフスキーの「罪と罰」は、19世紀のロシアの都市ペテルブルグを舞台に、「非凡な人間には自らの思想を実行する上で必要であれば、障害を踏み越える権利がある」と信じる貧しい元学生ラスコーリニコフが、金目当てのために強欲な金貸しの老婆を計画的に殺害する話である。しかしラスコーリニコフは殺害現場に居合わせた老婆の妹まで殺す羽目になり、そのため罪の意識にさいなまれることになる。
クリスは、妊娠したノラに対して「生まれてこないのが一番幸せだ」と言っている。この言葉は、彼自身に対する言葉でもあるのだろう。自ら犯した罪に対する罰を運良く免れることができたが、ほんのささいなきっかけで人生の運は反転する。
相手に握られたマッチポイントは、たまたま運が良かったことで逃れることができた。しかし、人生の試合は振り出しの戻ったわけではない。彼にはこの先、マッチポイントをずっと握られて、いつゲームセットになるのかおびえて暮らす毎日が待っている。人生は運によって左右されるというアレンの哲学だ。
ところで、今日は「キスの日」。
1946(昭和21)年の今日、日本で初めてキスシーンが登場する『はたちの青春』(佐々木康監督)が封切りされた。
当時、映画製作もGHQの検閲下にあり、民間情報教育局(CIE)のコンデが、完成した脚本を校閲しキスシーンを入れることを要求したらしい。主演の大坂史郎と幾野道子がほんのわずかに唇を合わせただけだったらしいのだが、それでも映画館は連日満員になったそうだ。なんか、ニュー・シネマ・パラダイスを思い出すなあ。













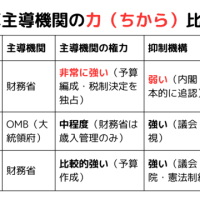






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます