
〈『追悼 義農松田甚次郎先生』(吉田六太郎編)、吉田矩彦氏所蔵〉
では引き続いて、各投稿をざっと振り返ってみたい。
**********************************************************【中編】**********************************************************
・福島 遠藤修司
「一つになつて先生の御遺志をついで奮斗しようではないか」という一言は次のことを示唆してくれる。それは、
農村文化の向上と農産物増産のために東奔西走した松田甚次郎の精神を引き継いで奮闘しようという人物はこの遠藤のみならず少なからずいた、ということはこの『追悼 義農松田甚次郎先生』から知ったところだが、あれっ、「羅須地人協会」の実践を引き継いで奮闘しようとした人物は一人も見当たらないのではなかろか。
ということをだ。・京城 栴 文楨
〝福島 遠藤修司〟において遠藤は、「一粒の麦、地に落ちて死なずば唯一つにてありなん。死なば多くの果を結ぶべし」と言っていたが、いみじくもこの栴 文楨も「一粒の麦はおちたがそれより芽生えた夛くの美しき果子は益々光り輝くでありませう」と同じ意味のことを海外の京城で言っていることから、松田甚次郎がこのように高く評価をされていたことはほぼ妥当であったであろうということを知ることができる。
・長野 宮下 清
ここで気になったことが「昭和十二年十二月上旬……「時局下に一農民として」の講演会」という記述だ。もしかすると、甚次郎がこのようなタイトルの講演をしたことを真壁は「時流に乗り、国策におもね」と揶揄したのだろうか。
・朝鮮 伊藤重次郎
ところで、先に京城から寄せられた「追悼」を引いたが、この京城とは今のソウルに当たるだろうから、今回のものとを併せると、当時の朝鮮から複数の「追悼」が寄せられていたということになる。そうなると、私にはある不安が生じてくる。それは「最上共働村塾」の「開塾趣意」(昭和七年八月)の中に、
更に次三男の靑年を滿鮮の曠野に耕作出來る拓殖訓練も授け、強烈なる皇國精神の發動を以つて、農村のどん底の立場や、不景氣、失業苦のない明るい規範の社會を招来するまで務めねばなりません。各々の立場を意識的に分擔し、お互に信じ、共働し、隣保し、以つて日本農村をして、全人類に先驅する正しい皇道日本たらしめねばなりません。〈『土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)226p〉
という件(くだり)があったからである。もう少し具体的に言うと、「次三男の靑年を滿鮮の曠野に耕作出來る拓殖訓練も授け」ということが実際になされて、その結果、栴 文楨 や伊藤重次郎は「滿鮮の曠野」に行ったのだったということになるのだろうか、という不安が生じてきたからである。というのは、以前私は、
実際に、甚次郎と「寝食労働を共にして修業」した者は「青少年」ではあるが、その中の何割りが「滿鮮の曠野」へ行ったというのだろうか。私にはそのような塾生を見つけることはできなかった。
と述べたが、実はこの二人は「そのような塾生」であり、しかも「在鮮の最上會員達」ということだから、この二人のみならず最上共働村塾出身の人物が当時朝鮮に結構居たということになりそうだ。つまり、この度「そのような塾生」を見つけてしまったようだ。どうやら、私には大きな新たな課題が課せられてしまった。・福岡 福田榮三郎
福田榮三郎は「自給自足の一農夫として立上がり、農の尊さ、農道の信念に生き、野の父として師として御導き下さいました」と言っているわけだから、このことからは、甚次郎がこの講演で「滅私奉公」を訴えていたわけでもなければ、「欲しがりません勝つまでは」の精神を昂揚しようとしていたわけでもなかろうということが言えるのではなかろうか。言い換えれば、甚次郎のこの講演は「国策におもね」ようとしたものでもなければ、(このような講演によって)「そのことで虚名を流」そうとしたものでもなかろう。なぜなら、すでに甚次郎の高名は遠く九州は福岡にまで知れ渡っていたということを、この福田の「農村先覚者、師たることは知つては居りましたが」という一言がはしなくも教えてくれる(と私には思える)からである。
・静岡 太田良元治
甚次郎の存在とその主張は、『土に叫ぶ』が出版さる昭和13年以前に既に静岡の太田良元治たちにも知られていた蓋然性が低くない。
「全き農魂の人でありました。野の師父とし、大東亜眞の建設はかゝる人の実行によつてこそ築かれるべきであることを」という発言に少し引っかかるが、「全き農魂の人でありました。野の師父とし」という太田良元治の一言は、甚次郎の実践を讃え、彼を尊崇していたが故のことであろう。
・盛岡 西川大作
松田甚次郎は当時多くの人たちから敬慕されていたであろうということである。
・岩手 藤沢美雄
甚次郎は塾生たちと一緒に泥まみれになりながら農産物の増産に邁進したということを示唆している。
・岩手 小坂友次郎
やはり「賢治さんは知りませんが」とか「松田さんを通じて賢治さんを知りました」である。この『追悼集』の発行は昭和19年3月だから、賢治没後約10年半が経った頃の事である。ということは、賢治が亡くなってからそれほども経ったというのに、地元の人間であるはずの小坂友次郎にしてこうだったのだから、賢治は案外地元でさえも知られていなかったようだということが示唆される。
・盛岡 鏑 慎二郎
鏑の「「小作人たれ」といふ師の訓へと、農民達の幸福のために、敢然と己を没して闘ひ徹された松田さん」という、甚次郎に対する人物評はかなりしかるべきものであろう。つまり、甚次郎の生き様はまさにこれに近かったであろうことを、私は改めて確信した。
賢治から「小作人たれ/農村劇をやれ」と強く「訓へ」られ、故里鳥越に戻ってそのとおり実践し、農村文化の向上を目指し、農産物の増産のために「敢然と己を没して闘ひ」ついに35歳にして斃れたのだ、と。
・岩手 安藤玉治
この「追悼」を読んで、「はねおきて収穫物を入れた小屋にいきいつもの通り電気のスヰッチを入れ、脱穀機をあらん限りふみ食前の稲こきにがんばつた」とあったから、安藤は実際に米を作っていたのだということに私は気づいた。そして、それゆえに安藤玉治は、安藤自身が「松田甚次郎さんについての本格的な評伝は、本書が初めてのもだと思う」と239pで言っているところの『「賢治精神」の実践―松田甚次郎の共働村塾』を書いたのであり、書けたのだということに私は思い至った。
・満州 渡部由夫
「私たちは同志的な結合でもつて遺志を継いでこそ英魂を慰めることでありませう」という記述からは、満州においても甚次郎は渡部のような人達から敬慕されていたであろうことが容易に想像できる。
同じ頃(昭和15年1月頃)、ベストセラー『土と戦ふ』において菅野正男は、「宮澤賢治の考えて居た事を私達は満州の大平野の中に実現しようとして居るのです」と書いているから、甚次郎の影響だけではなく、満蒙の地には宮澤賢治の影響も及んでいたということになる。
・室蘭 島貫太吉
「宮澤賢治は三十八歳にして逝き、今また松田先生三十五歳にして去る。吾等の師父達の日々はその瞬間々々に於ていのちの火花を散らして行つたのである」という一文から、入隊中のある一人が賢治と甚次郎を同列に見ていたということも知った。この二人を比較すると、とかく甚次郎一人が国策におもね虚名を流したと誹られがちだが、それはおかしいぞということをこの一文は示唆していそうだ。
・東京 川上治雄
「「土に叫ぶ」勤王村の確立に献身して」とか「先生は農村と都会との交流を常に理想とし日本の青年が堅き結束を図つて八紘一宇の理念たる大東亜共栄圏の建設に邁進し寄與せんとしつゝあつた」という一文もあった。そして、もし甚次郎が本心からそのために、「献身的に努力」し「大東亜共栄圏の建設に邁進寄与せん」と実際にしていたというのであれば、「時流に乗り、国策におもね、そのことで虚名を流した」と言って誹る人がいても多少はやむを得ないのかな、という不安が多少生じてしまった。しかしながら、現段階では、甚次郎自身が塾生や聴衆に対してそのようなことをズバリ明言したということを示すものを私は見つけられずにいるから、その不安はとりあえずは拭える。しかも、現時点ではこれはあくまでも川上治雄の認識の仕方に過ぎないとも考えられる。とはいえ、今後は、「甚次郎は塾生や聴衆に対してそのようなことを確かに言っていた」ということ示す資料や証言を見逃さないようにしたい。
・「熱と智と行の人」 小野武夫
甚次郎が、
爾来幾夛の波瀾を経、其の間「土に叫ぶ」外一・二の著書を公けにし、又、新聞雑誌に筆を執り、且つ又自宅附近に農園や塾を開いて遠近より松田君の徳を慕ふて集り来る青年のために実践的指導をなし、其の上に各地方からの依頼に應じて講演にも出かけ、最近の数年間の同君の生活は文字通り多忙力闘の連続であつたのである。
という小野の言はまさにそのとおりであった、と私は推断できた。そしてまた、ここまだ読んできた多くの「追悼」はこの推断が間違っていないことを裏付けているはずだ。そこで、「自宅附近に農園や塾を開いて遠近より松田君の徳を慕ふて集り来る青年のために実践的指導をなし、其の上に各地方からの依頼に應じて講演にも出かけた」松田甚次郎に私は改めて敬意を表した。当時、このようなことを実践し、しかもそこへ「徳を慕ふて集り来る青年」がいたり、「各地方からの依頼に應じて講演にも出かけ」たりしていた人物を、私は松田甚次郎以外に知らないことに私は気付く。どうやら、これが甚次郞の大いなる特徴であろう。
**************************************************これらのことより*****************************************************
松田甚次郎の精神を引き継いで奮闘しようという人物が少なからずいた。
やはり、甚次郎の当時の評価はかなり高かった。
「最上共働村塾」の「開塾趣意」の中に、
甚次郞が「滿鮮の曠野に耕作出來る拓殖訓練も授け」ようとした次三男の靑年の何人かが、実際に当地へ行ったということは否定できない
満蒙においても甚次郞を崇敬していた人物がいたが、それは賢治の場合にも同様であった。
「時流に乗り、国策におもね、そのことで虚名を流した」と誰かが誹っているが、そもそも時流に乗る前に、既に甚次郞の高名は早い時点から知られていたから、この論理は当て嵌められない。
当時岩手では、賢治よりも松田甚次郎の方が世間に知られていた。
甚次郞については、まさに「自宅附近に農園や塾を開いて遠近より松田君の徳を慕ふて集り来る青年のために実践的指導をなし、其の上に各地方からの依頼に應じて講演にも出かけた」と小野が言うとおりだったであろう。
甚次郞は、「「土に叫ぶ」勤王村の確立に献身して」とか「農村と都会との交流を常に理想とし日本の青年が堅き結束を図つて八紘一宇の理念たる大東亜共栄圏の建設に邁進し寄與せんとしつゝあつた」、と見ていた塾生があった。
やはり、甚次郎の当時の評価はかなり高かった。
「最上共働村塾」の「開塾趣意」の中に、
更に次三男の靑年を滿鮮の曠野に耕作出來る拓殖訓練も授け、強烈なる皇國精神の發動を以つて、農村のどん底の立場や、不景氣、失業苦のない明るい規範の社會を招来するまで務めねばなりません。各々の立場を意識的に分擔し、お互に信じ、共働し、隣保し、以つて日本農村をして、全人類に先驅する正しい皇道日本たらしめねばなりません。
と謳われていた。甚次郞が「滿鮮の曠野に耕作出來る拓殖訓練も授け」ようとした次三男の靑年の何人かが、実際に当地へ行ったということは否定できない
満蒙においても甚次郞を崇敬していた人物がいたが、それは賢治の場合にも同様であった。
「時流に乗り、国策におもね、そのことで虚名を流した」と誰かが誹っているが、そもそも時流に乗る前に、既に甚次郞の高名は早い時点から知られていたから、この論理は当て嵌められない。
当時岩手では、賢治よりも松田甚次郎の方が世間に知られていた。
甚次郞については、まさに「自宅附近に農園や塾を開いて遠近より松田君の徳を慕ふて集り来る青年のために実践的指導をなし、其の上に各地方からの依頼に應じて講演にも出かけた」と小野が言うとおりだったであろう。
甚次郞は、「「土に叫ぶ」勤王村の確立に献身して」とか「農村と都会との交流を常に理想とし日本の青年が堅き結束を図つて八紘一宇の理念たる大東亜共栄圏の建設に邁進し寄與せんとしつゝあつた」、と見ていた塾生があった。
ということなどが言えるようだ。
そこで、この時点で私が言っておきたいことは次のことである。
太平洋戦争が起こったのは1941年(昭和16年)であり、それ以前の昭和12年12月の講演(「時局下に一農民として」の講演会のこと)であれば、まだ少なくとも太平洋戦争は起こっていなかったことになるから、「時流に乗り」とは言えない。それとも日中戦争はそれこそ昭和12年12月に始まっているようだから、甚次郎は早速時流に乗ってこのタイトルの講演をしたのだろうか。しかしもしそうだったとすれば、「国策におもね」とは言えないだろう。それは、もし「国策におもね」て早速昭和12年12月に「時局下に一農民として」の講演を甚次郎が行ったとすれば、「国策」を担っていたと言われ得るかもしれなが、少なくとも「おもね」という表現にはならないであろうからである。
そもそも、もし「おもね」というのであれば、昭和19年頃になると敗色濃厚だったから、あの人の講演「今日の心がまえ」における、
それは、西田良子が、
つまり、真壁は「賢治の作品はあまり勉強していると思えなかった。村塾の経営とその自給自足主義や農民劇は賢治の教えの実践とみられるが、しかし時流に乗り、国策におもね、そのことで虚名を流した。これは賢治には全く見られぬものであった」と甚次郎のことを揶揄しているわけだが、彼が初めてこう言ったのは、昭和49年の『北流』第八号(岩手県教育出版部)においてである。つまり、昭和49年頃に、大戦敗戦前のことを振り返って疾うに亡くなった甚次郎のことをこう揶揄していたことになるする。となれば、賢治も戦意昂揚のために結構利用されていたということにも言及せねばなかったのではなかろうか。しかし真壁がそのようなことを言っていたということを示す資料や証言を私は未だに見つけられずにいる。言い換えれば、甚次郎と賢治に対する真壁の評価の仕方は公平ではなかったということになるのではなかろうか。
そもそも、もし「おもね」というのであれば、昭和19年頃になると敗色濃厚だったから、あの人の講演「今日の心がまえ」における、
私は「今日の心がまえ」という主題から非常に離れていたようであります。主題に少しも触れなかったではないか、と思っておいでの方もあるかも知れない。しかし 「雨ニモマケズ」の精神、この精神をもしわれわれが本当に身に附けることができたならば、これに越した今日の心がまえはないと私は思っています。〈『宮沢賢治の世界』(谷川徹三著、法政大学出版局、昭和45年)31p〉
ならばまさに「おもね」と言えるかもしれないが、甚次郎の場合はそうとは言えまい。それは、西田良子が、
「雨ニモマケズ」の中の「アラユルコトヲ ジブンヲカンジョウニ入レズニ」という<忘己><無我>の精神や「慾ハナク」の言葉は戦時下の「滅私奉公」「欲しがりません勝つまでは」のスローガンと結びつけられて、訓話に利用されたりした。〈『宮澤賢治論』(西田良子著、桜楓社)166p〉
と言っているからなおさらにだ。つまり、真壁は「賢治の作品はあまり勉強していると思えなかった。村塾の経営とその自給自足主義や農民劇は賢治の教えの実践とみられるが、しかし時流に乗り、国策におもね、そのことで虚名を流した。これは賢治には全く見られぬものであった」と甚次郎のことを揶揄しているわけだが、彼が初めてこう言ったのは、昭和49年の『北流』第八号(岩手県教育出版部)においてである。つまり、昭和49年頃に、大戦敗戦前のことを振り返って疾うに亡くなった甚次郎のことをこう揶揄していたことになるする。となれば、賢治も戦意昂揚のために結構利用されていたということにも言及せねばなかったのではなかろうか。しかし真壁がそのようなことを言っていたということを示す資料や証言を私は未だに見つけられずにいる。言い換えれば、甚次郎と賢治に対する真壁の評価の仕方は公平ではなかったということになるのではなかろうか。
畢竟するに、甚次郞は時局に敏感だったと言えるかもしれないが、「国策におもね」とまでは言えまい。にもかかわらず、甚次郞一人だけを吊し上げていた人がいた、ということになりそうだ。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “「松田甚次郎の再評価」の目次”へ。
“「松田甚次郎の再評価」の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

《新刊案内》
『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

は、岩手県内の書店で店頭販売されておりますし、アマゾンでも取り扱われております。
あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守
☎ 0198-24-9813
なお、目次は次の通りです。
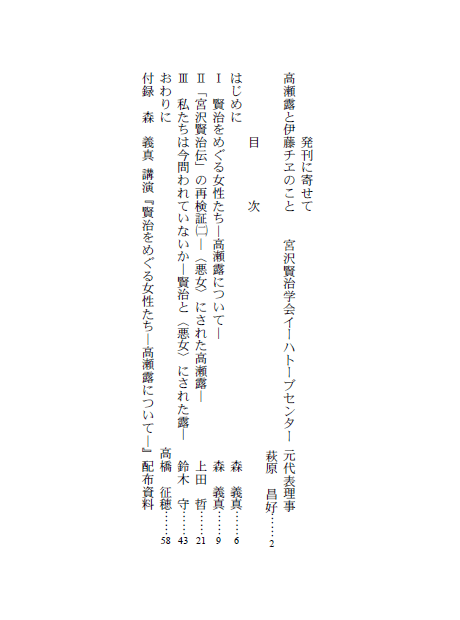
そして、後書きである「おわりに」は下掲の通りです。
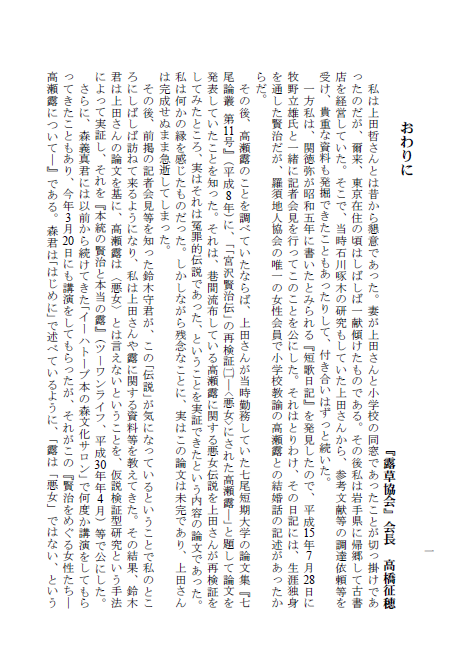
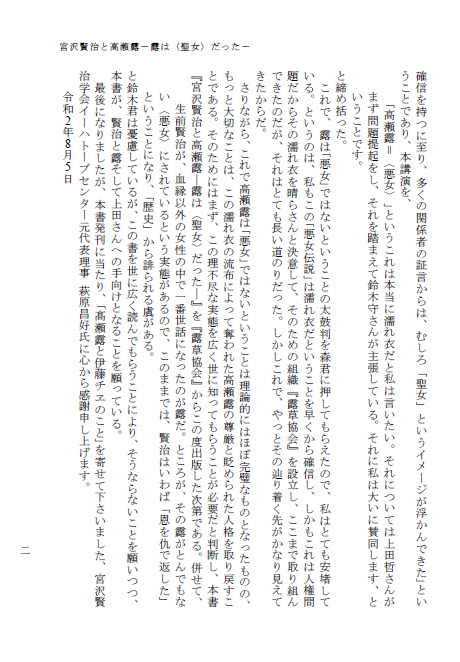


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます