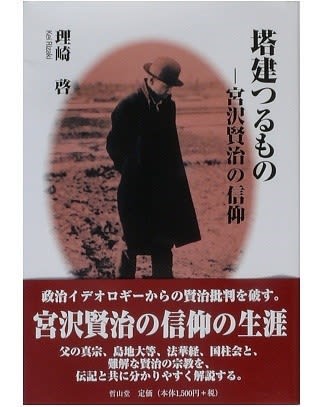
《『塔建つるもの-宮沢賢治の信仰』(理崎 啓著、哲山堂)の表紙》
では今度は、「二、大等と法華経」という章に入るが、この章はちょっと私にはわかりにくかった。したがって、理崎氏が言おうとしているところを正しく伝えられるか自信がないのだが、私なりの理解で投稿してみたい。
まず、島地大等についてである。同書によれば、
島地大等は明治8年、越後国中頸城郡の真宗寺に生まれた。宗門の大学林で摩訶止観などの天台教学を学び、卒業後は天台宗大学の講師となった。…(投稿者略)…二十八歳の時、盛岡・島地黙雷の願教寺に入婿となった。大正8年に東大文学部講師となり、日本仏教史を中心に華厳学や天台学などを講じ、15年には東大に印度哲学講座を開設している。当時の仏教会を代表する碩学と言っていい。
〈41p〉とある。
なお、田口昭典氏の『宮沢賢治と法華経について』によれば、賢治は大正2年の「舎監排斥運動」に関わって退寮させられて、
四月 清養院(曹洞宗)に下宿
五月 徳玄寺(浄土真宗)に移る
八月 願教寺(浄土真宗)で島地大等の法話を聞く
〈『宮沢賢治と法華経について』(田口昭典氏著、でくのぼう出版)32p〉五月 徳玄寺(浄土真宗)に移る
八月 願教寺(浄土真宗)で島地大等の法話を聞く
ということであり、島地大等の法話を聞いたことで、法華経に触れる下地ができたと述べていた。また、田口氏は上掲書で、
近代の仏教学者として有名で、仏教系大学の教授となって、天台学の研究にも当たった。大谷光瑞氏の仏教探検隊にも参加したり、門主が幼少時にその教育を担当したり、一九一九年(大正八年)以後は東京帝国大学で印度哲学、日本仏教学史、天台学などを講じ、その学徳は並ぶ物がなかった。
〈同33p〉そうか、確かにこれならば理崎氏の言うとおり大等は碩学だったでろう。そういえば、そうそう、この願教寺とは賢治と同僚だった白藤慈秀が後に院代となったお寺でもあった<*1>。
そして理崎氏は続けて、賢治はしばしば大等の講習会に参加して彼の講話を何度も聴いたであろう、と述べ、賢治が「赤い経巻」と呼んだ島地大等篇の『漢和対照妙法蓮華経』を賢治は読んで感銘を受けたというが、それはいつかということとか、何故感銘を受けたのが法華経だったのかということを理崎氏は次に考察している。
<*1:投稿者註> 『こぼれ話 宮沢賢治』(白藤慈秀著、トリョウコム)70pによれば、大正15年に、
私も花巻農学校をやめて、盛岡市本願寺派願教寺の住職島地大等師の院代となって願教寺に師住し、寺院生活をすることになった。
という。 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “『理崎 啓氏より学ぶ』の目次”へ。
“『理崎 啓氏より学ぶ』の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

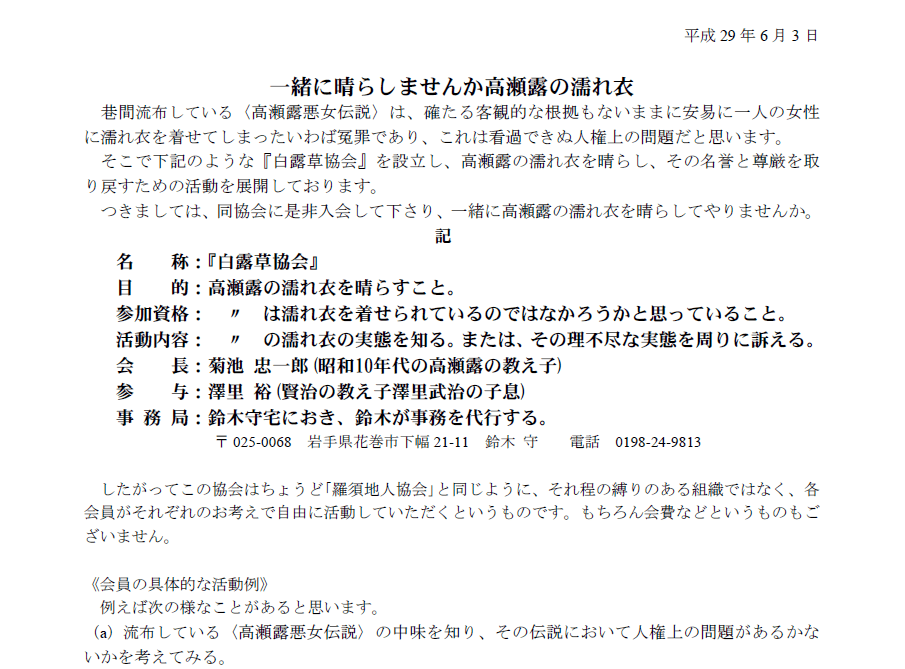
なお、ブログ『みちのくの山野草』にかつて投稿した
・「聖女の如き高瀬露」
・『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』
や、現在投稿中の
・『「羅須地人協会時代」再検証-「賢治研究」の更なる発展のために-』
がその際の資料となり得ると思います。
・「聖女の如き高瀬露」
・『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』
や、現在投稿中の
・『「羅須地人協会時代」再検証-「賢治研究」の更なる発展のために-』
がその際の資料となり得ると思います。
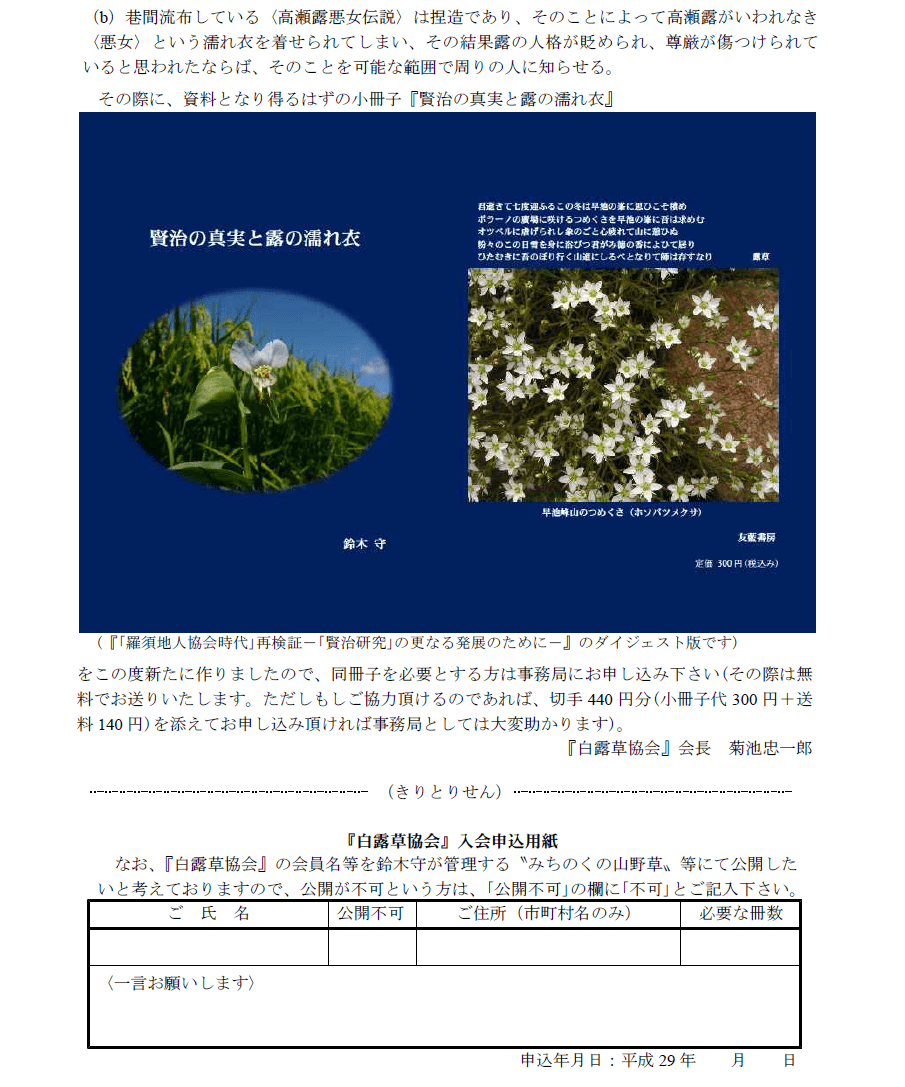






















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます