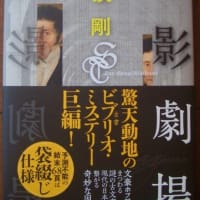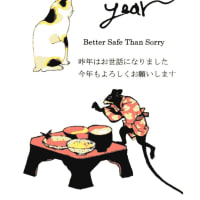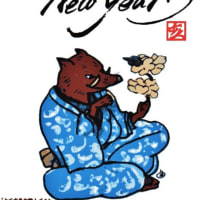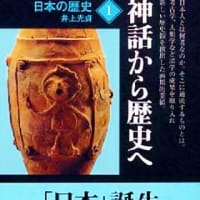***江戸文化の挿絵2―勝川春朗(北斎)***
葛飾北斎(1760-1849年)と聞いて、大抵パッと頭に浮かぶ絵は「富嶽三十六景 凱風快晴」(通称:赤富士)でしょうか。私は北斎85歳の時完成した「怒濤図 女波」のブラックホールさながらの浪の渦絵が一番好きです。
90歳まで生きた北斎はあらゆるジャンルの絵画を描いています。6歳から絵を描くようになり、14歳で木版彫刻術(彫り摺りのコツ)を学び、貸本屋の小僧として働きそこで絵を独習したそうです。
19歳で彫師より画工になることに決めた北斎は勝川春章に入門し勝川春朗と号しました。20歳代の春朗(北斎)は、2流戯作者の挿絵を描いたり、春町や京伝と同じように、自らも戯作することに熱中していたそうです。しかし、春町や京伝はたまた馬琴や一九などのように戯作の才能はなく、下手だったようです。そして浮世絵の方に天職を見出し家業を譲って絵師を職業にします。

これは、山東京伝作『昔々桃太郎発端話説(ももたろうほつたんばなし)』1792年蔦屋刊の挿絵で、描いたのは32歳の春朗時代の北斎(36歳で二代目宗理を襲名)です。
このお話は「舌切り雀」がベースになっているので雀が擬人化されて描かれています。人物はあまり魅力的ではありませんが、動物はさすがに上手いです。後ろの衝立の画には京伝の弟子・鬼武の署名があります。

そして北斎といえば、妖怪画も有名ですが、ここにでてくる化物妖怪はまさしく北斎タッチの化物妖怪たちです。春町、京伝、清長、歌麿などと比べると春朗(北斎)の挿絵は明らかにタッチが異なっていて、今風に云えば劇画っぽいと思います。
この頃は、「江都両国橋夕涼花火之図」など江戸名所図も手懸けていて、風景版画の出発点の時期でもありました。
葛飾北斎(1760-1849年)と聞いて、大抵パッと頭に浮かぶ絵は「富嶽三十六景 凱風快晴」(通称:赤富士)でしょうか。私は北斎85歳の時完成した「怒濤図 女波」のブラックホールさながらの浪の渦絵が一番好きです。
90歳まで生きた北斎はあらゆるジャンルの絵画を描いています。6歳から絵を描くようになり、14歳で木版彫刻術(彫り摺りのコツ)を学び、貸本屋の小僧として働きそこで絵を独習したそうです。
19歳で彫師より画工になることに決めた北斎は勝川春章に入門し勝川春朗と号しました。20歳代の春朗(北斎)は、2流戯作者の挿絵を描いたり、春町や京伝と同じように、自らも戯作することに熱中していたそうです。しかし、春町や京伝はたまた馬琴や一九などのように戯作の才能はなく、下手だったようです。そして浮世絵の方に天職を見出し家業を譲って絵師を職業にします。

これは、山東京伝作『昔々桃太郎発端話説(ももたろうほつたんばなし)』1792年蔦屋刊の挿絵で、描いたのは32歳の春朗時代の北斎(36歳で二代目宗理を襲名)です。
このお話は「舌切り雀」がベースになっているので雀が擬人化されて描かれています。人物はあまり魅力的ではありませんが、動物はさすがに上手いです。後ろの衝立の画には京伝の弟子・鬼武の署名があります。

そして北斎といえば、妖怪画も有名ですが、ここにでてくる化物妖怪はまさしく北斎タッチの化物妖怪たちです。春町、京伝、清長、歌麿などと比べると春朗(北斎)の挿絵は明らかにタッチが異なっていて、今風に云えば劇画っぽいと思います。
この頃は、「江都両国橋夕涼花火之図」など江戸名所図も手懸けていて、風景版画の出発点の時期でもありました。