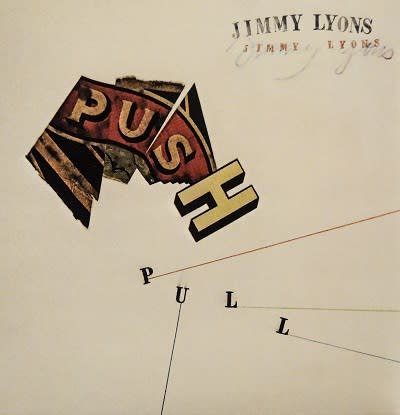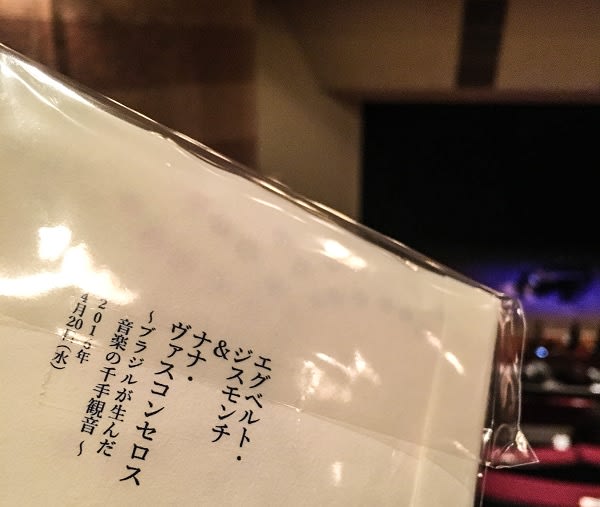1970年12月20日深夜に、コザ市(現・沖縄市)において、米兵が沖縄人をクルマで轢いた。集まってきた人たちに対し米軍警察が威嚇発砲し、それまで鬱積していた沖縄人の怒りが弾けた。人びとは米軍人のクルマを次々にひっくり返し、火を放った。いわゆる「コザ暴動」である。
そのときから45年以上が経ち、「コザ暴動」を振り返るプロジェクトが、「コザ暴動プロジェクト in 東京」(2016/4/29、主催・明治大学「島しょ文化研究所」)として行われた。
■ 「コザ暴動」写真展
比嘉康雄、平良孝七、國吉和夫、比嘉豊光、松村久美、吉岡功、大城弘明、山城博明の各氏により撮影された「コザ暴動」。プリントはインクジェットプリンターでなされた簡易なものだった。事件の大きさゆえ、誰が撮っても似たようなものになるのかなと思いながら観ていたが、個性はそれぞれに出ている。「暴動」の最中に撮られたものは少なく(故・比嘉康雄ら)、むしろ、明け方、「暴動」の後に撮られた作品が多い。夜中に駆けつけられなかったという理由もあるだろうが、一方、この後のシンポジウムで松村久美氏が発言したように、顔を撮ってはならぬという圧力もあったのだった。故・平良孝七による写真にはユーモアのようなものがあった。
■ シンポジウム第1部「写真に映し出されたコザ暴動」
パネラー:國吉和夫(写真家)、小橋川共男(写真家)、松村久美(写真家)、倉石信乃(明治大学)、比嘉豊光(写真家、コーディネーター)

最初に、現場で怒りを爆発させる沖縄人の声(ラジオ沖縄)、「暴動」の映像(琉球放送)が流された。後者から聞こえてくる、機動隊も沖縄人だろう・沖縄人の味方をしろとの声には、まさに辺野古で行われている抑圧と同じ構造があった。さらに、映像を観ながら、会場での「うちなーぐち」による対話があり(わたしにはまったく解らない)、これはトークの最初に意図的に「うちなーぐち」を混ぜたことを含め、比嘉豊光氏の意図的な仕掛けのように思われた。
比嘉氏によれば、昨年(2015年)、沖縄において「戦後70年・沖縄写真 まぶいぐみ」というスタンスや世代の違いを超えた写真展を行い、撮った側と観る側との共有、歴史の記録・記憶が重要だと考えたことが、今回のプロジェクトの背景にあるのだという。そして、当時「暴動」を撮った写真家たちは皆若く、結果として場所と時代との共有になっているのだ、と。
各氏の発言により、次のようなことがわかる。
「暴動」前日の12月19日には、市内の美里中学校で「毒ガス即時完全撤去を要求する県民大会」が行われた(前年の1969年に、米軍基地の知花弾薬庫から毒ガスが漏れる事故があった。>> 森口豁『毒ガスは去ったが』)。その取材のために多くのジャーナリストや写真家が参加し、コザや那覇にいた。もちろん、戦後25年経っても、沖縄を下に見るアメリカの存在や、多発し続ける米兵の凶悪犯罪に対し、人々の怒りが鬱積していた。起こるべくして起こった事件であった。
人びとは、建物に延焼しないようクルマを道の真ん中でひっくり返した。対象は、あくまで米軍なのであり、その観点で焼き討ちするべきクルマを選び、また略奪など関係のない暴力行為は一切起きなかった。「暴動」に直接参加した人も、遠巻きに見ていた人も、火の海の中で、罰が当たったのだというような満足感を顔に出し、顔が輝いていた。指笛を吹き、カチャーシーを踊っている人も少なくなかった。米兵や米軍警察は、次の段階に備えて銃を水平に構え、実弾を装着していた。米軍ヘリは目が開けられないほどの強いサーチライトを人びとに当て、催涙ガスも使った。明け方になり顔が識別できるようになってくると、人びとは去っていった。
倉石氏が、写真と沖縄との関係について発言した。明治の上杉茂憲(沖縄県令)や大正期の鎌倉芳太郎(紅型等の研究者)が撮った沖縄は、ヤマトが観る文化財としての対象であった。戦前に木村伊兵衛が沖縄を撮ったときの視点は、観光や技法解説といったものであり、植民地・満州に向けられた視線と同じであった。戦後、岡本太郎、濱谷浩、再び木村伊兵衛らが沖縄を撮る(山田實らによる組織が、「本土の大家」の受け皿となった。>>『山田實が見た戦後沖縄』)。依然として、沖縄は被写体としての立場を強いられていた。こういった視線の起点は、ペリーによる沖縄の踏査(ダゲレオタイピストや素描家を伴っていた)、すなわち植民地に向けられる目線にさかのぼることができる。一方、「コザ暴動」の写真には、ヤマトとの非対称性が見られず、一時的に写真家の権力構造がフラットになったことによる解放感が感じられるのだ、と。
比嘉氏は、写真を通じてのヤマトの沖縄収奪に関して、それを共有しながら現場に「戻す」作業が必要なのだと発言した。それに呼応して、松村氏、國吉氏が、自分たちの死後には、遺された者たちにとってフィルムが「ゴミ」になることを懸念し、しかるべきところに収めてゆくことの大事さを語った。
「文化植民地化」に関して、倉石氏がさほど悲観すべきではない若い沖縄の存在として挙げた例として、次の名前があった。石川竜一(>> 木村伊兵衛賞受賞)。ミヤギフトシ(「六本木クロッシング2016展」に出展中)。山城知佳子(「沖縄・プリズム1872-2008」では、自ら海のアーサに絡みつかれていた)。根間智子。かれらの作品は、「本土」を媒介せず、沖縄から自律的につくられたものだという。
会場からは、当時の沖縄において、黒人兵士が反戦のビラを日・英2か国語で撒いていたという証言があった。
■ シンポジウム第2部「コザ暴動から見る沖縄の現在と日本」
パネラー:比屋根照夫(琉球大学)、今郁義(映像ディレクター)、金平茂紀(TBSキャスター)、川端俊一(朝日新聞)、後田多敦(神奈川大学、コーディネーター)、外間氏(「コザ暴動」に居合わせた方)

まさに交通事故のあと、今氏(映画『モトシンカカランヌー』の製作や全軍労スト支援のため沖縄入りしていた)が、クルマから米兵を引っ張り出そうとしていた。そこに居合わせた方が、急遽登壇した外間氏である。氏は、米軍警察が上に向けて威嚇射撃したあとに、向こう側で米兵が銃を水平に向けて撃つ準備をしていたのを目撃している。外間氏は、会場に向けて、「皆さんに問題提起します。(問題の構造は)あのころから変わっていません」と呼びかけた。
川端氏は、昨年(2015年)、朝日新聞夕刊において「新聞と9条 沖縄から」の連載を執筆した方である。氏によれば、当時、米兵による交通事故(「轢殺事件」)が頻発しており、「コザ暴動」の前にも、米軍警察を遠巻きにした人びとからの投石などもあった。糸満で主婦が轢き殺されたにも関わらずそれを犯した米兵は無罪となり、琉球新報でも、その実態を報じる連載を「暴動」2日前にはじめたばかりであった。やはり、起こるべくして起こった事件なのだった。本来は、自分の身に危害が及ぶ場合でなければ民間人に発砲してはならないという米軍のルールがあったにも関わらず、「暴動」を抑えるために、米兵は実弾を装填した。米兵は沖縄人を人間以下の存在として扱っていた。
当時大学院生の比屋根氏にとっても、「ひたひたと世の中が変わる足音があった」という。その現象として、「暴動」のあと、バスに米兵が乗ってくるとき、指でピースサインを作っていたり、あるいはコザの黒人街にベ平連の事務所があって連帯のメッセージを発信していたり(第1部で会場から紹介のあった事例)、ということがあったという。
アメリカ大統領選の取材のためワシントンDCに居る金平氏は、スカイプで参加した。氏が強調したのは本土メディアの劣化のひどさであり、沖縄の米軍基地問題はもう終わったものとする風潮や(「あそこはもうしょうがないんですよ」と切り捨てる)、霞が関・永田町目線となってしまう政治部の体質についてであった。氏は、1995年の米兵による少女暴行事件のことや、当初は「県内移設」という考えなどなかったことを、メディアが本来は触れるべきであるのにそうしないことを指摘した(その意味で、金平氏も、外間氏も、「普天間移設」ではなく、正しく「辺野古の新基地建設」と表現していた)。氏によれば、アメリカ人に沖縄のことを考える視線は無く、トランプに至っては、アメリカの同盟国は恩返しをしろと発言する始末。それに直接的・間接的に同調する東京の人が、現在と構造のまったく変わらない「コザ暴動」をどう受け止めるかが重要なのだとした。
呼応して、川端氏は、「沖縄に米軍基地がある」「米軍基地が東アジアの安定に寄与している」という前提をこそ、メディアが問い直すべきではないのかと発言した。そして、メディアにおいてもっとも怖いものは、自らの「忖度」である、と。
後田多氏は、沖縄が今でも植民地であること、コザ暴動の相手は実はヤマトであったのだと指摘した。
そして、ふたたび比嘉豊光氏が、この写真展とシンポジウムを「見てくれてありがとう」ではなく、「あなたがたは何を引き取るのか」という問いが重要なのだと発言した。
■
大阪でも、この10月頃に写真展を企画しているという。
■
終わってから、会場にいらしていた森口豁さんにご挨拶した。前日に上映された森口氏のドキュメンタリー『かたき土を破りて』には、本シンポジウムの冒頭で流された琉球放送の映像よりもさらに前の様子が撮られていたという(『沖縄 こころの軌跡 1958~1987』に書かれているように、氏はそこに立ちあっている)。
森口氏の関連イベントは以下の通り。
●『~沖縄を語り続けるヤマトンチュ~ 森口豁トークショウ Vol.2』(『島分け・沖縄 鳩間島哀史』1982年、『ひめゆり戦史・いま問う国家と教育』1979年の上映あり): 国立市キノ・キュッヘ(木乃久兵衛)、2016/5/15(日)16:00
●『沖縄の傷痕 アメリカ世の記憶 森口豁×金城実』: 沖縄愛楽園交流会館、2016/4/15-6/30
●『伝えたい!沖縄の今 作家・目取真俊講演会』: 浦和コミュニティセンター、2016/6/5(日)18:45
■
シンポジウムに参加したNさん(沖縄オルタナティブメディア)、Tさん(研究者)と、神保町で飲んで帰った。
●参照
比嘉豊光『赤いゴーヤー』(「コザ暴動」の写真を所収)
三上寛『YAMAMOTO』(「十九の春」において「コザ暴動!コザ暴動!」と叫ぶ)
森崎東『生きてるうちが花なのよ 死んだらそれまでよ党宣言』(主人公たちは「コザ暴動」を経験している)
高嶺剛『夢幻琉球・つるヘンリー』 けだるいクロスボーダー(「コザ暴動」のエピソードが入っている)
比嘉豊光『光るナナムイの神々』『骨の戦世』
仲里効『眼は巡歴する』
仲里効『フォトネシア』