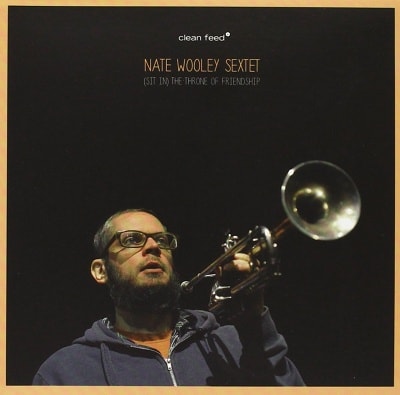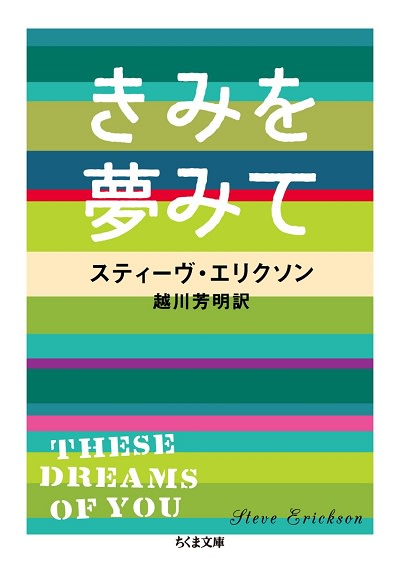ジム・ホール『The Complete "Jazz Guitar"』(Pacific Jazz / Essential Jazz Classics、1956-60年)を聴く。

Jim Hall (g)
Carl Perkins (p)
Red Mitchell (b)
Bonus Tracks:
John Lewis (p)
George Duvivier (b)
Percy Heath (b)
Connie Kay (ds)
名盤として名高い『Jazz Guitar』(Pacific Jazz、1957年)は、ホール20代のときの作品。昔図書館で借りてイイカゲンにしか聴いていなかったこともあり、ボーナストラックが5曲も入った廉価盤をあらためて聴いた。
いくら音量を大きくしても大きくならないホールの音色は、やはりとんでもなく気持ちがいい。上品というのか、カシミヤのようだというのか、とても柔らかで、和音を通じて周囲と溶け合うような感覚である。かつてはそれが物足りなくて、いまひとつ熱心に聴かなかったギタリストなのではあるけれど。この後、ホールのギターは成熟を重ね、まるで、丁寧に漉いた和紙を何葉も何葉も重ねていくような素晴らしいものになっていく。
ボーナストラックがまたなかなか良くて、特に、変態男爵(と勝手に呼んでいる)ジョン・ルイスによる、沈思黙考の沼に沈んでいくようなピアノについ聴き入ってしまう(とくに「I Should Care」)。
ウィリアム・クラクストンによるジャケット写真も秀逸。
●参照
チャーリー・ヘイデン+ジム・ホール
ミシェル・ペトルチアーニの映像『Power of Three』
マイケル・ラドフォード『情熱のピアニズム』 ミシェル・ペトルチアーニのドキュメンタリー