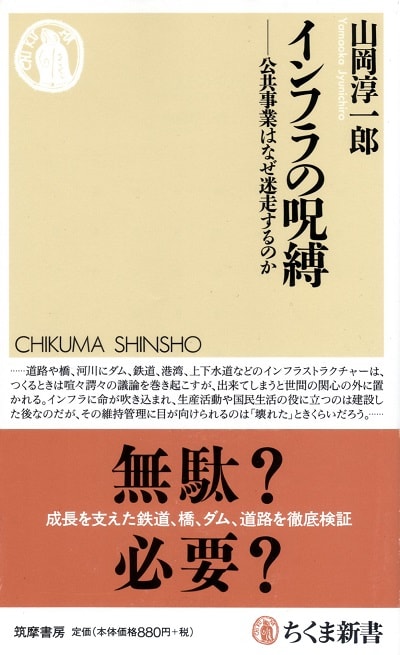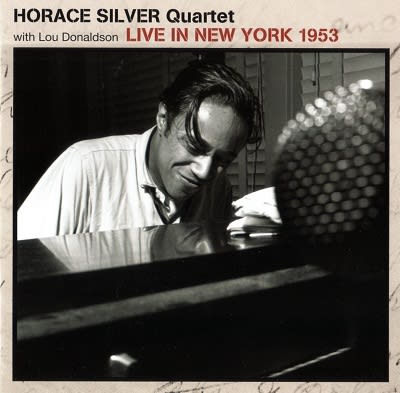先日乗った飛行機のヴィデオプログラムのなかに、『歌のトップテン』があり、あまりの懐かしさにリピートまでして観てしまった。
番組には、内山田洋とクール・ファイブも登場。ふと自問自答した。「あれ?内山田洋・・・前川清・・・???」 そう、似ているふたり、ではない。内山田洋とクール・ファイブのヴォーカル担当が前川清なのであり、バンマス内山田洋は童顔のギタリストである。混乱したじゃないか。
何を今さら、じっくりと「恋さぐり夢さぐり」を聴いたわけだが、これが痺れる。前川清は、直立不動で、歌う前におもむろにマイクをすっと口の前に持ってきて、悠然と、しかも熱く歌う。他のメンバーによるサックスやハモりもまた良い。そんなわけで、忘れられず、ベスト盤を購入した。毎晩のように聴いては、なにものかに対して恥じらっている。

何しろ、「恋さぐり夢さぐり」だけでなく、「そして、神戸」、「長崎は今日も雨だった」、「噂の女」、「東京砂漠」など、いい曲揃いである。こっそり練習して、今度カラオケで歌ってみようかな。これでわたしも立派なオッサン。
それにしても、前川清の声は素晴らしい。憂いものびやかさもある。昔は、志村けんや欽ちゃんにツッコミを入れられるとぼけたオッサンとしか思っていなかった。
ところで、前川清のオフィシャルサイト「清にゾッコン!」がなかなか愉しい。物販サイト「KIYOSK」(笑)には、「長崎は今日も飴だった」という飴が売っている(笑)。