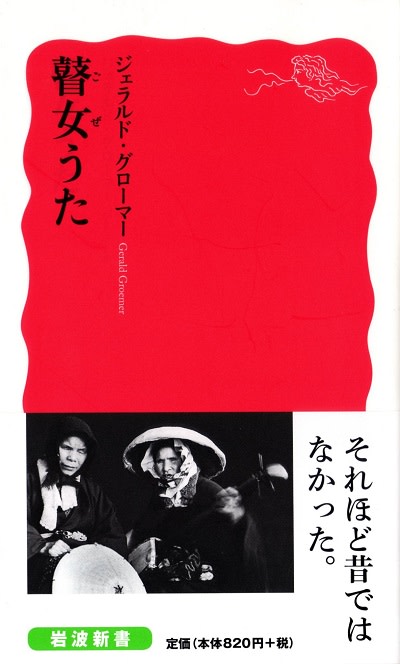岡田暁生+フィリップ・ストレンジ『すごいジャズには理由がある 音楽学者とジャズ・ピアニストとの対話』(ARTES、2014年)を読む。

アート・テイタム、チャーリー・パーカー、マイルス・デイヴィス、オーネット・コールマン、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスとスコット・ラファロ。文字通り、ジャズの歴史を体現するプレイヤーたちの演奏について、何がどのように独創的なのかを語る対話集である。
とても面白い。しばらくサックスを齧って生煮えのままだった自分は、楽譜は適当に読み飛ばすだけだが、それでも、とても面白い。
テイタムの和音の使い方が斬新だったこと、バップ・ピアニストと違って左手を多様に使っていたこと。その文脈で、コールマン・ホーキンスのソロが和音構造的であること。バードのソロが、ずっと先の小節を見据えた鳥瞰的なものであったこと。オーネットの革命が相当に理知的なものであったこと。コルトレーンの音数は世評ほど多いわけではなく、むしろ硬いリードを使った音色にアイデンティティを見出していたであろうこと。ラファロのアクロバチックなベースソロが、技術の水準としても異次元なものだったこと。ああ、なるほどねと膝を叩くような箇所がそこかしこにある。
それにしても、「僕はアイラーはぜんぜん聴かない。Never!」とか、ウィントン・マルサリスの『至上の愛』について「フリー・ジャズのコピーなんてなにかのギャグですよ」とか、ストレンジ氏の言はときどき極端で、それもまた愉快(共感しかねるところもあるが、それはそれ)。
●本書での引用
チャーリー・パーカーと『OMNIBOOK』
ユセフ・ラティーフの映像『Brother Yusef』
藤岡靖洋『コルトレーン』、ジョン・コルトレーン『Ascension』
ラシッド・アリとテナーサックスとのデュオ
ビル・エヴァンス『The Complete Village Vanguard Recordings, 1961』