ようやく年末の休みに入り、本屋を彷徨いたくなって丸の内の丸善に出かけて何冊か買い込み、ご飯を食べてくたびれて帰って、ちょっと本を読んだら厭きて、気が向いて、鈴木志郎康『日没の印象』(1975年)を観る。
>> 鈴木志郎康『日没の印象』
この映像作家は当時40歳、ふと古い16mmカメラのシネコダック16を買う。25mmレンズが1本だけついている。そして100フィート巻のフィルムを入れると高揚してしまい、周りの私的な風景だけを撮り始める(大辻清司も登場する)。そう、まるでボレックスを入手したジョナス・メカスであり、散文的なタイトルと番号を時々挿入するスタイルは明らかにメカスの影響を受けている。
メカスとの大きな違いは、気負って、照れながら語る方法論が本人の独白の大半を占める点だ。だからと言って本当の技術論ではないのであって、「空間論」と銘打っておきながらその論はなく、また、「ワイドコンバーターを付けてみたが何ということはなかった」などの印象にとどまっている。外と中に向けて発信する内向きの視線であり、のちに円周魚眼レンズによって自室内を撮った丸い作品群、『眉宇の半球』にも通じるものがある(買っておけばよかった!)。
しかしその揺らぎが悪くないのだ。映像に挿入された自筆では、焦点の定まらない映像を、「とまどい」と表現している。吉増剛造が8ミリ映画について、「脈動を感じます。それはたぶん8ミリのもっているにごり、にじみから来るのでしょう」(『8ミリ映画制作マニュアル2001』、ムエン通信)と表現した。それらは小型映画に向けられた愛情に他ならない。
リドリー・スコット『ロビン・フッド』(2010年)を観る。12世紀、イギリスを留守にして十字軍だのフランスでの戦争だのに夢中になったリチャード獅子心王、その弟の出来が悪いジョン王。その時代の伝説となったロビンの物語である。

フランスとの闘いの場面は鳥瞰や矢の動き(CGか)など、そうとうオカネがかかっているようで迫力がある。主演のラッセル・クロウより、突然、ベルイマン映画のマックス・フォン・シドーが出てきて驚く。そして中世の浮かれた雰囲気は、舞台は異なるが、ケネス・ブラナー『から騒ぎ』で描かれたそれを思い出させてくれて愉しい。良い映画である。
しかし、リチャード獅子心王(Richard the Lion Heart)なんて、彼に限らないが(シャルル禿頭王とか)、あらためてヘンなセンスのネーミングだ。中学生のとき読んだ筒井康隆『虚構船団』においても、そんな名前の王が次々に出てきては殺され、去っていく歴史が構築されていた。このどうしようもない時間の流れ方は、ギボン『ローマ帝国衰亡史』を参考に描かれたと記憶しているが、ヘンな名前付けも面白がっていたに違いない。つい自分の名前も、「○○ the Coward」(○○卑怯王)とか、「○○ the Small Heart」(○○小心者王)とか名乗りたくなってしまうぞ。
ジョン・ファーマン『とびきり愉快なイギリス史』(ちくま文庫、原著1990年)という本がある。現題を『The Very Bloody History of Britain』といって、それならば素直に『とびきり血塗られたイギリス史』とでもした方がよかったかと思うのだが(だって、大英博物館を見物した人はみんなそう思うでしょう?)、まあ愉快なことに変わりはない。この第9章「いい子のリチャードと悪がきジョン」で、このふたりの王について書かれている。

それによれば、リチャードが殺された石弓は、自分がフランスに持ち込んだ武器だったそうである。ジョンについてはひどい書きっぷり。
「本当にいやな奴で、苦しんでる貧しい国民から金を絞りあげては贅沢三昧、フランスの領土を守るのにつぎ込むんだから。でも、マ、考えてみると王室ってみんなそんなもんだったかな。戦争っていうとまるきり下手で、負けてばっかり(「グニャ剣」って呼ばれていたのはちゃんと訳ありなんだ)。」
「ジョン王は、ひどい食べっぷりでも有名だったんだけど、実際1216年には自分で自分の命を喰い縮めてしまった。」
前者のダメダメぶりは映画でもうまく描かれているが、後者はない(余計か)。この時代には、十字軍が遠征先からナイフとフォークを持ちかえったり(1100年)、イギリスではじめてスパイスや胡椒が使われたり(1140年)、ジョン王がマグナ・カルタに判をつかせられたり(1215年)、と面白い話はいろいろあって、これも映画にはない(これも余計か)。しかし、マグナ・カルタへの流れはもう少し具体的にした方がよかった。自由憲章の約束とその反故はあるのだけど。
毎朝、旧江戸川のカワウとゆりかもめをじろじろ見る。
カワウは日によって大勢で水面に居ることがある。両足を揃えての着水が見ものである。たまにチャプンと潜り、しばらくして浮かび上がったときに魚をくわえていると拍手したくなってしまう。いまは繁殖羽で頭と脚の付け根が白い。


ゆりかもめも可愛い。胸をくっとつきだしていて、ツンツンしていて、まるで毛皮を纏った貴婦人である。赤い脚がオシャレ。





●参照
○旧江戸川のカワウ(2010年12月)
○旧江戸川のゆりかもめ、カワウ、ドバト(2010年2月)
○川本博康『東京のカワウ 不忍池のコロニー』(科学映像館の無料配信映画)
○行徳近郊緑地保全区域内鳥獣保護区におけるカワウの生息状況調査について(市川市)(浜離宮のカワウ追い出しによって行徳に移動したことがわかる)
○行徳のカワウコロニー(行徳野鳥観察舎日記)
1985年夏、群馬県御巣鷹山への日航機墜落事件を描いた、横山秀夫『クライマーズ・ハイ』(2003年)。小説と、原田眞人による映画(2008年)との間に、NHKで放送されたテレビドラマ(2005年)がある。主役は佐藤浩市、映画の堤真一と比べても悪くない。詰め込み過ぎの感があった映画よりも丹念に描いていて、これも悪くない。
山口県の宇部商が、甲子園の決勝戦で桑田・清原を擁するPL学園と対決した夏でもあった。私の3つ上、親戚も出ていて、記憶は決して消えない。編集局に置いてあるテレビ画面に、東農大二高とどこかとの勝者が宇部商と対戦するというニュースがうつし出されていた。なお小説では、《農大二、宇部商に惜敗》という記事が登場する。
音楽は大友良英とサインホ・ナムチラック。昨日観るまで気が付かなかった。もっともサインホは、収録当時、東京でのライヴをやらなかったようではある。あの凄まじい声をまた浴びたいと思い続けている。
それにしても、まるで生死も人生もかけて仕事場で闘う姿を見ると、理屈抜きで泣きそうになるほど熱くなってしまう、何でかな(笑)。『プロジェクトX』で燃えるサラリーマンを笑うことなどできないね。

●参照
○横山秀夫『クライマーズ・ハイ』と原田眞人『クライマーズ・ハイ』
○山際淳司『ルーキー』 宇部商の選手たちはいま
○サインホ・ナムチラックの映像(大友良英+サインホ)
○TriO+サインホ・ナムチラック『Forgotton Streets of St. Petersburg』
○姜泰煥+サインホ・ナムチラック『Live』
○ジョン・ブッチャー+大友良英、2010年2月、マドリッド
○大友良英+尾関幹人+マッツ・グスタフソン 『ENSEMBLES 09 休符だらけの音楽装置展 「with records」』
○『その街のこども』(大友良英による音楽)
○『鬼太郎が見た玉砕』(大友良英による音楽)
ヴァシリー・カンディンスキーは自分にとって何人かの特別な画家のひとりだ。そんなわけで、三菱一号館美術館で開かれている『カンディンスキーと青騎士展』にいそいそと足を運んだ。

展示は、カンディンスキー・コスモス(ケイオスか?)が開闢する前の風景画や宗教画などから始まる。既に紫やピンクや青や黄の使い様がただごとでなく、ムルナウやミュンヘンといった南ドイツを描いた作品群は素晴らしい。ただ、後戻りできない宇宙を開いてしまってからは、素晴らしいという言葉を超えてしまう。本当である。こればかりは現物を目の当たりにしないと体感できない。
以前も感じたことだが、カンディンスキーに比べると、教え子でありパートナーであったミュンターの作品はフォロワーの域を超えるものではない。マルクの素晴らしい作品何点かを観ることができるのは嬉しいが、1点だけあるクレー作品はかなり格落ちであり、やはり天才クレーの世界を見せつける作品なら他にごまんとある筈だ。そんなわけで、「青騎士」に焦点を当てるのはいいとして、全体的にアンバランスな展示ではあった。しかし、展覧会なんて、脳を震わせる作品がひとつでもあればいいのだ。
今回の作品群はミュンヘンのレンバッハハウス美術館の所蔵品であり(ミュンヘンにはちょっと足を踏み入れたことがあるだけで、この美術館には行ったことがない)、ミュンターが寄贈したものが中心であるようだ。1996年に池袋のセゾン美術館で開かれた『カンディンスキー&ミュンター 1901-1917』でも同美術館の所蔵品が含まれていたが、当時のカタログを確認してみると、重なる作品はさほど多くなかった。むしろ、カタログにレンバッハハウス美術館の学芸員が寄稿したテキストに挿入されている優れた作品群、たとえば、カンディンスキーの「ミュンヘン―イーザル川」という初期の小品、それから宇宙開闢後の大作「山」や「印象III(コンサート)」が今回展示されているわけで、これは眼が悦ぶ。
それにしても、カンディンスキーは1910年ころに至る数年間に恐ろしいほどの変貌を遂げている。必ずしもアートシーンに受容されなかったという環境やミュンターとの私生活によるものとは思えない。これが100年前なんてなあ。

『カンディンスキー&ミュンター 1901-1917』カタログ(セゾン美術館、1996年)
今年の夏につかこうへいが亡くなって、たまに蒲田を通過すると聞こえてくるメロディを思い出して、深作欣二『蒲田行進曲』(1982年)を観る。パンフレットもその辺で50円で買っておいた。

松坂慶子は美しいなあ。それにしてもクサい映画だなあ。中村雅俊「恋人も濡れる街角」なんて聞こえてくると恥ずかしくなってくるぞ。
つかこうへいが自身の作品を小説化した角川文庫を読んだのは確か中学生のとき。「階段落ち」のヤスが調子にのって松坂慶子に豚汁を魔法瓶に入れて持ってこさせる場面があったような気がするが、映画にはなかった。最後の「階段落ち」も、そこでお終い、ヤスの生死はわからないままだったような・・・。まあ、つかこうへいがパンフに書いているように「久しぶりに、嘘にみちた映画らしい映画」かもしれないから、監督が職人の深作欣二であることも含めて、これでいいのだ。
昨晩(12/24)、NHKで放送されていたドキュメンタリー『つかこうへい 日本の芝居を変えた男』を録画しておいて、さっき観た。不幸にも演劇にまったく縁のなかった自分にとって、つかこうへいといえば『蒲田行進曲』だけである。それでも、役者の地を引きだしていく様には眼を奪われた。
本名・金峰雄(キムボンウン)の在日コリアン2世、遺書には、遺灰を日本と韓国の間、対馬あたりに撒いてくれと書いてあったという。たしかペンネームの由来は「いつか公平な世の中に」であったはずだが、そのことはドキュでは触れられていなかった。また在日としてのアイデンティティを問うた作品の韓国公演が失敗に終わった原因も、「目新しさがなかった」という理由で片づけられていた。そんなあたりが生煮えな印象であるが、今更ながら、つか演劇に興味が出てきている。遅いか。
蒲田には当面用事がない。とりあえず、近いうちに銀座の「ニューキャッスル」で、「蒲田」を食べなければならない。

「ニューキャッスル」の「蒲田」
イランの映画作家モフセン・マフマルバフが『カンダハール』(2001年)を発表した後の発言録、『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない 恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』(現代企画室、2001年)。同年の「9・11」直前であり、タリバン政権下のアフガニスタンの姿を伝えている。外部からアフガニスタンに向けられる視線の不在を訴えているレポートでもある。
タリバンがバーミヤンの大仏を破壊したのは2月であった。そして北部同盟のマスードが暗殺されたのは「9・11」の2日前であった。

「もし、アフガニスタンが山岳地帯でなかったら、ソ連はアフガニスタンを容易に征服していただろう。あるいは、アメリカがその野望を、実行に移していただろう。しかし、峻険な地形は、軍事費を増大させるばかりか、戦後の再建と平和に必要な費用も莫大なものにする。アフガニスタンの山岳が険しい地形でなければ、間違いなく、その経済的・軍事的・政治的・文化的な未来は違っただろう。これは、アフガンの民の歴史的運命に書き込まれた、地理的な不運というものなのだろうか?」
ここでマフマルバフは、その後の泥沼の拡大再生産を予見している。岩山と部族社会という側面は現代の支配方策を持ってしても突き崩すことが難しいものであり、アフガンはもとより、同じ側面を持つイエメンでも、「アラビア半島のアルカイダ」が拠点にしている。シンポジウム『中東の今と日本 私たちに何ができるか』(2010/11/23)においても、「アフガンの治安悪化についての誤算は地域性や民族性であり、全国横断的な政治団体はできないということ」との指摘があった(田中浩一郎氏)。
重要な指摘は、タリバンが「政治的にはパキスタンに庇護された傀儡政府」であり、「個々の人間としては、ムジャーヒディーンを育てるパキスタンの神学校(マドラサ)で教育された、飢えた若者たち」であったということ。また、世界の麻薬市場で得られる利益の800分の1しか生産国アフガンが得ていないこと(まるでコーヒー市場のように!)。
一方では、アフガンに対する世界の無関心を嘆くあまり、まるで帝国が介入すればまだましな方向に向かうかのように書いているようにも感じられる。女性が顔を隠すことへの西側的な批判の視線も気になるところではある。米国介入後のアフガンについて、2001年時点でもやもやしていたマフマルバフの考えに、どのような発展、あるいは、変化があっただろう。
「アフガニスタンには、クウェートとは違って、石油もそれによる余剰収入もない。仕事を待ち望むアメリカ軍に、その費用を払うことができない。しかし、他の答えも聞こえてくる。アメリカがあと何年かターリバーン政権の存続を許していれば、東洋のイデオロギーについて世界中で醜悪なイデオロギーが作られ、アフガニスタンでの近代主義と同様、それに対する拒否反応を起こすだろうからだ。世界のある地域では革命的で改革的だと思われているイスラームが、ターリバーンの逆行的なそれと一緒くたにされたら、世界はイスラームの拡大に対し常に反発を示すだろう。」
●参照
○中東の今と日本 私たちに何ができるか(2010/11/23)
○ソ連のアフガニスタン侵攻 30年の後(2009/6/6)
○『復興資金はどこに消えた』 アフガンの闇
○ヴィム・ヴェンダース『ランド・オブ・プレンティ』(「9・11」後の病んだ米国)
○マイケル・ウインターボトム『マイティ・ハート 愛と絆』(病んだ米国の非対称な視線)
○コーヒー(1) 『季刊at』11号 コーヒー産業の現在
○コーヒー(4) 『おいしいコーヒーの真実』
●参照 イラン映画
○カマル・タブリーズィー『テヘラン悪ガキ日記』『風の絨毯』、マジッド・マジディ『運動靴と赤い金魚』
○サミラ・マフマルバフ『ブラックボード』(マフマルバフの娘)
○バフマン・ゴバディ(1) 『酔っぱらった馬の時間』
○バフマン・ゴバディ(2) 『ペルシャ猫を誰も知らない』
○バフマン・ゴバディ(3) 『半月』
○バフマン・ゴバディ(4) 『亀も空を飛ぶ』
○ジャファール・パナヒ『白い風船』
○アッバス・キアロスタミ『トラベラー』
○アッバス・キアロスタミ『桜桃の味』
板橋文夫『うちちゅーめー お月さま』(アカバナー、1997年)が発表されたとき、ゴリゴリの板橋文夫がなぜ沖縄なのか、変化球ではないのかと奇妙な印象があった。ピアノとピアニカ、曲によって石垣の唄者、大工哲弘が参加する。
実際にこの盤を聴く前に、新宿ピットインで行われたライヴ(1997年?)に足を運んだ。大工節とでも言うべき独特の発声を行う大工哲弘の存在も、そのときにはじめて認識した。彼が唄い、板橋文夫が微妙(笑)に声を出す「生活の柄」に惹きこまれてしまった。山之口獏の詩に高田渡が曲を付けた唄であることはその後に知った。自分に知らない世界を見せてくれたという意味で、忘れられないライヴである。
そして板橋文夫のこの仕事は、変化球ではなかった。沖縄音楽が好きで入り込もうとしている姿が見えた。
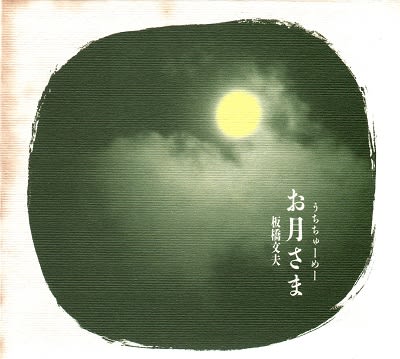
この盤に収められている曲は定番ばかりだが、いつ聴いても新鮮で清々しい。「てぃんさぐの花」はピアノとピアニカのふたつの演奏があり、糸満の大度海岸で記録されたらしい(あの岩礁を前にピアノに向かう板橋文夫を想像するだけで嬉しくなる)。それに「月の美しゃ」、「生活の柄」、「えんどうの花」、「安里屋ユンタ」。
またこの人が、沖縄に向かわないかな。
●参照
○ユーラシアン・エコーズ、金石出(板橋文夫)
○本間健彦『高田渡と父・豊の「生活の柄」』、NHKの高田渡
○「生活の柄」を国歌にしよう
○山之口獏の石碑
○糸満のイノー、大度海岸
サックスのみのソロを聴くのは割と襟を正すようなところがあって、それというのも、何も助けのない時空間で吹くのは特別なことに違いないからだ。それでも阿部薫などはどうも作り上げられた幻想としか捉えることができず、苦手である。尤も、直接的であるから苦手だと意識するわけではある。
若松孝二『エンドレス・ワルツ』(1995年)において、阿部薫の音を吹きかえたのは柳川芳命だった。そうは言っても、阿部薫とは違う。そもそもこの若松孝二らしからぬエネルギーを持たない映画は、主演の選び方において重大な間違いを犯している。(ところで、公開後しばらくして、フェダインのライヴを聴いたとき、この映画にも出演していたサックスの川下直弘さんが、「まだ観ていない。レンタル屋にあるかな」と呟いていた。)
このプレイヤーが羽野昌二と共演した記録も聴いてみたくはあるのだが、まずはソロ『地と図 '91』(Art Union Records、1991年)でも個性が出ているような気がしている。ライナーノートで本人が「サックス本来のもつメロディー楽器としての機能に立ち戻り、「唄う」ことに視野を広げてみた」と書いているが、実際に聴きこんでみると、眼前に現れるのは「ど演歌」である。ど演歌と言って悪ければ、新井英一を聴くようなアジアン・ブルースである。特に5曲目、アルトによる演奏の情念の鬱屈さは吐きそうだ。(勿論評価している。)

『浦邊雅祥ソロ』(PSF、1996年)も、ここのところ頻繁に聴いている。まだ一度も訪れたことがないのだが、明大前のキッドアイラック・ホールで記録された1時間弱の演奏である。観客が息を潜める中、高音で、まるで削った金属塊に魂を込めて投げ出すような感覚、それが断続的に繰り返される。大変な緊張感である。
この強度が何なのか、実際に演奏に立ち会ってみるまでは判断できない。

●参照 サックス・ソロ
○マッツ・グスタフソンのエリントン集
○ロル・コクスヒル
○ジョン・ブッチャー
○ペーター・ブロッツマン
○リー・コニッツ+今井和雄『無伴奏ライヴ・イン・ヨコハマ』
李恢成『流域へ』(講談社、1992年)を読む。最近講談社文芸文庫版で復刊されたが、上下巻でそれなりに高いため、単行本を古本で買った。
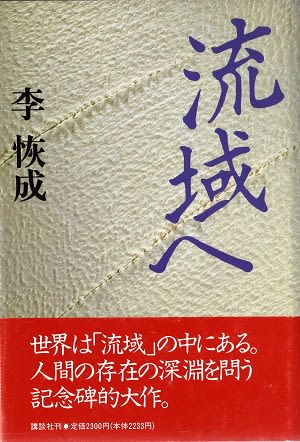
中央アジア、カザフスタンやウズベキスタンには、多くのコリアンが住んでいる。本作は、彼らの現在と歴史を追って中央アジアへと旅立つ在日コリアンの小説家の物語であり、サハリン出身ということからも、李恢成本人が反映されているように思われる。かつて朝鮮半島から中国東北部、またソ連へと多くの人々が移り住んだ歴史がある。1937年、スターリンは国防と管理のしやすさのため、獄寒の荒地へと、コリアン17万人を強制移住させた。まさにディアスポラであった。本作でも「三七年問題」として繰り返し追及されている。
確かに冗長な小説である。しかし、そうでなければならない小説でもある。中央アジアに住む「コレサレム」にとっても、サハリンを逃れ日本に住む在日コリアンにとっても、また彼らが想いを馳せる、北朝鮮や韓国に渡った人々にとっても、ここで言う「民族」とは何か、「異郷」とは、「故郷」とは何か、人が生きるとは何か、そんなことを問うには、冗長でなければならないからだ。
勿論、共産主義というイデオロギーの嘘も、日本にもソ連にも遍く違う形で存在する差別感情も衝く。
「日本のテレビや新聞の世論調査では、「日本人に生れてよかった」というのが国民的常識に近いらしい。しかし、「日本に生れてよかった」といっている日本人のかなりの層は「日本に生れて困った」とか「日本でくらしていてつらい」と思っている在日外国人のことを知らない国民でもあった。」
しかし到達するのは、民族や血や土地という呪縛をやや超えようとする人間観のようなものであった。ここに登場するクリミア・タタール人の独立運動家は、この複雑な流域にあって、在日コリアンの小説家にパレスチナのことを問われ、ロシア人の妻をふりかってから、「わたしにはいつも人間しか存在していません」と静かに言う。
意識しようとしまいと、誰もが流域に、流刑地に存在する。そこに居るとは、たまたまそこに居るに過ぎない。
「「わたしはひとの立場になって人間は考えることができない存在だと思っているのですが・・・・・・」 愈真が考えこみながら行った。 「・・・・・・でも、こうも思いますね。他人の立場がわからなければ自分の存在も知ることはできないもんです」
「どういうことでしょう?」
「ええ。人間の苦しみはそれほど深いということでしょうか。それを理解し、なにかを乗りこえるのは至難のわざです。恋というのも双方の立場が理解されないとうまくいかないものですからね。失礼だけど、あなた方の場合も、そうだったんじゃありませんか」
小説家はホテルのベッドで寝ることができない。ベッドが、長年にわたり苛烈な目をみたであろう人の形に変わり、「万人用の鋳型」になっている「寝棺」であったからだ。彼はこの「寝棺」を、「三七年問題」の象徴のように考えつつも、その考えを超えようとする。結論など出ることはない。迷い悩まなければならない。
「だが、寝られぬ理由を、ひとえにこの「寝棺」のせいにしてしまうのはなんと安易なことだろう。ひとはそんなに神々しくはない。生きていくときの良心の疼きが悪夢を生み出しているのもたしかだった。ひとは他人のことばかり思って夜をすごすほど人間に忠実でもないのだ。このベッド、「寝棺」になにもかも押しつけてしまうとき、人間のあらたな偽善や不幸がはじまるのかもしれない。」
●参照
○李恢成『沈黙と海―北であれ南であれわが祖国Ⅰ―』
○李恢成『円の中の子供―北であれ南であれわが祖国Ⅱ―』
○李恢成『伽�塩子のために』
○朴三石『海外コリアン』、カザフのコリアンに関するドキュメンタリー ラウレンティー・ソン『フルンゼ実験農場』『コレサラム』
NHKの「新日曜美術館」で、比嘉康雄の特集を組んでいた。報道写真家を志しながらも、カメラを真後に向け、事件に象徴される沖縄ではなく、ひとりひとりの顔に体現される沖縄を撮るようになった写真家の移り変わりを追っていて興味深かった。そして比嘉康雄は、久高島の祭祀へと向かう。そのとき、写真家の中で生まれた言葉は、「際に立ち会う」であったという。
沖縄は常に<際>(きわ、マージナルな場)にあったし、現在もそうあり続けている。<際>に立つことは世界を見ることだ、それは真実だと思う。かつて、ヤマトゥから沖縄という<際>へと身を寄せた東松照明はこんなふうに書いた。
「いま、問題となっているのは、国益のためとか社会のためといったまやかしの使命感だ。率直な表現として自分のためと答える人は多い。自慰的だけどいちおううなずける。が、そこから先には一歩も出られない。ぼくは、国益のためでも自分のためでもないルポルタージュについて考える。 被写体のための写真。沖縄のために沖縄へ行く。この、被写体のためのルポルタージュが成れば、ぼくの仮説<ルポルタージュは有効である>は、検証されたことになる。波照間のため、ぼくにできることは何か。沖縄のため、ぼくにできることは何か。」(「南島ハテルマ」、『カメラ毎日』1972年4月号所収)

『時の島々』の表紙にもなっている写真。キヤノン・ぺリックスに28mm、トライXで撮られたもの。
東松照明にとって、<際>への移動こそがアイデンティティであった。それでは、もとより沖縄という<際>にあって沖縄を写す写真家とは何だろう。比嘉康雄は、沖縄のなかでもさらなる際、久高島に視線を向けた。<際>から<際>への移動があった。そうではなく、いまの政治と社会にあって沖縄が<際>であり、移動がないと言うことはできないが、それでも、あからさまな形ではないということである。この内部での跳躍を、勇気であり、かつ、表現であると見るべきか。
豊里友行『沖縄1999-2010 ―戦世・普天間・辺野古―』(沖縄書房、2010年)を凝視していると、そのような思いが去来する。摩文仁、渡嘉敷島、辺野古、勝連、北谷、普天間、泡瀬、嘉手納、コザ、象の檻・・・。ここには決定的な場所も時間もある。象徴性も事件性もあり、モノクロ写真のクオリティは高い。飲んだくれる米兵や彼らにサービスを提供する女性たちに迫った写真など素晴らしいと思う。そして840円という低価格は過激であり、廉価で売られた土門拳『筑豊のこどもたち』のことを思い出す。

その一方で、あまりにも多くの情報が肩に圧し掛かってきて、写真というアートとしてどう捉えるべきなのかとも思ってしまう。
以前、飲み会で北井一夫さんにこの写真のことを問うてみる機会があった。そのときのコメントを書くのはルール違反だが、間接的に豊里さんにぶつけてみる意味で、私信ではなく、ここにあえて書いてみる。これを私はどう受け止めるべきなのか、それも判断しかねている。
曰く、
沖縄の政治家や学者などのコラムがあるのには違和感がある。
政治に依存しすぎてはならない、政治は力なのだから。
沖縄という特権に嵌ってはならない。
表現者は、何かに依存せず、孤独でなければならない。
『東京ベクトル』の方向性は良かった。
石川真生のあり方を見て考えてみてはどうか。
※公式の場でもなく、発言そのものでもないため、文責は当方にあります
●沖縄の写真
○比嘉豊光『光るナナムイの神々』『骨の戦世』
○仲里効『フォトネシア』
○『LP』の「写真家 平敷兼七 追悼」特集
○「岡本太郎・東松照明 まなざしの向こう側」(沖縄県立博物館・美術館)
○平敷兼七、東松照明+比嘉康雄、大友真志
○沖縄・プリズム1872-2008
○東松照明『長崎曼荼羅』
○東松照明『南島ハテルマ』
○石川真生『Laugh it off !』、山本英夫『沖縄・辺野古”この海と生きる”』
○豊里友行『彫刻家 金城実の世界』、『ちゃーすが!? 沖縄』
●久高島
○久高島の映像(1) 1966年のイザイホー
○久高島の映像(2) 1978年のイザイホー
○久高島の映像(3) 現在の姿『久高オデッセイ』
○久高島の映像(4) 『豚の報い』
○久高島の猫小(マヤーグヮ)
○久高島で記録された嘉手苅林昌『沖縄の魂の行方』、イザイホーを利用した池澤夏樹『眠る女』、八重山で演奏された齋藤徹『パナリ』
NHK「BS世界のドキュメンタリー」枠で放送された、『復興資金はどこに消えた』(フランス・Premieres Lignes / AMIP、2007年)を観る。アフガニスタンに流入するオカネが、不正と腐敗により、消えていく姿を追ったドキュである。
アフガンには、2001年の暫定政権成立以降、国際支援の名のもとに多額のオカネが集まっている。米国(国際開発局:USAID)、日本(JICA)、英独仏など欧州諸国、世銀やADBなどの機関からの拠出である。それが汚職により本来のところに辿り着かないことが問題となっており、ドキュでも、CNNがカルザイ大統領に対し、汚職と麻薬取引の解決について質問を浴びせる様子が収められている。
このドキュでは、まず、米国が「アフガンで680万校の学校を修復・建設した」と表明している点を追う。探しても人々が流入するカブール市内には壁も屋根もない学校が見つかるばかり、実際のところ、郊外の学校に充てられたらしいことがわかってくる。学校だけではない。イタリアのNGO・インテルソスが関与した病院建設事業では、結果的にオカネが辿り着かず、手抜き工事の結果、建物が数年で駄目なものになっている。そのことをインテルソスは認めようとしない。
また、何世代も貧しい人々が住んでいた地で、強制的に立ち退かせ、次々に、豪華な邸宅が完成している。たとえば建設費40万ドルであったり、月額2万ドルの賃貸住宅であったり。誰が関与しているかはわからない状況である。元計画相の国会議員、ラマザン・バシルドストが調べた結果、公的資金がそこに流入していたことが見えてくる。たとえば900m2の国防省保有の土地を、知事、将軍、メディア社長、警察本部長、テレビジャーナリストたちが、せいぜい200-300ドル(!)のオカネで手に入れているのだ。それを指示していたのがモハマド・ファヒム副大統領・国防相であり、彼はマスードの暗殺(2001年)の後に北部同盟の幹部となってタリバンと対峙し、米国ラムズフェルド国防長官(当時)と密な関係を築いた人物であった。
そのような腐敗政治、社会の上層部のみ潤い、国際支援とヘロイン取引それぞれ40億ドルが海外の投資家を引寄せ、富裕層向けのショッピングモールが出来たりもしている。恐ろしい。これがアフガンの現実の一側面か。
日本のアフガン支援(5年間で総額50億ドル)については、シンポジウム『中東の今と日本 私たちに何ができるか』(2010/11/23)において次のような実態の報告があった(伊勢崎賢治)。
○民主党は、テロ特措法によるインド洋での給油活動の停止をせざるを得なかった。その代わりに、米国を納得させるため、鳩山政権が5年間で総額50億ドルの援助を合意した。
○50億ドルの使途は、①治安支援(優秀な国軍と警察を作る)、②タリバン兵の社会復帰支援、③民生支援。
○①については、警察を短期間に急増させることになり、腐敗の象徴と化している。これを命令したのはブッシュ政権下のラムズフェルドである。カルザイ政権にとっては、カネで結びつけることができる力が増えたわけで、歓迎だろう。こんな恥かしい使途を公言するのは日本くらいだ。
○②については、結局はタリバンとの関係がグレーな民兵にカネが流れることになり、逆効果。
○③については、軍事組織が人道支援などすべきではないし、NGOがターゲットになってしまう。
国際貢献などという言葉の裏を考えなければ駄目だということだ。
●参照
○中東の今と日本 私たちに何ができるか(2010/11/23)
○ソ連のアフガニスタン侵攻 30年の後(2009/6/6)
○番組サイト(BS世界のドキュメンタリー)
旧江戸川には、もやい用の杭がたくさん立てられている。日や時間によって、すべての杭の上に鳥が一羽ずつ止まっていたり、ほとんどいなかったり。ある時、鳥が種を運んで来たのか、ある杭の上に草が生えていた。毎日気になって見ていると、だんだん枯れてきた。
いまの鳥はカワウとゆりかもめ。翼をときに広げて威張るカワウは、たまに腰を付きだしているかと思うと、プッと糞をする。京浜工業地帯の建設とともに消えた千葉県・大厳寺のコロニーでは、糞を農業肥料として使うためにカワウ保護をしており、さらに、カワウが樹上から落す食べかけのハゼ、カレイ、コハダなどを住民がせっせと拾い、動物の餌にしていたという。
東京湾におけるカワウのコロニー史は、羽田(空港の開発により1940年代に消滅)、大厳寺(京浜工業地帯の建設により1971年に消滅)、不忍池、浜離宮(1995年頃追い出し)、いまは木更津の小櫃川河口(盤洲干潟)や行徳の新浜鴨場など、といった変遷があるということになる。旧江戸川のカワウは行徳あたりから魚を獲りに来ているのかな。
カワウの首や足の付け根は白くなっている。繁殖羽であるらしい。

朝、コンデジで撮影

朝、コンデジで撮影
●参照
○川本博康『東京のカワウ 不忍池のコロニー』(科学映像館の無料配信映画)
○旧江戸川のゆりかもめ、カワウ、ドバト(2010年2月)
○行徳近郊緑地保全区域内鳥獣保護区におけるカワウの生息状況調査について(市川市)(浜離宮のカワウ追い出しによって行徳に移動したことがわかる)
○行徳のカワウコロニー(行徳野鳥観察舎日記)
上巻からしばし時間をおいて、ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー 資本主義と分裂症』(中)(河出文庫、原著1980年)を読む。

いくつものプラトー、そのいくつかに、電車の中で、文字通り引くほど、頬が笑いで痙攣するほど、仰天させられる。先生、何考えてるんですか。
<顔貌性>の議論。シニフィアンが顔を作るのではなくその逆であり、読む者のイメージとしては、逃走線がレーザー光線のように<ホワイト・ウォール>を形成する。いや、その<ホワイト・ウォール>は地層のようなものではなく、いつまでも逃走の可能性を秘めた<ホワイト・ウォール>そのものである。そして主体性の<ブラック・ホール>からの脱出。このコンテクストに恋愛を絡める下りで引きながらも感動してしまう。
<なる>ことの議論。男性と女性、人間と動物などという二元論を突破するために、ここでは、「あらゆる生成変化は分子状」だと喝破する。やはり視覚的なイメージがあらわれる。具体的な姿、実は<ブラック・ホール>の底に淀んだ分子たちの集合体が、マッスとしてではなく、分子レベルで他の領域へと遷移していき、それらが逃走線を描くイメージが。ここでも、分子状の生成変化が<性愛>に結び付けられ、また仰天する。
「性愛とは数限りない性を産み出すことであり、そのような性はいずれも制御不可能な生成変化となる。性愛は、男性をとらえる女性への生成変化と、人間一般をとらえる動物への生成変化を経由する。つまり微粒子の放出である。」
性愛は置いておいても、よく私たちが、受苦の者たちと化した場合の想像力を問うとき、この分子状の生成変化を意味しているのではないか?そして、かつて丸山眞男が<であること>と<すること>を議論したことにあわせて、<なること>を積極的に加えることが重要なのではないか。
議論は生命のありようにまで進む。それはあまり明快にも感じられなかったが、生成変化を、<脱地層化の剰余価値>を生命の場として位置付けていることだ。これが大団円であればそれなりに感動もするが、さて、このあとどのように滅茶苦茶な議論がなされるのか。
彼らによれば脱領土化、逃走線の絶えざる形成に、クレーやカンディンスキーの絵画、また音楽が、リズムが、関連付けられる。ドゥルーズを読むことは音楽のノリに付き合うことだと感じていた自分には、奇妙に共感できる主張であった。ドゥルーズを読むことは音楽を聴くこと、ではなく、脱領土化のシミュレーションに付き合っていること。
「硬質な切片は、社会的な規定を受けとり、前もって定められ、国家によって超コード化されると思われがちだ。逆に柔軟な切片性の線は、空想や幻想など、内面の営みとされる傾向にあるようだ、そして逃走線は、あくまでも個人の問題で、各個人がそれぞれに逃走し、「責任」を、世界を逃れ、砂漠や芸術に逃避することだと考えられているようだ。勘違いもはなはだしい。柔軟な切片性は空想とはおよそ無関係だし、ミクロ政治学は、その広がりと現実性において、もう一つの政治学に劣るものではないのである、大規模な政治学がモル状の集合をあやつるには、助力にもなれば妨害にもなるミクロの貫入やミクロの浸透を欠くことができない。それに、集合が大きくなればなるほど、集合に巻き込まれた審級の分子化が促進されるのである。また、逃走線とは決して世界を逃れるものではない。むしろ水道管を破裂させるようにして、世界に逃走を強いるところにこそ、逃走線の本領があるのだ。」
●参照
○ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー』(上)
○ジル・ドゥルーズ『フーコー』
○フェリックス・ガタリ『三つのエコロジー』














