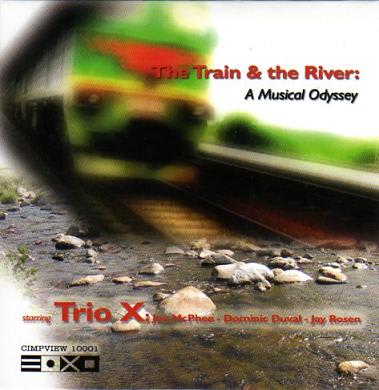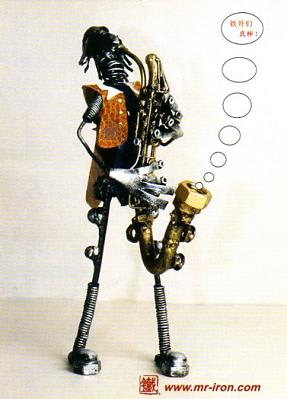ラーメンも日本蕎麦もうどんも、もちろんスパゲッティも焼きそばも、カップ麺も好物である。当然ながら沖縄そばも食べずにはいられない。
■大東そば(那覇、ニューパラダイス通り)
那覇に行くたびに食べている気がする。麺は独特のしこしこ感があってしみじみ旨い。鰆を「づけ」にした大東寿司も旨い。いつだったか、南大東島に行こうかと思って、1ヶ月ほど前に船運会社に問い合わせたところ、そんな先の運行スケジュールなんか決めていないと言われ、笑って諦めた。船が断崖絶壁に着くため、クレーンで人ごと上陸するという島であり、いまだ憧れている。
今回ここに行く前に、沖映通り沿いのソフトバンクの携帯ショップの前に取材陣が群がっていた。野次馬として近づくには空腹すぎて、横目で睨んで通り過ぎた。店内のテレビに目をやると、そこが映っていて驚愕。千葉から女性をさらって来ていた容疑者が逮捕された直後だった。
ところで店内では、オリジナルのTシャツを売っている。黒地で、そばが箸からひょろひょろと垂れ下がっている秀逸なデザインである。結局今回も買わなかった。


糸満の海にデジカメが落下したので、ここから後は、ケータイで撮る。
■うるくそば(那覇、奥武山公園近く)
麺は平打ち、細麺、太麺の3種類、スープは鰹だしと豚骨の2種類から選ぶ仕組。もう鰹だしがなくなっていたので豚骨スープを選んだ。スープのせいか、ラーメンのノリだ。
■いしぐふー善(宜野湾市)
宜野湾市立博物館を見学した後に彷徨っていて発見した。普天間基地の南西あたりの住宅街にある。薄焼き卵が上に乗っているのがユニークで、トッピングの軟骨ソーキは別にわさびを付けて食べる。アグー豚を使ったスープを売りにしているが、従来の鰹節と豚だけではないようなコクがある。この凝りかた、ラーメン店のオリジナリティの出し方とかなり共通点があるようだ。ここも旨い。また食べたいぞ。


■どらえもん(那覇、国際通り)
いつか入ってみようと思っていた宮古そばの有名店。何故「どらえもん」なのかわからないが、確かに店内にドラえもんの人形が飾ってある。麺はつるつるしこしこ。子どもたちは凄い勢いで食べていたので本物である。皆で旨い旨いと繰り返した。


今回なんとなく感じたのは、沖縄そばのラーメン化である(誰かがもう言っているかもしれないが)。スープにコクを持たせ、スープだけでなくトッピングも工夫している。はじめて沖縄を訪れたときには、ラーメン屋が少ないなあという印象が強かった。ところが最近とくにラーメン屋が増えているようで、沖映通りには「暖暮」、宜野湾の国道58号沿いには池袋の「大勝軒」が店を出していた。何年か前に、杉並の「沖縄タウン」にある「琉球製麺」で食べたときにも同じ違和感を抱き、本土だからラーメンとブレンドしているのかなと感じていたのだが、沖縄でもそうだったわけだ。良いことか悪いことか。