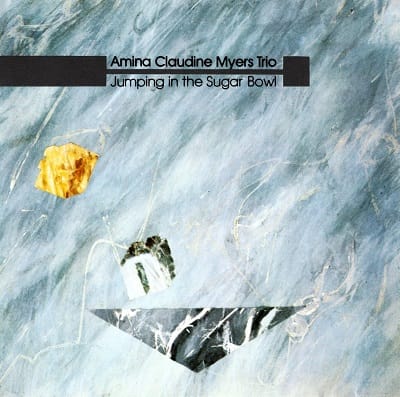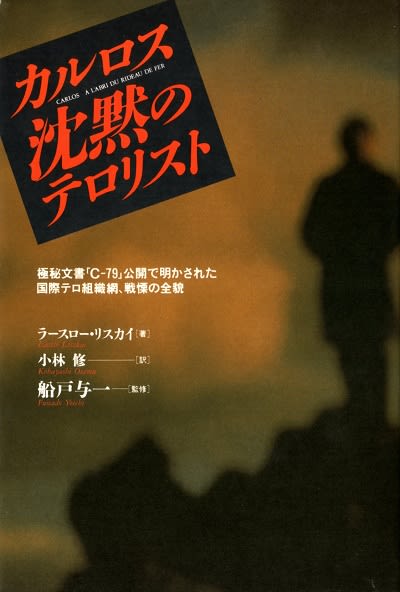ドン・デリーロ『コズモポリス』(新潮文庫、原著2003年)は、自ら率先して破滅していく若い金持ちの物語である。
実業家の「彼」は、資本主義システムの中を知的に泳ぎ、富豪となった男。ひたすら長いリムジンに乗り、ネットを通じてオカネを操り、欲しいものをすべて手に入れる。マーク・ロスコの絵を買わないかと持ちかけられると、逆に、ロスコ・チャペルをわがものにしようとさえする男である。
あるとき、「彼」は、散髪に行きたくなり、リムジンで街の反対側へと出かける。その過程で、日本円に投資しすぎて自社を潰し、なぜか自分のボディーガードを殺し、丸腰で危険地帯の床屋に辿りつき、果ては、自分の命を狙うスラム街の男のもとへ乗り込んでいく。
すべては、身体感覚が欠如していた世界にあって、それを希求してのことであった。すべてが情報としてフラットかつ過剰であれば、踏み入ってはいけない領域も、身体的・感覚的な閾値としてではなく、ただの情報として得られているのみ。そのようなものは破るのが身体感覚の反乱というものだ。従って、愛人には護身用のスタンガンを試すよう頼み、通りがかった映画撮影に全裸でもぐりこみ、全財産を失うリスクを承知しながら投資し、そして、自分の命をも身体感覚のために差しだす。
現代社会のカリカチュアかもしれないが、もはや、現代社会がカリカチュアそのものなのであり、なかなかの感覚だ。
この小説は、ポール・オースターに捧げられている。その一方で、オースターも、『最後の物たちの国で』(>> リンク)や『リヴァイアサン』を、デリーロに捧げている。なるほど、暴力や虚無のなかに足を踏み外してしまいそうな世界の形成は、オースターのものでもある。

この作品が、デイヴィッド・クローネンバーグによって映画化されている(2012年)。ジャカルタ行きの機内で、日本公開前に観ることができた。
リムジンに乗って物語が進んでいくロード・ムーヴィーとは、奇しくも、レオス・カラックス『ホーリー・モータース』(2012年)(>> リンク)と共通している。2012年はリムジン・ロード・ムーヴィー元年か。
映画では、破滅の物語をかいつまんで巧くまとめている。しかも、クローネンバーグ独特の奇妙なモノ感覚がある。リムジンの中から見える外界は、ドライに分割されすぎていて、まさに只の情報そのものだ。次々に現れる人物たちも、やはり、代替可能な情報である。この寄るべなさこそが、デリーロの「米国」あるいは「資本主義」なのだろう。
小説から映画まで10年近くの時間差があるが、それでも、デリーロの作品が「昔の未来小説」になっていないのはさすがである。一方、投資対象が日本円から中国人民元に変えられているのは妥当なところか。小説にあった「全裸のシーン」は、狂気と身体感覚の復権とを象徴しているように思われるだけに、映画にも入れてほしかったところ。
途中で、「彼」がファンだという、スーフィー教徒のラッパーが亡くなるというエピソードがある。映画では、確かに、白装束のスーフィー教徒が機械的に手を直角に掲げてくるくる回る場面が再現されている。ピーター・ブルック『注目すべき人々との出会い』(1979年)(>> リンク)以外に、このような場面が挿入された映画があるだろうか?
●参照
○ポール・オースター『最後の物たちの国で』(ドン・デリーロに捧げられている)
○ピーター・ブルック『注目すべき人々との出会い』、クリストのドキュ、キース・ジャレットのグルジェフ集
○レオス・カラックス『ホーリー・モータース』