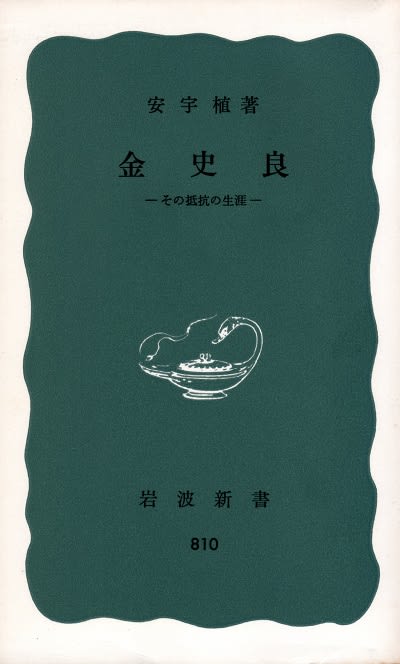ポール・オースター『トゥルー・ストーリーズ』(新潮文庫、原著1997-2002年)を読む。
書店で読んだことのない『The Red Notebook』を見かけ、あれこれは未訳だったっけと探すと、既に日本独自版のエッセイ集のなかに収められていた。なぜ今まで気が付かなかったのだろう。

ここに集められているエッセイ「赤いノートブック」、「その日暮らし」、「スイングしなけりゃ意味がない」、「事故報告」などのなかでは、実にたくさんの偶然話が紹介されている。オースター自身の体験もあれば、近い人に聞いた話もある。
それらは信じ難いものばかりだ。「事実は小説よりも奇なり」とはよく言われることだが、まさに、このような実話を小説にすると、出来過ぎた物語だとして一蹴されてしまうだろう。それが味噌なのであって、実は、オースターの作品世界は、世界のフシギを核として創りあげられている。
世界はもともとフシギなものであり、いくつもの円環が形成されている。大抵の場合、誰もそのことに気づかない。わたしもこのような信じ難い偶然話をしろといわれても、ひとつかふたつひねり出せば上出来である。むしろ、オースターという魔術師であるからこそ、世界のフシギが吸い寄せられ、そこで可視化されるのである。ちょうど、「今日の偶然」なるメモをいくつも残していた赤瀬川原平のように。
●ポール・オースター
ポール・オースター+J・M・クッツェー『ヒア・アンド・ナウ 往復書簡2008-2011』(2013年)
ポール・オースター『Sunset Park』(2010年)
ポール・オースター『Invisible』(2009年)
ポール・オースター『闇の中の男』再読(2008年)
ポール・オースター『闇の中の男』(2008年)
ポール・オースター『写字室の旅』(2007年)
ポール・オースター『ブルックリン・フォリーズ』(2005年)
ポール・オースター『オラクル・ナイト』(2003年)
ポール・オースター『幻影の書』(2002年)
ポール・オースター『ティンブクトゥ』(1999年)
ポール・オースター『リヴァイアサン』(1992年)
ポール・オースター『最後の物たちの国で』(1987年)
ポール・オースター『ガラスの街』新訳(1985年)
『増補改訂版・現代作家ガイド ポール・オースター』
ジェフ・ガードナー『the music of chance / Jeff Gardner plays Paul Auster』