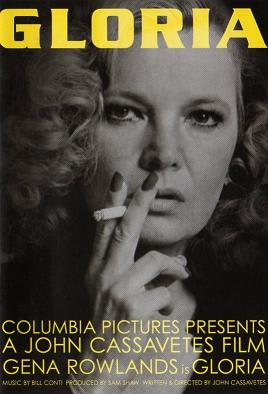インターネット新聞JanJanに、渡辺豪『国策のまちおこし 嘉手納からの報告』(凱風社、2009年)の書評を寄稿した。
>> 『国策のまちおこし 嘉手納からの報告』に見る「アメとムチ」

沖縄タイムスの記者である著者は、『「アメとムチ」の構図 普天間移設の内幕』(沖縄タイムス社、2008年)を書いてもいる。
『国策のまちおこし 嘉手納からの報告』は、アジア最大級の米空軍基地である嘉手納基地にほとんどの面積を奪われている沖縄県の嘉手納町が、如何に町内活性化のための莫大な補助金を獲得してきたか、そしてその結果生じた問題を、取材によって検証した労作である。
嘉手納をはじめ沖縄の米軍基地が、戦争を機に暴力的に確保された場所であることは確かだ。そして日本政府は、米軍に居続けてもらうために、いまだ基地を差し出し続けている。住民に暴力を振るっているのは、米軍よりもむしろ日本政府だと断言できる。
本書において明らかにされているのは、いまや沖縄だけでなく日本全国で使われるようになった「アメとムチ」という手法が、まさに嘉手納町の補助金獲得のプロセスと並行して定着してきたということである。
1996年、前年の沖縄における米兵の少女暴行事件を契機として、普天間基地の移設など「ガス抜き」の試みがはじまっていた。いわゆる「島田懇談会」に基づく、基地被害を受けている自治体に対する巨額の補助事業もそのひとつだ(現在また議論されている「嘉手納統合案」も、この頃にいちど没案になっている)。しかし実際には、名護市が新基地(辺野古の計画は、決して負担軽減の代替などではなく、機能がアップした新基地にすぎない)を受け入れることを条件とした「北部振興策」とセットとなって動いていた。
そのようななか、嘉手納町は、「ハコもの」建設と、「ハコ」の中身の目玉として那覇防衛施設局(現・沖縄防衛局)の誘致に全精力を費やす。本書では、その結果、やはり「ハコ」の維持に苦労していること、古い地域が破壊されてしまったこと、そして基地負担軽減や失業対策という根本的な対策にはつながっていないことを、具体的に示していく。官公庁の縦割りや政治家のエゴなどが障壁となってきたことが、実感できる検証である。
だからといって、政府の「アメとムチ」手法の源流のひとつとなったことを取り上げて、嘉手納町の努力を簡単に批判していいことにはならない。基地被害を沖縄に押し付けている本土の人間は、私も含め、そのような自治体を批判する権利を持たないといっても極論ではないだろう。基地という異物が消える見通しがないなかで、また生きるための選択肢が決定的に少ないなかで、最大限の変革を求めたことの結果であるからだ。
むしろ、国策の都合にあわせて、住民をオカネでどのようにでも抑圧できるという国家の思想こそが問われなければならないのである。これはまた、地方自治・地方自立の思想とも完全に逆行している。著者はいみじくも、日本政府には、沖縄の負担軽減を行うつもりなどさらさらなかったのだということを、次のように指摘する。「……沖縄振興の目的は、沖縄の自立的な発展ではなく、むしろ自立の芽を摘み、基地を維持するためだった、ととらえれば腑に落ちる」と。
それでは、新政権に何を期待すればいいのか。少なくとも、いまの段階で、嘉手納統合だ、いや辺野古だ、という限られた選択肢を云々することは、あまりにもビジョンがなさすぎると言わざるを得ないだろう。なぜならば、本書でも具体的に示されているように、基地をなくすという根本的な解決なしには、永遠に地方自治も、住民の基本的人権も、手に入れることはできないだろうからである。
●参照
○渡辺豪『「アメとムチ」の構図』