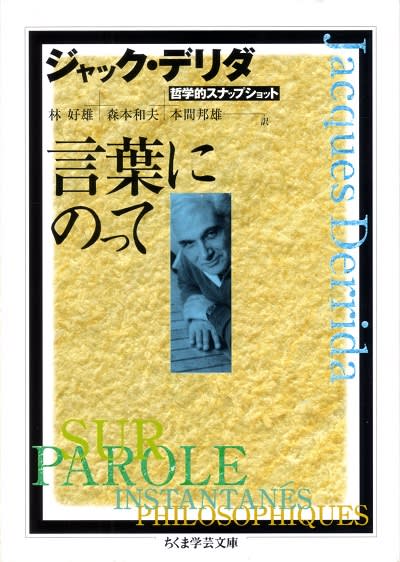名護市の住民投票(1997年)は、辺野古基地に対して、暴力的なローラー作戦にも関わらずNOの民意を示した、画期的なものであった。しかし、カネや権力を直接的に用いた大きな暴力が大きな歪みを生み出し続けている。(宮城康博『沖縄ラプソディ』)
◆
野中広務は、辺野古基地建設に拘泥した。1997年、名護市の住民投票の際にも、基地賛成票を集めるべく、カネを提示し、地元建設業や防衛施設局(当時)の戸別訪問を現地入りまでしてプッシュしている。しかし、住民投票では「基地ノー」が示された。
◆
3年前の辺野古
◆
6年前の辺野古
◆
鎌田慧氏「辺野古の新基地建設に関し、現地の人々が「イヤだ」と言っているのに、「負担軽減だ、良いではないか」としてこれ以上押し付けるのは、もはやファシズムだと言うことができる」
◆
石川文洋氏「辺野古には2011年12月にフェンスが設置された。銃剣で取られた自分の島であり、非常に抵抗感がある。嘉手納のせいでベトナム人が死ぬのを多く見てきた。日本が許可して、他国の人を殺すわけである。オカネをもらえばそれでいいのか」
◆
「少数を犠牲にした大多数の幸福を、はたして幸福と認められるのか、という論理をたてるしかない。まして、新軍事基地の建設に幸福などあるわけがない。」(鎌田慧『沖縄 抵抗と希望の島』)
◆
辺野古を認めるということは、日本の環境影響評価政策がまったく無意味であったことを意味する。
◆
辺野古の問題を政局の文脈でばかり報道するのは知的怠惰。
◆
辺野古に関しては、池田和子『ジュゴン 海の暮らし、人とのかかわり』(平凡社)もぜひ。
◆
『科学』2013年7月号(岩波書店)は、「沖縄の自然」特集を組んでいる。米軍基地が大規模な環境破壊だということが二の次にされているいま、改めてぜひ。
◆
原科幸彦『環境アセスメントとは何か』 ここでは、事業の意思決定過程を透明化が望まれることが強調されている。辺野古のプロセスでもその問題点が明らかだった。しかし、事態は世界の常識に逆行している。
◆
いかに辺野古の環境影響評価が出鱈目で暴力的なものであったか。
◆
新崎盛暉『沖縄現代史』、シンポジウム『アジアの中で沖縄現代史を問い直す』 基地の移設は基地の強化をもたらす。このことは、辺野古新基地の問題が「普天間移設」というオブラートに包んで語られることと無関係ではない。
◆
琉球新報『ひずみの構造―基地と沖縄経済』 「アメ」が如何に自治体財政を歪めているか。公共工事の本契約は「本土」の企業とであり、県内事業者は下請け。オカネは県内で還流せず「本土」に流れていき、県内の経済波及効果があらわれない「ザル経済」。
◆
高野孟『沖縄に海兵隊はいらない!』 北朝鮮や中国や台湾での有事を想定するというが、そのような事態が仮にあるとして、そのときに必要な機能は海兵隊ではない。もはや、米軍基地縮小に伴い日本の軍備増強が必要というトレードオフは成り立たない。
◆
渡辺豪『「アメとムチ」の構図』 組織的なネゴや権力争いや目くらましや恫喝はあっても、カネを通じて以外の住民への気遣いや、歴史認識は露ほども見られない。また、国家ビジョンも、米国の軍事戦略に如何に乗るか以外のものは悲しいほどにない。
◆
屋良朝博『砂上の同盟 米軍再編が明かすウソ』 沖縄は、米軍にとって既得権益かつ再編予算のピースであり、日本にとって本土に基地を置かないための存在である。それは、沖縄が戦略拠点であるという「神話」によって守られている。
◆
前泊博盛『沖縄と米軍基地』 沖縄の海兵隊の主力部隊が1956年に岐阜県と山梨県から移転してきた理由は、戦略上の理由ではなく、海兵隊の「素行の悪さ」にあった。すなわち、犯罪輸出である。