1963(昭和38)年第14回「NHK紅白歌合戦」の視聴率81.4%という驚異的な数字が2023(令和5)年第74回では29.0%に<大暴落>した。その原因は一つではなく幾つかの要因が複合的に重なり合った結果だが、高度経済成長期による社会変動とそれに伴う日本人の日常生活および精神の変容が主因である。
60年前は東京オリンピックの開催年、白黒テレビがカラー受像機に変わる時期だったのだが、それを購入できないでいる国民もいたことを考えると、「81.4%」という数字はまさに年末の国民的行事に違いなかった。師走の慌ただしさを乗り越えた大晦日、夜9時になると家族全員がお茶の間に集まりテレビの画面を食い入るように見つめる。紅組・白組の歌手たちの晴れ姿、一世一代の歌唱に老いも若きも引き込まれ、『いい歌だ』『新人だがうまいね』『流しを5年やってデビューしたんだって』『やっぱりトリを取るだけあって流石だね』…気が付くと番組は「ゆく年くる年」に変わり、永平寺の除夜の鐘の響き、にぎわう境内、明治神宮の初詣へとカメラは切り替わる。
出稼ぎに出ていた男手たちも正月だけは田舎の家に帰り、老親や妻子と三が日だけは過ごそうとした。「盆暮れ」すなわちお盆は先祖の霊を迎え、正月は一年の計を立てるために家族全員が顔を合わせる習わしだった。それが高度経済成長期に崩れ始める。新幹線・高速道路網の整備に伴う土木工事、ホテル・デパートなどの商業施設や公共団地の建築ラッシュ、大都会は男手ばかりでなく女手まで必要としていた。地方都市から大都市への人口流失は必然的だった。経済面ばかりではなく、流行の先端を走るきらびやかな文化に若者たちは憧れ、子供の将来を決定づける充実した教育環境に親たちは目の色を変えた。大学受験では遅い、中学・高校受験から始めなければ…小学生のための受験塾が雨後のタケノコのように現れ始める。親子が遊べる遊園地・レジャー施設・テーマパークの登場…。
 生産活動・消費活動を満足させてくれる都会、「子どものため」というお墨付きを得た若い親たち。地方から転出する家族を止めようがない。故郷には地方公務員や教育従事者が残り、寺の跡取り息子が兼業農家を続ける。大家族だった一家はバラバラになり、多くは東京・大阪・名古屋などで核家族を形成し老親だけは残り墓守をする。もはや三世代同居、老いも若きも子供たちまでもが一体となって「紅白歌合戦」に夢中になることは<ゆめまぼろし>となっていた。
生産活動・消費活動を満足させてくれる都会、「子どものため」というお墨付きを得た若い親たち。地方から転出する家族を止めようがない。故郷には地方公務員や教育従事者が残り、寺の跡取り息子が兼業農家を続ける。大家族だった一家はバラバラになり、多くは東京・大阪・名古屋などで核家族を形成し老親だけは残り墓守をする。もはや三世代同居、老いも若きも子供たちまでもが一体となって「紅白歌合戦」に夢中になることは<ゆめまぼろし>となっていた。 かつて大人たちが買っていたレコードはターンテーブルの上で回ったが、やがて音源はカセットデッキ、CDプレイヤーに挿入されるようになり、購買層も若者中心になっていった。当然、音楽制作もその潮流に乗った内容と形式になる。昭和歌謡の時代は、「〇〇〇〇ショー」と歌手名を入れたタイトルの興行だった。今や、ショーはコンサートに変わり、歌手はアーティストと呼ばれる風潮となっている。歌謡曲の詞やメロディーは時代遅れとなり、レコード会社専属という雇用形式から才能ある新人との契約・マネジメントによって、時代と若者の心情にフィットした音楽が売り出されてゆく。ロックンロール・ジャズ・フォークソング・ニューミュージック…とジャンルも多様化する。
故郷を離れ都会で暮らしていても家族や田舎との絆が生きていた時代は、「望郷」「母への思い」「恋人への慕情」「都会暮らしの哀感」…の詞はリアリティがあったが、その実態を失った社会変化によってそれらは色あせたものになった。しかし、「孤独」「痛み」は人間が生きている以上消えることはない。平成・令和でも時代に内在している虚しさ・悲しみ・叫び、その反転作用としてのアイドル志向へ変容しているだけなのだ。
ただ不思議なことに、時代遅れとなったはずの「歌謡曲・演歌」がしぶとく生き残っている。一つには高齢者(筆者も含めて)にとって<青春>は60年前で、旧友たちと会えば決まって歌うのは「昭和歌謡」になる。少子高齢化社会では、われら老人たちが人口のマジョリティを占めているので、カラオケリクエスト曲ナンバーもそれに対応している。したがって、作詞家・作曲家の先生方の著作権使用料は相当なものだと思われる。
 「歌謡曲・演歌」がいまも制作され、テレビ番組にも生き残っているのはなぜか。併せて「カヴァー曲」の問題、「自分自身の痛みによる歌唱」についても考えてみたい。
「歌謡曲・演歌」がいまも制作され、テレビ番組にも生き残っているのはなぜか。併せて「カヴァー曲」の問題、「自分自身の痛みによる歌唱」についても考えてみたい。





















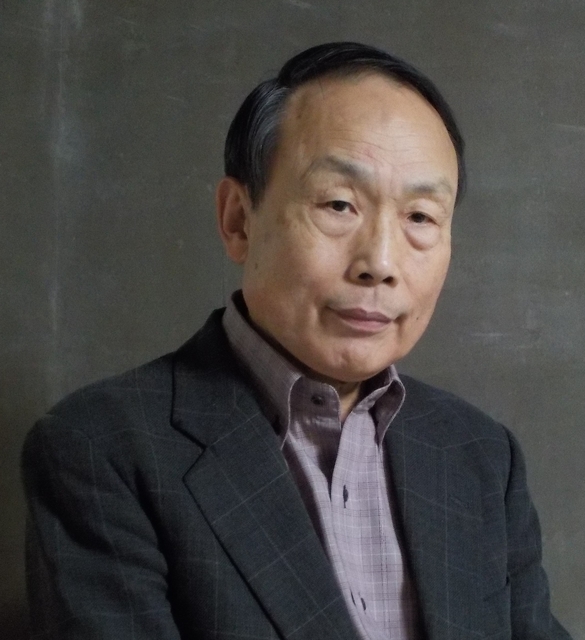




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます