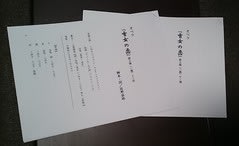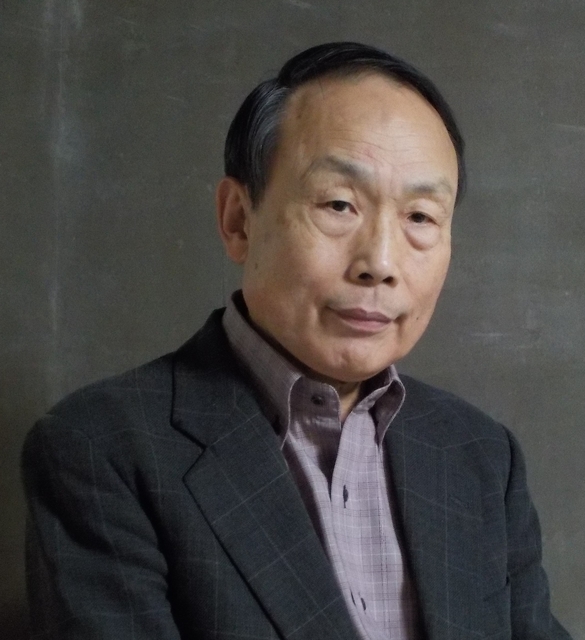古代に始まる「叙情詩・叙事詩・劇詩」の文芸分野は、時代が下ると「詩」「小説」「戯曲」となって独自のフィールドを形成していくが、詩人が小説を書き、小説家が戯曲を、劇作家が詩を書くことは洋の東西を問わず珍しいことではない。わが日本でも島崎藤村(詩→小説)、三島由紀夫(小説/戯曲)、三好十郎(詩→戯曲)らは自らのその時の創作欲に応じた表現ジャンルを選んでいる。
筆者も三十代に童話創作に打ち込んだ時期があったが、二十代から今日まで継続してきたのは演劇であり、その上演活動の中で劇作と演出を担ってきた。そして、数年前にオペラ関係者との出会いがあったことで、舞台劇から歌劇に創作の場をシフトすることになった。
 戯曲は文学であるが、演劇という劇場芸術においては脚本と呼ばれ俳優の手に渡るときには台本となる。そこに書かれた人物の対話(=台詞)は俳優の演技表現の基になるものだが、歌劇では脚本はリブレットとも呼ばれ、台詞ならぬ歌詞およびその詞に付曲された楽譜によってオペラ歌手は歌い演じることになる。
戯曲は文学であるが、演劇という劇場芸術においては脚本と呼ばれ俳優の手に渡るときには台本となる。そこに書かれた人物の対話(=台詞)は俳優の演技表現の基になるものだが、歌劇では脚本はリブレットとも呼ばれ、台詞ならぬ歌詞およびその詞に付曲された楽譜によってオペラ歌手は歌い演じることになる。 いきおい文学的要素より音楽的要素の比重がはるかに大きくなる。必然的に、オペラの創作においては、脚本家は作曲家との協働作業を求められることにもなるので、舞台劇脚本における自分一人の創作作業とは異なるものとなる。
いきおい文学的要素より音楽的要素の比重がはるかに大きくなる。必然的に、オペラの創作においては、脚本家は作曲家との協働作業を求められることにもなるので、舞台劇脚本における自分一人の創作作業とは異なるものとなる。
日本の創作オペラの代表作に『オペラ 夕鶴』(作:木下順二/作曲:團伊玖磨)があるが、これは舞台劇『夕鶴』で音楽を担当した團伊玖磨による戯曲のオペラ化である。戦後の名作劇だったこともあり、劇の台詞を最大限に尊重しつつ作曲した苦労は並大抵ではなかったろう。「オペラ『夕鶴』の15年」團伊玖磨~1966年2月12日東京文化会館・上演プログラム)筆者にとって、主人公つうを演じた伊藤京子の美しさとリリック・ソプラノの歌唱の豊かさは印象的だったが、写実的なことばをベルカント唱法で聴くことに違和感を覚えたのも事実だった。「どんなことばも、みんなうたってしまう不自然さ」が、《夕鶴》のなかにはある。(「夕鶴の音楽」木村重雄~同上プログラム)
さて、筆者が今回書き上げた『雪女の恋~ニ幕~』は、当初からオペラ脚本として創作された作品である。したがって、そこに書かれた言葉はセリフではなく、ソリストの独唱(詠唱)や重唱および混声合唱団のコーラスのための「詞」である。つまり、付曲されることを前提として考えられた言葉になる。『オペラ 夕鶴』の場合と違って、作曲家とのやり取りを繰り返しながら脚本の執筆を進めることになるわけだが、まず始めの第一稿は、脚本家サイドだけによる創作だ。
「雪女」を題材にした音楽劇を構想したのは数年前になる。東京ミニオペラカンバニ―vol.1『悲戀~ハムレットとオフィーリア(一幕)』と並行するように、次回公演の作品として下準備を始めた。「雪女」に関する民話・伝説の資料を国立国会図書館に何度か出向いて数十冊の書籍から該当ページのコピーを取り、それを物語の構成別・内容別に分類し、その中から適切なものを絞り込んでいった。それはイソップ寓話と同様に「〇〇と△△が出会って、~なった」という程度の骨組みだけのエピソードである。これを念頭に置きながらも、まったく新しい作品世界を構築しなけらばならないと同時に、前回の公演に出演したソリスト4名に充てた役を設定するという「座付け作者」およびプロデューサーとしての創作上の前提も必須条件だ。
基礎資料の整理後は、オリジナル作品としてのエピソードの列挙や劇としてのプロット立てに取り掛かる。新鮮な発想や印象的な場面を生み出すには、書斎を出て非日常的な時間・空間に身を置くことが望ましい。毎月、近場の温泉宿に一人一泊旅。深夜に起き出してパソコンに向かい、車内書斎として往復のグリーン車内を利用して執筆する。
さて、なんとか第一稿を脱稿したら、すぐさま作曲家へ郵送する。それからが「劇脚本」が「オペラ脚本」へ変わっていく道程である。
筆者も三十代に童話創作に打ち込んだ時期があったが、二十代から今日まで継続してきたのは演劇であり、その上演活動の中で劇作と演出を担ってきた。そして、数年前にオペラ関係者との出会いがあったことで、舞台劇から歌劇に創作の場をシフトすることになった。
 戯曲は文学であるが、演劇という劇場芸術においては脚本と呼ばれ俳優の手に渡るときには台本となる。そこに書かれた人物の対話(=台詞)は俳優の演技表現の基になるものだが、歌劇では脚本はリブレットとも呼ばれ、台詞ならぬ歌詞およびその詞に付曲された楽譜によってオペラ歌手は歌い演じることになる。
戯曲は文学であるが、演劇という劇場芸術においては脚本と呼ばれ俳優の手に渡るときには台本となる。そこに書かれた人物の対話(=台詞)は俳優の演技表現の基になるものだが、歌劇では脚本はリブレットとも呼ばれ、台詞ならぬ歌詞およびその詞に付曲された楽譜によってオペラ歌手は歌い演じることになる。 いきおい文学的要素より音楽的要素の比重がはるかに大きくなる。必然的に、オペラの創作においては、脚本家は作曲家との協働作業を求められることにもなるので、舞台劇脚本における自分一人の創作作業とは異なるものとなる。
いきおい文学的要素より音楽的要素の比重がはるかに大きくなる。必然的に、オペラの創作においては、脚本家は作曲家との協働作業を求められることにもなるので、舞台劇脚本における自分一人の創作作業とは異なるものとなる。日本の創作オペラの代表作に『オペラ 夕鶴』(作:木下順二/作曲:團伊玖磨)があるが、これは舞台劇『夕鶴』で音楽を担当した團伊玖磨による戯曲のオペラ化である。戦後の名作劇だったこともあり、劇の台詞を最大限に尊重しつつ作曲した苦労は並大抵ではなかったろう。「オペラ『夕鶴』の15年」團伊玖磨~1966年2月12日東京文化会館・上演プログラム)筆者にとって、主人公つうを演じた伊藤京子の美しさとリリック・ソプラノの歌唱の豊かさは印象的だったが、写実的なことばをベルカント唱法で聴くことに違和感を覚えたのも事実だった。「どんなことばも、みんなうたってしまう不自然さ」が、《夕鶴》のなかにはある。(「夕鶴の音楽」木村重雄~同上プログラム)

さて、筆者が今回書き上げた『雪女の恋~ニ幕~』は、当初からオペラ脚本として創作された作品である。したがって、そこに書かれた言葉はセリフではなく、ソリストの独唱(詠唱)や重唱および混声合唱団のコーラスのための「詞」である。つまり、付曲されることを前提として考えられた言葉になる。『オペラ 夕鶴』の場合と違って、作曲家とのやり取りを繰り返しながら脚本の執筆を進めることになるわけだが、まず始めの第一稿は、脚本家サイドだけによる創作だ。

「雪女」を題材にした音楽劇を構想したのは数年前になる。東京ミニオペラカンバニ―vol.1『悲戀~ハムレットとオフィーリア(一幕)』と並行するように、次回公演の作品として下準備を始めた。「雪女」に関する民話・伝説の資料を国立国会図書館に何度か出向いて数十冊の書籍から該当ページのコピーを取り、それを物語の構成別・内容別に分類し、その中から適切なものを絞り込んでいった。それはイソップ寓話と同様に「〇〇と△△が出会って、~なった」という程度の骨組みだけのエピソードである。これを念頭に置きながらも、まったく新しい作品世界を構築しなけらばならないと同時に、前回の公演に出演したソリスト4名に充てた役を設定するという「座付け作者」およびプロデューサーとしての創作上の前提も必須条件だ。
基礎資料の整理後は、オリジナル作品としてのエピソードの列挙や劇としてのプロット立てに取り掛かる。新鮮な発想や印象的な場面を生み出すには、書斎を出て非日常的な時間・空間に身を置くことが望ましい。毎月、近場の温泉宿に一人一泊旅。深夜に起き出してパソコンに向かい、車内書斎として往復のグリーン車内を利用して執筆する。
さて、なんとか第一稿を脱稿したら、すぐさま作曲家へ郵送する。それからが「劇脚本」が「オペラ脚本」へ変わっていく道程である。