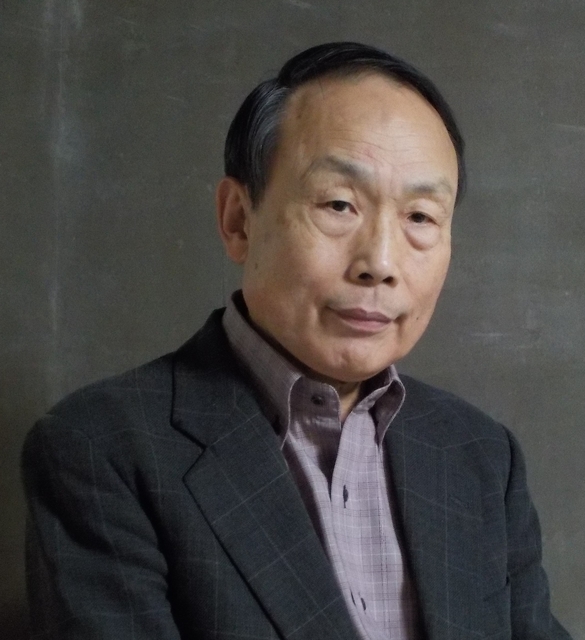大学の授業で「美空ひばり」を取り上げたことがある(ブログ記事/語られる歌と歌われる音楽(1)カテゴリー「オペラ」2017年8月6日)。
慶應義塾大学2006年度(秋学期)講義表【「感動の要因」⑤―2娯楽性・別世界と自己投影~宝塚歌劇団と美空ひばり~】、感動の要因のうち「娯楽性」の側面から対照的な二つの例に光を当てる試みだった。
…作り手と受け手の関係は、映画や演劇ばかりではない。音楽の場合、演奏者や歌手が舞台で表現し、聴衆が客席でそれを鑑賞する、そこに感動が生まれる―それは全く同じ相互作用である。
宝塚歌劇は言うまでもなく演劇の一分野であり、生の音楽とダンス・歌と芝居による華やかな世界を繰り広げるエンターテインメントである。歌舞伎に「女形」があるように宝塚歌劇には「男役」があり、100年の歴史を刻んでいる女性だけのプロ劇団は世界に例がない。本拠地の関西とともに東京宝塚劇場にも多くのファンが押し寄せるのは、現実世界からひと時離れ、その美しくも華やかな憧れの世界に身を置けるからだ。
一方、美空ひばりは「離れる」のではなく、現実世界そのものに身を置いてそこに沈潜する。その時代と社会に生きる大衆が味わう辛さや痛み、憧れや夢、悲しみやあきらめ、そして、いたわりの心情をその人物になり切って歌う。昭和は歌謡曲から演歌へと推移していくが、歌手が詞の世界に主人公として存在できたのは美空ひばりただ一人である。…
「歌は三分間のドラマである」とされるが、ほとんどの歌手は人物の状況や心情を高唱してもその顔は歌手本人のままである。しかし、美空ひばりは違う。詞に描かれている人物になりきって歌う。歌手自身の個人的な思いは内包して表には出さない。人物を演じ切るのだ。その典型が代表曲の一つ『悲しい酒』(作詞:石本美由起/作曲:古賀政男)である。実際のステージでの歌唱(ツーコーラス・セリフ入り版)によって検証してみよう。
 冒頭のイントロが流れると、「ひばりの顔」は消えて、詞の主人公である女が立ち現れる。
冒頭のイントロが流れると、「ひばりの顔」は消えて、詞の主人公である女が立ち現れる。ひとり酒場で 飲む酒は
別れ涙の 味がする
飲んで棄てたい 面影が
飲めばグラスに また浮かぶ
別れ涙の 味がする
飲んで棄てたい 面影が
飲めばグラスに また浮かぶ
この「一節4行」によって、いわゆる5W1H(いつどこでだれが何をどのように)が、すなわち主人公の状況と心情が表現される。もちろん、その構成に沿って人物の情感を細やかに湧出し詞の世界を音楽的に描き出すのは作曲の仕事だ。詞先・メロ先を問わず、歌謡曲作法の常道である。
1コーラス目で、ひばり、いや「女」は、忘れたはずの相手をつい思い浮かべてしまう自分に苦笑しているかのようだ。悲嘆の感情は見えない。ここが女優でもあるひばりの表現力の深さであり、並みの歌手には真似ができないところだ。
セリフ部分のイントロが始まると、平静を装う自分は消えて、胸の奥にしまってあった感情が表れてくる。“悲しい酒”を口にした主人公の生理的必然性を作詞家はきちんと計算している。ひばりの目に涙が浮かんでくる。
(セリフ)ああ 別れたあとの心残りよ
未練なのね あの人の面影
淋しさを忘れるために
飲んでいるのに
酒は今夜も 私を悲しくさせる
酒よどうして どうして
あの人を
あきらめたらいいの
あきらめたらいいの
未練なのね あの人の面影
淋しさを忘れるために
飲んでいるのに
酒は今夜も 私を悲しくさせる
酒よどうして どうして
あの人を
あきらめたらいいの
あきらめたらいいの
二節目に入ると、見開いた目に涙がいっぱいたまり、やがて一滴二滴と頬を伝う。しかし、歌は乱れない。3行目のサビ(〽好きで添えない…)を歌い上げる瞬間をキッカケにして歌い手としての感情を切り替える。
一人ぼっちが 好きだよと
言った心の 裏で泣く
好きで添えない 人の世を
泣いて怨んで 夜が更ける
言った心の 裏で泣く
好きで添えない 人の世を
泣いて怨んで 夜が更ける
エンディングの際には、涙は消えて、人物「女」から歌手美空ひばりに戻っていく。
「演じる歌」というのは、詞の理解力すなわち人間の機微を実感できる感性、それらの土台となる過酷ともいえる人生体験の持ち主で、天性の歌唱力に恵まれ、実人生以上に「歌の世界」に自らを捧げた歌い手によって初めて表現できるものなのである。












 美空ひばりである。平成元(1989)年6月に亡くなるまで43年間国民的スターであり続けた“歌謡界の女王”は、女性として史上初の国民栄誉賞を受賞した(没後の1989年7月2日)。そして、ひばりの活躍の場は歌謡界のみならず、映画界にも及んでいた。150本を超える映画に出演し、そのほとんどが主演という映画女優でもあったのだ。
美空ひばりである。平成元(1989)年6月に亡くなるまで43年間国民的スターであり続けた“歌謡界の女王”は、女性として史上初の国民栄誉賞を受賞した(没後の1989年7月2日)。そして、ひばりの活躍の場は歌謡界のみならず、映画界にも及んでいた。150本を超える映画に出演し、そのほとんどが主演という映画女優でもあったのだ。 この「映画女優」であることが、ひばりの「歌唱表現」を豊かにしている要素になっている。詞の世界に描かれている人物になりきって、その人物の言葉を歌うことが出来ているのだ。
この「映画女優」であることが、ひばりの「歌唱表現」を豊かにしている要素になっている。詞の世界に描かれている人物になりきって、その人物の言葉を歌うことが出来ているのだ。
 「ケイコしていてつくづく感じるのですが、越路さんという人は、実に「苦しむ人」なんです。こういう話はこれまで公開したことはないのですが、この3年くらい彼女は苦しんでいます。たとえば愛の讃歌をケイコしていて、「あなたの燃える手で私を抱きしめて」と歌いますね。これを彼女はもう何千回も歌っているわけでしょう。ところが、当の彼女だけが、この歌に対して、歌うたびに白紙の状態なんです。ケイコ場で、ひとり自分の手を見つめたり、恋する人の手というものを想定しながら「あなたの燃える手で」「あなたの燃える手で」と繰り返している。これはどういうイメージなんだろうと苦しんでいる。『愛の讃歌』にしても『サントワマミー』にしても、あれだけ歌いこんでいて、「むつかしい」「どうやって歌おうか」ということなんです。みていると痛々しい感じがする」。
「ケイコしていてつくづく感じるのですが、越路さんという人は、実に「苦しむ人」なんです。こういう話はこれまで公開したことはないのですが、この3年くらい彼女は苦しんでいます。たとえば愛の讃歌をケイコしていて、「あなたの燃える手で私を抱きしめて」と歌いますね。これを彼女はもう何千回も歌っているわけでしょう。ところが、当の彼女だけが、この歌に対して、歌うたびに白紙の状態なんです。ケイコ場で、ひとり自分の手を見つめたり、恋する人の手というものを想定しながら「あなたの燃える手で」「あなたの燃える手で」と繰り返している。これはどういうイメージなんだろうと苦しんでいる。『愛の讃歌』にしても『サントワマミー』にしても、あれだけ歌いこんでいて、「むつかしい」「どうやって歌おうか」ということなんです。みていると痛々しい感じがする」。
 ここには、ピアフ自身か書いた原詩の世界は跡形もない。西洋人の愛の形ではない日本人の“二人だけの世界”が描かれている。越路はこの「翻案詞」をメロディに乗せてささやくようにそしてダイナミックに歌い演じた。自分自身の根底から湧いてくる心情と思いを込めて歌い上げた。ここに、借りものではない越路吹雪の『愛の讃歌』が誕生する。
ここには、ピアフ自身か書いた原詩の世界は跡形もない。西洋人の愛の形ではない日本人の“二人だけの世界”が描かれている。越路はこの「翻案詞」をメロディに乗せてささやくようにそしてダイナミックに歌い演じた。自分自身の根底から湧いてくる心情と思いを込めて歌い上げた。ここに、借りものではない越路吹雪の『愛の讃歌』が誕生する。