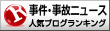日中・日韓関係が緊迫しています。いずれも領土が関わっているわけですが、それ以前の
日中戦争や朝鮮併合などの経緯を私たち日本人があまり知らないことが基本的な認識の
違いになっているように感じます。自分の受けた痛みは忘れないが人を傷つけたことは
忘れやすいものです。
そんなことが気になって、このあいだから南京事件の本を読んでいます。いまだにそれが
あったことを認めない人たちがいて、いろいろな所で主張したり出版したりしているので、
議論が分かれているような印象を受けます。しかし規模は確定しにくいものの、あったこと
は東京裁判をはじめ国際的に認められた定説のようです。
私が全く知らなかった、南京近郊・幕府山付近の揚子江河原でなされた捕虜虐殺を検証した
「南京虐殺と日本軍」 (渡辺 寛、1997、明石書店)。
氏は 「日曜歴史家」 と謙遜していますが、当事者であった山田支隊の栗原利一元陸軍伍長の
証言 (127p~) をはじめ関係者の日記などの綿密な考証によって、日本軍が1937年12月16.17
日に幕府山付近の揚子江河原で2万数千名の中国軍捕虜を射殺したことを論証しています。
これは軍服を着替えたいわゆる 「便衣兵」 などではなく、捕えて武装解除した軍人捕虜を虐殺
した事件でした。福島民友新聞社発行の「郷土部隊戦記」「ふくしま 戦争と人間」 などによる
従来の定説、「捕虜を捕獲した山田支隊の指揮官たちが、中支那派遣軍の 『始末せよ』 との
命令を無視して捕虜を解放しようとしたのに、銃殺されると勘違いした捕虜たちが暴動したので
やむなく銃撃し一部を殺したが、大半は逃げてしまった」 とする説は完全に否定されました。
松井石根中支那派遣軍司令官 (大将) は南京への入城式の訓示で誰ということではなく不逞の
行動があったとして将兵を叱責しましたが、まもなく不本意ながら更迭されてしまいました。
(松井将軍は東京裁判で刑死)。 南京とその周辺で重大な不祥事があったことを大本営は承知し
ていたのでしょう。
また中島今朝吾第16師団長は 「だいたい捕虜はせぬ方針なれば片端よりこれを片付くることと
なした」 と日記に書くほどで (245p)、狂っていたとしか思えないのですが、このような指揮官
の下にいた軍隊が行儀が良かったとは思われません。
日本軍が慈愛に満ちた皇軍であったなどというのは全くの神話でしょう。補給がなく餓死した
兵隊がたくさんいますし、特攻のようにあたら命を粗末にする作戦を実施して恥じない軍隊で
した。自分の兵たちさえも粗末に扱う日本軍が、小馬鹿にしている中国軍を丁重に扱うわけが
ありません。
そもそも柳条湖事件以来、中国の弱体に付け込んでしたい放題を繰り返した日本軍です。満州
事変も上海事件も、宣戦布告もない 「事変」 として戦っていたのです。そうしてついに米英に
宣戦布告し戦争に突入しました。日本人はアメリカに負けたことはよく分かっていますが、その
前に中国大陸で2千万人ともいわれる中国国民を殺した事をほとんど忘れているように思います。
安倍総理のように侵略の定義は定まっていないとか、西部邁氏や小林よしのり氏のように自衛
戦争で別に悪いことではなかったとか、いろいろ主張がありますが、犠牲者を悼む気持ちが
感じられません。それではとても相手国と理解し合うなど出来ようはずがありません。
今時のネトウヨ=ネット右翼の投稿などを見ていると、そうした歴史に関する理解がなく、ただ
中国韓国を生意気だと非難し馬鹿にしているだけのようです。戦前の差別意識丸出しという感じで、
「暴支膺懲」(ぼうしようちょう=横暴な支那を懲らしめる) などという言葉 (1937.8.15 近衛声明)
を思い出すほどです。ひょっとしたらNHK経営委員の長谷川三千子女史ではありませんが、神国
日本とか八紘一宇などと言い出しかねない勢いで、いま戦ったら勝てるぞ、というくらい好戦的です。
その戦争を戦うのはあなたたち自身だということが分かっていますか? 一つの戦闘なら勝つ
かもしれませんが、いまや日本をしのぐ経済力の中国を相手に20年戦争を戦い抜けますか?
10倍の人口を持つ中国を完全に屈服させ支配することができますか? 何千万人も殺して彼ら
の心を親日に変えることができますか? 戦争が長引いたらどのように終戦に持っていくのですか?
そして日中全面戦争となったとき、アメリカはどこまで日本を支援してくれるのですか? 世界の
諸国民は日本を応援してくれますか?
歴史も知らず展望もないまま、やたらと敵意を煽り立て、異なる意見には集中攻撃で炎上させる
ネトウヨの諸氏はほとんど犯罪者に近いと言わなければなりません。できるだけ、機会あるごと
にその間違いを指摘し反論していかなければ、日本の世論が彼らのネット攻撃に引きずられて
しまうのではないかと、心配です。
そして唯我独尊の日本は世界の孤児になりかねません。
2度にわたって周辺国と血みどろの戦いを繰り広げ、2度とも敗戦したドイツは徹底的にナチス
の時代を反省し、今やEUの中核として信頼されています。それに引き替え、わが国はどうで
しょうか。一億総ざんげ、ですべては終わり、デタラメな戦争指導者たちまでが今では神として
靖国神社に祭られている始末です。
ワイツゼッカー大統領の演説 から、ごく一部を引用します。
われわれは今日、戦いと暴力支配とのなかで斃れたすべての人びとを哀しみのうちに思い浮かべ
ております。
ことにドイツの強制収容所で命を奪われた 600万のユダヤ人を思い浮かべます。
戦いに苦しんだすべての民族、なかんずくソ連・ポーランドの無数の死者を思い浮かべます。
ドイツ人としては、兵士として斃れた同胞、そして故郷の空襲で捕われの最中に、あるいは故郷
を追われる途中で命を失った同胞を哀しみのうちに思い浮かべます。
虐殺されたジィンティ・ロマ (ジプシー)、殺された同性愛の人びと、殺害された精神病患者、
宗教もしくは政治上の信念のゆえに死なねばならなかった人びとを思い浮かべます。
銃殺された人質を思い浮かべます。
ドイツに占領されたすべての国のレジスタンスの犠牲者に思いをはせます。
ドイツ人としては、市民としての、軍人としての、そして信仰にもとづいてのドイツのレジスタンス、
労働者や労働組合のレジスタンス、共産主義者のレジスタンス――これらのレジスタンスの犠牲者を
思い浮かべ、敬意を表します。
積極的にレジスタンスに加わることはなかったものの、良心をまげるよりはむしろ死を選んだ人びと
を思い浮かべます。
今日の人口の大部分はあの当時子どもだったか、まだ生まれてもいませんでした。この人たち
は自分が手を下してはいない行為に対して自らの罪を告白することはできません。
ドイツ人であるというだけの理由で、彼らが悔い改めの時に着る荒布の質素な服を身にまとう
のを期待することは、感情をもった人間にできることではありません。しかしながら先人は彼ら
に容易ならざる遺産を残したのであります。
問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。後に
なって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を
閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、
またそうした危険に陥りやすいのです。
自由を尊重しよう。
平和のために尽力しよう。
公正をよりどころにしよう。
正義については内面の規範に従おう。
今日五月八日にさいし、能うかぎり真実を直視しようではありませんか。
「アレクサンドロスの征服と神話」 (『興亡の世界史1』、
森谷公俊、2007、講談社)。
アレクサンダー大王の父フィリッポス2世はギリシア世界に覇権を確立し、コリントス
同盟を結んで対ペルシア遠征を決定 (前337)。 しかしその翌年フィリッポス2世が暗殺
され、アレクサンドロス3世 (大王) が弱冠20才でその後を継ぎマケドニアの王位に就く。
前334年、父王の整備した当時初の常備軍マケドニア軍とギリシア諸国の連合軍を率いて
東征し、エジプトを降伏させ、アケメネス朝ペルシアを滅ぼし、さらに中央アジアを平定し
インダス川に至る。中央アジアやインドでは諸部族の抵抗強く、多くの町で虐殺を繰り
返す。将兵の厭戦気運が高まり、ついに軍を返した (前325)。
この間わずか12年で空前の大領土を征服し、前323年バビロンにて死去。後継者が決まって
いなかったため将軍たちの後継争いが起こり、やがて3分割される。
当初の目的・名分はペルシア戦争の仇を撃つ、ということで、アケメネス朝ペルシアを滅ぼす
までは良かったのですが、その後は大王個人の、神になりたいという欲望のままに軍を進め、
虐殺を繰り返しました。
文化的にはギリシア人が東方に発展してギリシア文化が広まったと言われていますが、森谷
氏によればそれは以前から交流があったことで、大王によって突然起こったことではない。
また社会制度としては、大王はペルシアの制度と支配階級を温存したので、東方でギリシア
的社会ができたわけでもない、ということです。20か所ともいわれるアレキサンドリアを
建設しましたが、後に残ったのはエジプトの1つだけ。
こういうと稀代の英雄を軽く見るようですが、私が思うに個人的な野心だけで大征服をなし
遂げたもので、文化や制度を変えた人ではない。ローマのシーザーのように夷狄を同化した
わけでもなし、ナポレオンのように新社会の法典を整備したわけでもない。蒙古のように
ただ虐殺し征服して君臨しただけ、ということになってしまったのです。
つまり、征服に理念がない。何のために沢山の人を殺戮したのか。死の直前、自身の神格化
を命じたそうですが、その後熱病で死んだのは神罰ではないか、と感じました。しかし、
もう少し長生きしたらナポレオンのような悲運が待っていたかもしれませんから、あるいは
幸運だったのかもしれません。
(わが家で 2014年2月13日)
「イスラームのロジック」 (中田考 2001年、講談社)。
中田氏は、イスラームを理解するにはブタの禁忌といった表面をとらえて異文化として
納得するのではなく、「全人類に向けられた普遍的メッセージとしてイスラームに向き
合う必要がある。」 (11p) と主張しています。また梅棹忠夫氏や小室直樹氏の論を引いて
イスラームをある意味で理想的な、完成された宗教として位置付けています (75p)。
しかしイスラームを初めから普遍的理想的なものとして見るのも、一つの固定観念では
ないかと思います。それでは冷静な他宗教との比較検討ができません。
また 「偶像とは自己の欲望の投影に他ならず、(中略) 唯物論、無神論、無宗教等は
人間の我執の幻影への隷属、形を変えた偶像崇拝なのである。」 (38p) と断定していま
すが、きわめて乱暴な論理です。イスラームにおいては絵画彫刻ばかりか音楽を含むあら
ゆる芸術が偶像崇拝として禁止されていますが、とても非人間的なことだと思います。
イスラームで言葉だけがなぜ偶像の範囲に入らないのかといえば、それは神が言葉で語って
いる、というその1点だけでしょう。私は浅学菲才ですが、仏教的に言えばすべては輪廻
するのであり、「無謬不可変の言葉」 もいつか偶像になりうるのではないでしょうか。
イスラーム神学では神の存在の否定から出発し、もし 「造り主」 が存在するならばそれは
かくかくしかじかの性質を持っていなければならない、そういう性質を持つ者はすべて
アッラーフと同一である。ということだとしています。(131p~)
その属性とは、
1.本体属性 存在すること。全き存在者、必然存在者、宇宙の作り手。 空間を占めず、
空間を占めるものに依拠するものでもない存在。
2.否定的属性 宇宙に存在する者すべてに神性を否定することから出てくる。
① 時間において始点を持たない無始 ②時間において終点を持たない無窮、
③生成消滅するものと共通点を持たない非生成、 ④他の何物にも依存しない自存、
⑤無比である唯一性。
3.有意属性
①能力 ②意思 ③知識 ④生命 ⑤聴力 ⑥視力 ⑦言語能力。
未だこのほかにイデア属性の7つの有意属性を加えて20とし、それら全部を3つのカテゴリー
に分類するということです。
こうした複雑な神学論は、要するに神の存在を宇宙の存在にとって必要不可欠とする論理に
ほかなりません。実際に 「イスラームに神なし」 などと言えばジハードの対象になりかね
ないはずでしょう。
それに言語能力も神の属性に数えられていますが、神が語ったという聖典クアルーンは
アラビア語で書かれ、1字1句の改変も許さないもので、従って翻訳してはならないそうです。
全知全能の神はなぜ諸国民にすぐ分かるようにしなかったのか、じつに不思議です。にも
拘わらず、アッラーフはいきなりああしろこうしろと人間に命令するたいへん横暴な神で、
アラビア語を学ばなければ何を命ぜられているのかさえ、正確には分かりません。
この本で、仏教徒としてはイスラームを理解することがたいへんな困難だということが
よく分かりました。
(わが家で 2014年2月23日)
「モンゴル帝国と長いその後」(『興亡の世界史09』 杉山正明、2008、講談社)。
チンギス・カーン (~1227) を創始者とする騎馬遊牧民国家モンゴル (イェケ・
モンゴル・ウルス、1206~) は急速に拡大し、その孫クビライ (1260即位) の
時代に東は中国から西はロシア、中東まで、宗主国ダイチン・グルン (大元) と
チャガタイ、フレグ、ジョチの分家3グルンの連合体として人類史上最大の版図
を支配しました。
しかし文化の中核としての文字を持たなかったので、被支配地の文化をそのまま
利用するのが統治の基本だったようです。中国では漢字文化を利用し、中東では
イスラームに改宗する、といった具合です。
杉山氏は世界帝国としてのモンゴルを高く評価し、統治システムや領域内の駅逓
システム、民族差別・宗教差別のない社会制度が生まれたとしていますが、世界的
普遍的なモンゴル文化というものが生まれ発展したとは言えないようです。
杉山氏は随所に独断的な判断を示しています。日本への蒙古襲来については、
「純客観に、突風や台風などがなくても、遠征は失敗した。」(330p) というの
ですが、その根拠は客観的な分析ではありませんし、始まる前に客観的に分析
して勝敗が分かる戦いなどありません。
また、モンゴルを高く評価するあまり贔屓が過ぎると感じます。一例ですが、
日本には 「茶道・能・書院造り、儒・仏・道三教兼通型の知的体系、漢文典籍と
それを模した五山版 (中略) など、日本文化の基層となるものはほとんどこの時
とその前後に導入・展開した」 (330p) と主張しますが、それはモンゴル文化では
なく異民族に圧迫されていた宋・南宋の文化で、たまたま元と同時代だったという
ことではないのでしょうか。
チンギスの血統は後々までロシアやインド (ムガール帝国) など各地で貴種として
迎えられ、妻に娶られることも多かったそうですが、貴種崇拝はどこでも、現代で
さえあることで驚くにはあたりません。それが人間精神の解放と社会の発展に役
立ったかどうか、が問題になるのではないでしょうか。単に支配したということ
だけでは、アレクサンダー大王と同じであまり意味がないでしょう。
(わが家で 2014年2月20日)
「イスラーム帝国のジハード」 (『興亡の世界史6』、
小杉泰、2006、講談社)。
この本で一番驚いたのは、クアルーンは唯一神アラーのムハンマドに対する命令で
始まっているいうことです。クアルーンの冒頭は 「読め」 ! です。(56P)
「イスラームは 『命令の体系』 であるから、信徒たちはその体系が法として示され
れば、国家や権力の介入もなしに、法に従う。ウンマ (イスラーム共同体) は法に
よって自律的に運営される」。(231P)
これは素晴らしいことのようでもあり、恐ろしいことでもあります。神との契約は
一方的な命令だったわけで、選び取って契約したものではない。また一神教は生まれ
てすぐ信徒にするわけで、考える暇もなく神に命ぜられるというわけです。
これでは人間精神の解放など永遠にあり得なくなってしまいます。このようなことを
私はとても受け入れられません。
イスラームはメディーナ聖遷以降戦えば勝つという勢いで、わずか20年ちょっとで
大征服を成し遂げました。領土拡大は大きな利益をもたらし、早くも第2代正統カリフ
・ウマルの時にその分配がイスラームにとって大きな課題になった、とも。(169P)
イスラームは防衛的なジハードだと主張するけれど、必ずしもそうではない面も
あったわけです。
大征服後の改宗は徐々に進んだもので、「コーランか剣か」 ということで改宗させた
というのは完全な誤りだそうです。ウマイヤ朝では異教徒が圧倒的に多く彼らと共存
したが、ムスリムの中ではコーランに反してアラブを優先しました。
アッバース朝になりムスリムが民族の別なく公平に扱われたため改宗が大いに進ん
だそうです。これは私が思ったとおりでした
アッバース朝第7代カリフ、マアムーンはギリシア文化の翻訳を奨励しました。
ギリシア哲学の合理的思考を取り入れたムウタズィラ学派を公認し、異端審問
までも開始しました。(234P)
ムウタズィラ学派がそれまでと異なっていた最大の論点は、神アラーと聖典クア
ルーンがともに永遠で絶対のものであるのはおかしい、神が全知全能で永遠なの
だから、クアルーンは創造物である、ということです。これはすばらしく合理的で、
クアルーンを 「不磨の大典」 とする弊害を避けることができた可能性がありま
した。
ところが保守的なウラマー (法学者) たちが頑強に抵抗し、3代後にムウタズィラ
学派は公認から外れ、ほとんど消滅してしまいました。これによりウラマーの権威
が向上し、聖典解釈の権限がウラマーにあることが社会的に確認されるようになっ
たということです。
これは上からの改革が失敗したということであり、いまトルコの世俗主義政権や、
エジプトの民族主義政権がイスラーム復興運動に揺さぶられているのと同じ構図
かもしれません。そしてそれは皮肉にも西欧流の民主主義の導入によって生じて
いるのです。
イスラーム復興運動は一般に原理主義と呼ばれ、穏健派から過激派まで幅がある
ようですが、厳格な聖典重視で残念ながら人間精神の解放には結びつきません。
個人的な聖典解釈で勝手に 「ジハード」 を行う過激な原理主義集団もあります。
ジハードは3つの側面があり、心のジハード、社会的ジハード、剣のジハード、と
されます。剣のジハードはいわゆる防衛戦争であり、ウンマ (イスラーム共同体) の
指導者、つまりカリフなど政教一致の統治者が発動すべきものだそうです。個人的
にそれを行うことは原則に反することになります。いまスンニ派にはそのような
統治者が存在しないので、個人がジハードと称して自爆テロなどを行なうことに
なってしまっているわけです。
小杉氏の言う多数派=「中道派」 が彼らを制御することができないのは残念な
ことですが、それが宗教というものかもしれません。
最後に、一夫多妻制は夫が戦死した寡婦の生活保障制度だといいます。(131P)
それはイスラーム草創当時の、迫害と戦っていた時代にはやむをえなかったかも
知れません。しかしメディーナ聖遷以降は戦えば勝つという勢いで、わずか20年
ちょっとで大征服を成し遂げるのですから、いつまでもそのような制度が必要だっ
たとは思えません。
ムウタズィラ学派の 「クアルーン創造物説」 が主流派になっていれば、人間と
しての男女平等といった、イスラームにとって革命的な新理論が生まれたかもしれ
ないのに、と思います。惜しまれることでした。
(わが家で 2014年2月11日)