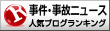保阪氏が、アジア太平洋戦争が8月15日に終わらなかった場合を研究した、
「本土決戦幻想 オリンピック作戦編」 (保阪正康、毎日新聞社 2009年)。
アメリカ軍は1945年11月からオリンピック作戦 (九州上陸作戦)、さらに1946年
3月からは関東平定のコロネット作戦を実施する計画だったそうです。
対する日本軍の本土決戦作戦は 「決号作戦」。その内容は、空海陸すべて特攻
あるのみ。作戦をとりまとめた参謀本部第一 (作戦) 部長宮崎周一中将の戦後の
記録によると、これは 「絶体絶命の一戦」 で、
「作戦は連続不断の攻勢。戦法は航空全機特攻、水上、水中すべて特攻、戦車に
対して特攻、地上戦闘だけが特攻を避けられよういわれはない」 (65-66p) と
述べているそうです。
攻勢といってもすべてが特攻。たとえば対戦車特攻とは、予科練乙飛第24期の
石井三郎氏によれば、「街道の両脇に5メートル間隔の蛸壺を掘り、そこに一人
ずつ爆雷をかかえて潜み、30キロくらいのスピードで進んでくる戦車に対し、体
当たり攻撃を敢行する」 (249p) というのだそうです。もはや作戦などと呼べる
ものではありません。そして兵士だけではなく、沖縄戦のように必ず民間人も
参加させられることになったでしょう。特攻を武士道の美学だとか論じる人たち
は、それなりに飛べるゼロ戦などによる航空特攻しか頭にないようですが、特攻
全体の実態を見つめる必要があると思います。
この 「決号作戦」 というような馬鹿げた作戦を、軍の幹部や中堅は本当に実施
するつもりだったというわけですから、まったく聖断は日本を救ったと言えるで
しょう。しかし私は、その聖断を3月10日の東京大空襲の時点でなぜできなかった
か、と問いたい。
10万人が犠牲となり帝都の3分の1以上にあたる約41平方キロメートルもが一夜に
して灰燼に帰した大空襲の廃墟を、昭和天皇は3月18日に自ら視察し、富岡八幡宮
で報告を聞いています。
日本軍に本土防衛能力がないことは明白で、その惨状を目の当たりにすれば、自ら
の赤子を無駄死にさせないために終戦の決断はできるはず。そうすれば沖縄戦も
ヒロシマもナガサキもソ連参戦もなかったわけです。原爆やソ連参戦は予想外に
しても、日本国民の悲惨は十分に予測できたはずです。終戦の詔勅のような言葉
だけは飾っても、まったく無慈悲な天皇でした。
反乱が怖ければ、大元帥として戒厳令を布けばよかったのではないか。何度も
クーデター未遂の前例があるにもかかわらず、8月15日の時に、何の防備もしな
かったのも怠慢だったと思います。もし玉音放送に失敗したら、相当な混乱が
起きた可能性があるのです。
この本からはもう1か所、大仏次郎氏の 「敗戦日記」 の引用に感じるところが
ありました。8月16日付に、
「不臣の罪を自覚し死をもって謝罪すべきものは数知れぬわけだがその連中は
ただ沈黙している。東條など何をしているのかと思う。レイテ、ルソン、硫黄島、
沖縄の失策を現地軍の玉砕で申訳が立つように考えているのなら死者に申訳ない
話である。人間中最も卑怯なのが彼らなのだ。」 (165p)
東條はこの後自決に失敗して結局刑死しましたが、「敗戦の責任」 は問われて
いません。その東條を、東京裁判で開戦責任を否定する論陣を張ったからといって
英雄視し、東條の孫たちがあちこちで祖父弁護の講演をして回っている、などと
いうのですから、あきれてものが言えません。
なお6月23日は沖縄守備の第32軍牛島司令官が自決し組織的抵抗が終わった日で、
この日を 「沖縄慰霊の日」 としています。しかし実際には牛島中将が 「生きて
虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし」 として最後まで戦うよう
命令して自決したために、ゲリラ的戦闘はその後も行なわれました。
沖縄方面の守備軍を代表して宮古島から第28師団納見敏郎中将、奄美大島から
高田利貞陸軍少将、加藤唯男海軍少将らが参列して降伏文書に調印したのは、9月
2日のミズーリ号より遅い9月7日のことです。
(わが家で 2014年6月27日)
ともいえない」 と評する小川榮太郎氏が、百田尚樹氏の 「永遠の0」 とその
映画について語った、「永遠の0と日本人」 (小川榮太郎、幻冬社文庫 2013年)。
この本は、図書館の予約で借りたもので、手に取って少しでも立ち読みできたら
借り出さなかったと思う、特攻作戦肯定のひどい本です。
「私は、本書で、特定の史観やイデオロギーを主張、宣布しているのではない。
結論を出したいのではなく、問いを出している。一番やめてほしい反応は、
『右翼による戦争肯定』 『特攻賛美』 という類のレッテル張りだ。」 (252p)
と著者は言います。
しかし、ろくに事実を踏まえることもなく、だだ特攻の青年たちは純粋だった、
特攻作戦は正しかった、と主張することは、肯定のレッテルに他なりません。
そのようないいかげんな議論に対しては、徹底的に批判せざるを得ないのです。
絶対に生還しえない特攻に悩み、それを昇華した青年たちの純粋さに我々は
心を揺さぶられます。
しかし百田氏は原作で作戦としての特攻を明白に否定しています。百田氏が
作品を離れて何を言っているかはこの場合問題ではありません。ところが
小川氏は 「永遠の0」 について語りながら、原作とはまったく逆の論理を
展開している。それでいて原作を褒めちぎる、こんな評論がありうるので
しょうか。
小川氏は、戦争は悪ではない、アメリカに裁かれ保護されている戦後日本
はおかしい、大東亜共栄圏は解放の理念だった、など、極右も真っ青の論理
を展開します。そして特攻の再評価に至ります。
いわく、「特攻作戦は、立案者にも志願者にも、静かな理性と諦念と勇気
があるだけだった。作戦遂行の過程の全てが、狂的なものからもっとも遠
かった。」 (204p)
しかし、立案者のどこに静かな理性があったのか。百田氏の表現を借りれば
「軍のメンツのためだけ」 に無駄死にさせる特攻作戦の立案者と命令者には、
理性も諦念もありはしない、と思います。もちろん自分が特攻するのではない
から勇気など必要ではありません。また特攻は志願と言いながら実質は命令
だったことはあきらかで、百田氏の著作でも描かれていますが、そのことを
無視してキレイゴトばかり並べても全然説得力がありません。
「昭和19年の秋になれば、敗色はもはや濃厚だったが、敗北のしかたをどう
するかは重苦しい悩みだった。(中略) 終戦工作に入るとすれば、逆にその
前にどんな無茶をしてでも戦果を上げるべきだった。」 (213p)
と小川氏は言います。特攻の主唱者とされる大西中将は敗戦のしかたを考え
ていたというのですが (参謀長小田原少将からの角田和男のあやふやな伝聞
「修羅の翼」 角田和男) 、軍令部次長となった大西氏は原爆が落とされても
最後の聖断の直前まで2000万人特攻を頑強に主張し続けました。とても敗北
のしかたを考えていたとは信じられませんし、もし考えていたとしてもそれは
狂気のような形だったでしょう。このような大西氏を称賛する小川氏は、見る
目が曇っていると言わなければなりません。
他に日本の政治軍事の指導部が昭和19年頃に敗戦の仕方に悩んでいたなどと
いうことを証明できる史料はありません。それどころか、本土決戦に備え
大本営を長野県松代に移すための松代大本営の建設工事発令は1944年9月22日
なのです。
特攻舟艇 「震洋」 の研究開始はもっと早く1944年4月、人間ロケット 「桜花」
は5月です。軍部はもうその頃から、負けっぷりを良くするために 「桜花」 や
「震洋」 どを開発したのでしょうか? 軍全体としてそういう意思統一が
できていたとはとても考えられません。
「特攻がなければ本土は蹂躙されていた」 (227p) とありますが、本格的な本
土空襲が始まったのは1944年10月の敷島隊レイテ特攻の後なのです。大村空襲
は神風特攻隊と同日の10月25日、東京中島飛行機工場空襲は11月24日、その後
全国の主要都市が空襲を受け、壊滅しました。死者10万人という東京大空襲は
1945年3月10日です。
小川氏は沖縄を本土と認めないお考えのようですが (沖縄は立派に日本本土
であることを私は最近な教えられました)、4月1日に米軍が上陸し、特攻や
集団自決など凄惨を極めた沖縄戦は牛島司令官の6月23日自決直前の命令で
個別ゲリラ戦に移行し、戦闘はなかなか終結しませんでした。そうして8月に、
まだ空襲されていなかった広島・長崎に原爆が落とされました。
いくら特攻しようと、その戦果を誇大に数え上げようと、本土は沖縄を含め
さんざんに蹂躙されていたのです。特攻のおかげで本土が守られ、いい終戦
の形ができたなどと美化するのは、事実に照らしてまったくの誤りです。
小川氏は、もう一度日本が特攻を命ずることがあれば、きっとそれを賛美し
激励することでしょう。
「若死が悲惨で中途で無念な死なのではない。彼らは、これ以上ないほど
命を生き切っている。」 その彼らに、「蛇のように賢しらな人間が囁く。
君らは体制に利用され、天皇制に利用され、軍部に利用され、財閥に利用
されているだけだと。」 (247p)
私は、原作中で、軍部のメンツのために利用されたと言い切っている百田氏
に賛成します。実際のところ、未熟な予備士官を特攻用に訓練して、やっと
飛べるようになったばかりでもう特攻です。武士道も、美学も、「命を生き切る」
も何もあったものではないのです。そうした特攻作戦の実態を小川氏は多少
の書物を読むだけで知ることができるはずなのに、百田氏の原作にさえそう
書いてあるのに、目をふさぎ、耳をふさぎ、ただ自己流の観念論を書き連ね
たのです。
私はたとえ 「賢しらな蛇」 と罵られようと、虐げられる者の立場に立つと
心に決めています。非道な作戦を遂行した軍部と、それを知って放任した
昭和天皇を許すことはできません。言論は自由であるけれど、小川氏の
ような、あたかも戦争指導者や指揮官のような目線で特攻隊員の心情を
語る言論は慎むべきではありませんか。
(わが家で 2014年6月23日)
2009年、単行本 太田出版 2006年)。
戦争を知らない孫たちが、見たこともなかった自分のお爺さんの秘密を解き明か
していきます。
お爺さんはゼロ戦の操縦士で、いつも生きて帰ると言って仲間に毛嫌いされて
いた宮部久蔵。しかし彼はかならず生きて帰ると妻に約束していた。彼は一度も
撃墜されたことはなかった。それは逃げ回っているからだと噂されていたが、
それ操縦と空戦の名人だったからこそ、そして生きて帰ると硬く決心していた
からこそ可能だったことが、まだ生きている多くの戦友からの取材で明らかに
なる。
戦地で心の触れ合いがあった人には必ず、命を大切にするようにと諭していた
宮部。しかし終戦の間際になって、彼は特攻で戦死する。かならず生きて帰る
と誓っていた彼は、優秀なパイロットで少尉となり指導教官として欠くことの
できない人材でもあった。だから特攻を命じられる立場ではなかったと思う。
ならば特攻を志願したことになる。
なぜ志願したのか。小説にはそのなぜ、は書かれていない。戦友の語りから、
自分の指導した促成の予備学生たちが次々と特攻で死んでゆくことに耐えられ
なくなったのではないか、と推測するしかない。宮部は自ら特攻することを選ば
なければならないところまで、精神的に追い込まれたのだ。
しかもその最後の出撃の時に、宮部は自らが生き延びる可能性を捨てて、ある
戦友に家族を託す。
映画化され大ヒットしている話題作で、ストーリーは素晴らしく、人気になる
のも頷けます。
特攻を美化しているなら批判しなければならないと思って図書館で借りようと
しましたが、数十人待ちなので、文庫を買ってしまいました。読んでみると、
登場人物の話のほとんどは、むしろ旧軍をきびしく批判する内容で、戦前の
体制や特攻自体をまったく賛美していません。これは、百田氏の日頃の発言
からすると、たいへん意外でした。
たとえば、アメリカは対空砲火という防御兵器に、原爆並みの開発費を投じて
VT信管という、相手の近くに飛べば爆発する高性能信管を開発したのに対して、
「日本軍には最初から徹底した人命軽視の思想が貫かれていた。そしてこれが
のちの特攻につながっていったに違いない。」 (326p)
「意地を見せるという軍部のメンツのために」 大和と数千の将兵を特攻で捨て
てしまった。(399p)
桜花は人間が操縦するロケット爆弾で、「よくもまあこれほど非人間的な兵器
が作られたものだと思います。」 (405p)
特攻の指揮者大西中将の自決には、
「多くの前途ある若者の命を奪っておいて、老人一人が自殺したくらいで責任
がとれるのか。」 (431p)
美濃部正少佐は 20年2月の木更津での連合艦隊沖縄方面作戦会議で全軍
特攻に真っ向から反対した。(434p) 他に進藤三郎少佐 岡嶋清熊少佐も自分
の隊から決して特攻機を出さなかった。(434-435p) など兵学校出の士官にも
立派な人はいたが、「残念ながらその数は非常に少なかった。」 (436p)
「やつらの死はまったくの無駄だった。特攻というのは軍のメンツのための
作戦だ。沖縄戦の時には、すでに海軍には米軍と戦う艦隊は無きにひとしかっ
た。(中略) まだ飛行機が残っていた。ならその飛行機を全部使ってしまえと
いうわけだ。」 (486p)
愚劣な軍上層部のために、戦略的には無駄死にとなった特攻隊員ひとりひとり
の、家族や故郷や母国を思う心情は、涙なくして読むことはできません。
しかし本編で1か所、不満があるとすれば、開戦時の対米覚書の手交の遅れに
ついてです。この文書を宣戦布告文書とし、手交の遅れを在米大使館の職務
怠慢と断定していますが (373p)、この作品が書かれた後で、こうした見方を
神話として否定する、井口武夫氏の 「開戦神話 対米通告はなぜ遅れたのか」
(2008年) が発表されています。この部分を再検討できるなら、ぜひそうして
ほしいと思います。
また、特攻を 「よくやった」 と評価した天皇の発言が盛り込まれていないのは
惜しまれます。
最後に、児玉清氏の解説は、ゼロ戦ファンらしく熱がこもっています。しかし
「ただひたすら、すべての責任を他人に押し付けようとする、総クレイマー化し
つつある昨今の日本、利己主義が堂々とまかり通る現代日本を考えるとき、
太平洋戦争中に宮部久蔵がとった行動はどう評価されるのか。」 (588p)
と論じていますが、私は現代日本がそのように一方的に批判されなければなら
ないとは思いません。現代にも、自らを犠牲にして世の為に尽くす人は、東日本
大震災を見るまでもなくけっして少なくありません。庶民には健全な精神が残っ
ています。政府高官や指導者のデタラメなやり方を批判できることは敗戦の
賜物であり、この言論の自由を失っては、特攻のような狂気の作戦さえ批判でき
なくなるのです。
児玉氏は個人主義を批判しますが、まかりまちがっても戦前戦中のような
「日本を取り戻す」 ことにならないよう、心したいものです。
(わが家で 2014年6月20日)
2009年、単行本 太田出版 2006年)。
戦争を知らない孫たちが、見たこともなかった自分のお爺さんの秘密を解き明か
していきます。
お爺さんはゼロ戦の操縦士で、いつも生きて帰ると言って仲間に毛嫌いされて
いた宮部久蔵。しかし彼はかならず生きて帰ると妻に約束していた。彼は一度も
撃墜されたことはなかった。それは逃げ回っているからだと噂されていたが、
それ操縦と空戦の名人だったからこそ、そして生きて帰ると硬く決心していた
からこそ可能だったことが、まだ生きている多くの戦友からの取材で明らかに
なる。
戦地で心の触れ合いがあった人には必ず、命を大切にするようにと諭していた
宮部。しかし終戦の間際になって、彼は特攻で戦死する。かならず生きて帰る
と誓っていた彼は、優秀なパイロットで少尉となり指導教官として欠くことの
できない人材でもあった。だから特攻を命じられる立場ではなかったと思う。
ならば特攻を志願したことになる。
なぜ志願したのか。小説にはそのなぜ、は書かれていない。戦友の語りから、
自分の指導した促成の予備学生たちが次々と特攻で死んでゆくことに耐えられ
なくなったのではないか、と推測するしかない。宮部は自ら特攻することを選ば
なければならないところまで、精神的に追い込まれたのだ。
しかもその最後の出撃の時に、宮部は自らが生き延びる可能性を捨てて、ある
戦友に家族を託す。
映画化され大ヒットしている話題作で、ストーリーは素晴らしく、人気になる
のも頷けます。
特攻を美化しているなら批判しなければならないと思って図書館で借りようと
しましたが、数十人待ちなので、文庫を買ってしまいました。読んでみると、
登場人物の話のほとんどは、むしろ旧軍をきびしく批判する内容で、戦前の
体制や特攻自体をまったく賛美していません。これは、百田氏の日頃の発言
からすると、たいへん意外でした。
たとえば、アメリカは対空砲火という防御兵器に、原爆並みの開発費を投じて
VT信管という、相手の近くに飛べば爆発する高性能信管を開発したのに対して、
「日本軍には最初から徹底した人命軽視の思想が貫かれていた。そしてこれが
のちの特攻につながっていったに違いない。」 (326p)
「意地を見せるという軍部のメンツのために」 大和と数千の将兵を特攻で捨て
てしまった。(399p)
桜花は人間が操縦するロケット爆弾で、「よくもまあこれほど非人間的な兵器
が作られたものだと思います。」 (405p)
特攻の指揮者大西中将の自決には、
「多くの前途ある若者の命を奪っておいて、老人一人が自殺したくらいで責任
がとれるのか。」 (431p)
美濃部正少佐は 20年2月の木更津での連合艦隊沖縄方面作戦会議で全軍
特攻に真っ向から反対した。(434p) 他に進藤三郎少佐 岡嶋清熊少佐も自分
の隊から決して特攻機を出さなかった。(434-435p) など兵学校出の士官にも
立派な人はいたが、「残念ながらその数は非常に少なかった。」 (436p)
「やつらの死はまったくの無駄だった。特攻というのは軍のメンツのための
作戦だ。沖縄戦の時には、すでに海軍には米軍と戦う艦隊は無きにひとしかっ
た。(中略) まだ飛行機が残っていた。ならその飛行機を全部使ってしまえと
いうわけだ。」 (486p)
愚劣な軍上層部のために、戦略的には無駄死にとなった特攻隊員ひとりひとり
の、家族や故郷や母国を思う心情は、涙なくして読むことはできません。
しかし本編で1か所、不満があるとすれば、開戦時の対米覚書の手交の遅れに
ついてです。この文書を宣戦布告文書とし、手交の遅れを在米大使館の職務
怠慢と断定していますが (373p)、この作品が書かれた後で、こうした見方を
神話として否定する、井口武夫氏の 「開戦神話 対米通告はなぜ遅れたのか」
(2008年) が発表されています。この部分を再検討できるなら、ぜひそうして
ほしいと思います。
また、特攻を 「よくやった」 と評価した天皇の発言が盛り込まれていないのは
惜しまれます。
最後に、児玉清氏の解説は、ゼロ戦ファンらしく熱がこもっています。しかし
「ただひたすら、すべての責任を他人に押し付けようとする、総クレイマー化し
つつある昨今の日本、利己主義が堂々とまかり通る現代日本を考えるとき、
太平洋戦争中に宮部久蔵がとった行動はどう評価されるのか。」 (588p)
と論じていますが、私は現代日本がそのように一方的に批判されなければなら
ないとは思いません。現代にも、自らを犠牲にして世の為に尽くす人は、東日本
大震災を見るまでもなくけっして少なくありません。庶民には健全な精神が残っ
ています。政府高官や指導者のデタラメなやり方を批判できることは敗戦の
賜物であり、この言論の自由を失っては、特攻のような狂気の作戦さえ批判でき
なくなるのです。
児玉氏は個人主義を批判しますが、まかりまちがっても戦前戦中のような
「日本を取り戻す」 ことにならないよう、心したいものです。
(わが家で 2014年6月20日)
保阪正康氏が昭和史前半の研究者・ジャーナリストら12人と対談した、「保阪正康対論集 昭和の戦争」
(保阪正康、半藤一利、伊藤桂一、戸部良一、角田房子、畑郁彦、森史郎、辺見じゅん、福田和也、牛村 圭、
松本健一、原 武史、渡辺恒雄 共著。 朝日新聞社、2007)。
太平洋戦争についての深い考察を示してきた保阪氏の対論ということで期待したのですが、たいへん
不満が残りました。
まず冒頭の半藤一利氏との対論では、歴史にイフはないことを前提にしつつ、あの戦争をどこかで止める
ことはできなかったか、ということを検討しています。
まずハル・ノートを受諾したら・・・
保阪 「いわゆる最後通牒ですね。(中略) これを受諾すると日本の勢力範囲は満州事変以前に戻って
しまいます。当時の日本の権力図を見ると、とても受け入れられるものではなかったでしょう。」
半藤 「この時点でこんなものを出してくるのは外交の常識にも反しています。」 (9p)
というのですが、ハル・ノートは最後通牒ではないと東郷外相に進言した吉田茂氏の自伝をこのお二方
なら当然承知しているはず。それでいてこういうハル・ノート悪玉論は歴史研究者としてどうかと思われ、
がっかりです。
南部仏印進駐はどうか。それに対してアメリカが石油輸出禁止をしてきました。
半藤 「日本は大慌てです。(南進論の主唱者岡軍務局長は) アメリカがここまでやるとは思わなかった、
などと・・・」
保阪 「それが海軍の一方的な希望的観測なんですよ。」
半藤 「これは海軍の責任は極めて重い。」
と海軍悪者論になって行きます。しかしその直前7月2日の御前会議決定に、「対英米戦を辞せず」 と
いう文言が入っていることについては、
半藤 「それは東條らの意向を受けて、単に心がまえとしての意味だったらしいんだが・・・」(12-13p)。
何をおっしゃるウサギさん。当時はドイツが快進撃を続けている時期で、「バスに乗り遅れるな」 が
合言葉だったといわれています。石油の前に鉄くずなどいろいろな物資がすでに次々と禁輸になって
いたのですから、石油禁輸に大慌て、などというのは海軍のごく一部の人の責任逃れのジェスチャー
でしょう。
「対英米戦を辞せず」 が単なる心がまえだったとは、とても思えません。お2人になにか先入観が
あるように感じます。
戦争を始めないこと、あるいはもっと早い終結ができたのは天皇だけだった、と私は思います。しかし
半藤氏も保阪氏も、立憲君主である天皇は輔弼の臣のすることを拒否できないし、情報過疎におかれた
無力な存在で、無理に戦争を止めたらクーデターが起こったに違いない、と決めつけます。
天皇は平和志向だったのだが、反対したらテロやクーデターになったに違いないというのはこの対談で
何度も使われていて (18Pほか)、天皇免責にはとても便利な論理です。私が思うに、それなら終戦など
反乱リスクのある決断の時は、天皇を護持する側が先手を打って戒厳令を布いたらいいのではないか
と思いますが、お二人は出来ない、できないばかりですから、そのようには考えないのでしょう。
しかし、「輔弼」 とは天皇を 「補佐し助言する」 ことで、本来の権限そのものは天皇にあるわけですし、
責任を負うのは国会や国民にではなく天皇に対してであり、最終的には天皇の承認が不可欠です。
明治憲法第3条の 「天皇は神聖にして犯すべからず」 というのは、それ自体は無答責=責任を問われ
ないという明文の規定ではありません。かりに無答責と解釈したとしても、実態は違います。
総理を指名することは天皇の専権事項ですし、講和・宣戦・条約締結など国家の最重要事項はすべて
御前会議で決定されています。閣僚や重臣からの上奏も上がるし、報告を求めることもいつでも可能
でした。戦時中は詳細な戦闘報告もぼ毎日上がっている。
大日本帝国は 「万世一系の天皇之を統治す」 とある上に、特に天皇機関説を否定した1935年 (昭和10)
以降は理論上も天皇本人の直接統治になって、無答責ではなくなってしまったという解釈も可能です。
軍の統帥権はもともと天皇直属で、戦時には政府とは別に、軍事戦略・作戦を指導する大本営が設置
されるのが慣例でした。
つまり明治憲法では 「天皇は君臨し、かつ統治す」 であり、「国王は君臨すれども統治せず The King
reigns, but does not govern. (元は16世紀リトアニアの宰相ヤン・ザモイスキの言葉)」 を原則と
する西欧的な立憲君主制とは明白な隔たりがありました。立憲君主論で天皇を免責するのは牽強付会
であり、歴史を研究する態度ではありません。
保阪・半藤の2人にしてこんな話をしているとは、正直ガッカリしました。
また松本健一氏との対話では、先の戦争の呼び名 (大東亜戦争、太平洋戦争、など) を云々したあと、
保坂 「私は開戦詔書の中に、ある一文を入れて欲しかった。すなわち 『アジアの鉄鎖を打破する使命
を自覚し』 という一言があれば、われわれはどれほど 『崇高な戦争を戦った』 と思えたことか。」 (190p)
ちょっとちょっと。台湾、朝鮮を併合し満州に傀儡政権を作っていた大日本帝国がそんな文言を開戦詔書
に入れたら、それこそ反日独立運動を奨励するようなものですから、入れたくても入れられなかったのが
実情でしょう。残念な気持ちは分からなくもありませんが、保阪氏ともあろう方が何を寝ボケているので
しょうか。
続いて松本氏が 「東条英機が悪いという言い方も可能だが、私は彼に任せた近衛文麿に大きな責任が
あると考える。」 (191p) と言い出すのです。
近衛首相の和平交渉案に東條が強硬に反対して近衛が政権を投げ出したのですが、後継首班は天皇が
直接に指名するのであり、東條の場合は木戸内大臣の進言が採用されたらしいと言われています。
近衛に東條を選ぶ権限はまったく露ほどもありません。どうやったら近衛が自分の内閣を潰した東條に
「任せる」 ことができるのでしょうか。お2人とも、基本的な歴史認識が甘いように思われます。
ざっと読むだけでこれです。保阪氏と対談者それぞれに基本的な勘違いがたくさんあります。よほど気を
つけて読む必要がある本です。
(わが家で 2014年6月15日)