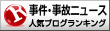「イスラーム戦争の時代」 内藤正典著、日本放送協会 2006年。
2001年9.11以後に続発した大規模テロなどイスラームの活動の原因と、相互理解の道を探った本です。著者は一橋大学教授で現代イスラーム研究家です。
著者はムスリムではないようですが、公平にイスラームと他社会の関係を検討し相互理解の方途を考えるのかと思いきや、はっきりとイスラームの立場に立った論説です。
「テロなのか抵抗運動なのかという点に拘泥すると、いずれにせよイスラム主義者側の目的が、神の定めとしてのジハードであるという本質を見失う。」「加害者側にジハードとしての正当性の認識があっても、被害者には理不尽な死以外の何物でもない。だからこそ、テロに至る前の段階での不公正感の高まりを解消しなければならない。」 (52p)
この考え方は、イスラムの抵抗は正しく、犠牲者が出ても仕方がない、という考えに結び付きます。
1997年のエジプト・ルクソール神殿のテロ事件で日本人10人を含む50四人が犠牲になったことについて、著者はあるイスラム指導者に質問したが、その答えは「仕方がない」というものだったといいます。「彼の答えは、テロの目的はイスラムに反するエジプトの体制を打倒するためであり、その目的が神が定めた義務としてのジハードである (彼らはそう信じている) 以上、『外国人観光客が殺されたのは仕方がない』 という意味だった。」 (87p) 著者は愕然とし怒りを覚えた、というのです。「このロジックはイスラーム法至上主義者の間では成り立っても、多くのムスリムが是認しているわけではない。」(88p)
しかしまた、「大多数のムスリムが平和的なのは事実そのとおりなのだが、平和的なムスリムとテロを実行するムスリムとの間に線引きをすることはできない。」 なぜならば、「イスラームに上意下達の命令系統を持つ教会組織が存在しない。」だから 「ジハードの呼びかけをしても、動くか動かないかは、ムスリム個人の判断にまかされている。」 したがって、「多くの個人がジハードとしてのテロもやむなしという方向に傾けば、暴力の件数と犠牲者は一層増加する」 こととなる。(74p)
私はこれまで、なぜイスラーム世界は非道なテロ事件に対して、非難の声明も実行者は地獄に落ちるなどの批判もしないのかと不思議でしたが、著者がその理由を明快にしてくれました。ジハードの戦士にとって、「死は神に殉じるのであるから、殉教者として来世での楽園暮らしが約束されると信じている。ジハードに打って出ない人びとは、日々の暮らしに喜びを見出し、ジハードの戦士を支援する。」(255p)
やはり平和的なムスリムといえどその心はテロリストと通じている、区別は難しいということです。敵を殺すだけならまだしも、無関係の人々を殺戮することが教義として許されている、奨励されることがあるというのはたいへん珍しい、恐ろしいことです。
著者が言うように、「ムスリムと戦うことは不毛で」あり、 「ムスリムの中から一万人に一人でもジハードの戦士が現れれば、世界を混乱に陥れるには十分である。」
まったくその通りですが、これでは到底イスラームとの和解はあり得ない。共存はできなくはないが、そのためにはムスリムに改宗してもらうか、ジハードの内容に関する教義を変えてもらうほかない。もっとも、改宗や棄教などの勧誘は死罪に当たるということなので、困難ですが、やらなければならない。改宗を死罪とする、カルトのようなイスラームに対する非暴力の 「逆ジハード」 、 「精神のレコンキスタ」 を始めなければならない。この本を読んで強くそう感じました。
「オリエント世界はなぜ崩壊したか」 宮田 律著、新潮社 2016年。
著者は 一般社団法人 現代イスラム研究センター理事長で、現代イスラム政治やイラン政治史に詳しいそうです。
イスラム研究者だけあって、イスラム寄りの見解が多いのは当然ながらイスラムの歴史が 「寛容」 の統治だというのには、なるほどと感じました。それはオスマン・トルコで完成の域に達したミレット制という、諸宗教の信徒集団に独自の法制度の適用を認める、いわば宗教的自治制度というべきものだそうです。専制君主とみられがちなイスラムのカリフやスルタンですが、宗教的な意味では協議の解釈権は学者たちが持っており、けっして専制君主ではなかった。
しかしイスラムの寛容とは、つまり「強者の寛容」ではなかったか、と思います。イスラムは草創時こそ少し苦労しましたが、ちょっと避難した (ヒジュラ) 程度で、たちまち権力を握り、あとはずっと支配者でした。しかもペルシアからスペインにまたがる大帝国をあっという間に作り出しました。もともと商業的な遊牧民を基盤としていて、支配下に入ればそれでよし、商売相手を殺しても無意味という計算があったのではないでしょうか。
現代イスラムの混乱は、西欧諸国がでたらめに国境線を引き、世界大戦のために部族間の争いを利用してきた歴史のせいです。しかしイスラムの諸集団も、てんでに利用できるものはなんでも利用してきたから、こういう無茶苦茶なことになっているのではないか、と感じます。
強者の寛容は、苦境になると残虐になります。いまイスラム原理主義はムハンマドの時代へ先祖返りした人たち。実はムハンマドの在世時に、敵方を斬首して皆殺しにしました。(クライザ族虐殺事件)
2015年にフランスで、風刺漫画を掲載したシヤルリー・エブド襲撃事件が起こり、12人が射殺されました。風刺漫画がムハンマドを侮辱した、冒涜だ、というのですが、これはイスラムは完全無欠で、一切の批判を許さない、という体質の現れです。侮辱されたら無差別に虐殺していいのでしょうか。原理主義はイスラムではない、というイスラム教徒は、なぜシヤルリー・エブド襲撃事件を非難しないのでしょうか。なぜ、犯人は地獄に落ちるという説教がなされないのでしょうか。イスラム世界が事件を黙認している、暗黙に支援しているように思えるのはなぜですか?
イスラムは素晴らしい、どんどん信徒が増えている、と言いますが、批判すれば暗殺、改宗すれば死刑、改宗を勧めても死刑、ムスリムの子は生まれた時からイスラムで死ぬまで変われない、というシステムで増えているのです。こういうのはカルトと呼ぶべきです。
それでいて、難民はキリスト教国を目指す。なぜイスラム教国に避難しないのか? なぜサウジやイランやトルコは自国で難民の面倒を見ないのか? 反イスラムの機運は当然ですが、むしろ、反カルトと呼ぶ方がいいと私は思います。
体質転換を図らなければイスラム復興など不可能。トルコは現実主義からイスラム教に回帰してしまいました。滅びるほかないでしょう。残念ながら。
「1941 決意なき開戦」 堀田江理著、人文書院 2016年。
日米開戦に至る経緯をたどり、国際情勢の推移も踏まえつつ、日本指導部が 「決意なく」 なし崩しに開戦を決定するに至ったことを明らかにします。
しかし、組閣後の連絡会議で、東条氏が開戦論を抑えるために尽力したかのように書いていますが (285P~)、根拠が薄弱です。「東条の心中で、ますます開戦への疑問が募っていた。」(298P) 東条は、開戦を強硬に主張する杉山参謀総長に、「『オ上ニゴ納得シテイタダクノハ容易デハナイト思フ』と述べた。オ上のほうは、東條が開戦強硬派を抱き込むことを大いに期待していた。それこそが、東条内閣に課された使命なのだった。」(299P)
とするのですが、天皇が開戦に反対で、そのために東条氏を首相にしたというのは天皇の責任を回避するための後講釈だと思います。交渉継続のことは明示されてはいなかった。東條内閣成立時に、海軍に、互いに協力して、といえば東条に協力してやれという意味に取られる可能性も大いにあったはず。
東條自身は、組閣にあたって東郷重徳に入閣を打診したとき、「強硬意見を持した自分に大命が降下したのであるから、駐兵問題については何処迄も強硬なる態度を持続していい筈と思ふ」 (「東郷重徳外交手記」160-161p ~安井淳 「開戦過程の研究」 40p) と発言しています。
東條総理という、肝心なところがあいまいなので、折角の大著も画龍点睛を欠く、と言わなければなりません。
(わが家で 2019年3月13日)