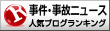南京事件の論客、笠原十九司 (とくし) 氏の、「南京事件論争史」 (笠原十九司、平凡社
新書、2007年)。
南京での虐殺事件は東京裁判でも訴因の一つとされ、当時の中支那方面軍司令官松井
石根大将がその責を問われB級戦犯として死刑になっています。
しかし、南京大虐殺については、その後「まぼろし」説などが登場、無かったとする説から
中国の主張する30万人以上説まで諸説が入り乱れています。しかし、入り乱れているという
のは見かけのことで、否定派が次々と非学問的な書物を出版することで事件の存在を曖昧
にしようとしている、というのが笠原氏の見解であり、私もそれに同意します。
著者は、まぼろし説の原型は東京裁判の弁護側陳述にあるとしてその論点をリストアップし
(87-88p)、論争の時系列で反論していきます。
① 伝聞証拠説 南京安全区国際委員の証言や記録は直接目撃したものではない。
② 中国兵・中国人犯行説 敗残の中国兵や中国人が混乱に乗じて行ったことがすべて
日本兵の仕業とされている。
③ 便衣兵潜伏説 殺害した市民とは実際は便衣兵 (ゲリラ) だったので不法殺害では
ない。安全区に潜伏したために市民が疑われて殺されたのは中国側の責任。
④ 埋葬史料うさんくさい説 中国の慈善団体による埋葬史料には戦死者を含んだり、
誇張もあり、杜撰で信用できない。
⑤ 南京人口20万人説 占領前の南京の人口は20万人で、皆殺しでもしなければ20万人
虐殺はありえない。
⑥ 戦争につきもの説 (これは問題外でしょう=rocky)
⑦ 挑発・調達説 物資については軍票や対価を払ったので椋奪ではない。また受取人
が避難・逃亡して不在だっただけ。
⑧ 大量強姦否定説 組織的な大量強姦はなかった。安全区国際委員会の記録も伝聞
である。売春を強姦と報告したケースもある。
⑨ 中国の宣伝謀略説 排日・侮日のプロパガンダ。
⑩ 中国とアメリカの情報戦略説 南京在住の中国びいきの欧米人が中国の宣伝が以降
のお先棒を担いだ。アメリカがこれに与した。
あったかなかったか、については 「あった」 というのが結論です。東京裁判でA級戦犯
無罪・松井将軍無罪の判決書を書いたインドのパル判事は、南京事件について、こう言って
います。
「南京における日本兵の行動は凶暴であり、かつベイツ博士が証言したように、残虐はほと
んど3週間にわたって惨烈なものであり、合計6週間にわたってつづいて深刻であったこと
は疑いない。事態に顕著な改善が見えたのは、ようやく2月6日あるいは7日を過ぎてから
である。弁護側は、南京において残虐行為がおこなわれたとの事実を否定しなかった。かれ
らはたんに誇張されていることを愬 (うった) えているのであり、かつ退却中の中国兵が、
相当残虐行為を犯したことを暗示したのである。」(73p)
また旧陸軍軍人の親睦組織・偕行社の 「証言による南京戦史」 (畝本正巳編、「偕行」 1984年
4月~1985年2月) には、「編集者の意図に反して、虐殺をやった、見たという証言や記録が
かなり出てきてしまい」、1985年3月に編集部の加登川幸太郎氏が 「その総括的考察」 を書い
て、「捕虜の処理の適正を欠いた根本の責任は軍上層部にあるが、しかし前線部隊にも軍規・
風紀の乱れがあり、掠奪・暴行などの不法行為が多発した事実を指摘し、それらの非行を
戒めるために、異例な陸軍参謀総長閑院宮載仁親王の軍規・風紀引き締めの訓示 (1938年
1月4日) が出され」 たこと、不法殺害の推定数を板倉由明の1万3千人、畝本正巳の3000~
6000人を併記し、「この大量の不法処理には弁解の言葉はない。中国人民に深く詫びるしか
ない。まことに相すまぬ、むごいことであった。」 と結んだとのことです。(155-156p)
当時日本と防共協定を結んでいたドイツの外交官ローゼンの南京状況報告には、「中国の
敗残兵を日本軍が便衣兵として連行して殺害したのを 『いかなる軍事裁判も、またこれに
類する手続きも一切行われた形跡がなかった』 と、『あらゆる戦時国際法の慣例と人間的
な礼節をかくも嘲り笑う日本軍のやり方』をきびしく批判していた。」 (190p) そうです。
中国やアメリカの陰謀ばかりとは言えません。
近年は、便衣兵の殺害は戦時国際法違反にならないとか、30万人・20万人は多すぎるとか
の条件闘争? になってきているようです。しかし、かりに便衣兵といえども何らの裁判
なしにいきなり処刑では、「戦時国際法の慣例と人間的な礼節」 を踏みにじると言われて
も仕方ありません。
被害者数の正確なカウントは不可能ですが、20万人は嘘だ、というのと、虐殺自体が嘘だ、
ということは別です。
否定派の議論は、今となっては確認できないことを言い立てて、何とかして 「なかったこと」
にしたいという意図がありありで、信頼に欠けます。日本の言論界はどうかしています。
(わが家で 2014年9月30日)
遼太郎の代表作を解剖した、「誤謬だらけの 『坂の上の雲』」 (井弘之、合同出版、2010年)。
『坂の上の雲』 は私も読みましたが、明治の日本軍と戦争をあまりに賛美するので途中で投げ
出したくなった記憶があります。
著者はこの小説が事実に基づいて書かれた 「歴史書」 だと司馬氏が言っていることに注目しま
す。「この作品は、小説であるかどうか、じつに疑わしい。ひとつは事実に拘束されることが
百パーセントに近いからであり、いまひとつは、この作品の書き手 ―私のことだ― はどう
にも小説にならない主題を選んでしまっている。」 (『坂の上の雲』 第8巻 330ページ、本書15p)
そしてそれが司馬氏の巧妙な作話術 (歴史書としては詐術) であることを丹念に立証していきます。
日露戦争は同時に朝鮮植民地化戦争だったということに私は気が付いていませんでした。朝鮮
は日露戦争の後にたまたま植民地になったのではなく、日本は日清戦争より前、征韓論のころ
から朝鮮を狙っていました。1985年には駐韓三浦公使らが親露派の皇后閔妃を虐殺しています。
そして日露開戦に先立つ1903年12月30日、閣議で 「韓国に関していはいかなる場合に臨むも、
これを我が権勢の下に置かざるべからざるはもちろんなり」 とする 『対露交渉決裂の際、日本
の採るべき対清韓方針』 を決定。(75P) 大韓帝国は1904年1月21日、世界各国に対し中立宣言
を発しましたが、日本軍はこれを無視して2月6日に韓国釜山などの電信局を占領 (76P)、2月8日
仁川上陸。そして2月10日ようやく日露相互で宣戦が布告されます。2月20日にはソウルを占領し、
反対する大臣イ・ヨンイクを日本に連行する等の強圧のもとで、2月23日に韓国に対し日本軍
に協力させる 「日韓議定書」 を締結させました (76-77p)。そしてポーツマス条約でロシアに
対し、日本が韓国における 「卓絶した利益を有する」 ことを承認させました。
司馬氏はこうした韓国植民地化にまったく触れようとしないのですから、史観というにはあまり
に一方的な、ジコチュウ史観とでもいうべきでしょう。氏は日露戦争を祖国防衛戦争として描き
ますが、戦場は朝鮮や遼東半島、中国東北部で日本本土ではありません。日本海海戦のロシア
艦隊は日本本土上陸作戦のためにやってきたのではないので、朝鮮中国への軍隊と軍事物資の
輸送路確保のための制海権の争いでした。
韓国を取ったらその隣の満州、満州を収めたらその隣の華北やシベリアという具合に、「祖国
防衛のためと称して外国に攻め込んで戦う」 というのが日本の伝統のようです。
また日露戦争時の日本軍は 「前代未聞なほどに戦時国際法の忠実な遵法者として終始し、戦場
として借りている中国側への配慮を十分にし、中国人の土地財産をおかすことなく、さらには
ロシアの捕虜に対しては国家をあげて優遇した。」 (『坂の上の雲』 第7巻 218ページ) と
司馬氏は言いますが、これについても反する証拠が沢山あります。
まず何より、宣戦布告前2月8日に旅順ロシア艦隊を夜襲したこと。韓国の中立宣言を無視して
侵攻したこと。韓国内で1904年7月に日本軍が勝手に 「軍律」 を制定し、連座罰まで設けて
強制したこと (97p)。樺太南部で捕虜となったロシア兵180名を虐殺したこと (85p) などなど。
司馬氏が明治の日本軍を持ち上げるのは昭和の堕落との対比のためなのですが、著者は、昭和の
退廃はすでに明治から孕まれていたにすぎない、とします。また、日清日露の戦争は遅れて近代
化した日本の選択の余地のない進路だった、「韓半島は日本に向けられた匕首である」 から、
韓国植民地化は地政学上必然だった、というのが司馬史観の見方ですが、けっしてそうではない、
と著者は考えます。
私には、当時の日本がなぜ朝鮮をそれほど欲しがったのか分かりません。韓半島は匕首、など
というのは被害妄想でなければ取ってつけた屁理屈、だと私は思います。未開野蛮の人たちで
さえ、征服されようとすれば反抗します。朝鮮は近代化は遅れたものの、明の滅亡後は儒教文化
の中心を自認するほどの文化国家で、日本に対する反抗につぐ反抗はむしろ当然だったでしょう。
明治政府成立直後から起こった 「征韓論」 について、研究してみる必要がありそうです。
(わが家で 2014年9月25日)
(日本放送出版協会、2007年)
サイパンと東京の中間にあり、空襲から本土を防衛するために死守すべき硫黄島。2万1千の
守備隊を指揮する栗林中将は全島を地下壕要塞化し、バンザイ突撃を禁じ各隊が塹壕陣地を
死守してゲリラ的に戦うことを命令。5日で落とせると思っていたアメリカ軍に戦死者7千余、
戦傷者2万1千人という予想外の大損害を与え、2月19日から3月26日まで36日間も抗戦を
続けて称賛され、映画 「硫黄島からの手紙」 にも描かれました。
しかし大本営は硫黄島を捨て石と決めており、増援も補給もまったくしませんでした。したく
ても船も護衛もないのは、兵たちは知らなかったが軍中央は分かっていたのです。
兵たちは、火山島のため40度近くにもなる塹壕の中にひそみ、抗戦を続けたのでした。そして
栗林中将の司令部は3月26日に壊滅しましたが、当時まだ数千人の兵が残っていました。降伏
を許さない戦陣訓と最後まで抗戦せよという栗林中将の遺命のため、指揮系統も食料も水も
弾丸もない状態で、仲間の死体と共に眠り、最後まで抵抗をつづけました。
米軍が最後の日本兵の集団を捕捉した、と記録したのは5月17日、司令部壊滅からなんと51
日目でした。負傷などで捕虜となり生還したのは2万1千人のうち1千人程度とみられ、2万人
が戦死または病死・餓死しました。どこにあるか分からない塹壕などに、未収集の遺骨がたく
さん残されています。
栗林中将の作戦指揮と兵の敢闘はまことに驚嘆すべきですが、本土攻撃を遅らせるという戦略
目的上は殆ど効果がありませんでした。東京大空襲は3月10日、名古屋3月12・19日、大阪が
3月13日、神戸3月17日と大規模な空襲が続きますが、これらは硫黄島守備軍がまだ頑強に
抵抗している間のものです。
また硫黄島の玉砕があたらしい日本の礎になったのか、私には疑問です。優秀な兵たちが生き
て日本に帰ったほうが、よほど戦後復興に役立ったのではないかと思うのです。映画 「硫黄島
からの手紙」 のように、戦闘はいつも英雄的で美しく描かれますが、実際はむごたらしいもの
です。増援せず補給も送らず、撤退も降伏も許さず、見殺しにする。それを玉砕という美しい
言葉に言い換え、美談に仕立て、国民を駆り立てました。
言葉は恐ろしい。
日本軍の徒手空拳での全員玉砕戦法も恐ろしい。
NHK取材班が生還者の貴重な生の声を記録したことに感謝します。
そうした玉砕戦を本土で実施しようとしていた当時の軍部は狂っていたと考えざるを得ません。
終戦に最後まで抵抗した阿南陸軍大臣は、「一死大罪を謝す」 として自決したことで評価され
ますが、私には大馬鹿、狂人としか思えません。あえて死者に鞭打ちますが、愚劣な戦争指導
と終戦引き延ばしのために無為に数十万の軍民を死なせておいて、一死で許してもらおうなど
とは、甘すぎませんか。死ねば許されるなどと考えるからデタラメができるのです。生き恥を
さらしてこそ、償いができるのではないでしょうか。
そして靖国神社に祀られましたが、どの面下げて戦死させた人たちにまみえるのでしょう。
同様に大西中将も特攻作戦を主張して最後まで終戦に抵抗し、自決して靖国神社に祀られて
いますが、あってはならないことだと私は思います。
(わが家で 2014年9月13日)
今日の朝刊で 「昭和天皇実録」 が公表されたと報道されました。大部のもので、すぐ
読むことも困難だと思いますが、毎日新聞によれば、戦前については天皇を平和志向の
立憲君主として描いているようです。
一方、昭和期を取り上げて天皇制の実態を批判的に分析した、「天皇の昭和史」。
(藤原彰ほか、新日本出版社、2007年)
この本では、昭和天皇は決して平和志向ではなく、また決して立憲君主的ではなかった
と論じています。立憲君主的とは、内閣や輔弼の官の上奏を、意に沿わなくても裁可
する、総ての法律勅令などは大臣の副署を必要とする、ということです。しかし実際は
内奏や御下問、人事への介入などを通じて天皇がコントロールしていた、として多くの
実例を挙げています(47-48p)。
たとえば1939年阿部信行組閣時には、陸軍大臣に梅津か畑を選ぶよう指示し、同8月
山下泰文と石原莞爾の親補職就任に反対、1944年8月には山下泰文のシナ派遣軍総参謀
長就任を拒否しました。
それより何より、そもそも総理大臣の指名は憲法上も天皇の権限ですが、大臣の副署も
何も不要ですから、気に入らない者は憲法に則ってたとえ元老の推薦であろうと拒否
できるわけです。いやいやながら指名するなどという必要はありません。
また輔弼・輔翼は各大臣・総長が独立して行うので、当然のように情報の天皇への独占的
集中がおこりました。(51p)
そして天皇は陸海軍を直接統帥する大元帥で、そうとうな軍事知識を持ち、作戦にも
御下問などを通じてしばしば容喙しました。(53-54p)
不思議なのは、軍部大臣現役制で陸軍が大臣を推薦しないという方法で組閣を妨害した
時、天皇がこれを傍観していたことです。1937年、広田内閣総辞職後に宇垣一成に組閣
の大命を下しましたが、陸軍は大臣を出さず、宇垣が天皇に優諚 (宇垣を予備役から
現役に復帰させ陸軍大臣の兼務を許す命令) をお願いしたもののこれを却下し、大命は
返上されました。
また1940年米内内閣時には、陸軍が畑俊六陸相を単独辞職させ後任を推挙しなかった
ため、内閣は崩壊しました。
天皇は、自ら指名した総理また総理候補者にたいし陸軍が公然と反旗を翻すことを容認
したわけです。軍を統帥する大元帥として、個人名を挙げずともただ大臣を出すようにと
命ずればよいのですから、なぜ手をこまねいたのでしょうか。立憲君主ならば軍の行動は
憲法違反だと考えても不思議はないはずですが。
この本にはありませんが、天皇が国政をコントロールするもう一つの手段は、勅語の存在
です。教育勅語や軍人勅諭など堅苦しいものもありますが、たとえば1932年1月に「満州
事変に際し関東軍に賜りたる勅語」というものが出されています。これは関東軍の行動を
褒めちぎり激励するもので、以後関東軍への批判は許されないという風になっていきます。
先日の平山周吉著 「昭和天皇 『よもの海』 の謎」 のページで書きましたが、仮に昭和天皇
が一見立憲君主的に振る舞ったとしても、明治憲法で 「天皇に輔弼の臣のいうことを
拒否する権限があるのは当然」 と解釈されていたということです。臣下の言うことを
そのまま聞かなければならない、などとは明治憲法もその学説も考えていません。むしろ
臣下が天皇のご意向を酌んで、裁可していただける案を提出するのが実態だったので、
「ある意味では強い御親政のようで」 (「石井秋穂大佐回想録」) あったのでした。
「昭和天皇実録」 は良く見せようという意図が働いていると思われ、注意して読まな
ければならないと思います。
(わが家で 2014年9月9日)
「昭和天皇 『よもの海』 の謎」。 (新潮社、2014年)
著者は雑文家、と称しており、安井淳氏のような史料批判や原著ページの明記などが
ありませんが、いくつも参考になるところがありました。
明治天皇の御製 「よもの海みなはらからと思ふ世に など波風のたちさわぐらむ」。
日露戦争に際して明治天皇が開戦前に平和への思いを詠んだものと言われ、ルーズベルト
大統領が感銘したと伝えられています。
平和を願う昭和天皇は1941年9月6日の御前会議で、帝国国策遂行要領を審議した際に
詠じてその意を表したとされています。しかし佐々木信綱 「明治天皇御製謹解」 (昭和
16年) には 「戦時中にしてこの御製を拝す」 (46p) とあり、また渡辺幾次郎 「明治天皇
と軍事」 (昭和11年) には 「開戦当初 『正しく心緒を述ぶ』 と題されて詠じたもうた」
とあるそうで、いずれも日露開戦を決定したのちにこの歌を詠んだと伝えられています。
波風が立つのでやむなく開戦になってしまった、まったく我が意ではないのだが、という
ことですが、開戦前と開戦後ではその意味あいがかなり違ってきます。昭和天皇の真意は
ともかくとして、やむなき開戦決意と解釈することが可能だし、そう解釈できると考えた
知恵者が軍部内にいたのではないか、と著者は推理します。
また昭和天皇はこの歌を 「などあだ波の」 と詠んだと、近衛と杉山の2人が書き残して
います。「明治天皇御製」 と佐々木信綱の 「明治天皇御製謹解」 は当時の大ベストセラー
で、この歌もよく知られていたはず。御前会議出席の7人のうち2人もが間違うとはどう
いうことでしょうか。記録のとおりに詠んだ可能性もありそうです。工藤美代子氏もたしか
「近衛家七つの謎-誰も知らなかった昭和史」 で単なる記憶違いではないかもしれないと
疑問を呈しています。「あだ波」 のあだとは敵のこと。敵がうるさく騒ぐのであれば、
不本意ながら開戦を決意せざるを得ない、という意味に取ることもできるかもしれません。
というのも、この会議で対米交渉が主、開戦準備は従、ということが確認されたのですが、
議題の当初の書き順は開戦準備が先になっており、天皇が前日急いで陸海軍総長を召して
説明をさせ交渉が先であることを確認させた際、近衛が天皇に議題順序を変更すべきかと
確認しましたが、必要ないと言われたことになっています。
ところが昭和天皇独白録では、近衛が議題の変更はできないと強硬に主張したとなってい
て、まったく対立しています。著者は永野軍令部総長も、変更すべきかと確認したが天皇は
原案の順序でよろしいと答えた、と証言していることを指摘します (94p) (新名丈夫編
「海軍戦争検討会議記録」 昭和20年12月、出版昭和51年)。天皇の記憶が違っているのか、
わざとそのように言っているのでしょうか。「独白録」 は東京裁判用の自己弁護の回顧録
とみられ、あまり信頼できる文書ではありません。
また、交渉第一というなら、その交渉条件こそが大切なはずです。ところが帝国国策遂行
要領に付けられた条件は強硬でとても妥結できるような内容ではなかったのですが、天皇
も誰もこのことについて検討したり言及した様子はありません。実に不思議な話で、これ
では交渉第一はたんなるお題目、言い訳程度のものだったと考えざるを得ません。
だからこそ東條が、「よもの海」 を披歴され天皇は平和志向だとあわてたものの、翌日に
面会した東久邇宮に対して従来通り対米交渉軽視の姿勢を見せることができた (63p) ので
しょう。
また東條氏は、近衛総理の対米交渉=中国撤兵案を拒否して倒閣した10月中旬、組閣にあた
って東郷重徳に入閣を打診したとき、「強硬意見を持した自分に大命が降下したのである
から、駐兵問題については何処迄も強硬なる態度を持続していい筈と思ふ」 (「東郷重徳
外交手記」160-161p ~安井淳 「開戦過程の研究」 40p) と発言しています。東條氏に
大命を降下したさいのいわゆる「白紙撤回の御諚」 でも、東條氏が固執する交渉条件を
見直せという指示はなく、結局は戦争遂行能力の 「再検討」 としかなりえず、開戦に
進んでしまったのは当然です。
もう一つ驚いたことは、昭和天皇は自ら立憲君主であったと強調しますが、明治憲法でも
「天皇に輔弼の臣のいうことを拒否する権限があるのは当然」 と解釈されていたということ
です。(167p)
天皇主権説では当然のことですが、排撃された天皇機関説でも、
「国務大臣の進言を嘉納せらるるや否やは聖断に存する」 (美濃部達吉「逐条憲法精義」
昭和6年版) とあり、また
「任意に国務大臣の意見の採否を決したまうことを得」 (佐々木惣一 「日本憲法要論」
昭和8年版)、
「君主は国務大臣の同意なくして大権を行うこと能わずとなすがごとき者あらば、考えざる
の甚だしきものなり。」 (金森徳次郎 「帝国憲法要綱」 昭和5年版)
とされていました。
帝国国策遂行要領の原案を書いた石井秋穂の 「石井秋穂大佐回想録」 (昭和21年、未刊)
には、「天皇陛下は内閣の諸公が会議決定した政策を覆えしたり拒否されたりしたことは
なかった。(中略) ところが常の陛下は大臣が上奏する毎にいろいろと御注意を加えられて
は御拘束になり、または御奨励御激励されることによって方向を保たれたのである。大臣
たちにとっては誠に重圧でありうるさかったのである。即ち御親政あそばされないようであり、
またある意味では強い御親政のようでもあった。」 (280p) とあります。
旧軍人にしてこの感想です。天皇に批判的な 「天皇の昭和史」 (藤原彰ら、2007年、44-58p)
では、天皇が御下問や内奏への対応などを通じて実質的な親政を行っていたことを詳しく
指摘しています。明治憲法では天皇は無答責だ、というのは 「神聖ニシテ犯スヘカラス」
という言葉のみに頼った、極めていい加減な天皇像ということになってしまうでしょう。
(わが家で 2014年9月7日)