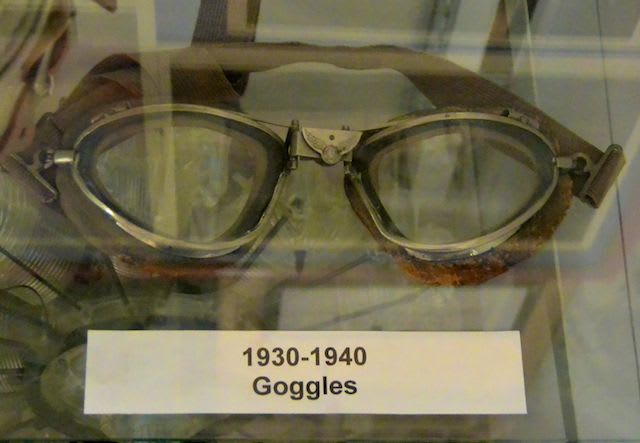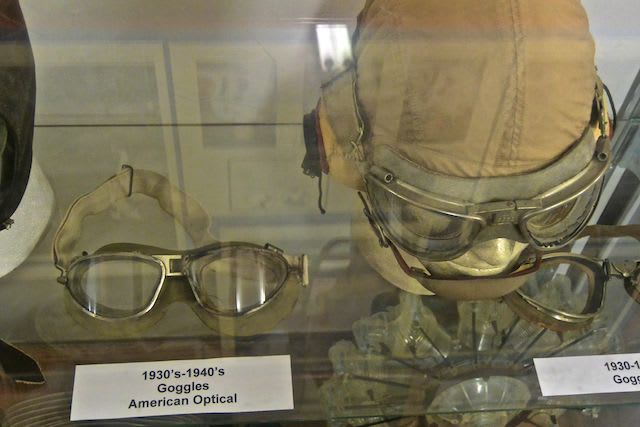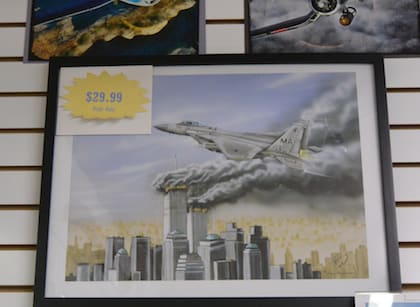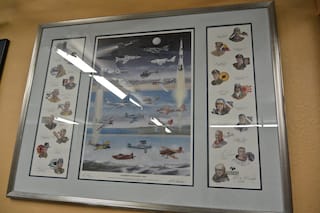さて、久しぶりですが、空母「ミッドウェイ」の話題に戻ります。
ちょうど八戸航空基地の話題が終わった後ですが、「ミッドウェイ」も
艦内の説明を終わり、ちょうどフライトデッキに出てきたところ。
ここからの「ミッドウェイ」の話題は、フライトデッキに展示されている
多くの航空機に焦点を絞っていこうと思います。
艦載機といっても、実際に「ミッドウェイ」に艦載されていたものもあれば、
時期的に合わなかったり、また規格が違ったりで、
ここから発艦したことがない機体も多いですが、「ミッドウェイ」は
その存在価値を「海軍歴史博物館」と自認しているので、
集まってくる機体は拒まずきちんと展示し、紹介しているのです。
これから説明という時に結論めいたことをいうと、わたしはこの展示で
アメリカの底知れない軍事技術のある時期までの集大成を見た気がしました。
固定翼出身の元海将がよくおっしゃることですが、軍艦、特に空母は
その国の科学技術と海事文化の粋を集めたものです。
近い将来に、日本が空母を持つという計画が世界の軍事ウォッチャーの間で
関心を集めていますが、もしそれが「オンゴーイング情報収拾」の段階なら、
関係者は過去の遺産と決めつけず、ぜひ「ミッドウェイ」に脚を運び、
アメリカの空母文化というものをリサーチしていただきたいと思いました。
今までアメリカ国内でいろんな旧軍艦利用型博物館を見てきましたが、
展示が充実し、そして観客が多く、メインテナンスが行き届いているのは
いずれも空母で、西の「ミッドウェイ」、そして東では「イントレピッド」でした。
特に「ミッドウェイ」はサンディエゴという海軍のお膝元にあって、
海軍からの直接援助や、ベテラン含む一般の大口賛助が集まりやすいのが大きいでしょう。
艦内スペースを海軍関係のイベントにしょっちゅう解放し、退役した軍人たちが
何かと集まるコミュニティの役割をしていることも、隆盛の理由だと思います。
そしてその結果、いたるところに観覧者のための工夫が凝らされ、
さらに大人から子供まで、楽しく過ごせるアミューズメントパークとして
人々を惹きつけることに成功しています。
たとえばフライトデッキでは、この写真のように、あちらこちらに乗員の等身大の人形や
パネルがあり、かつての雰囲気を伝えると同時に、観客の目を楽しませ、
「インスタ映え」のお手伝いもしてくれます。
ここにいるのは「トムキャット」から降りてきたという設定の搭乗員。
平面パネルの写真は実際の現役空母乗組員を撮影したものらしいですが、
この立体模型の人にモデルはいるのでしょうか。
子供が「はえ〜〜」って感じでその威容に見とれていますが、
デパートのマネキンのように嘘くさいイケメンなどではなく、
ガタイはいいけど額が妙に後退しているあたり、実にリアルです。

Grumman F-14 トムキャット Tomcat 戦闘機
コクピットにちゃんと二人パイロットが搭乗しています。
写真を見て初めて気がつきました。
この二人は、実在のF-14パイロットをデディケート(顕彰)していて、
前席のパイロットには、
ジェイ・”スプーク”・テイクリー少佐
VF-114 コマンディング・オフィサー 1983−1984
後席には
テッド・”スラップショット”・カーター少佐
VF-114 コマンディング・オフィサー 1998-1999
とその下の窓枠にペイントされています。
「スプーク」は幽霊、「スラップショット」はホッケーのステイックの
小さくて力強いスイングによる速いシュートを意味する言葉で、
いずれもパイロットの「タックネーム」(あだ名)です。
ちなみに、映画「トップガン」の「マーヴェリック」「グース」
そして「アイスマン」などの名前も皆タックネームです。
この二人はいずれも114戦闘機部隊にいた司令官で、よく見ると
このトムキャットの尾翼には、部隊ニックネームの
「アアドバーク(aardvark)」(ツチブタ)のイラストが描かれています。

わたしツチブタを見たことがないので、調べてみました。

あー、確かに。
アリクイに似ていると思ったら、やはり主食はアリだそうです。
アフリカにしか生息しない動物なのに、なぜアメリカ海軍の航空隊が
シンボルにしているのかは謎です。
ところで、不思議に思ったのは、VF-114は1993年に閉隊しているのに、
後席の司令官の任期が1998〜1999となっていることです。
不思議に思ってこの”スラップショット”司令官の経歴を少し調べてみると、
ウォルター・E・カーター・Jr.
スラップショットというだけあって本当にアイスホッケーの選手でした。
確かに海軍のパイロットとして各飛行隊の司令を歴任していますが、
VF-114ではなくVA-14、トップハッター
の司令官であったらしい・・・・・
つまり結論を言うとこの機体のペイント、間違っているのです。
2018年現在、アナポリスのスクールヘッドであり、ヴァイス・アドミラルでもある
偉い人の経歴を間違ってこんなところに堂々と書いてあるって、これ、まずくない?

F-14の裏側に回ると、内蔵している20ミリ砲の部分が透明になっていました。
こちらのコクピットには、
デイブ・”ブッシュワッカー”・ビョーク(北欧系かな?)
ニール・”カウボーイ”・ザーブ
とネーミングされています。
ブッシュワッカーとは「藪を切り開く人」という感じでしょうか。
ところで先ほど「トップガン」の話が出ましたが、
トップガンといえば何と言っても主役はこのF-14ですよね!
とかなんとか言いながら、正直わたしはこの映画、劇場で見たわけでもなく、
マーヴェリックの搭乗機がなんであるかなど、全く興味もなければ
今日に至るまで、記憶の端っこにも引っ掛けていなかったわけですが。
この撮影で、制作側は海軍に2億円という機材使用料を払っています。
しかし、宣伝料という意味でお金を払ってもよかったのは、
むしろ海軍の方だったかもしれません。
ご存知の通りこの映画は大ヒットし、海軍は機材使用料で儲けたのみならず、
映画を観てその気になった若者を海軍に呼び込むための「〇〇者ホイホイ」を設け、
(〇〇には心に浮かんだ言葉をそのまま当てはめてください)
〇〇者を海軍に取り込みにかかりました。
「ホイホイ」つまり映画館の出口に設けたリクルートブースです。
まさか映画館の出口で自分の人生を変えようなどという人がいるわけない、
と思ったあなた、アメリカ人を甘く見てはいけません。
映画を観た直後、文字通りホイホイと入隊申し込みをした〇〇者は
海軍がホクホクするくらいたくさんいたと言いますから驚きます。
今度「空母いぶき」が実写映画化されるそうですが、映画館の外に
海上および航空自衛隊の地本がブースを出してはどうでしょう?(提案)
もちろん、皆マーヴェリックのようなパイロットに憧れて入隊したのですが、
実際全海軍の中のたった12人の超トップクラスエリートである
トップガンどころか、航空に行けた人がそのうち一人でもいたかどうか・・。
実はこの時海軍、制作にあたりペンタゴンとも協力して、映画をヒットさせ、
海軍への入隊増加につなげようと最初から目論んでいたということだったので、
全ては
「計画通り」
だったのです。
しかも海軍にとどまらず、ペンタゴンまでが映画制作に介入し、
制作段階から幾度となくチェックを入れてきたということですから、
「トップガン」って実は「国策映画」でもあったということなんですね。
単純なところで「トップガン」という言葉を世の中に広めたというだけでも
映画の効果は大で、わたしは思うのですが、空の専門を自認するエアフォースは
「トップガン」=「パイロット」を世界中に刷り込んだこの映画に対し、
面白くない、というか苦い顔をしていたのではなかったでしょうか。
ともかく「トップガン」はヒットしました。
繰り返しますがその一因に、このF14のかっこよさがあったに違いありません。
なんの機体を使っているのか全く興味がなかったわたしがいうのもなんですが、
最初に見たときもあれが戦闘機のカタチとして、非常に洗練されているというか、
見た目がとにかく美しいとなんとなく感じていた気がします。
なんでも
映画の「もう一つの主役」はF-14トムキャットである
というのが制作サイドの宣伝文句の一つだったそうですね。
トップガンつながりで今回知ったことですが、トム・クルーズの演じた
タックネーム「マーヴェリック」役には、当初、
ショーン・ペン、マシュー・モディーン、ニコラス・ケイジ、
ジョン・キューザック、マイケル・J・フォックス、トム・ハンクス
という俳優たちが候補に挙がっていたそうです。
誰がやっていてもヒットはしたと思いますが、一つ言えるのは誰がなっても
マーヴェリックのイメージはトム・クルーズとは随分変わっていたことです。
個人的には無理と知りつつマシュー・モディーンを推しますが(笑)。
まずニコラスとマイケルって、あんまり海軍のドライバーって感じしないんだよな。
マイケル・J・フォックスは当時まだ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の
イメージが強すぎてシリアス感に欠けたと思うし、ニコラスは陰気なところはいいけど
どちらかというと役柄的にグースのイメージだと思います。
そしてトム・ハンクスははっきりいって陸軍の制服しかイメージできません。
(感想は個人のものです)
ある英語の映画蘊蓄サイトによると、実際の撮影は、ジンバルを備えた操縦席を作り、
そのセットで行われたそうですが、それとは別に俳優は役作りのため
複座のF-14に搭乗させられ、その駆動を実際に体験することになりました。
出演者がトム・クルーズも含めてゲロゲロに酔ってしまった中、
「トップガンには見えない」
とわたしが酷評していた「ERのグリーン先生」こと、グース役の
アンソニー・エドワーズだけは、一度も吐かなかったということです。
うーん、この話を知ると、彼が一番トップガンらしい気がしてきた(いい加減)
飛行シーンはスタントマンが行なっており、しかも映画撮影中に
機体が太平洋に墜落するという事故があり、結果スタントマンは亡くなっています。
だとすると映画会社はこの機体をどうやって弁償したのでしょう。
ついに待望の続編が誕生する運びになったわけですが、この作品で
トム・クルーズは前作の「マーヴェリック」のその後として登場し、
教官として女性パイロットを育てるというプロットだとか。
なんかの役で(海軍バーのマスターとかかな)出演するそうなので、
名悪役キャラ好きのわたしとしては、公開されたらぜひ観てみたいです。
今度はちゃんと注目するつもり。




























































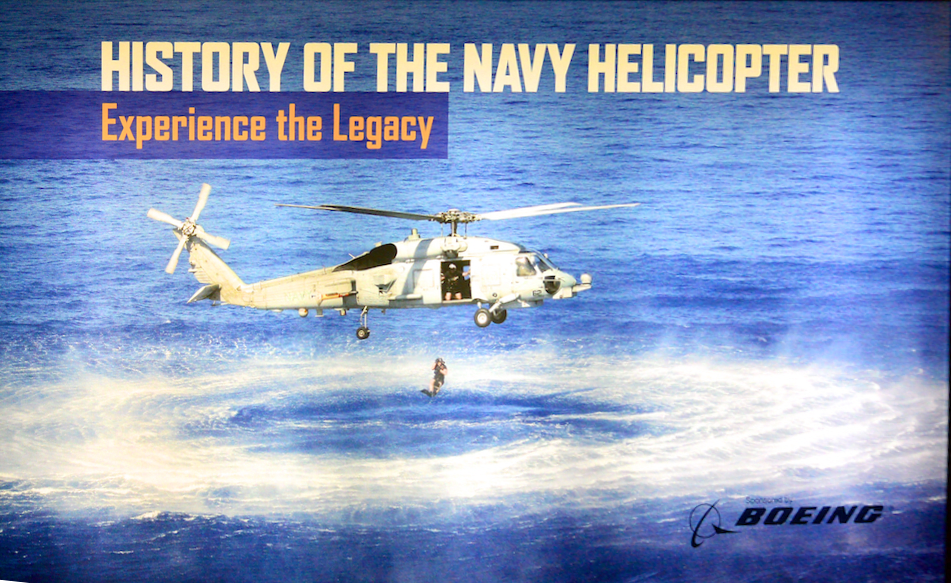



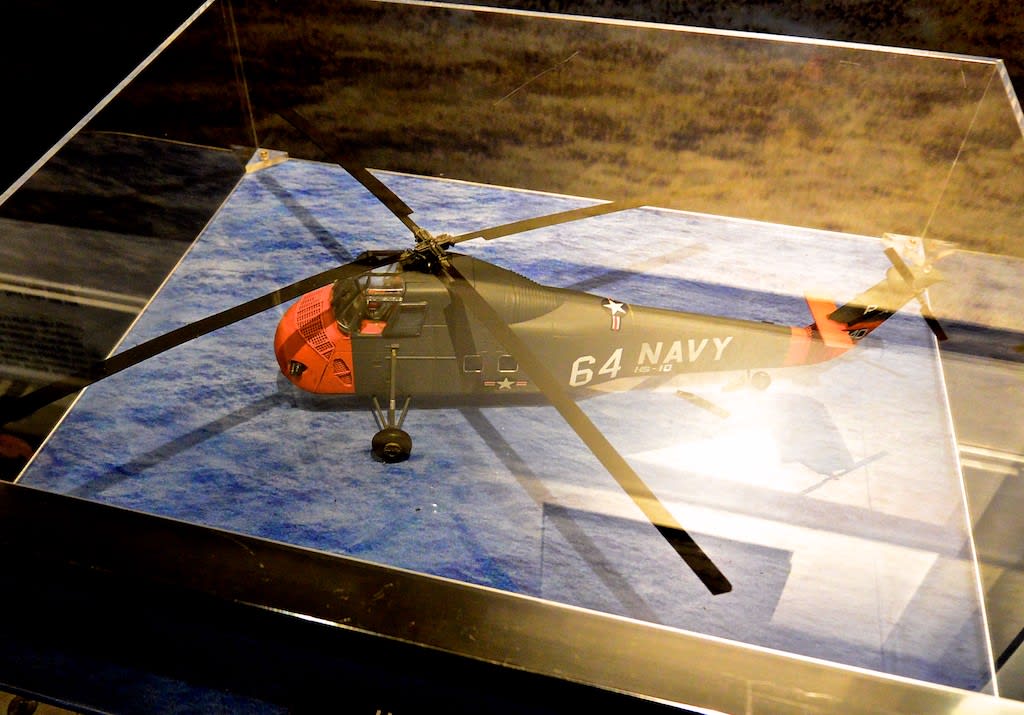


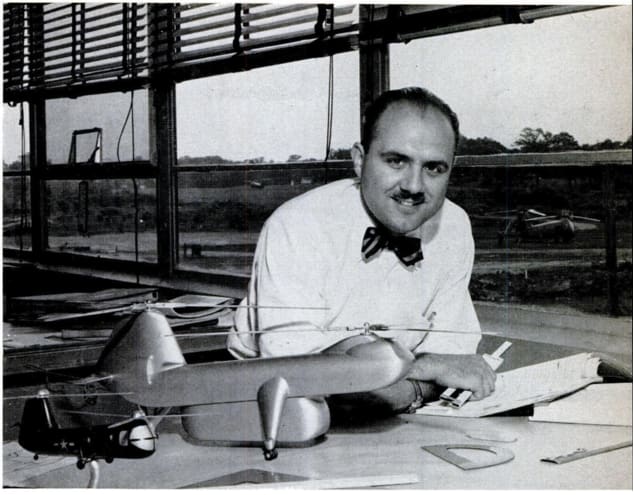






















































































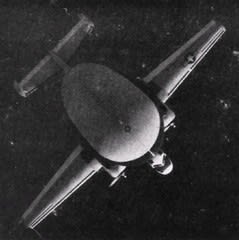 wiki
wiki







 wiki
wiki