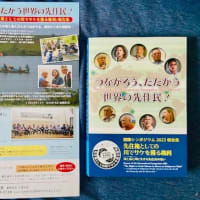さる、8月17日、北海道浦幌町のアイヌ民族グループ「ラポロアイヌネイション」が、祖先がサケを捕獲していた川でのサケ漁は先住民族の権利だとして、国と道を相手に漁業権を認めるよう札幌地裁に提訴しました。
訴状は、以下のURLにUPされているので、全文を読むことができます。
http://hiratatsuyoshi.com/KamuycepProject2020/archive/20200817raporoainunation_complaint.pd

訴状によると、ラポロアイヌネイションは、浦幌町内に居住・就業するアイヌで構成されているアイヌ集団であり、現在の構成員のほとんどは浦幌町を流れる浦幌十勝川の左岸沿いおよびその周辺に存在していた複数のコタン(アイヌ集団)の構成員の子孫であり、明治になるまで浦幌地域を支配領域(イオル)とし、サケをはじめとする自然資源を独占的・排他的に使用し、利用していました。このうちサケはアイヌにとって主要な食料であると共に、和人との交易品としても利用されており、重要な経済活動の資源でもありました。
明治6年に明治政府は現札幌市の主要な河川におけるサケの引き網漁を禁止し、明治11年に札幌郡におけるサケマス漁を一切禁止しました。その後、サケマス捕獲の禁止が全道に広がり、明治30年には、自家用としてのサケマスの捕獲も禁止しました。アイヌに関する唯一の例外は文化的伝承等のために北海道知事の許可を受けて一定数のサケの捕獲が認められているにすぎません。
しかし、明治以降の日本政府によるアイヌ諸集団のサケ漁を禁止する合法的理由は現在に至っても全く明らかになっておらず、かえって違法と考えられています。
『アイヌ政策史』(高倉新一郎著)によると、江戸時代におけるアイヌは「若しくは集団は共有の漁猟区を持っていて、団員はこれを自由に使用し得たが、団員以外の者が無断で闖入狩猟することは是を禁じ、若しも是を犯したがあれば贖罪が要求された」(P21)と記述されています。コタンが集団の漁猟区(イオル)を有し、その構成員のみが独占的・排他的に漁労を営んでいました。ところが、明治政府はアイヌ集団が有していた漁猟権を「一般人と同等」という同化政策のもと、和人による開発という目的のため、「為政者の都合」(高倉P406)によって完全に「無視」しました。
行政がまとめた最新の北海道史である『新北海道史』(昭46年北海道庁発行)にも「アイヌには、もしくは郡の共同利用に任され、その管理処分はを代表して酋長の手中にあった一定の漁猟区域があって、他の団体に対して排他的な権利を持っていた」(P886)と、行政として認めています。
以上から、アイヌはそれぞれの地域で一定の漁猟区域を有し、その土地や河川を独占的。排他的に利用していたことが明らかであり、それらが明治以降、和人への開拓地の提供のために「無視」されたまま、現在に至っていること、ゆえに、江戸時代に存在していた各地のアイヌの集団の漁猟権は法的には未だ存在していることを主張しています。
松浦武四郎が1856年に十勝の調査し、その内容を記した『武四郎廻浦日記』に、十勝川河口地域には100名を超えるアイヌが5つ以上のコタンで生活していたことを挙げます。さらに、諸資料によりアイヌは自らの食料としてサケを狩猟しただけではなく、交易品として用いていたことを挙げます。
そして古くからサケの網漁を行っていたと。その証拠は、かつて北海道帝国大学(北海道大学)の教授が1934年にこの地域のアイヌ 墓地からアイヌ遺骨65体と副葬品を発掘し持ち去った事件に対し、原告が返還請求を行い、返還された副葬品の中に漁網を修理する網針が含まれていたのです。他の文献証拠でも補強しています。
これらのことから原告ラポロアイヌネイションが十勝川河口地域でのサケ漁を行う権限を現在においても有していると主張し、さらに、サケ漁の権利を認めることにより、同地域のアイヌが経済的自立のために極めて重要だと加えます。より詳細な文献証拠を挙げつつ、結論として、原告ラポロアイヌネイションは浦幌十勝川河口から4キロメートルまでの範囲における、刺し網を使用したサケ捕獲権を有し、被告らはこの原告のサケ捕獲権を禁止し、制限することはできないと確認を求めています。
2017年、ラポロアイヌネイションのみなさんはアメリカにサケ漁を生業とする先住民族に会いに西海岸のオリンピック半島に出かけ、サーモンピープルと呼ばれるトライブの皆さんの豊かさに触れます(『アイヌの権利とは何か』(北大開示文書研究会編P125)。日本においても先住民族アイヌの権利としてのサケ狩猟権を勝ち取ろうと力強い一歩を踏み出しています。
訴訟の第1回期日は10月9日と決まりました。応援すると共に、今後も諸情報をお伝えして行きます。