さる2019年4月19日、参院本会議にて「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立し、それに関する各報道社で報じられたニュース26本を「アイヌ民族・世界の先住民族関連ニュースブログ」(こちら)にUPしました。全記事に記事元のURLを書いていますのですぐに確認できます。ロビー活動で奔走して下さった方達の努力もあり、10点の付帯決議が付されました。感謝です。実際の付帯決議を含めた法律をわたしはまだ未確認ゆえ、今回は各新聞社が賛否の声を紙面で紹介しているものをまとめました。羅列するだけにします。
菅官房長官「アイヌの人々が、とりわけ北海道の先住民族である、その認識を示したことは我が国における共生社会の実現に向けた大きな前進である」(STV4/19)
石井啓一国土交通相は19日の閣議後会見で「アイヌの人々が民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代に継承していくことは多様な価値観が共生し、活力ある共生社会を実現するために重要だ」と述べ、新法の意義を強調。(朝日4/19)
アイヌ協会加藤理事長は「泣いています。うれしくて。北海道旧土人保護法からアイヌ文化振興法、そして今の新法へと、抱えきれないような苦しみと悲しみの歴史があり、長い時間がかかった。いま先住民族と認めていただき、今日から出発できるということは、歴史の大きな一ページ。感謝しています」と話した。(朝日4/19)
アイヌ協会阿部一司副理事長(72)は「国が初めてアイヌのことを先住民族と認めて法律にしてくれた。(国に認められるよう訴えてきた)先輩たちに感謝したい」と話した。(道新4/20)
2020年4月にオープンするアイヌ文化の振興拠点「民族共生象徴空間」(白老町、愛称・ウポポイ)の地元、白老アイヌ協会の山丸和幸代表理事(70)は「アイヌの歴史や文化を伝え、若いアイヌが誇りを持てる拠点にしてほしい」と歓迎。新たに設けられる地域振興交付金は「アイヌだけでなく地域全体の生活が良くなる」と期待を込めた。(毎日4/20)
高橋はるみ知事は「アイヌの人たちの社会的、経済的地位の向上が図られ、民族としての誇りが尊重される社会の実現に向け、大きな一歩となる。法律制定はアイヌ政策を進める上で大きな力となる。道としては生活向上に加え、地域の活性化や産業・観光振興を含めた政策を総合的に推進しなければならない」と強調。交付金制度に関して「アイヌ文化振興が図られ、地域活性化にもつながることを期待する」とした。(道新4/20)
北海道大アイヌ・先住民研究センターの常本照樹センター長は「アイヌ文化振興・地位向上を実現し、地域も受益者とすることで新たな差別を生じさせなくしている。立法の趣旨を生かすため、関係自治体とアイヌとの緊密な連携が必要になる」としている。(毎日4/20)
「現状ではアイヌ個人の特定が難しく、アイヌ個人を対象とする政策を全国的に実施するのは難しい。(新法は)民族共生の理念に基づき、アイヌ民族が地域の人々と共に豊かになることを目指す日本型先住民族政策」と評価する。(毎日4/20)
札幌大の本田優子教授は、「アイヌ民族の経済的な自立につなげることが何より大切です。特に市町村が対象の交付金事業は、目先の利益や短期的な成果を目標とせず、例えばアイヌ民族が伝統的に活用してきた植物や木を育て加工品を商品化するなど、10年後や20年後を見据えたグランドデザインを明確にすべきです。
交付金を受ける市町村は、アイヌ民族や文化への理解を深めるとともに、アイヌ民族による専門的な役職や部署を設けるなど、当事者が主体となる仕組みを整えてほしい。
新しい挑戦に意欲的なアイヌ民族の若者も増えています。交付金の地域計画策定に携わる組織を各地のアイヌ協会につくるのも良いでしょう。アイヌ文化に関わる事業を自治体や企業に助言するアイヌ民族のコンサルティング会社など、事業を広く受注遂行するアイヌ民族の企業ができることも期待したい。
新法に足らざる点が多いのは事実です。ただ、アイヌ民族を先住民族と位置づけたことで国際的な先住民族政策のレベルを意識していくことになる。一足飛びに権利を保障することが難しいとしても、まずは新法が次世代のために有効に活用されることが大切です。(道新4/20)

二風谷民芸組合 貝沢守代表「いま本当に第一歩だと思う。文化を守っていく中にいくらかでも力を貸していただければという考えが多い」(STV4/19)
国会審議の中で、差別発言の事例として「アイヌなんていない」などが該当することが確認されたものの、差別にあたる言動の定義は曖昧な上、抑止策は決まっていないという課題が残されたようです。その報道のあとに、アイヌ民族に対するヘイトスピーチ(憎悪表現)への対策を求めてきた東京在住のアイヌ民族の新井かおりさんは「アイヌ民族への差別は法律違反だと明記されたことは大きな意味がある」と評価した上で、「抑止につながる実効策を進めてほしい」と求めたと。(道新4/20)
新法には土地や資源の回復など先住民の権利は明記されていない。伝統的儀式のための自由なサケ漁を求めてきた紋別アイヌ協会の畠山敏会長(77)は「アイヌから奪った権利に踏み込んでおらず現状と変わっていない」と批判。 (毎日4/20)
1997年のアイヌ文化振興法はアイヌ民族が長年求めていた生活、教育支援が盛り込まれなかったものの、アイヌ文化に関わる個人や団体を助成し、伝承活動を後押ししてきたことに対し、萱野志朗さん「十分ではなかったが、草の根の活動は根づきつつある」と。その振興法が内容を新法に包含したとして廃止となることを受け、民族共生象徴空間(ウポポイ)開設やアイヌ文化を活用した地域・産業振興に取り組む自治体への交付金も新設したが、そこに多くの人や予算が割かれると「これまでの地道な活動への支援がおろそかにならないか」と懸念を表明。
萱野公裕さん(志朗さんのご子息)は新法について「文化振興に地域、産業振興が加わったことで、苗木の幹は確かに太くなったと思う」と述べつつ、一方で「踊りや工芸など単にアイヌ文化を観光に利用するという発想ではなく、人(アイヌ民族)が主体的に関わることが欠かせない」と強調。(道新4/20)
アイヌ民族が長年求めてきた先住権や生活、教育支援が盛り込まれなかったことへの落胆の声として、日高管内平取町の「平取アイヌ遺骨を考える会」の木村二三夫共同代表(70)はかつての同化政策から大学進学率などに格差が残る現状を踏まえ、「新法では不十分。差別をなくすためにも、スタートラインの差がなくなる施策を進めてほしい」と訴えた。(道新4/20)
「奪った権利を回復する。当たり前のことに理解が得られるようにするのは、国の責任と義務ではないのか」と憤る。(毎日4/20)
目的はあくまで文化や経済、観光の振興。それに反対するアイヌ民族の団体「コタンの会」代表の清水裕二さん(78)は「生身のアイヌを観光の飾り物にすることは賛成できない。学校でアイヌの歴史や文化をきちんと教え、生活支援を考えてほしい」と訴える。(朝日4/19)
「こんな状態で『法案ができました』と言われて『はい分かりました』なんて(言えない)。悲しいという気持ちしかない」(HTB 4/19)
紋別アイヌ協会の畠山敏会長は、「先住民族であるアイヌの土地や資源に対する権利を保障しておらず、国際的な基準を満たしていない。過去にアイヌは住んでいた土地を追いやられて、過酷な労働を強いられた。国はそうした歴史を調べて国民が理解できるよう説明すべきだ」と国の対応を批判(NHK4/19)
日本共産党の紙智子議員は18日の参院国土交通委員会で、アイヌ新法案について、アイヌ民族への謝罪もなく議論が進んだと指摘し、「先住民族の権利に関する国連宣言」が認める諸権利を盛り込むよう求めた。(赤旗4/19)

 判決後の報告会(ディヴァン・スクルマンスタッフ撮影)
判決後の報告会(ディヴァン・スクルマンスタッフ撮影)




















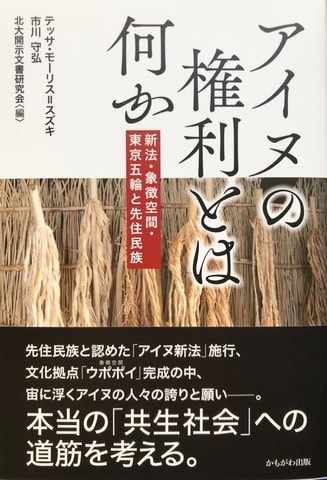

 釧路にある「松浦武四郎蝦夷地探検像」とても小さいものでした。
釧路にある「松浦武四郎蝦夷地探検像」とても小さいものでした。

 旭岡墓地での川村さんの解説
旭岡墓地での川村さんの解説 知里幸恵文学記念碑前で川村さんの解説
知里幸恵文学記念碑前で川村さんの解説
 最近、家のまわりに頻繁に現れて畑を荒らしてはみんなに怒られる鹿ちゃん。鹿ゆえにしかたがない? わたしはとても可愛いと思っています。
最近、家のまわりに頻繁に現れて畑を荒らしてはみんなに怒られる鹿ちゃん。鹿ゆえにしかたがない? わたしはとても可愛いと思っています。


 留萌の浜で釣れたヒメマス(釣人に写真を撮らせて頂いた)
留萌の浜で釣れたヒメマス(釣人に写真を撮らせて頂いた)