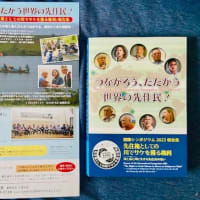国際捕鯨委員会(IWC)は商業捕鯨と科学調査捕鯨部門の他に、先住民生存捕鯨と呼ばれる第3の部門の捕鯨を管轄管理していることが分かりました。
先住民生存捕鯨の定義(1981年)
先住民生存捕鯨とは地方的原住民の消費のため、先住の人々による、彼らのためのもので、彼らは捕鯨及び鯨の利用に、引き続き伝統的に依存しているという点で、強い社会、家族、及び文化的な団結をもって結ばれているもの。
地方的消費とは原住民の栄養、生存、文化的必要性を満たすため彼らが鯨肉産物を伝統的に利用すること。この用語には生存のための捕獲から得られる副産物の交易も含まれる。
生存のための捕獲とは先住民生存捕鯨操業による鯨の捕獲である。
原住民生存捕鯨と商業捕鯨の区別などについても常に議論が分かれているようです。
アイヌ民族は一方的に漁業権を剥奪され、伝統的な捕鯨も断たれた長い時間があります。「引き続き伝統的に依存している」という部分、捕鯨を禁じられて集団の結びつきも破壊されたために「団結をもって結ばれている」というところも問題になります。
アメリカのシアトル近郊のマカー族が70年間の中断の後コククジラの狩猟捕獲枠を要求した際に、「いかなる“継続的にして伝統的依存性”も持っていない」と批判されたことも書かれています。奪われた歴史をどう考えるかですね。
捕獲限度は一人当たりの推定消費量からその地域人口の必要量を計算して決められていて(グリーンランドは、低めに設定)、これも逆に人種差別だ、という批判もあるとか。
グリーンランド漁業・狩猟協会(KNAPK)会長リーフ・フォンテインの言葉
「我々から産物を商業的に捕獲し交易する権利を奪うことは、我々を博物館のケースに閉じ込めることと同じだ。我々は21世紀に生きている民族で、大英博物館からの陳列物ではない。(・・・)商業は持続的開発の概念の一部であり、それに参加することは我々の権利である。先住民捕鯨者を非商業捕鯨体制に限定することは新植民地主義の何物でもない。」(インターナショナル・ハープーン、The International Harpoon, №3、2000、「商業的である権利」)
ハイ・ノース・アイランスURL参照:http://www.kujira.no/iwc_2003_aboriginal.htm
国際捕鯨委員会(IWC)のニュースが毎日新聞でも取り上げられました。(2月24日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100224ddm008030139000c.html
これらの議長提案がどう影響するのでしょうか。
山田洋次監督の映画「母べえ」を観ました。
吉永小百合が母親(母べえ)。千田未来が長女、佐藤未来が妹、坂東三津五郎が父親役で出演。戦時中に治安維持法で思想犯として父親が捕らえられ、大変厳しい獄中生活を強いられます。非衛生的で人間扱いされず、皮膚病で大変な状態が映し出されていました。こども達の演技が上手で涙をさそいます。獄中の皮膚病といえば、三木清を思い浮かべます。共産主義者をかくまった理由で治安維持法により投獄され、敗戦後も忘れ去られて9月26日に獄死。彼の死因は腎臓も病んでいましたが、疥癬といわれています。わたしの卒業した神学校での哲学の時間に講師の池明観さんが「戦時中の日本の最大の哲学者が忘れ去られ敗戦後に獄中死したとはたいへんな恥だ」と言われていたのを思い出します。池さんは当時韓国から亡命中だったはず。熱のこもった「哲学」「宗教哲学」の講義でした。
鶴べえも伯父役でいい味出していました。「おとうと」も楽しみですね。
急用が入り、26日からの紋別行きを断念しました。講演もワークショップも楽しみにしていたのですが。ディヴァンさんにも流氷を見せたかったし。報告を楽しみにしています。

留萌でもでらでらした海がみられました。
先住民生存捕鯨の定義(1981年)
先住民生存捕鯨とは地方的原住民の消費のため、先住の人々による、彼らのためのもので、彼らは捕鯨及び鯨の利用に、引き続き伝統的に依存しているという点で、強い社会、家族、及び文化的な団結をもって結ばれているもの。
地方的消費とは原住民の栄養、生存、文化的必要性を満たすため彼らが鯨肉産物を伝統的に利用すること。この用語には生存のための捕獲から得られる副産物の交易も含まれる。
生存のための捕獲とは先住民生存捕鯨操業による鯨の捕獲である。
原住民生存捕鯨と商業捕鯨の区別などについても常に議論が分かれているようです。
アイヌ民族は一方的に漁業権を剥奪され、伝統的な捕鯨も断たれた長い時間があります。「引き続き伝統的に依存している」という部分、捕鯨を禁じられて集団の結びつきも破壊されたために「団結をもって結ばれている」というところも問題になります。
アメリカのシアトル近郊のマカー族が70年間の中断の後コククジラの狩猟捕獲枠を要求した際に、「いかなる“継続的にして伝統的依存性”も持っていない」と批判されたことも書かれています。奪われた歴史をどう考えるかですね。
捕獲限度は一人当たりの推定消費量からその地域人口の必要量を計算して決められていて(グリーンランドは、低めに設定)、これも逆に人種差別だ、という批判もあるとか。
グリーンランド漁業・狩猟協会(KNAPK)会長リーフ・フォンテインの言葉
「我々から産物を商業的に捕獲し交易する権利を奪うことは、我々を博物館のケースに閉じ込めることと同じだ。我々は21世紀に生きている民族で、大英博物館からの陳列物ではない。(・・・)商業は持続的開発の概念の一部であり、それに参加することは我々の権利である。先住民捕鯨者を非商業捕鯨体制に限定することは新植民地主義の何物でもない。」(インターナショナル・ハープーン、The International Harpoon, №3、2000、「商業的である権利」)
ハイ・ノース・アイランスURL参照:http://www.kujira.no/iwc_2003_aboriginal.htm
国際捕鯨委員会(IWC)のニュースが毎日新聞でも取り上げられました。(2月24日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100224ddm008030139000c.html
これらの議長提案がどう影響するのでしょうか。
山田洋次監督の映画「母べえ」を観ました。
吉永小百合が母親(母べえ)。千田未来が長女、佐藤未来が妹、坂東三津五郎が父親役で出演。戦時中に治安維持法で思想犯として父親が捕らえられ、大変厳しい獄中生活を強いられます。非衛生的で人間扱いされず、皮膚病で大変な状態が映し出されていました。こども達の演技が上手で涙をさそいます。獄中の皮膚病といえば、三木清を思い浮かべます。共産主義者をかくまった理由で治安維持法により投獄され、敗戦後も忘れ去られて9月26日に獄死。彼の死因は腎臓も病んでいましたが、疥癬といわれています。わたしの卒業した神学校での哲学の時間に講師の池明観さんが「戦時中の日本の最大の哲学者が忘れ去られ敗戦後に獄中死したとはたいへんな恥だ」と言われていたのを思い出します。池さんは当時韓国から亡命中だったはず。熱のこもった「哲学」「宗教哲学」の講義でした。
鶴べえも伯父役でいい味出していました。「おとうと」も楽しみですね。
急用が入り、26日からの紋別行きを断念しました。講演もワークショップも楽しみにしていたのですが。ディヴァンさんにも流氷を見せたかったし。報告を楽しみにしています。

留萌でもでらでらした海がみられました。