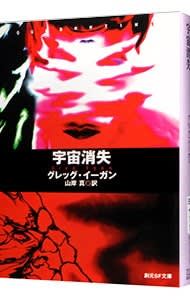
久々に本格的なSF小説を読んだ。
私が十代の頃は、空想科学小説と揶揄されて文壇では低く見られていた。いや一般的にも子供だましの娯楽小説だと蔑まれてきた。
そんな風潮を私は嫌悪した。戦争の悲惨さをめそめそと嘆き平和の大切さを訴える小説や、男女の出会いと別れをうじうじと書き綴る小説ばかりを純文学だと持ち上げる大人たちに反発した。
私にはSF小説こそ未来のフロンティアだと思えてならなかった。もちろんスペースオペラと称する娯楽小説もあまたあった。しかしACクラークやアシモフ、ハイラインのように人間の未来の可能性を高らかに謳い上げる本格的なSF小説は格別の存在であった。
しかし、残念なことにSF小説は、映像の力を借りてようやく世間から認知された。そのきっかけとなったのは「未知との遭遇」であり「ET」であった。もちろん「2001年宇宙の旅」や「機械仕掛けのオレンジ」などもあったが、いずれもアメリカで産まれた。アメリカこそが20世紀を代表する文化の具現者であったと私は高く評価している。
だが金を生むのは娯楽小説だ。「バックトゥザフューチャー」や「スターウォーズ」「ジェラシックパーク」などの映画は、あまりに面白くSFを特殊なものから普通のものへといとも簡単に広げてしまった。
この状況を悔しいと思ったSF小説家はいたはずだ。声には出さねどRニーブンやJパーネルらは映像化が難しいと思えるような作品を出して、更なるSF小説の可能性を広げた。その一つの頂点と評してもおかしくないのが、表題の作品の著者であるグレック・イーガンだと思う。
量子物理学をベースに未来社会を描写してみせた。脳に直接ソフトをダウンロードしたり、脳内に極小のチップを埋め込み、自分の性格、性向、精神安定性さえもコントロールする未来の地球人の姿は、まさにSF的。
でも、隠れたSF漫画の先進国である日本でも既にそのアイディアは使われていたぞと内心思いながらも、イーガンの描き出す未来社会に没頭した。ただ、読み込むのにはかなりの集中力が必要であり、ここのところ過労気味の私には辛かったのも確かでした。
5年前と比べても読書に対する集中力が低下している現実がよく分かりました。これは暑さ以上に精神的に堪えました。あぁ、早く涼しくなって欲しいです。


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます