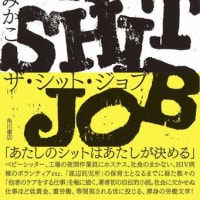佐藤賢一『ドゥ・ゴール』(角川選書、2019年)
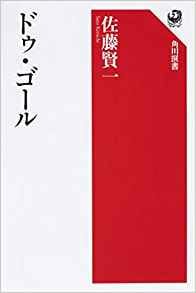 パリ北部の国際空港にも名前がついているシャルル・ド・ゴールについての評伝である。
パリ北部の国際空港にも名前がついているシャルル・ド・ゴールについての評伝である。
見開きに、ロンドンのBBCからフランス国民に向けてラジオ演説でレジスタンスを呼びかける有名な写真のしたにパリ凱旋をするド・ゴールの写真があるが、2メートル近い背丈は異様に目立っている。
これを見ながら、戦時中はあちこち指揮のために出かけていたというが、まっすぐ体を伸ばして寝ることができるベッドがあったのだろうかと、どうでもいい心配をしてしまった。(写真はウィキペディアから借用)

フランスは徹底した自主独立の国である。というか自主独立を国是としていると言ってもいい。そのために、核武装もするし、NATO軍からも撤退する。
そういった軍事的なことだけではなく、食料も自給率100%を超えるほど農業も自国産を大事にするし、買っておけばい何年でも保存がきくウランを大量に購入しておいて、原子力発電所をたくさん作って、エネルギー100%を自国で確保する。
食料もエネルギーも、おまけに政治そのものも、アメリカや中国に従属しているどこかの国とはおおちがい。
そういった国是を確立して、実際に政治の世界で実行したのが、シャルル・ド・ゴールだったということがこの評伝ではよく分かる。
かつてフランスではアメリカ嫌いと言われるような現象があった。英語を話せるのに、わざと知らないふりをする。観光客が英語で話しかけても答えない、みたいな。アラン・ドロンが英語をけっして学ぼうとしなかったのもそうした風潮に応えていたというような話を聞いたことがある。
それもNATOからの自立、どんな国際情勢にあっても、自国の自主独立の立場から発言するというド・ゴールの姿を国民が応援したからだろう。(フランス人はけっしてアメリカが嫌いというわけじゃない。)
最後に、佐藤賢一のこの評伝。文章としてはおそらく私が読んだ彼の作品の中で一番出来が悪いと思う。とにかく細かすぎて読むのがしんどい。固有名詞が多すぎるのだ。国際情勢や国内情勢をわかりやすく提示するような手法を取らないで、記録集みたいな書き方をしたからだ。なんか原典をただ翻訳しただけみたいにも見えないこともない。
ただ、最近テレビでNHKの映像の世紀を見ていたら、ちょうど戦中戦後のところだったが、フランスが、ド・ゴールがまったく出てこなかったので、フランスも、ド・ゴールもナチス・ドイツとの闘いをやっていたのだということがこの本でよくわかった。これまで私は戦中にド・ゴールはイギリスで安穏を暮らしているだけだと勘違いしていたので。
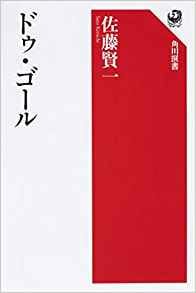 パリ北部の国際空港にも名前がついているシャルル・ド・ゴールについての評伝である。
パリ北部の国際空港にも名前がついているシャルル・ド・ゴールについての評伝である。見開きに、ロンドンのBBCからフランス国民に向けてラジオ演説でレジスタンスを呼びかける有名な写真のしたにパリ凱旋をするド・ゴールの写真があるが、2メートル近い背丈は異様に目立っている。
これを見ながら、戦時中はあちこち指揮のために出かけていたというが、まっすぐ体を伸ばして寝ることができるベッドがあったのだろうかと、どうでもいい心配をしてしまった。(写真はウィキペディアから借用)

フランスは徹底した自主独立の国である。というか自主独立を国是としていると言ってもいい。そのために、核武装もするし、NATO軍からも撤退する。
そういった軍事的なことだけではなく、食料も自給率100%を超えるほど農業も自国産を大事にするし、買っておけばい何年でも保存がきくウランを大量に購入しておいて、原子力発電所をたくさん作って、エネルギー100%を自国で確保する。
食料もエネルギーも、おまけに政治そのものも、アメリカや中国に従属しているどこかの国とはおおちがい。
そういった国是を確立して、実際に政治の世界で実行したのが、シャルル・ド・ゴールだったということがこの評伝ではよく分かる。
かつてフランスではアメリカ嫌いと言われるような現象があった。英語を話せるのに、わざと知らないふりをする。観光客が英語で話しかけても答えない、みたいな。アラン・ドロンが英語をけっして学ぼうとしなかったのもそうした風潮に応えていたというような話を聞いたことがある。
それもNATOからの自立、どんな国際情勢にあっても、自国の自主独立の立場から発言するというド・ゴールの姿を国民が応援したからだろう。(フランス人はけっしてアメリカが嫌いというわけじゃない。)
最後に、佐藤賢一のこの評伝。文章としてはおそらく私が読んだ彼の作品の中で一番出来が悪いと思う。とにかく細かすぎて読むのがしんどい。固有名詞が多すぎるのだ。国際情勢や国内情勢をわかりやすく提示するような手法を取らないで、記録集みたいな書き方をしたからだ。なんか原典をただ翻訳しただけみたいにも見えないこともない。
ただ、最近テレビでNHKの映像の世紀を見ていたら、ちょうど戦中戦後のところだったが、フランスが、ド・ゴールがまったく出てこなかったので、フランスも、ド・ゴールもナチス・ドイツとの闘いをやっていたのだということがこの本でよくわかった。これまで私は戦中にド・ゴールはイギリスで安穏を暮らしているだけだと勘違いしていたので。