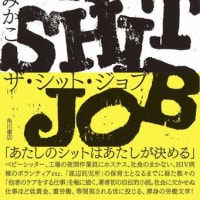橋本治『橋本治が大辞林を使う』(三省堂、2001年)
『桃尻娘』の作家ということくらいしか、私は知らなかったが、「ことば」について書かれたものに最近関心があるので、ぱらぱらとめくってみたら面白そうなことを書いているので、借りてみたのだが、案の定面白かった。何が面白かったかといって、この人が自分というものを若い頃からよく分かっていて、かつそのような自分をすごく好きだった人だということ。だからこの人は劣等感というものがないというわけ。自分のしたいことだけをしてきたし、自分がしたくてしなければならないことには一生懸命になって、到達目標達成のために集中するが、したくないことは他人ができようができまいがどうでもいいと考えるような人だから。
この人が漢字を覚えるようになった経験を書いているところがあるのだけど、それもすごく面白い。ラジオ全盛の時代で、いつも耳から入ってくるので覚えてしまった番組の決り文句(たとえば連続放送劇『笛吹童子』のオープニング)の音が、何気なく見ていた新聞の番組表にある笛吹童子という四文字漢字がそれではないかと思ったり、そのラジオドラマが映画化されて街中に張り出されたポスターにいつも耳にして覚えた作者の名前とか音楽家の名前らしきものを見つけてこの漢字があれというふうにして漢字を理解し、覚えていったというのですからね。相当に理屈っぽい子だったのだろうね。
この本はなぜ橋本治という作家が大辞林を使うのかということをテーマの一つにしているのだけれども、そんなことよりも、じつに面白い、ためになる話が満載といって言い。
モノローグとダイアローグもそうだ。独り言としてのモノローグの言葉と、外との関係を作るダイアローグの言葉があるなんてのは、当たり前じゃと思うのだが、現実のなかでは、その区別がきちんとついているのかと問われると、確信がない。分かっているようで分かっていないのではないか。それを教えてくれたのが、ある雑誌の企画で30人くらいの若者たちを集めたセミナーのフリートークで、一人の男の意見が周囲の反感を買ってしまい、彼一人が孤立したという話です。橋本によれば、そういうことになったのはこの若者の言葉が自覚のないモノローグだったからで、橋本がそのことを教えてやらなければ、彼はそのことがずっと分からないままであっただろうし、なぜ自分の言ったことが人の反感を買うのかも分からずにいただろうということで、しかも「そうなんだ」というモノローグの言葉から「そうなんですね」というダイアローグの言葉に置き換えることは、頭の問題ではなく、そのような音を口に出すという身体の問題であると、橋本が指摘しているのも、目からウロコのようにびっくり。
彼はそこからさらに敬語とは、尊敬語ではなく、現代においては、他者との距離あらわすものだと指摘している。身分の上下とか社会的地位だというものは、ある意味、現代においては意味をなさないものであるけれども、それでも人との距離は必要で、それを表すのが敬語だという橋本の説明は、なるほどと思わせる説得力をもっている。
『桃尻娘』とか『窯変源氏物語』とか読んでみようと思っている。
『桃尻娘』の作家ということくらいしか、私は知らなかったが、「ことば」について書かれたものに最近関心があるので、ぱらぱらとめくってみたら面白そうなことを書いているので、借りてみたのだが、案の定面白かった。何が面白かったかといって、この人が自分というものを若い頃からよく分かっていて、かつそのような自分をすごく好きだった人だということ。だからこの人は劣等感というものがないというわけ。自分のしたいことだけをしてきたし、自分がしたくてしなければならないことには一生懸命になって、到達目標達成のために集中するが、したくないことは他人ができようができまいがどうでもいいと考えるような人だから。
この人が漢字を覚えるようになった経験を書いているところがあるのだけど、それもすごく面白い。ラジオ全盛の時代で、いつも耳から入ってくるので覚えてしまった番組の決り文句(たとえば連続放送劇『笛吹童子』のオープニング)の音が、何気なく見ていた新聞の番組表にある笛吹童子という四文字漢字がそれではないかと思ったり、そのラジオドラマが映画化されて街中に張り出されたポスターにいつも耳にして覚えた作者の名前とか音楽家の名前らしきものを見つけてこの漢字があれというふうにして漢字を理解し、覚えていったというのですからね。相当に理屈っぽい子だったのだろうね。
この本はなぜ橋本治という作家が大辞林を使うのかということをテーマの一つにしているのだけれども、そんなことよりも、じつに面白い、ためになる話が満載といって言い。
モノローグとダイアローグもそうだ。独り言としてのモノローグの言葉と、外との関係を作るダイアローグの言葉があるなんてのは、当たり前じゃと思うのだが、現実のなかでは、その区別がきちんとついているのかと問われると、確信がない。分かっているようで分かっていないのではないか。それを教えてくれたのが、ある雑誌の企画で30人くらいの若者たちを集めたセミナーのフリートークで、一人の男の意見が周囲の反感を買ってしまい、彼一人が孤立したという話です。橋本によれば、そういうことになったのはこの若者の言葉が自覚のないモノローグだったからで、橋本がそのことを教えてやらなければ、彼はそのことがずっと分からないままであっただろうし、なぜ自分の言ったことが人の反感を買うのかも分からずにいただろうということで、しかも「そうなんだ」というモノローグの言葉から「そうなんですね」というダイアローグの言葉に置き換えることは、頭の問題ではなく、そのような音を口に出すという身体の問題であると、橋本が指摘しているのも、目からウロコのようにびっくり。
彼はそこからさらに敬語とは、尊敬語ではなく、現代においては、他者との距離あらわすものだと指摘している。身分の上下とか社会的地位だというものは、ある意味、現代においては意味をなさないものであるけれども、それでも人との距離は必要で、それを表すのが敬語だという橋本の説明は、なるほどと思わせる説得力をもっている。
『桃尻娘』とか『窯変源氏物語』とか読んでみようと思っている。