アレクサンドル・デュマ『三銃士』(岩波文庫)
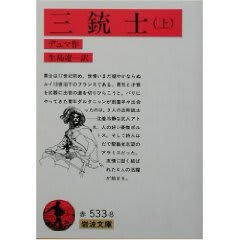 佐藤賢一の『褐色の文豪』を読んだことで、またデュマにたいする興味がわいて『三銃士』を読んでみた。以前読んだのは子どもの頃に子ども向けにリライトしたものだったので、原作を翻訳したものはこれが初めて。もっと波乱万丈の出来事が次から次へとでて来るのかと思ったら、意外にそうでもなかった。
佐藤賢一の『褐色の文豪』を読んだことで、またデュマにたいする興味がわいて『三銃士』を読んでみた。以前読んだのは子どもの頃に子ども向けにリライトしたものだったので、原作を翻訳したものはこれが初めて。もっと波乱万丈の出来事が次から次へとでて来るのかと思ったら、意外にそうでもなかった。
文庫本の上巻にあたる前半部は、まずダルタニャンと三銃士の出会いという形でこれらの主人公たちを紹介する部分があって、それがルイ13世の宮廷内でのルイ13世とトレヴィル殿にたいする枢機卿リシュリューの対立として描かれているのは興味深かった。
前半のメインは、王妃アンヌとイギリスのバッキンガム公との恋愛がらみの出来事だ。王妃アンヌにほれ込んでしまったバッキンガム公がやっとの思いで王妃と会うことができたとき、王妃が記念にダイヤモンドが12個もついた飾り紐をバッキンガム公に贈るのだが、それはルイ13世が王妃のために贈ったもので、それを知った枢機卿リシュリューがパーティーを開催して王妃にその飾り紐をつけて参加するように王から提案させる。困った王妃は侍女のモナシュー夫人に相談すると彼女がダルタニャンにバッキンガム公から返してもらってくるように働きかける。ロンドンまで行くダルタニャンと三銃士とそれを阻止せんとする枢機卿側の策謀ははらはらどきどきがなくもないではなかった。
1844年に『三銃士』は書かれ、新聞に連載された。まったく無名の男が王位を簒奪したナポレオンの帝政期をへて、大地主の利益に依拠した王政復古期、そして1830年の7月革命によってルイ・フィリップによる立憲王政期にあった。これらの時代は、いわばまったく無権利だったブルジョワジーが経済力をつけ、王政をフランス革命によって倒したが、そのまま自分たちの権力へは直結せず、そのあらぶるエネルギーを暴力的に発散していた時代であるといっていい。そういった秩序とか安定などをぶち壊してまで、自分の信ずるところを猪突猛進する人間形象が、『三銃士』のダルタニャンであり、三銃士たちであるといえるのではないだろうか。
ルイ14世統治下のがっちりと秩序と序列が決まった、息の詰まるような時代になる前の、まだおおらかな時代というのは実際そうだったのだろう。しかしだんだんと真綿で首を絞められるように、あれはするなこれは礼儀に反すると秩序という名によって自由な行動が狭められていくのを感じながら、大暴れするダルタニャンに、せっかく革命を起こして王政を転覆して自分たちの時代が来たと思っていたのに、思うに任せない新興ブルジョワジーのエネルギーの発露を描いたものであったればこそ、19世紀の前半にデュマの小説がたいへんな人気を博したのだろうと思う。
こう考えれば、デュマ自身があまりルイ13世統治下のフランスのことを熟知していたわけではなかったこともあり、この時代のことがそれほど綿密に描かれていない理由もうなずけるのだが、もう少しこの時代のことを知りたかった私としては不満が残った。
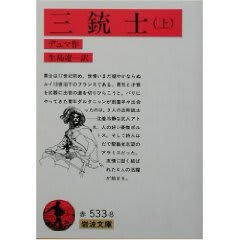 佐藤賢一の『褐色の文豪』を読んだことで、またデュマにたいする興味がわいて『三銃士』を読んでみた。以前読んだのは子どもの頃に子ども向けにリライトしたものだったので、原作を翻訳したものはこれが初めて。もっと波乱万丈の出来事が次から次へとでて来るのかと思ったら、意外にそうでもなかった。
佐藤賢一の『褐色の文豪』を読んだことで、またデュマにたいする興味がわいて『三銃士』を読んでみた。以前読んだのは子どもの頃に子ども向けにリライトしたものだったので、原作を翻訳したものはこれが初めて。もっと波乱万丈の出来事が次から次へとでて来るのかと思ったら、意外にそうでもなかった。文庫本の上巻にあたる前半部は、まずダルタニャンと三銃士の出会いという形でこれらの主人公たちを紹介する部分があって、それがルイ13世の宮廷内でのルイ13世とトレヴィル殿にたいする枢機卿リシュリューの対立として描かれているのは興味深かった。
前半のメインは、王妃アンヌとイギリスのバッキンガム公との恋愛がらみの出来事だ。王妃アンヌにほれ込んでしまったバッキンガム公がやっとの思いで王妃と会うことができたとき、王妃が記念にダイヤモンドが12個もついた飾り紐をバッキンガム公に贈るのだが、それはルイ13世が王妃のために贈ったもので、それを知った枢機卿リシュリューがパーティーを開催して王妃にその飾り紐をつけて参加するように王から提案させる。困った王妃は侍女のモナシュー夫人に相談すると彼女がダルタニャンにバッキンガム公から返してもらってくるように働きかける。ロンドンまで行くダルタニャンと三銃士とそれを阻止せんとする枢機卿側の策謀ははらはらどきどきがなくもないではなかった。
1844年に『三銃士』は書かれ、新聞に連載された。まったく無名の男が王位を簒奪したナポレオンの帝政期をへて、大地主の利益に依拠した王政復古期、そして1830年の7月革命によってルイ・フィリップによる立憲王政期にあった。これらの時代は、いわばまったく無権利だったブルジョワジーが経済力をつけ、王政をフランス革命によって倒したが、そのまま自分たちの権力へは直結せず、そのあらぶるエネルギーを暴力的に発散していた時代であるといっていい。そういった秩序とか安定などをぶち壊してまで、自分の信ずるところを猪突猛進する人間形象が、『三銃士』のダルタニャンであり、三銃士たちであるといえるのではないだろうか。
ルイ14世統治下のがっちりと秩序と序列が決まった、息の詰まるような時代になる前の、まだおおらかな時代というのは実際そうだったのだろう。しかしだんだんと真綿で首を絞められるように、あれはするなこれは礼儀に反すると秩序という名によって自由な行動が狭められていくのを感じながら、大暴れするダルタニャンに、せっかく革命を起こして王政を転覆して自分たちの時代が来たと思っていたのに、思うに任せない新興ブルジョワジーのエネルギーの発露を描いたものであったればこそ、19世紀の前半にデュマの小説がたいへんな人気を博したのだろうと思う。
こう考えれば、デュマ自身があまりルイ13世統治下のフランスのことを熟知していたわけではなかったこともあり、この時代のことがそれほど綿密に描かれていない理由もうなずけるのだが、もう少しこの時代のことを知りたかった私としては不満が残った。














