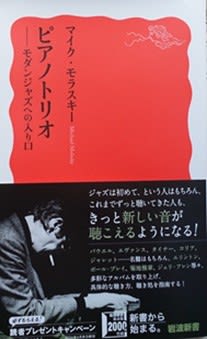

新聞で広告をみて買ってみました。
タイトルが「ピアノ・トリオ」、結構長い間ピアノ・トリオを聞いてきたのでどのように書いているのでしょうか。
まず、著者がどのような方かで、スタートがきまります、今回の著者マイク・モラスキー氏は知らない。結構なお年のようだが、早稲田大学の教授で日本文学、文化、ジャズ史、飲食史などの研究をされて、自身ピアノでクラブで演奏されていた方とうことだ。
日本での、ジャズ・ピアノ・アルバムの特異的な聞かれ方をどう表現されているかが興味あることだ。
さて本文を読む前に目次で構成をよむと、第1章が”ピアノ・トリオの聴き方”、2章が”初期のピアノ・トリオ”34章が”名盤を聞き直す”で5章が1970年以降のピアノ・トリオ”となっている。
ということで、ピアノ・トリオの流れを網羅した著書だと思う。
もちろん、文句を言おうと思って読むわけではなく、新し発見を楽しみにしながら、疑問があったら、その問題を提起したいというのが趣旨になる。
著書の内容は1950年ー60年の演奏が中心で、残された演奏の展開のなども具体的に提示すると書いてある。
さて読み始めたのだけれど、これがこちらには頭にはいってこない。ピアニストのそれぞれの特出したテクニックの解説をおこなっていくわけで、ピアニストのアルバムの曲を考察していく。
アルバムを並べると。エロル・ガーナー「コンサート・バイ・ザ・シー」、アーマッド・ジャマル「アット・ザ・パージング」、レッド・ガーランド「グルーヴィー」、ハンプトン・ホーズ「ハンプトン・ホーズ・トリオVol.1」など現代までの28アイテムぐらいになる。
それらのピアニストはある意味、ピアノ・技術の流れに確信を作っていった人たちで(それは間違いない)そこの健闘ということになる。
ということでないようからいうと、これまでにない力作となるであろう。とはいっても何とも頭にはいらない。
そこら辺の残念なところを記してまず最初に残念なのが、それこそ2数種のアルバムの演奏をかいせつしているのだが、アルバム名は書かれているが、ジャケットのヴィジュアル表示がない。私たちはジャケットの表情でアルバムを認識しているところが、あり、もちろん大体わかるものの、実は感覚として演奏には近づけない。ここら辺は編集者の不備としか思えない。
もちろん書かれてる中で持っているアルバムは多いけれど、聴きながらでないと、解らないような、これがテクニックの表現としてしょうないと言ってしまうかということがある。
たとえば記載されたアルバムオスカー・ピーターソンの「ナイト・トレイン」の記載を見てみよう。(こちらはアルバムを聴きながらの確認をする)
ちょっと長くなってしまうけれど、この本を知っていただくためにもあえて部分を引用させていただく。
「本盤ではは、『 Cジャム・ブルース』で確認してみよう。メロディが終わり、即興演奏に入るときはトリオはブレイクをいれるが、その瞬間にベースとドラムスがピタッと演奏を止め、ピーターソンがひとりでーしかも、右手の単音ラインのみでー弾き始めるのに、それっまでん三人が作り上げた前進力が一切止まることなく、まぎれもなくスイングしている。その後も数回同じ手法を繰り返すが、当然ながら毎回、即興ラインの内容が変わる。(0:52-0:56.1:08-1:12,1:25-1:29)。また、まるでビック・サウンドの金管楽器のセクションからソロイストが短いフレーズを好感して演奏するときと同様に、ピーターソンが大きなブロックコードといぎてのラインを交互に弾き、さらに演奏に熱が増すとがある。(2;05-32;30)。このように、p-ターソンのサウンドはメリハリのみならず、ドシドシ前進するドライヴ感をもってビック
バンドを彷彿させる。
ということで演奏の分析をされているけれど、(その内容は適格だとおもう)時計をみながらアルバムを再度聴くのはおっくになるので、すべてを確信するのは難しい。
試みとして、きれまでにないことではあるが、結構頭に入りずらい内容だと思った。
ジャズ・ピアニストになろうと思う人であれば、もちろんこれくらいの研究は当然であろうが、ぼけっと聞くこちらとしては、ちょっと大変な本だった。
最終章、「近年の『ジャズ神童』について」でエルダー・ジャンギロフとジョーイ・アレキサンダーを選択しているところなど、著者の耳は確かなジャズ耳だとおもうので、この本はある人にとってはとても凄い本だと思う。















