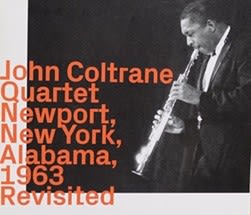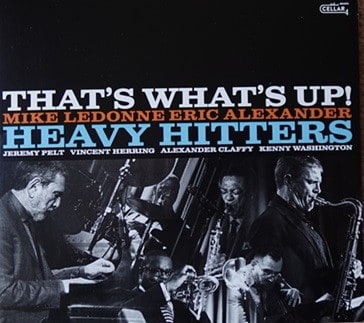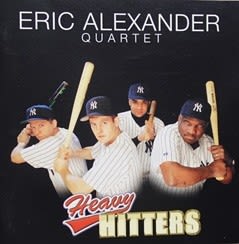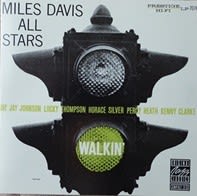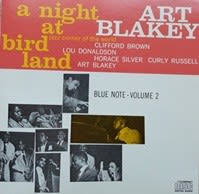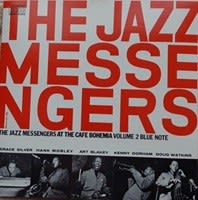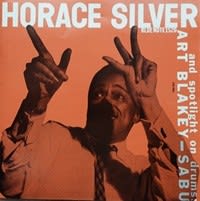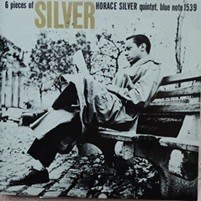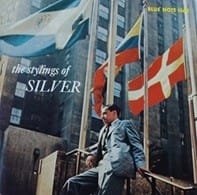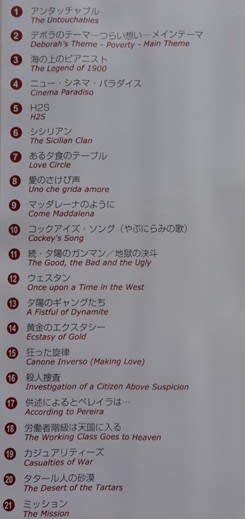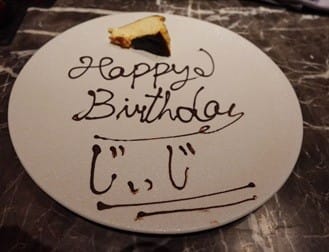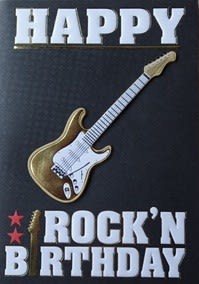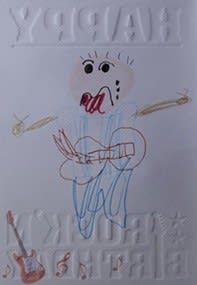サブスクで聞いたヴァイオリニストが凄い。年はというと10代だという。こんな音は10代で出せるわけがないと思う。
それで調べたら現在23歳になっているようだけれど、それでも凄い。
新しいアルバムが出たので買ってみた。メインがパガニーニの曲集なのだけれど、これが凄い。
「24のカプリース」というヴァイオリンのソロ曲で難曲、これまさにヴァイオリン・テクの集成。
そして驚くべき音圧を駆使して、しっかりと音を伝える。
こんな強いバイオリニストがいるのかと驚いている。
昨年日本にも来ているし、買ったアルバムの帯には、ヴァイオリンの女王などとうたっているので、人気を集めているのだろう。
まあヴァイオリンのアルバムは多くは持っていないけど。これは聴いておかなければいけない演奏だと思う。
彼女の紹介はネットにあったので引用しておこう。
若手ヴァイオリニストの登竜門とも言われるユーディ・メニューイン国際コンクールで1位と聴衆賞を獲得した、2002年スペイン生まれのマリア・ドゥエニャス。2018年にウラディーミル・スピヴァコフ国際ヴァイオリン・コンクール、2021年にゲッティング・トゥ・カーネギー・コンクール、ヴィクトル・トレチャコフ国際ヴァイオリン・コンクールで優勝するなど、多くの世界的コンクールで成功を収めています。
サブスクで聞いて良いとおもったので買ったので、決して見た目に惹かれたわけではありません。


でもまあ、素晴らしい容姿と音楽をもった人だと思う。
期待してます。
PAGANINI : 24 CAPRICES / MARIA DUENAS
DISC 1
1 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
2 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
3 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
4 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
5 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
6 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
7 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
8 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
9 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
10ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
11ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
12ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
13ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
14ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
15ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
16ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
17 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
18 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
19 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
20 ニコロ・パガニーニ: 24のカプリース 作品1 (第1番-第20番)
DISC 2
1 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)
2 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)
3 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)
4 24のカプリース 作品1 (第21番-第24番)
5 パブロ・サラサーテ: バスク奇想曲 作品24
6 ジョルディ・セルベリョ: ミルシテイン・カプリース
7 ヘンリク・ヴィエニャフスキ: エチュード・カプリース 変ホ長調 作品18の2
8 ガブリエラ・オルティス: De cuerda y madera
9 カミーユ・サン=サーンス: アンダルシア奇想曲 作品122
10 エクトル・ベルリオーズ: 夢とカプリッチョ 作品8
11 カミーユ・サン=サーンス: 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28